| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
私立アインクラッド学園
作者:美桜@気まぐれ更新
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動第二部 文化祭
第55話 Party-go-round
「き、キリト君。わ、わたし、変じゃないかな? 髪型とか乱れてない?」
「大丈夫。いつも通りばっちり決まってるよ、アスナ」
「そ、そう? うーん……なら、服の着方は? 表情は? 不自然じゃない……?」
「それも大丈夫。強いて言うなら、ちょっとそわそわしすぎってとこかな」
和人に言われ、明日奈ははっと我に返った。ちらっと横目に見たガラスに映った明日奈の頬は、鏡でなくともわかるほどに赤く色付いている。
明日奈はぱんぱんと頬を叩き、少しばかり大げさな、むっとした表情を彼に向けた。
「なによ。キリト君のほうこそ、さっきからずっと爪先パチパチ言わせてるじゃない。見てたよ」
「こ、これはその、爪の垢を取っていたと言いますか……」
「こんなところで垢なんて落とさないでよ」
明日奈は微々たるため息を吐き、その小さな拳をこつん、と和人の腕に当てる。そして、気になっていた"ある質問"を彼にぶつけた。
「ねえ、さっきまりちゃんと何の話をしてたの?」
「な、なにって……他愛のない日常会話だよ」
普段通りの話し方。しかし、和人の目にはどこか動揺の色が浮かんでいる。
「ふうん。わたしにはそうは見えなかったけど」
「なんだよ、なにか疑ってるのか?」
「べ・つ・に? まさか文化祭をサボろうだなんて、幾らのんびり屋なキリト君でも考えないだろうしー」
「はは、なるほどな。……まあ、そんなとこ。アスナの予想と大体合ってるよ」
「……はあ!? ち、ちょっと、おサボりは許しませんからね!」
既に彼の姿のなくなった舞台袖に、明日奈の声が虚しく響いた。
なんとか和人を連れ戻す──否、引き戻すことに成功したあたし、リズベットこと篠崎里香の出番は、このグループ内では1番。つまりトップバッターというわけだ。
と言っても、ソロではなく、中等部生であるシリカこと珪子とのデュエットである。しかし緊張することに変わりはなく、あたしは先ほどまでとほほと肩を落としていた──和人に叱責する事で、気合いを入れ直すそれまでは。
「トップバッター緊張するけど……頑張ろうね、珪子」
「はい、里香さん!」
あたしは珪子とハイタッチした。明日奈が和人の両肩をぽんと叩き、言う。
「ほーら。キリトくんは一応リーダー格みたいなものなんだから、しっかり気合い入れてかないとダメだよ」
「は、はいアスナさん……ええと、み、みんな! 今日まで頑張ってきてくれてありがとう。成功するかどうかなんて考えなくていい。精一杯楽しんで、最高の文化祭にしようぜ!」
「「「おー!!」」」
静かな舞台袖に、あたし達の声がこだました。
明日奈の礼儀正しい手短な挨拶が終わり、いよいよあたし達の出番が回ってきた。あたしは苦笑いを浮かべ、デュエットの相手である珪子に声を掛ける。
「さ、さすがに緊張するわね……こんなに人が来るだなんて、あたし聞いてないわよ」
「去年の倍以上は来てますね……席に座れなくて立ってる人までいてますし。もしかしてこれ、前代未聞なんじゃ……」
「け、珪子……逃げるんじゃないわよ……?」
「なっ……里香さんこそ、テンパって歌詞間違えないでくださいよ!」
「もう、2人とも喧嘩しないの。ほら、肩の力抜いて?」
舞台から戻ってきた明日奈が、可愛らしく左手の人差し指を立てて諭すように言う。
「落ち着いてみれば、案外緊張なんて忘れるものだよ。それに、仮に忘れられなかったとしても、緊張感を持つのは全然悪いことじゃないし」
「あ、ありがとう。やっぱり持つべきものはアスナね」
「ふふ、どういたしまして。でも、そこは親友って言ってほしかったなあ」
片手を口許にあて、明日奈はくすくすと笑った。あたしは明日奈の頭を撫でるようにぽんと叩くと、珪子を振り返って言った。
「それじゃ、行こっか」
「……はい!」
* * *
歌い終わり、わっという歓声と拍手が巻き起こる。その光景に、あたしの目からは思わず涙が溢れた。
観客席を見回すと、もう何ヶ月も顔を合わせていなかった家族や親戚が、泣きながら拍手していたのだ。一際大きく、歓声を上げて。
──あたし達の頑張りは、無駄じゃなかったんだ。
しかし、ここで満足してはならない。あたしにはまだ、1曲ソロが残されているのだ。
あたしは涙を拭うと、観客席に向かって大きく手を振った。ありがとう、と心の中で叫んだ。
「里香さん」
隣であたしの名前を呼んだのは、もちろん珪子だ。珪子が軽くウインクする。
「すっごくよかったですよ! あたし、生まれて初めて人前で歌ってて楽しいなって思えました。次はあたしのソロですから……里香さんの番はまだ先ですし、それまでゆっくり休んでいてくださいね」
あたしは「生意気シリカめ」と言うと、にこっと微笑む珪子の頭をわしゃわしゃ掻き回した。
「もう、なにするんですか里香さーん! あたしこれから、1人で歌うんですよっ」
「知ーらないっと。ま、頑張んなさいよ、珪子」
「もー……えへへ、はーい」
あたしが珪子の小さな背中をどんっと押すと、珪子は舞台のど真ん中で転倒した。観客席にたちまち笑い声が響き渡った。
* * *
「珪子たーん!」
「シリカたーん!!」
「最高ー!」
アイドルばりの歓声にすっかりスイッチが入ってしまったらしい珪子は、
「えへへ、みんなありがとニャ!」
などと言って猫っぽいポーズをとり、ファンサービスをしながら舞台袖へと戻ってきた。
「おかえり、アイドルたん」
「や、やめてくださいよ里香さん! すっごく恥ずかしかったんですから……」
「はーいはい、お疲れ様ね。次はアスナのソロだっけ?」
ふと明日奈に目をやると、彼女は手に"人"という文字を書いてはぱくっと食べるような仕草をする、という定番のおまじないを自分にかけていた。
「……アスナさん」
「……はっ!? な、何よ。わたしだって、緊張くらいするんだから……」
あたしが呼ぶと、耳まで赤らめた明日奈が必死に抗議した。生徒会として人前に立つことの多い明日奈だが、実は毎回緊張していたのだろうか。どこのドラマのツンデレヒロインだ。
「アスナ……肩の力、抜いて」
「い、言われなくても分かってるわよ……はい、行ってくる」
そう言った明日奈が一息つき終わった頃には、彼女の顔からはすっかり緊張の色が消えていた。
和人の方を向き、凛々しく微笑む。
「キリトくん……わたし、頑張るから。見ててね」
「ああ、勿論だ。ずっと見てるよ」
和人の言葉に満足したらしい明日奈は、一瞬だけへにゃりと微笑んだ。
* * *
音楽が鳴り終わる。
持ち前の透明感ある声で、ソロ曲《White flower garden》を歌い終えた明日奈が、恋人である和人の方を向いて、頑張ったよ! とでも言いたげに子供のように微笑む。
あたしの目から、再び涙がこぼれ落ちた。
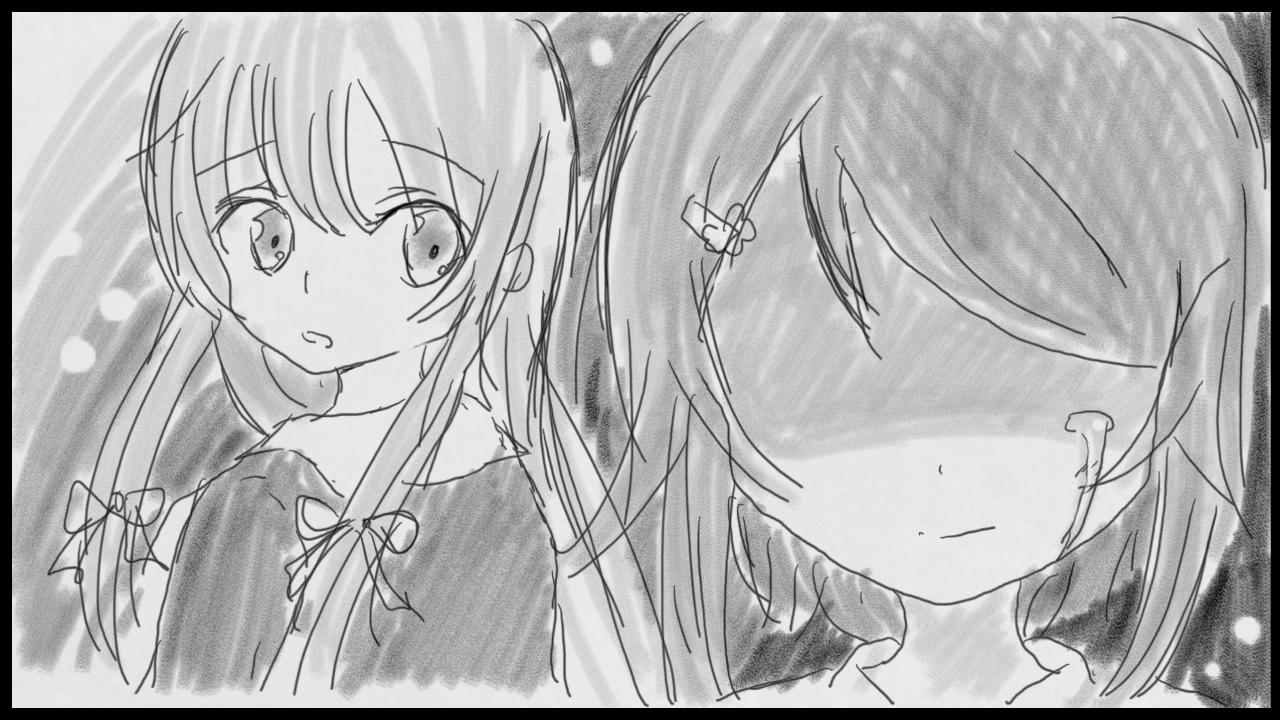
ページ上へ戻る「大丈夫。いつも通りばっちり決まってるよ、アスナ」
「そ、そう? うーん……なら、服の着方は? 表情は? 不自然じゃない……?」
「それも大丈夫。強いて言うなら、ちょっとそわそわしすぎってとこかな」
和人に言われ、明日奈ははっと我に返った。ちらっと横目に見たガラスに映った明日奈の頬は、鏡でなくともわかるほどに赤く色付いている。
明日奈はぱんぱんと頬を叩き、少しばかり大げさな、むっとした表情を彼に向けた。
「なによ。キリト君のほうこそ、さっきからずっと爪先パチパチ言わせてるじゃない。見てたよ」
「こ、これはその、爪の垢を取っていたと言いますか……」
「こんなところで垢なんて落とさないでよ」
明日奈は微々たるため息を吐き、その小さな拳をこつん、と和人の腕に当てる。そして、気になっていた"ある質問"を彼にぶつけた。
「ねえ、さっきまりちゃんと何の話をしてたの?」
「な、なにって……他愛のない日常会話だよ」
普段通りの話し方。しかし、和人の目にはどこか動揺の色が浮かんでいる。
「ふうん。わたしにはそうは見えなかったけど」
「なんだよ、なにか疑ってるのか?」
「べ・つ・に? まさか文化祭をサボろうだなんて、幾らのんびり屋なキリト君でも考えないだろうしー」
「はは、なるほどな。……まあ、そんなとこ。アスナの予想と大体合ってるよ」
「……はあ!? ち、ちょっと、おサボりは許しませんからね!」
既に彼の姿のなくなった舞台袖に、明日奈の声が虚しく響いた。
なんとか和人を連れ戻す──否、引き戻すことに成功したあたし、リズベットこと篠崎里香の出番は、このグループ内では1番。つまりトップバッターというわけだ。
と言っても、ソロではなく、中等部生であるシリカこと珪子とのデュエットである。しかし緊張することに変わりはなく、あたしは先ほどまでとほほと肩を落としていた──和人に叱責する事で、気合いを入れ直すそれまでは。
「トップバッター緊張するけど……頑張ろうね、珪子」
「はい、里香さん!」
あたしは珪子とハイタッチした。明日奈が和人の両肩をぽんと叩き、言う。
「ほーら。キリトくんは一応リーダー格みたいなものなんだから、しっかり気合い入れてかないとダメだよ」
「は、はいアスナさん……ええと、み、みんな! 今日まで頑張ってきてくれてありがとう。成功するかどうかなんて考えなくていい。精一杯楽しんで、最高の文化祭にしようぜ!」
「「「おー!!」」」
静かな舞台袖に、あたし達の声がこだました。
明日奈の礼儀正しい手短な挨拶が終わり、いよいよあたし達の出番が回ってきた。あたしは苦笑いを浮かべ、デュエットの相手である珪子に声を掛ける。
「さ、さすがに緊張するわね……こんなに人が来るだなんて、あたし聞いてないわよ」
「去年の倍以上は来てますね……席に座れなくて立ってる人までいてますし。もしかしてこれ、前代未聞なんじゃ……」
「け、珪子……逃げるんじゃないわよ……?」
「なっ……里香さんこそ、テンパって歌詞間違えないでくださいよ!」
「もう、2人とも喧嘩しないの。ほら、肩の力抜いて?」
舞台から戻ってきた明日奈が、可愛らしく左手の人差し指を立てて諭すように言う。
「落ち着いてみれば、案外緊張なんて忘れるものだよ。それに、仮に忘れられなかったとしても、緊張感を持つのは全然悪いことじゃないし」
「あ、ありがとう。やっぱり持つべきものはアスナね」
「ふふ、どういたしまして。でも、そこは親友って言ってほしかったなあ」
片手を口許にあて、明日奈はくすくすと笑った。あたしは明日奈の頭を撫でるようにぽんと叩くと、珪子を振り返って言った。
「それじゃ、行こっか」
「……はい!」
* * *
歌い終わり、わっという歓声と拍手が巻き起こる。その光景に、あたしの目からは思わず涙が溢れた。
観客席を見回すと、もう何ヶ月も顔を合わせていなかった家族や親戚が、泣きながら拍手していたのだ。一際大きく、歓声を上げて。
──あたし達の頑張りは、無駄じゃなかったんだ。
しかし、ここで満足してはならない。あたしにはまだ、1曲ソロが残されているのだ。
あたしは涙を拭うと、観客席に向かって大きく手を振った。ありがとう、と心の中で叫んだ。
「里香さん」
隣であたしの名前を呼んだのは、もちろん珪子だ。珪子が軽くウインクする。
「すっごくよかったですよ! あたし、生まれて初めて人前で歌ってて楽しいなって思えました。次はあたしのソロですから……里香さんの番はまだ先ですし、それまでゆっくり休んでいてくださいね」
あたしは「生意気シリカめ」と言うと、にこっと微笑む珪子の頭をわしゃわしゃ掻き回した。
「もう、なにするんですか里香さーん! あたしこれから、1人で歌うんですよっ」
「知ーらないっと。ま、頑張んなさいよ、珪子」
「もー……えへへ、はーい」
あたしが珪子の小さな背中をどんっと押すと、珪子は舞台のど真ん中で転倒した。観客席にたちまち笑い声が響き渡った。
* * *
「珪子たーん!」
「シリカたーん!!」
「最高ー!」
アイドルばりの歓声にすっかりスイッチが入ってしまったらしい珪子は、
「えへへ、みんなありがとニャ!」
などと言って猫っぽいポーズをとり、ファンサービスをしながら舞台袖へと戻ってきた。
「おかえり、アイドルたん」
「や、やめてくださいよ里香さん! すっごく恥ずかしかったんですから……」
「はーいはい、お疲れ様ね。次はアスナのソロだっけ?」
ふと明日奈に目をやると、彼女は手に"人"という文字を書いてはぱくっと食べるような仕草をする、という定番のおまじないを自分にかけていた。
「……アスナさん」
「……はっ!? な、何よ。わたしだって、緊張くらいするんだから……」
あたしが呼ぶと、耳まで赤らめた明日奈が必死に抗議した。生徒会として人前に立つことの多い明日奈だが、実は毎回緊張していたのだろうか。どこのドラマのツンデレヒロインだ。
「アスナ……肩の力、抜いて」
「い、言われなくても分かってるわよ……はい、行ってくる」
そう言った明日奈が一息つき終わった頃には、彼女の顔からはすっかり緊張の色が消えていた。
和人の方を向き、凛々しく微笑む。
「キリトくん……わたし、頑張るから。見ててね」
「ああ、勿論だ。ずっと見てるよ」
和人の言葉に満足したらしい明日奈は、一瞬だけへにゃりと微笑んだ。
* * *
音楽が鳴り終わる。
持ち前の透明感ある声で、ソロ曲《White flower garden》を歌い終えた明日奈が、恋人である和人の方を向いて、頑張ったよ! とでも言いたげに子供のように微笑む。
あたしの目から、再び涙がこぼれ落ちた。
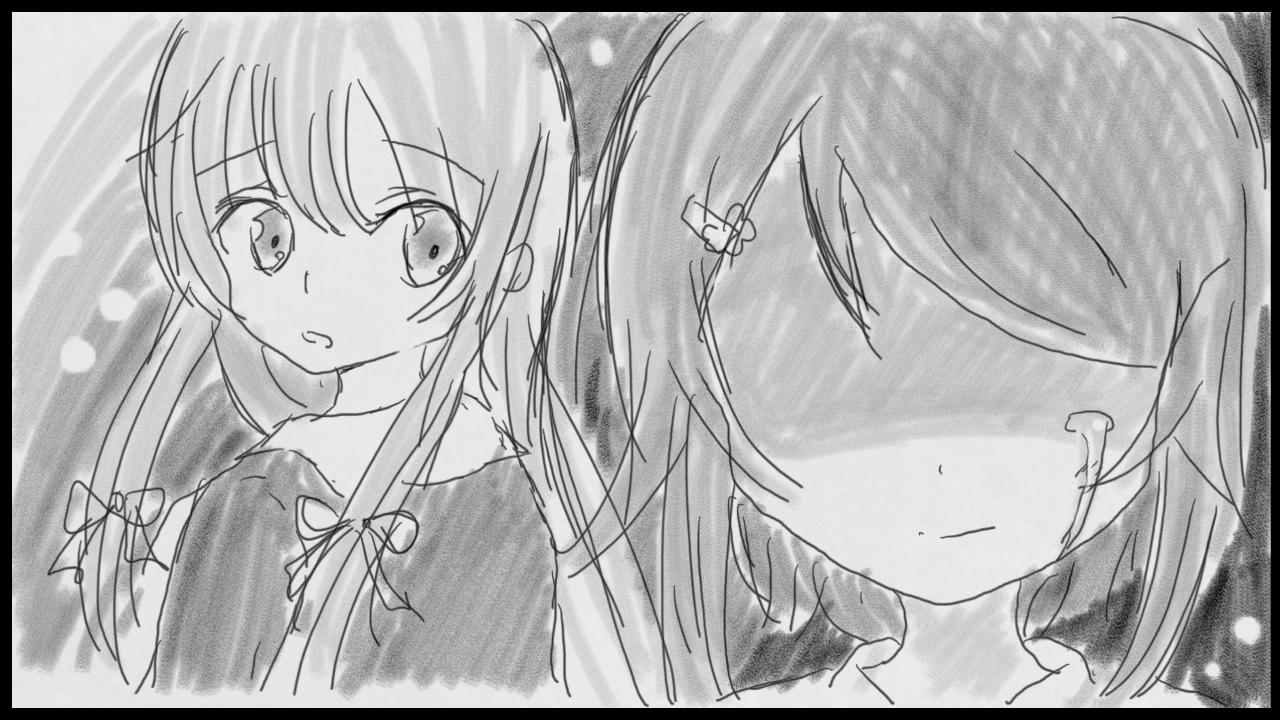
全て感想を見る:感想一覧
