| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
くらいくらい電子の森に・・・(誰も死ななかった編)
作者:たにゃお
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動第一章
――――途方にくれるしかなかった
彼が残していった、薄汚れたペンダントを握り締めたまま。
少しだけ姿を見せていた夕日は、燐光を放つ雲の谷間に落ちて
ただ、雲だけがその輪郭を光らせていた。
暗くなっていく。
――――日が完全に落ちて、手元が見えなくなったとき、
それは、光った。
さっきの雲みたいに、うすく輪郭を光らせて
それは、笑った。
――――目眩がするくらい、幸福そうな微笑を浮かべて。
第一章
僕は途方に暮れていた。
12月の秋葉原は、凍えるように冷たい。
それが、朝の5時ならなおさら。
マフラー1枚巻いてない首筋は、直に早朝の冷気で冷え切っている。たまに、両手を首にあててみる。どっちも冷たくて、なんの足しにもならなかった。
そして新聞紙ごしに感じられる、アスファルトの刺すような冷気が、絶望的に僕の体温を奪っていく……
…………
「バイト代出すから、並んで!お願い!」
同じサークルの柚木にそそのかされ、そして自分も「ちょっと並んでるだけで5000円だよ!?」という甘い言葉にのせられて、つい「並ぶ並ぶー」などと二つ返事で答えてしまった。そして当日、のこのことアキバくんだりまで出てくると、金の入った封筒と、新聞紙を持った柚木が微笑んでいたのだ。
「……これ敷いて、並んで」
「……どこに」
「……ソフマップ」
「……えーと……あれ?」
「……そう、あれ」
「……何時間?」
「……11時間」
柚木があごで指した方向には、建物を取り巻くように長蛇の列が出来ていた。
そして、僕は………

「おいお前、眠るなよ。死ぬぞ」
僕の直前に並んでいた男にたたき起こされ、がばと顔を上げた
「………おうちじゃない……」
「何いってんだ、大丈夫か!?」
風体の悪い男が、僕を心配そうに見下ろしている。絡まれるのかと、一瞬身構えてしまったがそういうつもりではなさそうだ。僕がうなずいて返すと、男は「銚子おでん」と書かれた缶を差し出した。ほわりとあったかい湯気が顔にかかる。
……生き返る……
一口かじってみる。缶詰のおでんなんて初めて食べたけど、思ったより旨い。男も、同じおでんを頬張り、眉をしかめていた。
「まずいな、これ。お前らオタクはこんなの食べてるのか」
「……僕、オタクじゃない」
…だめだ。まだ頭が朦朧としていて言葉が出てこない。小学生並みの語彙力だ。
「じゃ、なんでここに並んでるんだ」
「……5000円、くれるって言われたから……」
「5000円やるから並んでろって言われて、並んだのか!?」
「んー、今月、やばいし……」
「お前、たしか昨日の6時からここにいたよな?」
「はぁ…もう11時間すね…あはは」
「……普通に深夜バイト入れてたら、倍額以上稼げてね?」
「…………そのとおりです」
がっくりと肩を落とした。
本当に……本当にそのとおりだ……
僕だって「11時間」と聞いた瞬間、まわれ右で帰ろうと思った。でも
『約束…したのに。ひどい……』
とうち沈んだ顔で俯かれてしまい、後に引けなくなってしまったのだ。
でもあとで考えてみれば、僕は『5000円で11時間寒風に晒される』約束なんてしていない。
なんで僕はいつもこうなんだ…。なんかもうイヤになって、膝に顔をうずめた。
「ひでぇな、その友達。ていうか友達か?そいつ」
「………どうなんでしょうね……僕はどう思われているのでしょうね」
「パシリ」
……そのとおりだ。もう何を言い返す気力もない。会話が切れたので、あったかいおでんを口に運ぶ。柔らかく煮込まれた大根が、口の中でつぶれる。だし汁がじわーっとしみだしてきて、からっぽの胃に落ちていく。……なんかもう、情けないけど涙が出てきた……
……そういえばこの人は、僕のためにおでん缶を調達してくれたのだ。自分のことでいっぱいいっぱいで、お礼を言うのも忘れていた。
あらためて、男の横顔を見上げる。男はこちらを見ない。…僕が泣きそうな気分になっているのに勘付いて、見ない振りをしてくれているのか。僕よりちょっと上くらいなのに、随分しっかりしている。…視線を落とすと、黒いコートの袖口にキラリと光るものが。よく見ると
「……ガボール……」
男と目が合いかけたので、咄嗟にガボッ、ガボッとむせ込んでいる振りをした。何で僕はいつも余計な事を口走りそうになるのか。
一瞬だったけど間違いない。あの袖口に見えたのは、なんか笑う骸骨で有名な、ガボールのブレスレットだ!20万くらいするやつだ。今週のポパイで特集されたばかりだから、よく覚えている。…本物だろうか。
まぁいい。興味ない。『人畜無害』は僕の基本スタンスであり唯一の処世術だ。髑髏とか、少しでも悪そうに見えるアイテムは極力遠ざけることにしている。自分でもビックリするくらい、羨ましさを感じない。

おでんも食べ終わったし、開店までにはまだ時間もある。少し話しかけてみることにした。
「お兄さんは、なんで並んでるんですか」
「まぁ、そうな……転売、とか?」
ガボールの男は一瞬、肩を震わせた。
「買ったら即ヤフオクに出品?」
「あー…まぁ…な…」
「夜を徹して並ぶモチベーションを得られるほど、高額になるんですか、これは。1人1本なんでしょう」
「5000円で並ぶお前に言われたかないが…なにしろあれは業界初だからな!」
「業界初?…ていうかなんでこんな行列できてるんですか」
「そんなことも知らないで並んでたのか!?」
男が、あきれたようにつぶやいた。
「…『MOGMOG』とかいう大変なセキュリティソフトってことだけは…」
MOGMOGを買って来い。そう言われて、僕はこの封筒を貰った。なんか凄い機能満載で、しかも可愛い女の子がパッケージに使われていて、「業界の新スタンダード!」とまで言われている…とだけ聞いている。僕はとりあえず、2ヶ月前にウイルスバスターを更新したばっかりだから、たいして興味はないので、そう言った。
「なにを言う、ウイルスバスターとは別格だぞ!…なんだよ、その興味ゼロって顔。どんなソフトか知りたくないのかよ」
「知りたくない。知って欲しくなっても金がない」
「まぁそう言わずに聞け、暇だろ。…この『MOGMOG』って名前だけどな。ぶっちゃけ『モグモグ』、つまり食べるって意味だ」
「……食べる?」
「あぁ。このソフトが業界新スタンダードと言われている理由はそこにある。…最近、ウイルスの進化にワクチンの開発が追いついていないだろ。そこでだ。このソフト『MOGMOG』には、『消化機能』が搭載されている」
「食べて…消化すんの?」
「そう。不測のウイルスが侵入したら消化…解析して、ワクチンを自分で作り出す」
……す、すごい!それが出来たらもう怖いサイトはないな!…でも…
「…でも、ワクチンってすぐ出来るわけじゃないでしょ。ワクチン開発までに少し手間取ったり、その間にウイルスが悪さしたりしないの?」
「まぁな。でももちろん、それを補うためのシステムもある!…MOGMOG同士の口コミシステムだ」
「口コミシステム!?」
彼が嬉しそうに語るには…ウェブやメールのやり取りのさいに接触するMOGMOG同士が、自分が今まで解析したウイルスや、ウイルスの侵入経路(危ないサイトなど)などの情報をやりとりして、自分の中に蓄えていくそうだ。そんならMOGMOGサーバーでもつくって全部共有すればいいじゃん、と思ったけれど、そうなるとそのサーバーがターゲットになってMOGMOGが一網打尽にされる可能性があるから、念のため個別の情報交換システムを採用したらしい。だから、ネットに接続すればするほど優秀なセキュリティソフトに進化していくのだ。
……やばい、超ほしくなってきた……
「行列の理由が分かっただろう。セキュリティソフトとしては破格の値段だけどな」
「えっ…いくらするの?」
「聞かないで来たのか!?…えっと、金持ってるよな」
「うん、封筒に。……そういやいくら入って……げっ!!」
1枚、2枚、3枚、4枚……!!4万円!?
毎月の食費の倍額じゃないか!!
「そっ…そんなっ……!?」
「3万5千円だ。…5千円はお前への報酬か。他人事ながら腹の立つ奴だな」
「そりゃ凄いソフトかもしれないけど、セキュリティソフトに3万5千円はありえない。そんなの絶対出さない」
「ところが出しちゃうんだな、出しちゃう奴は」
男はにやにや笑っている。
「超、かわいいんだよ。MOGMOGは」
「……かわいい?パッケージが?」
「いや、MOGMOGがだ」
MOGMOGが業界新スタンダードと言われる理由はもうひとつある。「対人セキュリティシステム」だ。
最近、企業内での顧客名簿流出などの事件が大きな社会問題となっている。本当に怖いのは、無作為に知らない人のPCを荒らすクラッカーなんかより、有益な情報であることを知ってPCに近づく「人間」である、という発想から開発されたセキュリティシステム。MOGMOGはいわゆる、仮想人格でもあるのだ。カワイイ女の子の外見をした「それ」は、持ち主とコミュニケーションをとり、付属のカメラから持ち主の「網膜」を識別する。そして持ち主の行動パターン、知人、友人関係も「ぼんやりと」記憶する。そして知人がPCを利用しようとすれば、持ち主のケータイなどにアクセスして使用許可を得る。無論、セキュリティのレベルは調整できるので、あらかじめ数人に使用許可を出しておくことも可能。そして、まったく知らない人間が近寄ると、警戒レベルを上げてPCをロックする。
「そこまで……!」
「しかもMOGMOGは、キャラクターを選択出来る。デフォルトはメイドだけど、スク水とか、女教師なんかがあったかな。あとネコミミとか、体操服とかセーラー服、和服メイドとか、そこら辺の『いかにも』なやつが色々。…美少女がウザければ動物とか、もうカワイイのがウザい人のために、老人とか、カーソルとかもある」
「カーソルごときに人間関係把握されるの、イヤだなぁ…」
「……イヤだなそりゃ」
でもたしかに、それで3万5千円は安い。買ってしまう人は買ってしまうだろう。でも僕は『買ってしまう人』ではない。ていうか経済的な理由で『買ってしまう人』になれない。…となると何だか、柚木のために新聞敷いて11時間も寒風にさらされている自分が無性に哀れに思えてきて…。聞かなきゃよかった。もうあいつの頼みは聞かない。また膝に顔をうずめる。
「おっ、店が開くぞ!!」
行列がにわかに色めきたった。シャッターはまだ半開きだが、行列はすでに動き始めている。僕もあわてて立ち上がる。後ろに並んでいた薄黒いオーバーオールの一団から体当たりを受け、おでん缶が飛んだ。「押さないで下さい!」「列を崩さないでください!」警備担当者の怒号にも似た呼びかけが、空しく人波に飲まれていった…
「……はぁ、何とか買えたな……」
人ごみを掻き分け、ほうほうの体で辿り着いた駅前の喫茶店で、男がつぶやいた。肉体的疲労も、精神疲労もMAX……。さっさと漫喫にでも行って仮眠をとりたい…と切に思っていたのに、この男に「やめとけ。今日なんか人でいっぱいだぞ」と腕を引かれ、よく分からないうちに喫茶店に連れ込まれた。目の前で何だか高そうな珈琲が薫っているのに、もう眠りに堕ちてしまいそうだ……
「そういえば、名前を聞いてなかったな」
「ん…あぁ、姶良。姶良 壱樹っす」
あいら いつき、と読む。初見で読める人はまずいない。かっこいいと言ってくれるひともいるけど、画数が多くてテストの時にまどろっこしい思いをする。一木にでもしてくれれば楽だったのに。
「ほぅ、なんか今っぽい名前だな。俺は紺野 匠だ。よろしく」
「染物職人みたいな名前ですね……あ、何言ってんだろ…ごめん、眠くて…」
眠すぎて敬語も億劫になってきた。
「……大丈夫か、疲労困憊ってかんじだな」
「ええまぁ…まさか徹夜で並べって意味とは思わなかったんで、学校から直接来て…」
「漫喫行ってる場合じゃないだろう!寝なくて大丈夫か!?」
「……今日の1限の前に渡せって言われてるんで……」
「なんて奴だ…お前それヤフオクで売っちゃえよ!」
「そういうわけにもいかないでしょ…頼まれたんだから…」
なんとか、意識を保って薄笑いをうかべた。紺野さんが眉をひそめる。…ああ、僕は今、よほど情けない笑い方をしたんだな…
「……よし、じゃあ行くか」
紺野氏が立ち上がった。やっと眠れる。僕はひらひらと手を振って紺野氏を見送ろうとした。
「なにやってんだ。お前も来い」
「……え」
「学校。行くんだろ?おれも付き合おう」
「え、でもまだ7時…」
「いいから来いって」
紺野氏は伝票を掴んで歩き出した。
「お前がもってるそれ、ノーパソだろ」
高校の入学祝に買ってもらった、僕が持つ唯一の貴重品だ。頼れる古い相棒だが、古すぎて最近液晶が黄色っぽい。
「でも、さっき充電きれちゃったよ」
「学校でコンセント使えるだろ」
紺野氏は、振り返ってにやりと笑った。
「駄賃代わりにMOGMOGの中身を拝見するくらい、いいだろ?」
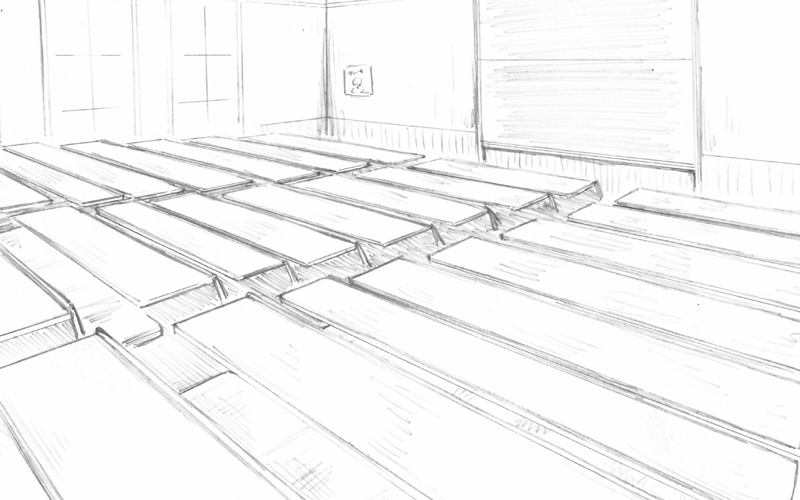
誰もいない朝の講義室は、まだ暖房が入ってなくてひんやりしていた。なんだか今日はどこに行っても寒い日だ。ノートパソコンのアダプタを差し込んでいると、紺野氏が早速MOGMOGの包装を乱暴に破き始めた。
「あぁ、そんな乱暴にしないでくれよ!渡すんだから」
「いいんだよ、こういうのは中身さえ手に入れば!……じゃ、入れるぞー。じゃじゃーん」
じゃじゃーん、じゃない。紺野氏の後ろには、無残に破られた包装がくしゃくしゃに積まれている。……眠気にかまけて、つい成り行きに任せてしまったけれど、僕はなにをやってるんだ。さっき会ったばかりの男と、他人のソフトを勝手に空けて「じゃじゃーん」とか言いながら自分のパソコンに挿入している……
「お、何か出たねー、認証コード出たねー。えーと……9,8,A,R…」
紺野氏は嬉々としてCDケースの認証コードを打ち込んでいく。いいのかなぁ…柚木、怒るだろうなぁ…
「おい、パスワードはどうする?」
「パスワード……じゃ、76ccb3…」
「なんだそりゃ」
「秘密……あれ?」
……パスワード?……認証コード……?
認証って、していいんだっけ……?
……もういいや…眠い……考えるのが眠気に追いつかない……あ、右肩が温まってきた……太陽があったかいや……
「な、な、な、なにやってんのよ――――――!!!」
突然の絶叫に、心地よい眠りの帳を破られて、がばと起き上がった。
「姶良っ!!……あんた……私のMOGMOGに何をしたっ!!!」
「………は」
カツカツという小気味よい足音に釣られるように、ゆらりと頭を上げると……目やにでかすむ視界の向こう側に、軽いウェーブのかかったショートヘアの輪郭にオレンジがかった桃色の唇。…もう少し視線を上げると、黒目がちなのに冷たい瞳と目が合った。…本当に、今日はどこに行っても、何をやっても寒い日だ…。
…一生懸命目をしばたかせて意識を通常レベルに戻すと、僕はうすぼんやりと、自分が死地っぽい場所にいることに気がついた。
怒りのあまり、顔を紅潮させた柚木の顔が、目の前にあったから……
「おっ……女……!?」
認証完了したことを示す電子音に、紺野氏のこわばった声が重なった。
……なんか、空気が重い……
「あ……ごめん、その……時間があったから、中見せてもらおうかな……って」
「認証コード、入れたよね」
朝の空気みたいに、冷たく澄みわたった柚木の声。……潮がひくように、僕の眠気が醒めていった……
「…パスワードも、入れたよね?」
「……あ、……そ、そう、だった……僕のパソコンに認証………!」
柚木は、眠気とショックで崩れ落ちていく僕から視線を外すと、くしゃくしゃに破られたMOGMOGの包装に視線をさまよわせ……おもむろに、紺野氏に照準を合わせた。
「姶良をそそのかしたのは、あんたね……?」
バネで言えば収縮するような、津波で言えば、遠く、遠くまで潮が引いた一瞬のような…そんな声だ。
「や、その……おい、姶良ぁ…彼女なんだったら最初からそう言えよぉ…」
「……だれが彼女だっ!!!」
柚木が溜めに溜めた怒りを一気に放出した。
……眠気は相変わらず酷いもんだったが、僕にも分かった。紺野氏は、僕が同級生にひどい扱いを受けたと思って(実際に相当ひどい扱いを受けたんだけど)昼行灯な風情の僕に代わって一泡ふかせてくれるつもりでいたのだろう。
どうせ日照不足なかんじのモヤシ野郎が来るだろうから脅しつけてやろうと思っていたら(性格を差し引けば)意外にも可憐な女子が怒りをあらわに詰め寄ってきた、と。
――うわ、なにその状況。最悪。
「楽しみにして1時間も早く来たのに!これ逃したら次の入荷はいつだと思ってんの!!最低っ!!」
紺野氏は、自分のMOGMOGが入ったバッグを背後に手繰り寄せた。そして後ろ手にジッパーを空けながら、柚木を刺激しない程度に私物をそっと放り込む。
「あっ……あんた、彼氏でもない男を寒空に11時間も放置して全然平気なのか!!」
「バイト代払ったもん!」
「手口は聞いたぞ、あんなのは詐欺だ!」
「じゃあ何、私に11時間寒風に晒されろっていうの!?」
「えっ……?」
「私の手入れが行き届いた肌が、荒れるじゃない!!」
三人の教室が、一瞬凍てついた。すごいな、女子のこういう論理展開……。
女の子次元の話は苦手だ。何を言っても『女の子常識』というあの不可解なルールを持ち込まれて何も言えなくなる。…紺野氏を横目で見る。社会人みたいだし、僕よりは女の子常識にメスを入れられるんじゃないか、と期待を込めて。言っちゃってくれ、僕には言えないあんなことやこんなことを!
「あ、あんたなぁ……」
絶句する紺野氏。……だめだ。多分この人も見た目程、女子に免疫はない。考えてみればこんな怖そうなひとに喧嘩を売る女子なんて聞いたことがない。
「何よ、なんか言いたいことがあるの!?」
「…え、えーとな……」
「さ…寒かった…すげぇ寒かった!お腹もすいた!」
我ながら情けない恨み言が、口を突いて出た。丁度いい塩梅に鼻水も垂れてきた。紺野氏がアテにならないなら、僕が時間を稼ぐしかない。どんだけ情けない手段だとしても。
「うっわ…」
これでうっすらと、本当にうっすらと抱いていた『柚木と恋愛フラグ』は、確実にへし折れたことだろう。そう思うとなんだか気が楽になってきた。
後ろを振り返ると、紺野氏が「設定開始」と表示されたノーパソをしまい始めている。あと数秒で駆け出すだろう。僕は紺野氏と目を見交わし、次の瞬間、出口に殺到した。
「あっ!こら待ちなさいっ!」
柚木が走って追いかけてきた。僕を一限前に呼んでおいて講義をさぼる気か。

喫茶「伯剌西爾」の古びたテーブルに落ち着く。何と読むのかは知らない。目の前には今日2杯目の珈琲。馥郁とした薫りが、ふわりと立ち昇る…などと、普段使わないような言葉で褒め称えたくなる。
大人の男である僕たちの全力疾走にぴったりついてきた柚木が、当然のようにケーキセットを手馴れたようすで注文している。きっと紺野氏におごらせる気だ。社会人は珈琲が一杯500円以上する喫茶店に、一日何度もふらりと入れるものなんだろうか。賭けてもいいがこのひとは『勝ち組の大人』だ。
「……キャラ選択画面だ」
紺野氏は息を弾ませて、ノーパソの画面を僕のほうに向けた。
―――いや、萌えキャラに興奮している時点で、勝ち組とは言えんかもしれない。
画面には、数種類の女の子が並んでいる。デフォルト設定のメイド、気が強そうな猫の耳をつけた女子、変な巻き髪のナース、むだに明るそうな、くい込むような体育着の女子…
僕は反射的にノーパソを閉じた。
「いやいやいや、こんなのがデスクトップをウロウロするとか社会生活に支障が」
「売れ筋のキャラは目立つところにあるんだよ!何ページが進めば大人しいのも出てくるから…とりあえずどれが好みだ!フォースで選べ!!」
「…フォース…」
どうやら紺野氏は、僕が思っているよりも年上らしい。
画面の下のほうに「1/2/3/4……」と数字が振ってある。まだいっぱいいるようだ。面倒だから数個飛ばして4をクリックする。4以降はメイド系のキャラクターが並んでいる。さすが人気ジャンルだ。居並ぶメイドさんは猫の耳やら肉球やらがついていたり、ミニスカートにニーソックス履いてたりする。日本人のメイド観は、アメリカ人の忍者に対する考え方と、よく似ているなぁ……。
そんなことを考えながらカーソルを右下まで漂わせ、ページを適当に切り替えようとしたそのとき、一人のメイドが目についた。
「ん…それか?」
カーソルの先を熱心に見つめていた紺野氏の表情が、わずかに変わった。
淡いすみれ色の、クラシカルなワンピース。少しだけフリルのついた、純白のエプロン。繊細なブロンドのストレート、その下に隠れて静かに光る、黒目がちなブルーグレーの瞳…よくあるといえば、よくある。でもなんというか、全体からかもし出される絵の雰囲気に、かすかに惹かれてマウスを止めた。
「…あ、これがいい。これに決めた」
「えー?もうちょっと見てから選ぼうよー。もっとカワイイのあるって絶対」
不満げにつぶやく柚木と見比べる。さっきから、自分のくせ気をさりげなく引っ張っている。髪の綺麗な子を見ると、柚木はいつも自分のくせ毛を引っ張るのだ。
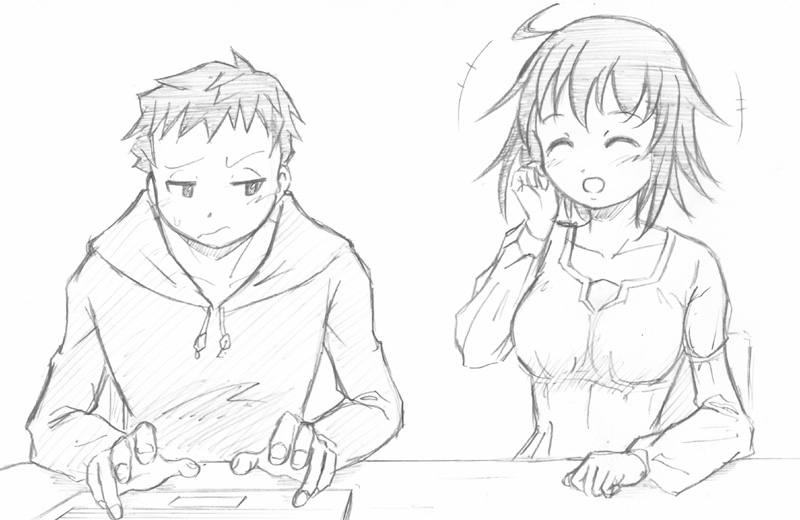
先刻、鬼の形相で僕らを追ってきた柚木は、今はびっくりするほど穏やかに、追加注文のシフォンケーキを頬張っている。
さっき紺野氏に、茶封筒を渡されてからというもの、ずっと機嫌がいい。…多分、紺野氏が弁償してくれたのだろう。…返さなきゃな。分割払いにしてもらってでも。…それにしても、不思議だ。
柚木の『上機嫌』の理由が、わからない。
一瞬、ちょっと多めに包んでもらったのかな、といぶかったけれど…
僕がそう思っているだけだが、柚木は『おごられる』のは好きみたいだけど、露骨に金を多めに渡したりしたら、侮辱と感じて機嫌を損ねると思う。あの子は実際に金銭がからむような生々しいやりとりが好きじゃない。要するに、金に困ってないのだ。
ふかふかのシフォンケーキをついばむ柚木の視線を追ってみる。時折、ちらっと紺野氏を見上げる。単なる物珍しさか、もっと別の理由か…僕には分からないし、詮索する理由もない。先刻盛大に鼻水を垂らした時点で、僕の恋愛フラグはへし折れたのだから。
「そうだ、姶良。カスタマイズしないのか?」
ぼーっとしているところに急に紺野氏に話しかけられ、慌てて視線を画面に戻す。
「キャラを選択してみろ」
さっき選んだメイドをクリックすると、メイドがアップで表示された。顔の横あたりに「カスタム」と書かれた赤いアイコンが光っている。
「服とか髪の色とか、あと瞳の色なんかをカスタマイズ出来るんだ」
瞳の色……。
「じゃ、変えようかな。瞳の色だけ…」
「…この色、あんまり好みじゃないか?」
…絡むなぁ。何なんだよこのひとは。
『瞳の色』をクリックすると、標準色パレットが表示される。僕はパレットの色を無視して『その他の色』を選択した。虹色のカラーテーブルが立ち上がる。…僕の入れる色は、もう決まっている。僕はカラーテーブルの番号入力欄にカーソルを置いた。
「76ccb3……と」
「それ、さっきのパスワード…」
「そう。僕の好きな色の番号」
彼女の瞳が、優しい空色に変わった。空に、すこし新緑を溶かしたような…淡いようで深い色合い。
チェレステ。ビアンキの伝統色。WEBの商品画像からひっぱって来た、僕の一番好きな色だ。
ビアンキはイタリアの自転車メーカー。車体に使われる緑がかった空色は「チェレステ(天空)」と呼ばれている。毎年ミラノの空の色を見ながら、職人が調合している、とロードバイクの雑誌で読んだ。この逸話を読むまでは「へんな色のチャリ」と思ってたけれど、今はビアンキのロードバイクが欲しくてたまらない。
で、腹が立つことに、柚木はビアンキのロードバイクを持っているのだ。
「おぉ、マルゲリータ王妃の、瞳の色だな」
…この色には、そういう説もある。紺野さんも、自転車が好きなんだろうか。
「……あぁ……まぁ……はい……」
ビアンキ持ってないくせにチェレステにこだわる自分がなんか妙に子供に思えて、気恥ずかしくなってきた。…だけど、チェレステの瞳に変えた瞬間、少女は、なんというか、冬の陽だまりみたいに透き通って、ほんのり温かくみえた。
言おうかどうしようか迷ったけれど、こういう乙女発言でいい目に遭ったことは一度もないので黙っておいた。
…そのあと、細かい色設定や性格設定や声設定など色々聞かれたけれど、面倒なので全部すっ飛ばしてデフォルトで通した。
『決定』ボタンを押すと、少女はくるりとスカートを翻して一回転して、ふわりとスカートのすそを持ち上げると、英国式に一礼した。
「お名前をください、ご主人さま」
イメージにぴったりな、透明で優しい声…!
人前で有頂天になりかけたけど、ぐっと堪えて名前の欄に『ビアンキ』と入力した。
「ビアンキです。…よろしくお願いします」
こうして、僕とビアンキの生活が始まった。

ページ上へ戻る彼が残していった、薄汚れたペンダントを握り締めたまま。
少しだけ姿を見せていた夕日は、燐光を放つ雲の谷間に落ちて
ただ、雲だけがその輪郭を光らせていた。
暗くなっていく。
――――日が完全に落ちて、手元が見えなくなったとき、
それは、光った。
さっきの雲みたいに、うすく輪郭を光らせて
それは、笑った。
――――目眩がするくらい、幸福そうな微笑を浮かべて。
第一章
僕は途方に暮れていた。
12月の秋葉原は、凍えるように冷たい。
それが、朝の5時ならなおさら。
マフラー1枚巻いてない首筋は、直に早朝の冷気で冷え切っている。たまに、両手を首にあててみる。どっちも冷たくて、なんの足しにもならなかった。
そして新聞紙ごしに感じられる、アスファルトの刺すような冷気が、絶望的に僕の体温を奪っていく……
…………
「バイト代出すから、並んで!お願い!」
同じサークルの柚木にそそのかされ、そして自分も「ちょっと並んでるだけで5000円だよ!?」という甘い言葉にのせられて、つい「並ぶ並ぶー」などと二つ返事で答えてしまった。そして当日、のこのことアキバくんだりまで出てくると、金の入った封筒と、新聞紙を持った柚木が微笑んでいたのだ。
「……これ敷いて、並んで」
「……どこに」
「……ソフマップ」
「……えーと……あれ?」
「……そう、あれ」
「……何時間?」
「……11時間」
柚木があごで指した方向には、建物を取り巻くように長蛇の列が出来ていた。
そして、僕は………

「おいお前、眠るなよ。死ぬぞ」
僕の直前に並んでいた男にたたき起こされ、がばと顔を上げた
「………おうちじゃない……」
「何いってんだ、大丈夫か!?」
風体の悪い男が、僕を心配そうに見下ろしている。絡まれるのかと、一瞬身構えてしまったがそういうつもりではなさそうだ。僕がうなずいて返すと、男は「銚子おでん」と書かれた缶を差し出した。ほわりとあったかい湯気が顔にかかる。
……生き返る……
一口かじってみる。缶詰のおでんなんて初めて食べたけど、思ったより旨い。男も、同じおでんを頬張り、眉をしかめていた。
「まずいな、これ。お前らオタクはこんなの食べてるのか」
「……僕、オタクじゃない」
…だめだ。まだ頭が朦朧としていて言葉が出てこない。小学生並みの語彙力だ。
「じゃ、なんでここに並んでるんだ」
「……5000円、くれるって言われたから……」
「5000円やるから並んでろって言われて、並んだのか!?」
「んー、今月、やばいし……」
「お前、たしか昨日の6時からここにいたよな?」
「はぁ…もう11時間すね…あはは」
「……普通に深夜バイト入れてたら、倍額以上稼げてね?」
「…………そのとおりです」
がっくりと肩を落とした。
本当に……本当にそのとおりだ……
僕だって「11時間」と聞いた瞬間、まわれ右で帰ろうと思った。でも
『約束…したのに。ひどい……』
とうち沈んだ顔で俯かれてしまい、後に引けなくなってしまったのだ。
でもあとで考えてみれば、僕は『5000円で11時間寒風に晒される』約束なんてしていない。
なんで僕はいつもこうなんだ…。なんかもうイヤになって、膝に顔をうずめた。
「ひでぇな、その友達。ていうか友達か?そいつ」
「………どうなんでしょうね……僕はどう思われているのでしょうね」
「パシリ」
……そのとおりだ。もう何を言い返す気力もない。会話が切れたので、あったかいおでんを口に運ぶ。柔らかく煮込まれた大根が、口の中でつぶれる。だし汁がじわーっとしみだしてきて、からっぽの胃に落ちていく。……なんかもう、情けないけど涙が出てきた……
……そういえばこの人は、僕のためにおでん缶を調達してくれたのだ。自分のことでいっぱいいっぱいで、お礼を言うのも忘れていた。
あらためて、男の横顔を見上げる。男はこちらを見ない。…僕が泣きそうな気分になっているのに勘付いて、見ない振りをしてくれているのか。僕よりちょっと上くらいなのに、随分しっかりしている。…視線を落とすと、黒いコートの袖口にキラリと光るものが。よく見ると
「……ガボール……」
男と目が合いかけたので、咄嗟にガボッ、ガボッとむせ込んでいる振りをした。何で僕はいつも余計な事を口走りそうになるのか。
一瞬だったけど間違いない。あの袖口に見えたのは、なんか笑う骸骨で有名な、ガボールのブレスレットだ!20万くらいするやつだ。今週のポパイで特集されたばかりだから、よく覚えている。…本物だろうか。
まぁいい。興味ない。『人畜無害』は僕の基本スタンスであり唯一の処世術だ。髑髏とか、少しでも悪そうに見えるアイテムは極力遠ざけることにしている。自分でもビックリするくらい、羨ましさを感じない。

おでんも食べ終わったし、開店までにはまだ時間もある。少し話しかけてみることにした。
「お兄さんは、なんで並んでるんですか」
「まぁ、そうな……転売、とか?」
ガボールの男は一瞬、肩を震わせた。
「買ったら即ヤフオクに出品?」
「あー…まぁ…な…」
「夜を徹して並ぶモチベーションを得られるほど、高額になるんですか、これは。1人1本なんでしょう」
「5000円で並ぶお前に言われたかないが…なにしろあれは業界初だからな!」
「業界初?…ていうかなんでこんな行列できてるんですか」
「そんなことも知らないで並んでたのか!?」
男が、あきれたようにつぶやいた。
「…『MOGMOG』とかいう大変なセキュリティソフトってことだけは…」
MOGMOGを買って来い。そう言われて、僕はこの封筒を貰った。なんか凄い機能満載で、しかも可愛い女の子がパッケージに使われていて、「業界の新スタンダード!」とまで言われている…とだけ聞いている。僕はとりあえず、2ヶ月前にウイルスバスターを更新したばっかりだから、たいして興味はないので、そう言った。
「なにを言う、ウイルスバスターとは別格だぞ!…なんだよ、その興味ゼロって顔。どんなソフトか知りたくないのかよ」
「知りたくない。知って欲しくなっても金がない」
「まぁそう言わずに聞け、暇だろ。…この『MOGMOG』って名前だけどな。ぶっちゃけ『モグモグ』、つまり食べるって意味だ」
「……食べる?」
「あぁ。このソフトが業界新スタンダードと言われている理由はそこにある。…最近、ウイルスの進化にワクチンの開発が追いついていないだろ。そこでだ。このソフト『MOGMOG』には、『消化機能』が搭載されている」
「食べて…消化すんの?」
「そう。不測のウイルスが侵入したら消化…解析して、ワクチンを自分で作り出す」
……す、すごい!それが出来たらもう怖いサイトはないな!…でも…
「…でも、ワクチンってすぐ出来るわけじゃないでしょ。ワクチン開発までに少し手間取ったり、その間にウイルスが悪さしたりしないの?」
「まぁな。でももちろん、それを補うためのシステムもある!…MOGMOG同士の口コミシステムだ」
「口コミシステム!?」
彼が嬉しそうに語るには…ウェブやメールのやり取りのさいに接触するMOGMOG同士が、自分が今まで解析したウイルスや、ウイルスの侵入経路(危ないサイトなど)などの情報をやりとりして、自分の中に蓄えていくそうだ。そんならMOGMOGサーバーでもつくって全部共有すればいいじゃん、と思ったけれど、そうなるとそのサーバーがターゲットになってMOGMOGが一網打尽にされる可能性があるから、念のため個別の情報交換システムを採用したらしい。だから、ネットに接続すればするほど優秀なセキュリティソフトに進化していくのだ。
……やばい、超ほしくなってきた……
「行列の理由が分かっただろう。セキュリティソフトとしては破格の値段だけどな」
「えっ…いくらするの?」
「聞かないで来たのか!?…えっと、金持ってるよな」
「うん、封筒に。……そういやいくら入って……げっ!!」
1枚、2枚、3枚、4枚……!!4万円!?
毎月の食費の倍額じゃないか!!
「そっ…そんなっ……!?」
「3万5千円だ。…5千円はお前への報酬か。他人事ながら腹の立つ奴だな」
「そりゃ凄いソフトかもしれないけど、セキュリティソフトに3万5千円はありえない。そんなの絶対出さない」
「ところが出しちゃうんだな、出しちゃう奴は」
男はにやにや笑っている。
「超、かわいいんだよ。MOGMOGは」
「……かわいい?パッケージが?」
「いや、MOGMOGがだ」
MOGMOGが業界新スタンダードと言われる理由はもうひとつある。「対人セキュリティシステム」だ。
最近、企業内での顧客名簿流出などの事件が大きな社会問題となっている。本当に怖いのは、無作為に知らない人のPCを荒らすクラッカーなんかより、有益な情報であることを知ってPCに近づく「人間」である、という発想から開発されたセキュリティシステム。MOGMOGはいわゆる、仮想人格でもあるのだ。カワイイ女の子の外見をした「それ」は、持ち主とコミュニケーションをとり、付属のカメラから持ち主の「網膜」を識別する。そして持ち主の行動パターン、知人、友人関係も「ぼんやりと」記憶する。そして知人がPCを利用しようとすれば、持ち主のケータイなどにアクセスして使用許可を得る。無論、セキュリティのレベルは調整できるので、あらかじめ数人に使用許可を出しておくことも可能。そして、まったく知らない人間が近寄ると、警戒レベルを上げてPCをロックする。
「そこまで……!」
「しかもMOGMOGは、キャラクターを選択出来る。デフォルトはメイドだけど、スク水とか、女教師なんかがあったかな。あとネコミミとか、体操服とかセーラー服、和服メイドとか、そこら辺の『いかにも』なやつが色々。…美少女がウザければ動物とか、もうカワイイのがウザい人のために、老人とか、カーソルとかもある」
「カーソルごときに人間関係把握されるの、イヤだなぁ…」
「……イヤだなそりゃ」
でもたしかに、それで3万5千円は安い。買ってしまう人は買ってしまうだろう。でも僕は『買ってしまう人』ではない。ていうか経済的な理由で『買ってしまう人』になれない。…となると何だか、柚木のために新聞敷いて11時間も寒風にさらされている自分が無性に哀れに思えてきて…。聞かなきゃよかった。もうあいつの頼みは聞かない。また膝に顔をうずめる。
「おっ、店が開くぞ!!」
行列がにわかに色めきたった。シャッターはまだ半開きだが、行列はすでに動き始めている。僕もあわてて立ち上がる。後ろに並んでいた薄黒いオーバーオールの一団から体当たりを受け、おでん缶が飛んだ。「押さないで下さい!」「列を崩さないでください!」警備担当者の怒号にも似た呼びかけが、空しく人波に飲まれていった…
「……はぁ、何とか買えたな……」
人ごみを掻き分け、ほうほうの体で辿り着いた駅前の喫茶店で、男がつぶやいた。肉体的疲労も、精神疲労もMAX……。さっさと漫喫にでも行って仮眠をとりたい…と切に思っていたのに、この男に「やめとけ。今日なんか人でいっぱいだぞ」と腕を引かれ、よく分からないうちに喫茶店に連れ込まれた。目の前で何だか高そうな珈琲が薫っているのに、もう眠りに堕ちてしまいそうだ……
「そういえば、名前を聞いてなかったな」
「ん…あぁ、姶良。姶良 壱樹っす」
あいら いつき、と読む。初見で読める人はまずいない。かっこいいと言ってくれるひともいるけど、画数が多くてテストの時にまどろっこしい思いをする。一木にでもしてくれれば楽だったのに。
「ほぅ、なんか今っぽい名前だな。俺は紺野 匠だ。よろしく」
「染物職人みたいな名前ですね……あ、何言ってんだろ…ごめん、眠くて…」
眠すぎて敬語も億劫になってきた。
「……大丈夫か、疲労困憊ってかんじだな」
「ええまぁ…まさか徹夜で並べって意味とは思わなかったんで、学校から直接来て…」
「漫喫行ってる場合じゃないだろう!寝なくて大丈夫か!?」
「……今日の1限の前に渡せって言われてるんで……」
「なんて奴だ…お前それヤフオクで売っちゃえよ!」
「そういうわけにもいかないでしょ…頼まれたんだから…」
なんとか、意識を保って薄笑いをうかべた。紺野さんが眉をひそめる。…ああ、僕は今、よほど情けない笑い方をしたんだな…
「……よし、じゃあ行くか」
紺野氏が立ち上がった。やっと眠れる。僕はひらひらと手を振って紺野氏を見送ろうとした。
「なにやってんだ。お前も来い」
「……え」
「学校。行くんだろ?おれも付き合おう」
「え、でもまだ7時…」
「いいから来いって」
紺野氏は伝票を掴んで歩き出した。
「お前がもってるそれ、ノーパソだろ」
高校の入学祝に買ってもらった、僕が持つ唯一の貴重品だ。頼れる古い相棒だが、古すぎて最近液晶が黄色っぽい。
「でも、さっき充電きれちゃったよ」
「学校でコンセント使えるだろ」
紺野氏は、振り返ってにやりと笑った。
「駄賃代わりにMOGMOGの中身を拝見するくらい、いいだろ?」
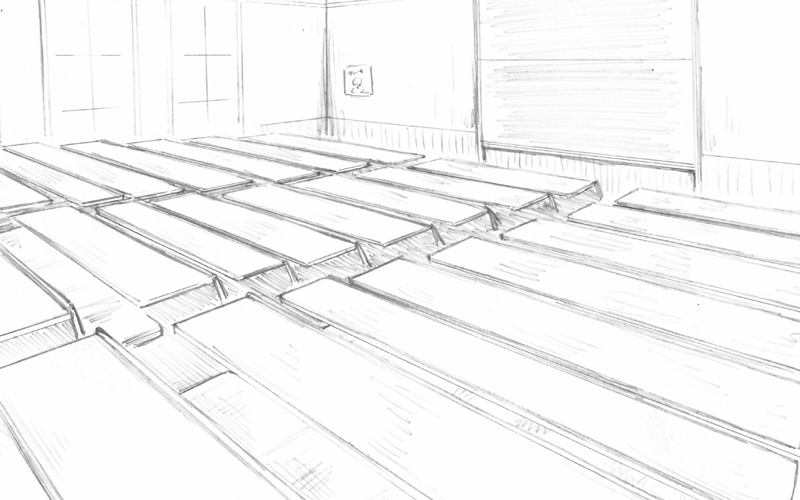
誰もいない朝の講義室は、まだ暖房が入ってなくてひんやりしていた。なんだか今日はどこに行っても寒い日だ。ノートパソコンのアダプタを差し込んでいると、紺野氏が早速MOGMOGの包装を乱暴に破き始めた。
「あぁ、そんな乱暴にしないでくれよ!渡すんだから」
「いいんだよ、こういうのは中身さえ手に入れば!……じゃ、入れるぞー。じゃじゃーん」
じゃじゃーん、じゃない。紺野氏の後ろには、無残に破られた包装がくしゃくしゃに積まれている。……眠気にかまけて、つい成り行きに任せてしまったけれど、僕はなにをやってるんだ。さっき会ったばかりの男と、他人のソフトを勝手に空けて「じゃじゃーん」とか言いながら自分のパソコンに挿入している……
「お、何か出たねー、認証コード出たねー。えーと……9,8,A,R…」
紺野氏は嬉々としてCDケースの認証コードを打ち込んでいく。いいのかなぁ…柚木、怒るだろうなぁ…
「おい、パスワードはどうする?」
「パスワード……じゃ、76ccb3…」
「なんだそりゃ」
「秘密……あれ?」
……パスワード?……認証コード……?
認証って、していいんだっけ……?
……もういいや…眠い……考えるのが眠気に追いつかない……あ、右肩が温まってきた……太陽があったかいや……
「な、な、な、なにやってんのよ――――――!!!」
突然の絶叫に、心地よい眠りの帳を破られて、がばと起き上がった。
「姶良っ!!……あんた……私のMOGMOGに何をしたっ!!!」
「………は」
カツカツという小気味よい足音に釣られるように、ゆらりと頭を上げると……目やにでかすむ視界の向こう側に、軽いウェーブのかかったショートヘアの輪郭にオレンジがかった桃色の唇。…もう少し視線を上げると、黒目がちなのに冷たい瞳と目が合った。…本当に、今日はどこに行っても、何をやっても寒い日だ…。
…一生懸命目をしばたかせて意識を通常レベルに戻すと、僕はうすぼんやりと、自分が死地っぽい場所にいることに気がついた。
怒りのあまり、顔を紅潮させた柚木の顔が、目の前にあったから……
「おっ……女……!?」
認証完了したことを示す電子音に、紺野氏のこわばった声が重なった。
……なんか、空気が重い……
「あ……ごめん、その……時間があったから、中見せてもらおうかな……って」
「認証コード、入れたよね」
朝の空気みたいに、冷たく澄みわたった柚木の声。……潮がひくように、僕の眠気が醒めていった……
「…パスワードも、入れたよね?」
「……あ、……そ、そう、だった……僕のパソコンに認証………!」
柚木は、眠気とショックで崩れ落ちていく僕から視線を外すと、くしゃくしゃに破られたMOGMOGの包装に視線をさまよわせ……おもむろに、紺野氏に照準を合わせた。
「姶良をそそのかしたのは、あんたね……?」
バネで言えば収縮するような、津波で言えば、遠く、遠くまで潮が引いた一瞬のような…そんな声だ。
「や、その……おい、姶良ぁ…彼女なんだったら最初からそう言えよぉ…」
「……だれが彼女だっ!!!」
柚木が溜めに溜めた怒りを一気に放出した。
……眠気は相変わらず酷いもんだったが、僕にも分かった。紺野氏は、僕が同級生にひどい扱いを受けたと思って(実際に相当ひどい扱いを受けたんだけど)昼行灯な風情の僕に代わって一泡ふかせてくれるつもりでいたのだろう。
どうせ日照不足なかんじのモヤシ野郎が来るだろうから脅しつけてやろうと思っていたら(性格を差し引けば)意外にも可憐な女子が怒りをあらわに詰め寄ってきた、と。
――うわ、なにその状況。最悪。
「楽しみにして1時間も早く来たのに!これ逃したら次の入荷はいつだと思ってんの!!最低っ!!」
紺野氏は、自分のMOGMOGが入ったバッグを背後に手繰り寄せた。そして後ろ手にジッパーを空けながら、柚木を刺激しない程度に私物をそっと放り込む。
「あっ……あんた、彼氏でもない男を寒空に11時間も放置して全然平気なのか!!」
「バイト代払ったもん!」
「手口は聞いたぞ、あんなのは詐欺だ!」
「じゃあ何、私に11時間寒風に晒されろっていうの!?」
「えっ……?」
「私の手入れが行き届いた肌が、荒れるじゃない!!」
三人の教室が、一瞬凍てついた。すごいな、女子のこういう論理展開……。
女の子次元の話は苦手だ。何を言っても『女の子常識』というあの不可解なルールを持ち込まれて何も言えなくなる。…紺野氏を横目で見る。社会人みたいだし、僕よりは女の子常識にメスを入れられるんじゃないか、と期待を込めて。言っちゃってくれ、僕には言えないあんなことやこんなことを!
「あ、あんたなぁ……」
絶句する紺野氏。……だめだ。多分この人も見た目程、女子に免疫はない。考えてみればこんな怖そうなひとに喧嘩を売る女子なんて聞いたことがない。
「何よ、なんか言いたいことがあるの!?」
「…え、えーとな……」
「さ…寒かった…すげぇ寒かった!お腹もすいた!」
我ながら情けない恨み言が、口を突いて出た。丁度いい塩梅に鼻水も垂れてきた。紺野氏がアテにならないなら、僕が時間を稼ぐしかない。どんだけ情けない手段だとしても。
「うっわ…」
これでうっすらと、本当にうっすらと抱いていた『柚木と恋愛フラグ』は、確実にへし折れたことだろう。そう思うとなんだか気が楽になってきた。
後ろを振り返ると、紺野氏が「設定開始」と表示されたノーパソをしまい始めている。あと数秒で駆け出すだろう。僕は紺野氏と目を見交わし、次の瞬間、出口に殺到した。
「あっ!こら待ちなさいっ!」
柚木が走って追いかけてきた。僕を一限前に呼んでおいて講義をさぼる気か。

喫茶「伯剌西爾」の古びたテーブルに落ち着く。何と読むのかは知らない。目の前には今日2杯目の珈琲。馥郁とした薫りが、ふわりと立ち昇る…などと、普段使わないような言葉で褒め称えたくなる。
大人の男である僕たちの全力疾走にぴったりついてきた柚木が、当然のようにケーキセットを手馴れたようすで注文している。きっと紺野氏におごらせる気だ。社会人は珈琲が一杯500円以上する喫茶店に、一日何度もふらりと入れるものなんだろうか。賭けてもいいがこのひとは『勝ち組の大人』だ。
「……キャラ選択画面だ」
紺野氏は息を弾ませて、ノーパソの画面を僕のほうに向けた。
―――いや、萌えキャラに興奮している時点で、勝ち組とは言えんかもしれない。
画面には、数種類の女の子が並んでいる。デフォルト設定のメイド、気が強そうな猫の耳をつけた女子、変な巻き髪のナース、むだに明るそうな、くい込むような体育着の女子…
僕は反射的にノーパソを閉じた。
「いやいやいや、こんなのがデスクトップをウロウロするとか社会生活に支障が」
「売れ筋のキャラは目立つところにあるんだよ!何ページが進めば大人しいのも出てくるから…とりあえずどれが好みだ!フォースで選べ!!」
「…フォース…」
どうやら紺野氏は、僕が思っているよりも年上らしい。
画面の下のほうに「1/2/3/4……」と数字が振ってある。まだいっぱいいるようだ。面倒だから数個飛ばして4をクリックする。4以降はメイド系のキャラクターが並んでいる。さすが人気ジャンルだ。居並ぶメイドさんは猫の耳やら肉球やらがついていたり、ミニスカートにニーソックス履いてたりする。日本人のメイド観は、アメリカ人の忍者に対する考え方と、よく似ているなぁ……。
そんなことを考えながらカーソルを右下まで漂わせ、ページを適当に切り替えようとしたそのとき、一人のメイドが目についた。
「ん…それか?」
カーソルの先を熱心に見つめていた紺野氏の表情が、わずかに変わった。
淡いすみれ色の、クラシカルなワンピース。少しだけフリルのついた、純白のエプロン。繊細なブロンドのストレート、その下に隠れて静かに光る、黒目がちなブルーグレーの瞳…よくあるといえば、よくある。でもなんというか、全体からかもし出される絵の雰囲気に、かすかに惹かれてマウスを止めた。
「…あ、これがいい。これに決めた」
「えー?もうちょっと見てから選ぼうよー。もっとカワイイのあるって絶対」
不満げにつぶやく柚木と見比べる。さっきから、自分のくせ気をさりげなく引っ張っている。髪の綺麗な子を見ると、柚木はいつも自分のくせ毛を引っ張るのだ。
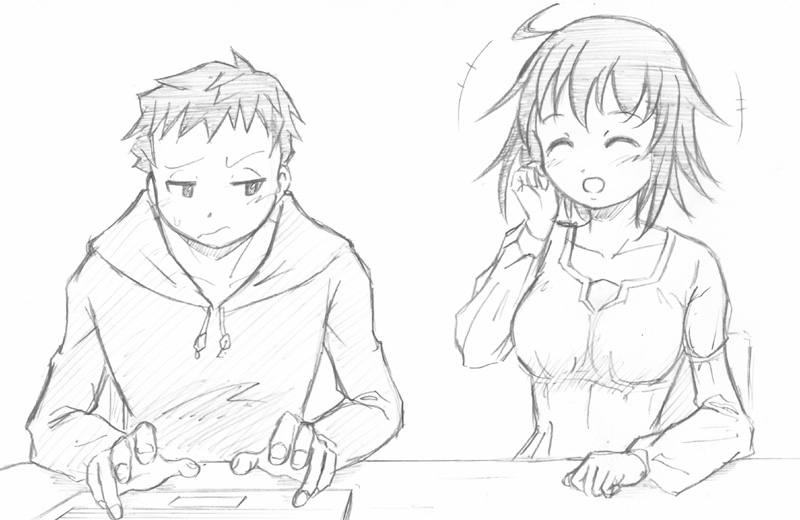
先刻、鬼の形相で僕らを追ってきた柚木は、今はびっくりするほど穏やかに、追加注文のシフォンケーキを頬張っている。
さっき紺野氏に、茶封筒を渡されてからというもの、ずっと機嫌がいい。…多分、紺野氏が弁償してくれたのだろう。…返さなきゃな。分割払いにしてもらってでも。…それにしても、不思議だ。
柚木の『上機嫌』の理由が、わからない。
一瞬、ちょっと多めに包んでもらったのかな、といぶかったけれど…
僕がそう思っているだけだが、柚木は『おごられる』のは好きみたいだけど、露骨に金を多めに渡したりしたら、侮辱と感じて機嫌を損ねると思う。あの子は実際に金銭がからむような生々しいやりとりが好きじゃない。要するに、金に困ってないのだ。
ふかふかのシフォンケーキをついばむ柚木の視線を追ってみる。時折、ちらっと紺野氏を見上げる。単なる物珍しさか、もっと別の理由か…僕には分からないし、詮索する理由もない。先刻盛大に鼻水を垂らした時点で、僕の恋愛フラグはへし折れたのだから。
「そうだ、姶良。カスタマイズしないのか?」
ぼーっとしているところに急に紺野氏に話しかけられ、慌てて視線を画面に戻す。
「キャラを選択してみろ」
さっき選んだメイドをクリックすると、メイドがアップで表示された。顔の横あたりに「カスタム」と書かれた赤いアイコンが光っている。
「服とか髪の色とか、あと瞳の色なんかをカスタマイズ出来るんだ」
瞳の色……。
「じゃ、変えようかな。瞳の色だけ…」
「…この色、あんまり好みじゃないか?」
…絡むなぁ。何なんだよこのひとは。
『瞳の色』をクリックすると、標準色パレットが表示される。僕はパレットの色を無視して『その他の色』を選択した。虹色のカラーテーブルが立ち上がる。…僕の入れる色は、もう決まっている。僕はカラーテーブルの番号入力欄にカーソルを置いた。
「76ccb3……と」
「それ、さっきのパスワード…」
「そう。僕の好きな色の番号」
彼女の瞳が、優しい空色に変わった。空に、すこし新緑を溶かしたような…淡いようで深い色合い。
チェレステ。ビアンキの伝統色。WEBの商品画像からひっぱって来た、僕の一番好きな色だ。
ビアンキはイタリアの自転車メーカー。車体に使われる緑がかった空色は「チェレステ(天空)」と呼ばれている。毎年ミラノの空の色を見ながら、職人が調合している、とロードバイクの雑誌で読んだ。この逸話を読むまでは「へんな色のチャリ」と思ってたけれど、今はビアンキのロードバイクが欲しくてたまらない。
で、腹が立つことに、柚木はビアンキのロードバイクを持っているのだ。
「おぉ、マルゲリータ王妃の、瞳の色だな」
…この色には、そういう説もある。紺野さんも、自転車が好きなんだろうか。
「……あぁ……まぁ……はい……」
ビアンキ持ってないくせにチェレステにこだわる自分がなんか妙に子供に思えて、気恥ずかしくなってきた。…だけど、チェレステの瞳に変えた瞬間、少女は、なんというか、冬の陽だまりみたいに透き通って、ほんのり温かくみえた。
言おうかどうしようか迷ったけれど、こういう乙女発言でいい目に遭ったことは一度もないので黙っておいた。
…そのあと、細かい色設定や性格設定や声設定など色々聞かれたけれど、面倒なので全部すっ飛ばしてデフォルトで通した。
『決定』ボタンを押すと、少女はくるりとスカートを翻して一回転して、ふわりとスカートのすそを持ち上げると、英国式に一礼した。
「お名前をください、ご主人さま」
イメージにぴったりな、透明で優しい声…!
人前で有頂天になりかけたけど、ぐっと堪えて名前の欄に『ビアンキ』と入力した。
「ビアンキです。…よろしくお願いします」
こうして、僕とビアンキの生活が始まった。

全て感想を見る:感想一覧
