| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
RSリベリオン・セイヴァ―
作者:伊波ヨシアキ
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動第一話「夜空の巫女」
前書き
一話です。あまりRSについて詳しく述べれませんが、二話から多分詳しい説明があると思います。
↓狼君のver3です。

↓狼君のver3です。

深夜
太陽が沈もうとも、街は眠らない。
世界有数の経済都市、東京メガロポリス。その都市は眠ることなく闇を嫌い、光で大いに闇を照らしていた。
地上には、居酒屋の明かりやビルの窓達の光、また、マンションや住宅街にも少なからず光が優しく燈っていた。今宵も、活気と人々の掛け声、乗り物の騒音でメガロポリスの夜は賑やかと活気に満ち溢れていた。
*
しかし、東京の「上空」だけは違った。地上とは対照的に首都の頭上を覆う漆黒の夜空は、静寂と月夜で包まれていた。
「まだ追ってくる……!?」
そんな、東京の夜空を一人のシルエットが何者かの追撃から逃れるかのように高速で飛行を続けていた。その姿は和服を纏った女性である。それは神社で神職を営む「巫女」を印象付ける姿である。
しかし、白い着物に紅い緋袴の様子に近いが、その姿は従来の巫女装束とは異なっていた。
それは和風を思わすレオタードで、月光にレオタードから食い込んだ足の付け根が照らされ、その優雅な姿は、男ならだれもが目を奪われる。そんなレオタードな巫女装束にまとい、月夜を舞うその姿は「かぐや姫」か「天女」を連想させるほどの華麗な美しさを見せる。しかし、そんな彼女の後から幾つかの機影が現れた。
「キサマ! その持っている刀をこちらによこせ!!」
そう叫ぶのはとあるISの集団であった。それも、所属の不明な機体であり、唯一確かなのは彼女らが纏うアーマーには「ファントムタスク」と書かれたエンブレムがされていた。
「どうしよう……この「RS」だけは絶対に渡すわけにはいかないのに……」
か弱い口調で巫女の少女は目の前の空をひたすら飛び続けた。その速さは巫女装束を纏っているだけで、ISのようにアーマーやブースターを装着していないのにもかかわらず、ISを上回るスピードであった。
「くそ! なんて速さだ!?」
「撃ち落せ! 何としてでもしてでもイレギュラー兵器を手に入れろ!? IS無くしてこの世界は成り立たないのだ!!」
先頭を飛ぶ指揮官機の指示によって彼女らは一斉にライフルを発砲、それを必死に掻い潜って巫女は逃走を維持する。
「……!?」
しかし、巫女の裾を銃弾が掠った。少女は、途端に生死の状況に追いやられていることをさらに実感し、激しい恐怖感にさらされることとなる。
「怖い……」
怖い、誰かに助けを求めたかった。しかし、今は彼女一人しか居ない。
――助けて、父様……!
「……ッ!?」
そのとき、目前を巨大な白い物体が遮った。旅客機である。
「うぅ……!」
巫女は、それをスレスレで間一髪に交わして旅客機の背中をギリギリに飛ぶが、目の前の巨大な垂直尾翼とぶつかってしまう。
肩に鈍く激しい痛みが走った。尾翼が彼女の肩を深く掠ったのだ。幸い大事には至らないが、その痛みに襲われてパニックに陥った。
「だ、誰か……誰か助けて……!?」
そのまま彼女はバランスを失い。徐々にメガロポリスが発する地上の光へ急降下していった。
世の中は嫌な事で出来ているものだ。だから、嬉しいことや楽しいことなんて自分が勝手に思っている幻想にすぎないのかもしれない。
それでも、人々はその幻想のために嫌なことに首を突っ込んで心身ともに傷ついたりするものなのだろうか?
いや、間違っても俺だけはそんなことはゴメンだね? 他人よりも自分が一番、愛よりもオカネ、仕事なんてクソくらえ、生涯は欲のため、まぁ……それが人間らしい人間なのかな?
少なくとも俺はそう思う。そう……思っていた。昨日までは。
あの少女と、謎の刀を手にするまでは、そう思い続けていた……
*
「旅客機とIS衝突寸前、か……」
朝、食卓でトーストを片手に新聞を読んでいた。そのなかである記事に目が留まったのだ。
「女性と思われしきシルエットが、旅客機正面に現れ間一髪のところで衝突は回避された……世の中、何が起こるのかわからないものだな?」
新聞を読み終えると、再びトーストを齧ってココアを流し込む。
俺の名は九条飛鳥、この家の長男として生を受けた「出来損ない」の愚息だ。
何が出来損ないだって? それは、文武両道にダメで、さらには等辺僕。そんな俺とは違って家族には優秀な奴らが多い。本当、神様って不公平なことをするよな?
だが、今日も何かを求めて俺は就活へ足を運ぶ、いつまでもウジウジしていたいところだが、はやく無職から脱しないと、俺の全てが完全に疑われてしまう……特に近所のご婦人たちに噂されるのはこれほど痛いことはない。
しかし、こんな俺でも普通校の藍越学園を無事に卒業したんだ。俺にだって運の一つぐらいはあるはずだ! そう、願って俺は玄関で靴を履くと、一直線に近場のハローワークへ向かった。
そのはずだった。しかし、俺はとても運が悪いようであった……
近場の職安にて、
「……ざけてんじゃねぇぞ!?」
若い怒号が室内に響き渡った。
俺は、顔を真っ赤にして席から立ちあがると、「男だから」といってさっきから小ばかにしてくる女職員へ怒鳴り上げた。
今まで小心者だったが、「親の顔が見てみたいものだわ?」とまで言われたら、流石に堪忍袋が爆発する。
「は、はい……」
職員の女は、半泣きで俺を見上げた。足はガタガタ震えだして……コイツ、失禁してんぞ?
よほど気の小さい女なのだろう? 中年のくせして。
「ケッ! やってられっか……」
唾を吐き、俺は安定書を出て行った。もう、こんなところは二度と来ないだろうな? いや、あんなことしちまったんだからもうここへは来れないだろう。しかし、自分がやったことには後悔はしない。
女尊男卑が始まったのは今更じゃない。ISと呼ばれる飛行パワードスーツが出来てから激しい性差別が広まったのだ。それは、男性が不遇されて代わりに女性が優遇されるという不条理な差別環境だ。よって、女達にとって俺たち男共は単なる労働力に過ぎない。楽したり、良い思いするのは皆女共ばかりだ……
「……」
帰り道を歩く中、俺は先ほどのことで益々イラつき始めた。何か、激しいことをして仕返ししてやりたくなる。何か……何か騒ぎを起こしてやりたい。そんな衝動に駆られてしまう。
しかし、そんな感情にまで上り詰めると、それは単なるテロリストと変わらない。もう止そう、こんなことばかり考えていると、性格が狂ってきそうだ……
何度か舌打ちした後、代わりにため息をしながら俺は家に向かう。けれど、どうせ家に帰ったって両親が口うるさく何かと説教をしてくるに違いない。
俺の親父は大手企業で働くリアリスト、お袋も弁護士を営むリアリスト、そんなお堅い夫婦に挟まれての俺はまさに地獄のような日常生活を送っている。
小学生のころからテストでは高得点を取れなどとプレッシャーをかけたり、高校生の時だって無理やり大学受験を受けさせられて案の定、落ちた。けど、それ以前に何をやっての上手いこといかない俺を見て、両親は徐々に俺に対して勘当の意を表してくる。
また、俺とは対照的で文武両道に優れた妹は、今年IS学園に入学して新たな青春を掴み取ろうとしているらしい。下らない。
俺は思いだせば思いだすほど嫌な感じになり、もう一度空を見上げてため息を漏らした。
「何か、良いこととかないかな……?」
そんな夢みたいなことに全てを期待することとなる俺は紛れもない哀れな人間の分類に入ることとなった。
さっきも言ったように、大学受験に関しては何度も落選し、それ以前に成績は下っ端、運動神経もゼロな俺には何の取り柄もないし何をやろうとしても自信はない。
「俺って……」
俺って、何のために生きてんだろ? 自分の存在理由にさえ疑問を持ち始めてしまった。
「はぁ……俺って、生きる価値なんてないのかも?」
そういじけながら俺は自宅の前に立った。そして、そこで考えた。
――どうせ、家に帰ったっていつもの生活しか待っていないんだ……
お堅い両親に板挟みされるよりもずっとマシな方法があるはずだ。俺は、徐々に落ち着きだして答えを求めだした。そして、出した答えが……
「……家出、しようかな?」
とはいえ、そんな度胸はあるはずもない。とりあえず家に一旦帰宅した。
玄関で「ただいま」も言わずに靴を脱いで自室へ向かう。学生のころはよく「ただいま」というのが癖になって帰ってきたら必ず言う台詞だったな? しかし、両親は俺が帰ってきても無反応だったけど……
「飛鳥か……」
階段へ向かう途中、廊下でトイレから出てきた親父とばったり会った。最悪のパターンだ。
「あ、ああ……」
俺は目を合わせずに階段を上る。
「……ところで、面接は受けることができたか?」
嫌味のように親父が言ってきた。俺は無視したいが、そうしたら後ろから鼻で笑われそうだから堂々と正直に言ってやった。
「ダメだった……」
そしてたら、
「フン、やはりな……」
聞き取れにくいような声で親父が呟いた。咄嗟に俺は舌打ちすると、親父は俺に向かって追い打ちをかける。
「大学受験に落ちたのはどこのどいつだ?」
アップで迫って指をさす親父には、毎度呆れる。おつむは一流でも、頭はガキ同然のようだ……
「はいはい……愚息である私ですよ?」
と、俺もそれ相応に言い返した。
「何だ! 父親に向かってその言い方は? 私がいてからこそ、お前は生きてゆけるのだぞ?」
またこれだ……親父は何かあると、「私がいてこそ!」と、いう口癖で俺を見下し始める。
「そもそも、お前は……」
――ああ、下らねぇ……
「……ウゼェ」
つぶやくと、俺はソッポを向いて自室へ向かった。
「こら! まだ話は終わってないぞ?」
親父が呼び止めるも、俺は軽くスルーした。
――冗談じゃねぇ! あんな糞リアリストの説教なんかこれ以上聞きたくねぇぜ……
俺はそう階段を上がって自室に入ろうとするが、目の前からいきなりドアが開き、勢いよく鼻先に激突してしまった。
「いってぇ~!」
「あ、兄ぃ?」
すりすりと鼻をなでる俺の前に一人の少女が部屋から出てきた。
コイツは俺の妹の九条舞香だ。俺よりも文武共に優秀で、今年から「IS学園」に通う予定らしい。
全く、どうして世の中に``まがいもの``なんか出てきちまったのかね?
IS、通称インフィニット・ストラトスは元々「宇宙開発」のために作られたパワードスーツである。
その性能は素晴らしく、兵器にも匹敵する代物であった。しかし、一つだけ欠点が存在する。
それは、「女」にしか扱うことのできないことであった。そのれに関し、世界は一時ISを欠如品として却下する予定であったが、それを許さない開発者の篠ノ之束は親友と共に「白騎士」事件というISによる暴走事件を起こした。
天災こと、篠ノ之束が世界各国の軍事施設へハッキングをかけ、日本めがけてミサイルをぶっ放してきやがった。そのミサイルの雨を、後に「白騎士」と呼ばれた親友がISを纏って上空のミサイルを全て撃ち落したのである。
これで世界は絶叫、ISを世界最強の兵器として評価し、ISの影響で世は女尊男卑と呼ばれる理不尽な世界へ変わっていってしまったのである……
「いきなり何しやがんだ?」
「アンタが、いきなり突っ込んできたんでしょ? 本当に邪魔ね」
と、高々と鼻で笑って舞香は部屋を後にした。
「ったく、本当に可愛くねぇアマだ……」
無論、俺の妹も今では立派な女尊男卑を掲げる高慢ちきなガキに成り下がっている。
「何よ! このダメ男。自殺しちゃえ!」
「んだとぉ?」
俺が怒るのを気に舞香は階段を駆け下りていった。
「何なんだよ……」
舌打ちすると、俺は部屋に入ってベッドに横たわった。横たわりながら目の前を見つめる白い天井を見続け、しばらくふて寝しようとした。けど、さっきからモヤモヤが残ってどうも落ち着いて寝付けない。俺は、ふとベッドから起き上がって再び部屋を出た。
「散歩、すっか……」
気を紛らわすため、俺はもう一度外へ出て帰ってきた道をもう一度歩いた。
*
――ああ、職安であんなことしなけりゃよかった……
今思えばとても後悔していた。一番家から近い職安で、頭に来たからってあんなことしでかしてしまえば、訴えられるか最低でも出入り禁止になってしまうだろう。
「ほかの職安で探すしかないか……?」
とはいえ、今日以外の職安はここから5キロ以上もある遠い地区にある。自転車で行くしか方法はない。
「あーあー……藍越学園を卒業したって、100パーセント就職できるってわけじゃねぇからな?」
偶然がごとく、補欠合格で運よく藍越に入学が成功し、そこでいろいろなことがありながらも学園生活を続かせて成績ギリギリでやっとの思いで卒業できた。
しかし。
「俺だけ特別出来が悪いのかな? それとも運の悪さ? どちらにせよ、俺のできの悪さは近所からも有名だったしな? ったく、高級住宅街とかにいるからだよな……
俺の家はそこそこな金持ちだったから、金持ち共が集う高級住宅街のエリア9に住んでいる。
IS社会になってから日本の富裕層が激しさを増し、貧困な人間たちによる犯罪が多発した、政府はメガロポリスを含む全都道府県を99カ所のエリアに分けた。
まるで階級社会のようで人道的にどうかと思われるが、被害の拡大を防ぐにはこれしか方法がない。何せ、自爆テロやレジスタンスによる抵抗などが相次いでいるため、危険を防ぐために厳重かつ細かくエリア化されるのだ。
公園まで歩き、俺はふとベンチに腰を下ろした。目の前に映る景色は女尊男卑なんて嘘のように男女が寄せあって仲良くしている。しかし、どうせ恋人とまではいかないんだろうな? きっと、男は女に遊ばれているのだろう? 今や、女の方が権力が強いからつき合ってといわれたら男の方は「YES」としか言えないだろう。
「……?」
そんなとき、
『助けて……』
「え?」
誰かは知らない見知らぬ声が、俺に囁くように呼びかけてきた。それも女の子の声だ。
「誰だ?」
呟き、辺りを見渡すが。先ほどのような光景が続くだけで俺に声をかけるような奴は一人もいなかった。
「……」
気のせいか、そう思って再びベンチへ深く腰を掛け直すのだが、
『誰か、助けて……』
「……?」
何度も俺に呼びかけてくる。いったいさっきから何なんだ?」
「何だよ……」
苛立ちながら俺はベンチから立ちあがってまた周辺を見る。けど、オレに近寄ってくる奴は居ない。
「さっきから何だ?」
『助けて……』
――しつこいな?
「何だよ? さっきから……え?」
その途端、俺の頭の中に山の光景が映った。それも知っている場所だ。そこから助け声が聞こえてくる。まさか、あそこに誰かが居るのか?
「……」
最近、夜更かしでゲームやパソコンのやりすぎで変な幻まで起こったのだろうか?
しかし、どうにも何度も空耳が続くとのは理解できない。俺の頭がまだ壊れていないのなら、あの声は実際に裏山から聞こえたのだ。
「……」
暇つぶしだ。そう俺は思って好奇心から裏山へ足を向けた。ニートゆえに腐るほど時間はある。どうせこのまま家に帰っても嫌な思いをするだけなんだし。
*
裏山は中学校の裏側にあるからそう呼ばれている。中学生のころはよくそこへ行って、頂上の丘まで登ったものだ。
「どこなんだ……?」
俺は息を切らしながら裏山の山道を歩いていた。裏山を歩くにつれて声が近づいてくる。
『助け……』
しかし、その声は徐々に弱っている。急がねば!
「どこだ! どこにいる?」
俺はつい声を出してしまった。まるで、本当に人を助けるかのように。
あわてた俺はいつの間にか走り回っていた。どうしてだろう? まだ本当に人が助けを求めているのかわからないのに……
だが、違った。今から起こる事実に、俺は頭の中が真っ白になったのだ。
「あぁ……っ!?」
茂みに横たわる人の姿を見た。それも見た途端にある一言が口に出た。
「綺麗だ……」
着物を着た美少女だ……それも着物は巫女を連想させるような和風のレオタード装束を纏っている。コスプレイヤーか? いや、ならどうしてこんな山の中で倒れているんだ?
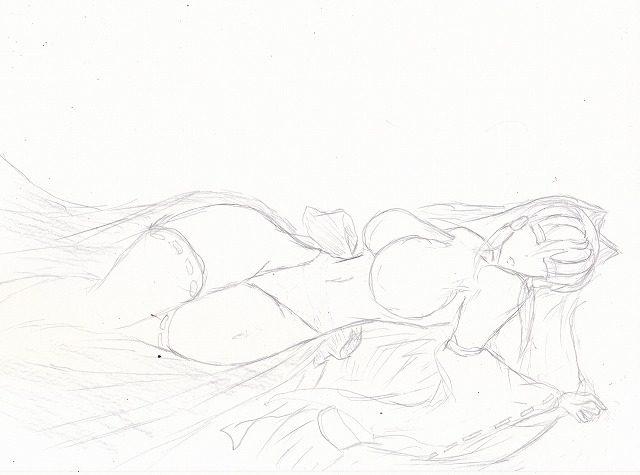
と、とにかく……俺は彼女へ駆け寄ると肩を持って揺さぶり始めた。ほのかな香りと共に柔らかい肌と生暖かい温盛が伝わってくる。
「大丈夫ですか!?」
「う、うぅ……!」
痛いところに触れたのか、彼女は意識を取り戻してゆっくりと目を覚ましだした。
「き、気が付いた?」
気が付いたはいいが、もし目を覚ましたら俺を見てなんていうか……大抵変質者だって言われそうだけど、いちよう訳ぐらいは言っておこう。
「こ、ここは……?」
ゆっくりと瞼を開け、視界に写る俺を見た。
――可愛い声してんな?
声優のようにかわいい声だった。そんな彼女が起き上がると、途端に肩の痛みに苦しみだしてしまう。
「あ、ごめん! さっき強くそこを揺さぶっちゃったから……」
「い、いいえ……自分の不注意で怪我をしただけですから……」
「そうか……え、怪我? 大丈夫なの?」
「肩の強打したと思われます。けど、そこまで酷い打撲では……」
「でも、血とか出てるかもしれない。待ってて? 手当てする物とか持ってくるから……」
そう立ち上がって彼女から背を向けたのだが、俺の手首を咄嗟に彼女が掴んだ。
「ま、待って……?」
「え、え?」
行き成り掴まれて俺は緊張と驚きが止まらなかった。何せ、女の子が俺の手を掴んだのだから。
「お、お願いです。しばらく、傍にいてください……」
――えぇー!?
途端に顔を赤くなった。無理もない。そんなことを女の子に言われるのなんて初めてだったからだ。
ま、彼女いない歴=年齢だから仕方がない。
「俺……九条、九条飛鳥」
しばらくは彼女の傍に座り、落ち着くまでいろいろと話を持ち掛けた。彼女は自分のことは詳しく話してくれなかったが、一様俺の話を聞いて安心している。俺も徐々に緊張がほぐれ、女の子相手でも落ち着いて会話ができるようになった。しかし、彼女のレオタードの下半身を見るたびに俺は興奮して息が荒くなりそうで、出来るだけ見ないように……なんて、できるはずがあるか!
「あ、あの……」
「え?」
「あまり見られると、恥ずかしいです……」
「ご、ごめん!」
しまった! やっぱり俺の下心は見抜かれていたか……
大概にややしばらくの気まずい沈黙が続いたが、そのうちに彼女の方から口を開けた。
「あの、一つお聞きしたいことが」
「な、なに?」
「もしかして……私の声を聞いてここまで来てくださったのですか?」
「え! じゃあ……もしかして、あの声は君が?」
「……」
彼女は黙って頷いた。
「あの、見つけてい頂いてありがとうございます。怪我の方は大したことはございませんので歩くことはできます」
と、彼女はゆっくりと立ち上がった。まだ痛むのか、肩に手を添えて歩き出す。
「ど、どうしたの?」
「ご迷惑をおかけすることはできませんので、それでは失礼致します……」
「あ、ちょ……」
引き留めようとした刹那。彼女から何かの音が聞こえた。かなり大きい。
「あ……」
ここまで大きくなるのなんて思わず、途端に顔を真っ赤にする彼女は恥ずかしさのあまり膝がガクッと落ちた。
「本当に、どうしたの……?」
「そ、その……お腹が……」
「腹痛かい?」
「い、いいえ……お腹の虫が……」
「虫? お腹に虫って……ああ、そういうこと?」
「うぅ……力が入らない」
少女は、空腹ゆえにこれ以上動けないらしい。
「まってて? 何か食べる物を持ってくるから」
俺は急いで近くのコンビニへ言ってパンやジュースを購入し、急いで裏山へ向かった。幸い、彼女はまだその場にいたようだ。いやぁ、偶然財布を持っていて助かった……
*
食べ物を目に彼女は無我夢中で食べ始めた。パンに齧りつき、ペットボトルのジュースをがぶ飲みする。
「ありがとうございますぅ~! 何とお礼を言ったらよいのかぁ……」
頬張りながら、うれし泣きしつつ俺に礼を言う彼女に俺は苦笑いを浮かべながら食べている彼女を見守った。
「い、いいって……」
――よほど腹が減ってたんだな?
しばらくして彼女は食べ終えると、俺に深々とお辞儀をした。
「本当に……本当に、助かりました。何とお礼を言ったらよいのか……私は、玄那 神社の巫女をしております天弓侍弥生と申します。先ほどはとんだ失礼を致しました。助けていただいたというのに名前もなのらず……」
ようやく彼女が自己紹介してくれた。
「いいんだよ? 誰だって見ず知らずの人に助けられれば、少し不安もあるさ? ところで、天弓侍さん……だっけ? 君はここで何をしていたの?」
「そ、それは……」
何か聞いてはいけないことだったのか、俺はとっさに口を押えた。
「あ、ごめん! 嫌なこと聞いたかな?」
「いいえ、そんなことは……ただ、重要な使いを任されておりましたから」
「重要な?」
「ごめんなさい。そこまでは言えなくて……」
「ま、いいさ? 俺には関係のないことなんだし、それよりも怪我の方は大丈夫?」
「はい、気を失っている間にも徐々に痛みが引いてきたのかもしれません」
「それはよかった」
「本当に、ありがとうございます」
そう言って今度こそ彼女は立ち上がった。
「傷の具合はいいの?」
「いつまでも長居をするわけにはいきません。それと、このご恩は一生忘れません。ありがとうございました……」
笑みを浮かべ俺に言う彼女は、女神のように美しく、可愛かった。
――か、可愛い……!
が、そのときだった。一発の銃声が俺たちの間に割りこんできたのだ。
「何だ!?」
俺は振り帰った。そこには木々を乱暴になぎ倒し、現れた数体の「IS」だった。
「あ、IS!?」
俺は当然驚いた。何せ、こんな山中にクマが出てもISが出るとは思わなかったのだ。
「くぅ……もう、追手が……!?」
彼女は表情を険しくさせ、ISに体を向けた。
「ついに見つけたぞ? キサマの持つ「RS」をこちらに渡してもらおう? そうすれば命までは奪わない」
先頭に立つISの女はそう巫女に言ってくるが。巫女の少女は断固として拒否する。
「なりません! このRSはこの世界をただすために必要なカギなのです」
「ケッ! 女のくせに、男の味方につきやがって……ん? そっちの男は何者だ!?」
荒っぽいISの女が俺の方へ睨み付けた。
「お、俺は……」
咄嗟に、「俺はただ彼女を助けただけだ……」と、言おうとしたが、ISに対してはどうにも言えなかった。
「まぁいい……お前を殺してでもRSは手に入る。安心しろ? 一人で死なせはしない。そこにいる男も後からお前の元へ行かせてやる」
残忍に笑む先頭のISは片手に持つアサルトライフルを彼女と俺に向けた。
「や、やば……!」
俺は無論そうつぶやく。しかし、彼女は肩の痛みをこらえて俺の片手を掴むと、勢いよく走りだした。ライフルの銃弾を潜り抜け、山道を駆けあがる。
「な、何がどうなってんだよ!?」
俺はつい自分だけ逃げ出したいと思った。だが、彼女は俺の手を引いて共に逃げてくれている。先ほどの俺の情もあったのだろうか、俺を見捨てずに一緒に逃げてくれている。
「……!」
俺は彼女の手を逆に引いた。俺が彼女の手を引いた形で先頭に立ち、共に逃げる。
「ついてきて! この山道なら少しは詳しいから?」
「は、はい……!」
息を切らしながらも、苦しさを忘れて俺は無我夢中で彼女の手を引っ張って逃げ回った。
とにかく俺は彼女と共に逃げまわった。くそ! こんなところで人生終わっちまうのかよ!?
どうしてこんなことになっちまうんだぁ~!?
太陽が沈もうとも、街は眠らない。
世界有数の経済都市、東京メガロポリス。その都市は眠ることなく闇を嫌い、光で大いに闇を照らしていた。
地上には、居酒屋の明かりやビルの窓達の光、また、マンションや住宅街にも少なからず光が優しく燈っていた。今宵も、活気と人々の掛け声、乗り物の騒音でメガロポリスの夜は賑やかと活気に満ち溢れていた。
*
しかし、東京の「上空」だけは違った。地上とは対照的に首都の頭上を覆う漆黒の夜空は、静寂と月夜で包まれていた。
「まだ追ってくる……!?」
そんな、東京の夜空を一人のシルエットが何者かの追撃から逃れるかのように高速で飛行を続けていた。その姿は和服を纏った女性である。それは神社で神職を営む「巫女」を印象付ける姿である。
しかし、白い着物に紅い緋袴の様子に近いが、その姿は従来の巫女装束とは異なっていた。
それは和風を思わすレオタードで、月光にレオタードから食い込んだ足の付け根が照らされ、その優雅な姿は、男ならだれもが目を奪われる。そんなレオタードな巫女装束にまとい、月夜を舞うその姿は「かぐや姫」か「天女」を連想させるほどの華麗な美しさを見せる。しかし、そんな彼女の後から幾つかの機影が現れた。
「キサマ! その持っている刀をこちらによこせ!!」
そう叫ぶのはとあるISの集団であった。それも、所属の不明な機体であり、唯一確かなのは彼女らが纏うアーマーには「ファントムタスク」と書かれたエンブレムがされていた。
「どうしよう……この「RS」だけは絶対に渡すわけにはいかないのに……」
か弱い口調で巫女の少女は目の前の空をひたすら飛び続けた。その速さは巫女装束を纏っているだけで、ISのようにアーマーやブースターを装着していないのにもかかわらず、ISを上回るスピードであった。
「くそ! なんて速さだ!?」
「撃ち落せ! 何としてでもしてでもイレギュラー兵器を手に入れろ!? IS無くしてこの世界は成り立たないのだ!!」
先頭を飛ぶ指揮官機の指示によって彼女らは一斉にライフルを発砲、それを必死に掻い潜って巫女は逃走を維持する。
「……!?」
しかし、巫女の裾を銃弾が掠った。少女は、途端に生死の状況に追いやられていることをさらに実感し、激しい恐怖感にさらされることとなる。
「怖い……」
怖い、誰かに助けを求めたかった。しかし、今は彼女一人しか居ない。
――助けて、父様……!
「……ッ!?」
そのとき、目前を巨大な白い物体が遮った。旅客機である。
「うぅ……!」
巫女は、それをスレスレで間一髪に交わして旅客機の背中をギリギリに飛ぶが、目の前の巨大な垂直尾翼とぶつかってしまう。
肩に鈍く激しい痛みが走った。尾翼が彼女の肩を深く掠ったのだ。幸い大事には至らないが、その痛みに襲われてパニックに陥った。
「だ、誰か……誰か助けて……!?」
そのまま彼女はバランスを失い。徐々にメガロポリスが発する地上の光へ急降下していった。
世の中は嫌な事で出来ているものだ。だから、嬉しいことや楽しいことなんて自分が勝手に思っている幻想にすぎないのかもしれない。
それでも、人々はその幻想のために嫌なことに首を突っ込んで心身ともに傷ついたりするものなのだろうか?
いや、間違っても俺だけはそんなことはゴメンだね? 他人よりも自分が一番、愛よりもオカネ、仕事なんてクソくらえ、生涯は欲のため、まぁ……それが人間らしい人間なのかな?
少なくとも俺はそう思う。そう……思っていた。昨日までは。
あの少女と、謎の刀を手にするまでは、そう思い続けていた……
*
「旅客機とIS衝突寸前、か……」
朝、食卓でトーストを片手に新聞を読んでいた。そのなかである記事に目が留まったのだ。
「女性と思われしきシルエットが、旅客機正面に現れ間一髪のところで衝突は回避された……世の中、何が起こるのかわからないものだな?」
新聞を読み終えると、再びトーストを齧ってココアを流し込む。
俺の名は九条飛鳥、この家の長男として生を受けた「出来損ない」の愚息だ。
何が出来損ないだって? それは、文武両道にダメで、さらには等辺僕。そんな俺とは違って家族には優秀な奴らが多い。本当、神様って不公平なことをするよな?
だが、今日も何かを求めて俺は就活へ足を運ぶ、いつまでもウジウジしていたいところだが、はやく無職から脱しないと、俺の全てが完全に疑われてしまう……特に近所のご婦人たちに噂されるのはこれほど痛いことはない。
しかし、こんな俺でも普通校の藍越学園を無事に卒業したんだ。俺にだって運の一つぐらいはあるはずだ! そう、願って俺は玄関で靴を履くと、一直線に近場のハローワークへ向かった。
そのはずだった。しかし、俺はとても運が悪いようであった……
近場の職安にて、
「……ざけてんじゃねぇぞ!?」
若い怒号が室内に響き渡った。
俺は、顔を真っ赤にして席から立ちあがると、「男だから」といってさっきから小ばかにしてくる女職員へ怒鳴り上げた。
今まで小心者だったが、「親の顔が見てみたいものだわ?」とまで言われたら、流石に堪忍袋が爆発する。
「は、はい……」
職員の女は、半泣きで俺を見上げた。足はガタガタ震えだして……コイツ、失禁してんぞ?
よほど気の小さい女なのだろう? 中年のくせして。
「ケッ! やってられっか……」
唾を吐き、俺は安定書を出て行った。もう、こんなところは二度と来ないだろうな? いや、あんなことしちまったんだからもうここへは来れないだろう。しかし、自分がやったことには後悔はしない。
女尊男卑が始まったのは今更じゃない。ISと呼ばれる飛行パワードスーツが出来てから激しい性差別が広まったのだ。それは、男性が不遇されて代わりに女性が優遇されるという不条理な差別環境だ。よって、女達にとって俺たち男共は単なる労働力に過ぎない。楽したり、良い思いするのは皆女共ばかりだ……
「……」
帰り道を歩く中、俺は先ほどのことで益々イラつき始めた。何か、激しいことをして仕返ししてやりたくなる。何か……何か騒ぎを起こしてやりたい。そんな衝動に駆られてしまう。
しかし、そんな感情にまで上り詰めると、それは単なるテロリストと変わらない。もう止そう、こんなことばかり考えていると、性格が狂ってきそうだ……
何度か舌打ちした後、代わりにため息をしながら俺は家に向かう。けれど、どうせ家に帰ったって両親が口うるさく何かと説教をしてくるに違いない。
俺の親父は大手企業で働くリアリスト、お袋も弁護士を営むリアリスト、そんなお堅い夫婦に挟まれての俺はまさに地獄のような日常生活を送っている。
小学生のころからテストでは高得点を取れなどとプレッシャーをかけたり、高校生の時だって無理やり大学受験を受けさせられて案の定、落ちた。けど、それ以前に何をやっての上手いこといかない俺を見て、両親は徐々に俺に対して勘当の意を表してくる。
また、俺とは対照的で文武両道に優れた妹は、今年IS学園に入学して新たな青春を掴み取ろうとしているらしい。下らない。
俺は思いだせば思いだすほど嫌な感じになり、もう一度空を見上げてため息を漏らした。
「何か、良いこととかないかな……?」
そんな夢みたいなことに全てを期待することとなる俺は紛れもない哀れな人間の分類に入ることとなった。
さっきも言ったように、大学受験に関しては何度も落選し、それ以前に成績は下っ端、運動神経もゼロな俺には何の取り柄もないし何をやろうとしても自信はない。
「俺って……」
俺って、何のために生きてんだろ? 自分の存在理由にさえ疑問を持ち始めてしまった。
「はぁ……俺って、生きる価値なんてないのかも?」
そういじけながら俺は自宅の前に立った。そして、そこで考えた。
――どうせ、家に帰ったっていつもの生活しか待っていないんだ……
お堅い両親に板挟みされるよりもずっとマシな方法があるはずだ。俺は、徐々に落ち着きだして答えを求めだした。そして、出した答えが……
「……家出、しようかな?」
とはいえ、そんな度胸はあるはずもない。とりあえず家に一旦帰宅した。
玄関で「ただいま」も言わずに靴を脱いで自室へ向かう。学生のころはよく「ただいま」というのが癖になって帰ってきたら必ず言う台詞だったな? しかし、両親は俺が帰ってきても無反応だったけど……
「飛鳥か……」
階段へ向かう途中、廊下でトイレから出てきた親父とばったり会った。最悪のパターンだ。
「あ、ああ……」
俺は目を合わせずに階段を上る。
「……ところで、面接は受けることができたか?」
嫌味のように親父が言ってきた。俺は無視したいが、そうしたら後ろから鼻で笑われそうだから堂々と正直に言ってやった。
「ダメだった……」
そしてたら、
「フン、やはりな……」
聞き取れにくいような声で親父が呟いた。咄嗟に俺は舌打ちすると、親父は俺に向かって追い打ちをかける。
「大学受験に落ちたのはどこのどいつだ?」
アップで迫って指をさす親父には、毎度呆れる。おつむは一流でも、頭はガキ同然のようだ……
「はいはい……愚息である私ですよ?」
と、俺もそれ相応に言い返した。
「何だ! 父親に向かってその言い方は? 私がいてからこそ、お前は生きてゆけるのだぞ?」
またこれだ……親父は何かあると、「私がいてこそ!」と、いう口癖で俺を見下し始める。
「そもそも、お前は……」
――ああ、下らねぇ……
「……ウゼェ」
つぶやくと、俺はソッポを向いて自室へ向かった。
「こら! まだ話は終わってないぞ?」
親父が呼び止めるも、俺は軽くスルーした。
――冗談じゃねぇ! あんな糞リアリストの説教なんかこれ以上聞きたくねぇぜ……
俺はそう階段を上がって自室に入ろうとするが、目の前からいきなりドアが開き、勢いよく鼻先に激突してしまった。
「いってぇ~!」
「あ、兄ぃ?」
すりすりと鼻をなでる俺の前に一人の少女が部屋から出てきた。
コイツは俺の妹の九条舞香だ。俺よりも文武共に優秀で、今年から「IS学園」に通う予定らしい。
全く、どうして世の中に``まがいもの``なんか出てきちまったのかね?
IS、通称インフィニット・ストラトスは元々「宇宙開発」のために作られたパワードスーツである。
その性能は素晴らしく、兵器にも匹敵する代物であった。しかし、一つだけ欠点が存在する。
それは、「女」にしか扱うことのできないことであった。そのれに関し、世界は一時ISを欠如品として却下する予定であったが、それを許さない開発者の篠ノ之束は親友と共に「白騎士」事件というISによる暴走事件を起こした。
天災こと、篠ノ之束が世界各国の軍事施設へハッキングをかけ、日本めがけてミサイルをぶっ放してきやがった。そのミサイルの雨を、後に「白騎士」と呼ばれた親友がISを纏って上空のミサイルを全て撃ち落したのである。
これで世界は絶叫、ISを世界最強の兵器として評価し、ISの影響で世は女尊男卑と呼ばれる理不尽な世界へ変わっていってしまったのである……
「いきなり何しやがんだ?」
「アンタが、いきなり突っ込んできたんでしょ? 本当に邪魔ね」
と、高々と鼻で笑って舞香は部屋を後にした。
「ったく、本当に可愛くねぇアマだ……」
無論、俺の妹も今では立派な女尊男卑を掲げる高慢ちきなガキに成り下がっている。
「何よ! このダメ男。自殺しちゃえ!」
「んだとぉ?」
俺が怒るのを気に舞香は階段を駆け下りていった。
「何なんだよ……」
舌打ちすると、俺は部屋に入ってベッドに横たわった。横たわりながら目の前を見つめる白い天井を見続け、しばらくふて寝しようとした。けど、さっきからモヤモヤが残ってどうも落ち着いて寝付けない。俺は、ふとベッドから起き上がって再び部屋を出た。
「散歩、すっか……」
気を紛らわすため、俺はもう一度外へ出て帰ってきた道をもう一度歩いた。
*
――ああ、職安であんなことしなけりゃよかった……
今思えばとても後悔していた。一番家から近い職安で、頭に来たからってあんなことしでかしてしまえば、訴えられるか最低でも出入り禁止になってしまうだろう。
「ほかの職安で探すしかないか……?」
とはいえ、今日以外の職安はここから5キロ以上もある遠い地区にある。自転車で行くしか方法はない。
「あーあー……藍越学園を卒業したって、100パーセント就職できるってわけじゃねぇからな?」
偶然がごとく、補欠合格で運よく藍越に入学が成功し、そこでいろいろなことがありながらも学園生活を続かせて成績ギリギリでやっとの思いで卒業できた。
しかし。
「俺だけ特別出来が悪いのかな? それとも運の悪さ? どちらにせよ、俺のできの悪さは近所からも有名だったしな? ったく、高級住宅街とかにいるからだよな……
俺の家はそこそこな金持ちだったから、金持ち共が集う高級住宅街のエリア9に住んでいる。
IS社会になってから日本の富裕層が激しさを増し、貧困な人間たちによる犯罪が多発した、政府はメガロポリスを含む全都道府県を99カ所のエリアに分けた。
まるで階級社会のようで人道的にどうかと思われるが、被害の拡大を防ぐにはこれしか方法がない。何せ、自爆テロやレジスタンスによる抵抗などが相次いでいるため、危険を防ぐために厳重かつ細かくエリア化されるのだ。
公園まで歩き、俺はふとベンチに腰を下ろした。目の前に映る景色は女尊男卑なんて嘘のように男女が寄せあって仲良くしている。しかし、どうせ恋人とまではいかないんだろうな? きっと、男は女に遊ばれているのだろう? 今や、女の方が権力が強いからつき合ってといわれたら男の方は「YES」としか言えないだろう。
「……?」
そんなとき、
『助けて……』
「え?」
誰かは知らない見知らぬ声が、俺に囁くように呼びかけてきた。それも女の子の声だ。
「誰だ?」
呟き、辺りを見渡すが。先ほどのような光景が続くだけで俺に声をかけるような奴は一人もいなかった。
「……」
気のせいか、そう思って再びベンチへ深く腰を掛け直すのだが、
『誰か、助けて……』
「……?」
何度も俺に呼びかけてくる。いったいさっきから何なんだ?」
「何だよ……」
苛立ちながら俺はベンチから立ちあがってまた周辺を見る。けど、オレに近寄ってくる奴は居ない。
「さっきから何だ?」
『助けて……』
――しつこいな?
「何だよ? さっきから……え?」
その途端、俺の頭の中に山の光景が映った。それも知っている場所だ。そこから助け声が聞こえてくる。まさか、あそこに誰かが居るのか?
「……」
最近、夜更かしでゲームやパソコンのやりすぎで変な幻まで起こったのだろうか?
しかし、どうにも何度も空耳が続くとのは理解できない。俺の頭がまだ壊れていないのなら、あの声は実際に裏山から聞こえたのだ。
「……」
暇つぶしだ。そう俺は思って好奇心から裏山へ足を向けた。ニートゆえに腐るほど時間はある。どうせこのまま家に帰っても嫌な思いをするだけなんだし。
*
裏山は中学校の裏側にあるからそう呼ばれている。中学生のころはよくそこへ行って、頂上の丘まで登ったものだ。
「どこなんだ……?」
俺は息を切らしながら裏山の山道を歩いていた。裏山を歩くにつれて声が近づいてくる。
『助け……』
しかし、その声は徐々に弱っている。急がねば!
「どこだ! どこにいる?」
俺はつい声を出してしまった。まるで、本当に人を助けるかのように。
あわてた俺はいつの間にか走り回っていた。どうしてだろう? まだ本当に人が助けを求めているのかわからないのに……
だが、違った。今から起こる事実に、俺は頭の中が真っ白になったのだ。
「あぁ……っ!?」
茂みに横たわる人の姿を見た。それも見た途端にある一言が口に出た。
「綺麗だ……」
着物を着た美少女だ……それも着物は巫女を連想させるような和風のレオタード装束を纏っている。コスプレイヤーか? いや、ならどうしてこんな山の中で倒れているんだ?
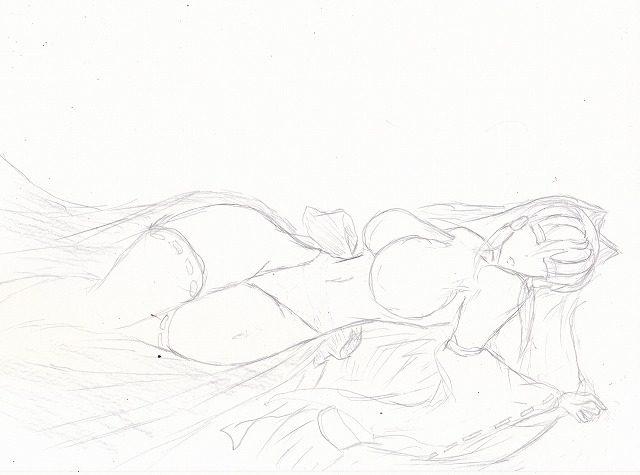
と、とにかく……俺は彼女へ駆け寄ると肩を持って揺さぶり始めた。ほのかな香りと共に柔らかい肌と生暖かい温盛が伝わってくる。
「大丈夫ですか!?」
「う、うぅ……!」
痛いところに触れたのか、彼女は意識を取り戻してゆっくりと目を覚ましだした。
「き、気が付いた?」
気が付いたはいいが、もし目を覚ましたら俺を見てなんていうか……大抵変質者だって言われそうだけど、いちよう訳ぐらいは言っておこう。
「こ、ここは……?」
ゆっくりと瞼を開け、視界に写る俺を見た。
――可愛い声してんな?
声優のようにかわいい声だった。そんな彼女が起き上がると、途端に肩の痛みに苦しみだしてしまう。
「あ、ごめん! さっき強くそこを揺さぶっちゃったから……」
「い、いいえ……自分の不注意で怪我をしただけですから……」
「そうか……え、怪我? 大丈夫なの?」
「肩の強打したと思われます。けど、そこまで酷い打撲では……」
「でも、血とか出てるかもしれない。待ってて? 手当てする物とか持ってくるから……」
そう立ち上がって彼女から背を向けたのだが、俺の手首を咄嗟に彼女が掴んだ。
「ま、待って……?」
「え、え?」
行き成り掴まれて俺は緊張と驚きが止まらなかった。何せ、女の子が俺の手を掴んだのだから。
「お、お願いです。しばらく、傍にいてください……」
――えぇー!?
途端に顔を赤くなった。無理もない。そんなことを女の子に言われるのなんて初めてだったからだ。
ま、彼女いない歴=年齢だから仕方がない。
「俺……九条、九条飛鳥」
しばらくは彼女の傍に座り、落ち着くまでいろいろと話を持ち掛けた。彼女は自分のことは詳しく話してくれなかったが、一様俺の話を聞いて安心している。俺も徐々に緊張がほぐれ、女の子相手でも落ち着いて会話ができるようになった。しかし、彼女のレオタードの下半身を見るたびに俺は興奮して息が荒くなりそうで、出来るだけ見ないように……なんて、できるはずがあるか!
「あ、あの……」
「え?」
「あまり見られると、恥ずかしいです……」
「ご、ごめん!」
しまった! やっぱり俺の下心は見抜かれていたか……
大概にややしばらくの気まずい沈黙が続いたが、そのうちに彼女の方から口を開けた。
「あの、一つお聞きしたいことが」
「な、なに?」
「もしかして……私の声を聞いてここまで来てくださったのですか?」
「え! じゃあ……もしかして、あの声は君が?」
「……」
彼女は黙って頷いた。
「あの、見つけてい頂いてありがとうございます。怪我の方は大したことはございませんので歩くことはできます」
と、彼女はゆっくりと立ち上がった。まだ痛むのか、肩に手を添えて歩き出す。
「ど、どうしたの?」
「ご迷惑をおかけすることはできませんので、それでは失礼致します……」
「あ、ちょ……」
引き留めようとした刹那。彼女から何かの音が聞こえた。かなり大きい。
「あ……」
ここまで大きくなるのなんて思わず、途端に顔を真っ赤にする彼女は恥ずかしさのあまり膝がガクッと落ちた。
「本当に、どうしたの……?」
「そ、その……お腹が……」
「腹痛かい?」
「い、いいえ……お腹の虫が……」
「虫? お腹に虫って……ああ、そういうこと?」
「うぅ……力が入らない」
少女は、空腹ゆえにこれ以上動けないらしい。
「まってて? 何か食べる物を持ってくるから」
俺は急いで近くのコンビニへ言ってパンやジュースを購入し、急いで裏山へ向かった。幸い、彼女はまだその場にいたようだ。いやぁ、偶然財布を持っていて助かった……
*
食べ物を目に彼女は無我夢中で食べ始めた。パンに齧りつき、ペットボトルのジュースをがぶ飲みする。
「ありがとうございますぅ~! 何とお礼を言ったらよいのかぁ……」
頬張りながら、うれし泣きしつつ俺に礼を言う彼女に俺は苦笑いを浮かべながら食べている彼女を見守った。
「い、いいって……」
――よほど腹が減ってたんだな?
しばらくして彼女は食べ終えると、俺に深々とお辞儀をした。
「本当に……本当に、助かりました。何とお礼を言ったらよいのか……私は、
ようやく彼女が自己紹介してくれた。
「いいんだよ? 誰だって見ず知らずの人に助けられれば、少し不安もあるさ? ところで、天弓侍さん……だっけ? 君はここで何をしていたの?」
「そ、それは……」
何か聞いてはいけないことだったのか、俺はとっさに口を押えた。
「あ、ごめん! 嫌なこと聞いたかな?」
「いいえ、そんなことは……ただ、重要な使いを任されておりましたから」
「重要な?」
「ごめんなさい。そこまでは言えなくて……」
「ま、いいさ? 俺には関係のないことなんだし、それよりも怪我の方は大丈夫?」
「はい、気を失っている間にも徐々に痛みが引いてきたのかもしれません」
「それはよかった」
「本当に、ありがとうございます」
そう言って今度こそ彼女は立ち上がった。
「傷の具合はいいの?」
「いつまでも長居をするわけにはいきません。それと、このご恩は一生忘れません。ありがとうございました……」
笑みを浮かべ俺に言う彼女は、女神のように美しく、可愛かった。
――か、可愛い……!
が、そのときだった。一発の銃声が俺たちの間に割りこんできたのだ。
「何だ!?」
俺は振り帰った。そこには木々を乱暴になぎ倒し、現れた数体の「IS」だった。
「あ、IS!?」
俺は当然驚いた。何せ、こんな山中にクマが出てもISが出るとは思わなかったのだ。
「くぅ……もう、追手が……!?」
彼女は表情を険しくさせ、ISに体を向けた。
「ついに見つけたぞ? キサマの持つ「RS」をこちらに渡してもらおう? そうすれば命までは奪わない」
先頭に立つISの女はそう巫女に言ってくるが。巫女の少女は断固として拒否する。
「なりません! このRSはこの世界をただすために必要なカギなのです」
「ケッ! 女のくせに、男の味方につきやがって……ん? そっちの男は何者だ!?」
荒っぽいISの女が俺の方へ睨み付けた。
「お、俺は……」
咄嗟に、「俺はただ彼女を助けただけだ……」と、言おうとしたが、ISに対してはどうにも言えなかった。
「まぁいい……お前を殺してでもRSは手に入る。安心しろ? 一人で死なせはしない。そこにいる男も後からお前の元へ行かせてやる」
残忍に笑む先頭のISは片手に持つアサルトライフルを彼女と俺に向けた。
「や、やば……!」
俺は無論そうつぶやく。しかし、彼女は肩の痛みをこらえて俺の片手を掴むと、勢いよく走りだした。ライフルの銃弾を潜り抜け、山道を駆けあがる。
「な、何がどうなってんだよ!?」
俺はつい自分だけ逃げ出したいと思った。だが、彼女は俺の手を引いて共に逃げてくれている。先ほどの俺の情もあったのだろうか、俺を見捨てずに一緒に逃げてくれている。
「……!」
俺は彼女の手を逆に引いた。俺が彼女の手を引いた形で先頭に立ち、共に逃げる。
「ついてきて! この山道なら少しは詳しいから?」
「は、はい……!」
息を切らしながらも、苦しさを忘れて俺は無我夢中で彼女の手を引っ張って逃げ回った。
とにかく俺は彼女と共に逃げまわった。くそ! こんなところで人生終わっちまうのかよ!?
どうしてこんなことになっちまうんだぁ~!?
後書き
予告
謎のIS集団に追われる身となった俺と美少女巫女の天弓侍弥生。ファントムタスクって何だよ!?
それに、RSっていったい……?
次回、RSリベリオン・サーヴァー
第二話「男の決意」
ページ上へ戻る謎のIS集団に追われる身となった俺と美少女巫女の天弓侍弥生。ファントムタスクって何だよ!?
それに、RSっていったい……?
次回、RSリベリオン・サーヴァー
第二話「男の決意」
全て感想を見る:感想一覧
