| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
ソードアート・オンライン 舞えない黒蝶のバレリーナ (現在修正中)
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。 ページ下へ移動第一部 ―愚者よ、後ろを振り返ってはならない
第1章
第1話 黒猫
前書き
2014.12.25
2枚目の挿絵を差し替えました。
2015.08.09
修正済
2枚目の挿絵を差し替えました。
2015.08.09
修正済
――――――――2009年9月。
男は、車を動かすべくキーを回した。同時にモーターが動きだし、車体全体が小刻みに震え始める。
日はとっくの前に落ちていた。先ほど居た建物の明かりがわずかばかりにこぼれてきているが、車のヘッドライトだけが今は頼りだ。
目の前には鬱蒼とした森林だけが広がっていて、人間の介入を拒絶しているようにも感じられてしまう。それがひどく、男を不安にさせた。
すると、そんなものを打ち消すように後部座席のドアが開いた。同時に見えた人物の姿を確認して、無意識に顔がほころぶ。
「手伝おうか?」
「いいえ、大丈夫。ありがとう」
そう言いながら、今しがたドアを開けた女性――――男の妻である彼女は、朗らかに微笑んだ。そして車内に上半身だけを入れ、抱きかかえている子どもを、気を使っているのがありありと分かる程丁寧に、チャイルドシートへ降ろす。彼女はシートベルトが着いたかをしっかりと確かめると反対側へ周り込み、後ろのドアをゆっくりと開け、車内に乗り込んだ。
そんな愛しい妻の姿を目で追いながら口を開く。
「……ずいぶん嬉しそうだね?」
「ええ。だって、2人で描いた夢へまた一歩近づいたのよ」
「それもこれも……、“彼”のおかげだな」
「ええ、そうね。まだあんな歳なのに……」
途端憂いと情けなさが入り混じったような光を帯びさせ、妻は目を細める。苦しさが溶け込んだような表情をする妻をルームミラー越しに見た男は、唇を引き締めてすでに装着していたシートベルトを外した。体ごと後ろへ乗り出し、優しく脆いその女性のしっとりとした肌に、自身のゴツゴツとした手を寄せる。視線が絡み合い、もう少しで吐き出す息が掛かってしまいそうだ。
「気にすることない。“彼”は強い。良く出来た子だよ」
「“彼”は特別な才能を持っているのよ。私たちが思っているほど、簡単な子ではないわ。いつか、何かが起きそうで怖いのよ……」
「……ならば、そうならないように見守っていよう。この子の成長と一緒に」
強い口調で言い切ると、不安そうに瞳の奥を揺らしながらも彼女はコクリと頷いた。男は微笑み、妻の頬をもう一度撫でると、チラリと横で眠る息子を見る。
ああ、愛おしい。決して失いたくない。
腹の底から湧き上がる強い思い。グラグラと視界が揺れそうなほど、体中の血液が駆け巡る。
……今度こそ、守るのだ。自らが未熟なせいで犯してしまった罪は、もう消せはしないけれど。
男は妻に悟られぬよう拳を握りしめると、体を前へ戻した。体勢を整え、再びシートベルトを締め――――そこでハッと今朝の会話を思い出す。
「そうだ。翠さんはどうなった?」
「ああ、そうそう! あなたには言っていなかったわね」
彼女の様子を窺いながら話題を変えると、打って変って空気が明るくなった。この切り替えの早さが彼女の良い所だ、と男は苦笑いを浮かべる。しかし彼女は男の下らない心情に気付く様子は無く、代わりに身に纏う雰囲気を一層優しいものに変えると、まるで自分のことのように穏やかな声音で、
「さっき翠の旦那さんからメールが来たのだけれど、無事赤ちゃんが生まれたんですって。双子の可愛い女の子だそうよ」
「良かったじゃないか! ずいぶん心配していたからな」
「ええ! 本当によかったわ。……名前ももう決まっているらしくて、上の子が直葉ちゃん、下が紅葉 ちゃんですって」
彼女は徐に鞄を探り、携帯電話の画面を開いて寄越してきた。数センチ程の長方形のそこには、2人の赤ん坊の姿が映しだされている。画面の光のせいなのか、それともその神秘的な雰囲気のせいなのか、妙に目が痛い。
「それでね、その子たちを見ていたら、……和人も来月で1歳なんだなーって思って」
ふわりと口元に笑みを浮かべながら、彼女はチャイルドシートですやすやと気持ちよさそうに眠る息子の頭を撫でる。和人は嬉しそうに、妻の手に顔を摺り寄せた。
男はそんな愛する2人の光景に、心が和むのを感じながら、視線を前へ戻した。そして、アクセルを踏み込む。
「早く、埼玉に戻ろうな」
「はい。早く、翠の幸せそうな顔が見たいわ」
その返答に、男は僅かに首を縦に振った。まあ、少しの異変も見逃すまいと、フロントガラスの向こう側を睨むように見ながらだが。
そして、もうすぐ下り坂だな、なんて思いつつブレーキを踏み込んだ――――つもりだった。
「――――っ!?」
すぐその異変に気が付いた。ガラスの向こう側ではない、……車自体に。
しかし、それを否定すべく何度もブレーキを踏む。ガタガタと鈍い音が響いているが、構わず同じ動作を何度も、何度もする。
すると、後部座席に座る彼女も異変に気が付いたようで、「どうしたの!?」と悲鳴に近い声をあげた。けれども、それに応える余裕はない。
スピードは一向に変わらない。むしろ、坂に入ったせいか、少しずつ速くなっていく。
それでも、諦めずに踏む。意味がないと分かりつつも、サイドブレーキを思いきり引いた。
――――やっと。
やっと、なんだ。
こんなところで……。
目の前に、カーブが見えた。その瞬間、思考が弾け飛ぶ。
白で塗りつぶされてしまう。
――――そして、そんな最中でも頭に浮かぶのは、和人と、“も う 1 人 の 我 が 子 ”の姿だった……。
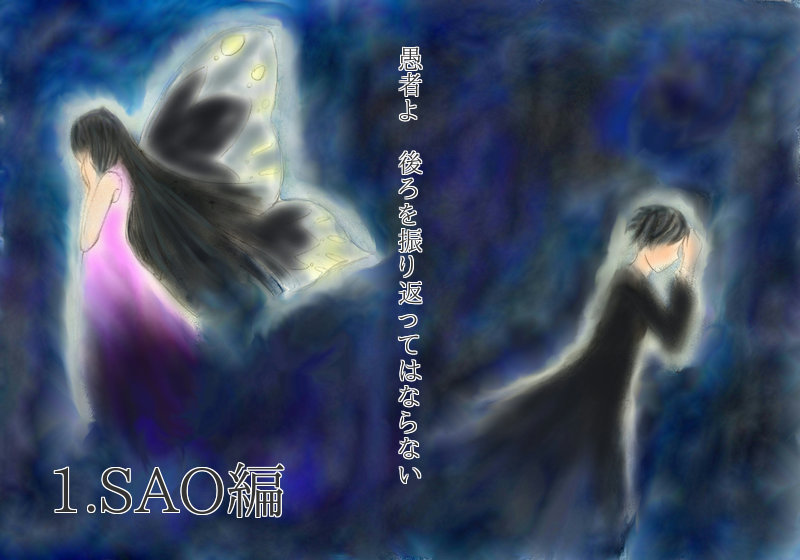
――――――――――――――――――――――――――――
愚者よ、後ろを振り返ってはならない
たとえ、己の身を滅ぼす結果になろうとも
――――――――――――――――――――――――――――
――――――――2018年 12月。
日本最大の芸術専門の大学。その隣には、付属の芸術教室があり、バレエや演劇、歌唱、絵画などを部門別に習うことが出来る。
そこに、私――――桐ケ谷紅葉は通っている。
私はバレエと演劇部門を掛け持ちしているのだが、今日も大人と混じって――――別に小学生のみのクラスもあるのだが――――バレエのレッスンをしていた。
そして今、来年の7月にある発表会での役が発表されたのだが――――少し、……否、かなり気まずい。
「――――紅葉ちゃんがオデット。いい?異論はないですよね?」
「……まぁ、小学3年生にもかかわらず、このクラスで一番上手ですし」
――――このクラス。
そう、ここは私以外全員が大人。しかも、将来を有望視されている人たちばかりだ。
その中に、私一人、小学生。
それはとても不思議な光景で、なんで私だけ、と口には出さずとも思っている。そして、天地がひっくりかえったとしても、この空間で浮いた存在であることは絶対に変わらない、とも理解している。
ちなみにオデットとは、『白鳥の湖』に出でくる、魔法によって白鳥に変えられてしまったお姫様のこと。
この役は、オディールという役との1人2役をしなければいけない、とても難しい役なのだ。……単刀直入に、簡潔に言ってしまえば――――主人公になる。
だから、何度でも言おう。
なんで私なの、と。
普通なら、小学生と大人では出来るハズがないのだ。身長差があり過ぎるのだから。
けれども、幸か不幸か私は同年代の子たちよりも頭一つ分以上身長が高い。1つ年上の兄よりもちょっと高いのだ。よって一緒に舞台の上に立っていても、ギリギリ通用してしまうのだった。
……けれど、問題はそこではないのだ。
この役は、非常に難しい役なハズなのだ。とても高度なテクニックを要求されるから、到底私みたいな子どもが出来るはずがない。本来なら、私よりずっと経験のある人がするべきなのに……。
「じゃあ、これでレッスンは終わりです」
私が、拒めるわけがない。
そんな意味を込めながら視線を先生に送っていると、いつのまにか話がまとまっていたようで、その一声でレッスン終了になってしまった。
私は部屋の隅に畳んで置いていたカーディガンを取りに行こうと、大人たちの波に逆らって歩く。するとその途中で、立ち止まって話す2人の女性とすれ違った。
「――――あの子、演劇部門の方でも主役になったそうよ」
ドクン。心臓が飛び上がった。
グラグラと地面が揺れた気がして、思わず歩みが止まる。……しかし、その間も容赦なく会話は続いていく。
「えぇ~? 本当?」
「うんうん、本当。そろそろ芸能界からお声が掛かるんじゃないかって噂もあるし」
「まったく――――恐ろしい子ね」
「本当ねぇ。……しかも、あの子いくつ教室に通っていると思う?」
片方の女性が立ちすくむ私をチラリと見やる。その口元が弧を描いた。
……ああ、近くにいるのを分かっているのに会話しているのだ。わざと聞こえるように話して、なんて嫌らしい。
「え……、バレエと演劇だけじゃないの?」
「それが違うみたいなのよね~。絵画とか、あと弓道と剣道も他の教室で習っているみたい」
「ええー、嘘ぉー。じゃあ、いつ勉強しているの? 頭も凄く良いって噂でしょ」
「それはアレよ。“天才少女”だからねぇ」
「まさに文武両道ってことかぁ。あーあ、私も才能が欲しかったぁ」
「リノは今のままでも十分素敵だよ。“普通”が一番!」
「そうね~!」
きゃらきゃらと、笑い声が耳を劈く。
私は好きでやっているのに。どうしてこんな事を言われなければいけないのだ。
こうやって疎まれ、あるいはその逆に異常にすり寄ってくる人たちもいる。しかも厄介なことに、全員に当てはまるものは上辺だけの好意だ。
こうやって自分のプライドが傷つけられれば、わざと聞こえるように嫌味を言うくせに、普段は優しい大人の仮面を身に着けている。いっそ女優や俳優にでもなってしまえばいいのに。きっとお似合いだ。
そう内心毒を吐いてしまうくらい、私の周りにいる人たちはみんな、気持ちの悪い好意を顔に張り付けている。
芸術教室の人たちだけじゃない。クラスの子も、学校の先生も、近所の人たちも。
けれど私は、そんなものはいらない。
私は、“普通”なのだから。
……“普通”、なのに。
――――他の同い年の子達と、何にも変わらないのに!!
石のような足を引きずりながら歩き出した。まるで背後の笑い声に追い立てられているみたい。……私は、何も悪くはないはずなのに。
鬱々とした気分のまま教室の扉を開けて廊下に出た。カーディガンの上から、ヒヤリとした空気が肌を刺す。なんとなく、この空間までもが自分の敵のような気がしてきた。圧倒的な破壊力を持った強烈で鋭い竜巻が、私の胸に穴を空けて行き、ぽっかりと空いたそこからドロドロと液体が漏れ出て行く。突き抜ける痛みと強い漂流感に、ぎゅっと両手を握りしめた。顔の筋肉が強張り、あまりの空虚さに足を進めることが出来ない。足が樹の幹になったみたいだ。筋肉が仕事を忘れたと言わんばかりに動かなかった。
濁流が治まるのをただひたすらに耐えようと、私は背中を丸める。
――――しかしその時、打ち消すように肩に軽い衝撃があった。
「もーみじっ」
「あ……、待っていてくれたの?」
サッと、目の前の景色が晴れた気がした。それはもう、太陽の光が差し込んできたみたいに。体の硬直が嘘のように、すうっと消える。
……私の周りには嘘をロウで固めたような人たちばかりだけれど、こうして純粋な好意を向けてくれる人もいるんだ。
私は、胸がじんわりと温かくなるのをハッキリと感じながら、目の前の人物――――如月幸歌をまじまじとみた。
幸歌は、笑窪がよく似合う笑顔を浮かべながら、
「って言っても、私もさっきレッスン終わったばかりだよ?」
と、イタズラっぽく言った。
私は、その笑顔に釣られるようにして笑う。
幸歌は、私より3つ年上の小学6年生にもかかわらず、対等に接してくれる。親友だと、胸を張ってはっきりと宣言できる存在でもあるだろう。
彼女は少し前まではバレエ部門にも入っていたので、そのつながりで仲が良くなった。今でこそ声楽部門の方に専念するためバレエはやめてしまっているが、関係が崩れたわけではない。
むしろつながっている糸が、太く、強くなったようだ。
そして、今日もいつものように、レッスン終わりで疲れたと悲鳴を上げている体をなだめながら、2人で廊下を歩く。
「幸歌、発表会のやつ、ソロに選ばれたんだって?」
「あーうん。……そうなんだけど、ね……」
めずらしく歯切れの悪い言葉に、私は首をかしげた。
幸歌の表情を見れば、眉根を寄せ、どこか困ったような顔をしている。
しかし、唇を1度ギュッと引き締めると、覚悟を決めました、と言わんばかりの雰囲気で口を開いた。
「実は私、断っちゃった」
「へ……っ、えぇっ!?」
イタズラを告白するみたいな軽い調子でとんでもない事を告げられ、思わず大声を上げた。廊下で反響し前を歩く人たちが振り返るが、構ってなどいられない。
――――全く予想していなかった。
断るなんて、そんな。あんなに発表会を楽しみにしていたのに!!
衝撃的な事に口をあんぐりと開け棒立ちしていると、依然として何でもないような涼しい顔をしている幸歌が、早口にまくし立てるような口調でさらなる爆弾を投下する。
「あはは、そんな驚かないでよ。紅葉には話してなかったけど、私来年引っ越すんだ。だから、来年の7月なんてもうここにはいないの」
……は?
続けざまに大爆発が起きて、私の頭が上手く言葉の意味を拾ってくれなくなってしまった。自然と眉間に皺が寄って行き、つい問い詰めるかのようなキツイ物言いと固い声になる。
「ねえ、幸歌。もう一度言ってよ。私、聞こえなかったみたい」
「ええ~、この距離で聞こえないの? ……もう、仕方がないなぁ。本当は、そんな何度も言いたくないのに」
幸歌ののんびりとした話し方と柔らかな声音が、今日ほど苛立たしく思ったことはない。……けれど、私を焦れさせていることくらい幸歌なら気付いているだろうに、彼女は決して笑顔を崩さなかった。
そして、その優しい微笑みを湛えたまま、ひどく残酷で決定的な一言を私に突き付ける。
「引っ越すの、私。もうこの教室には通えないような、遠いところへ」
深く太いため息が意図せずとも口からこぼれた。目を固くつぶり、手の平に爪が刺さるくらい両手を握りしめる。
「……どうして、もっと早く言ってくれなかったの? 急に決まったことではないんでしょ」
……私に言う時間なら、たっぷりあったはずなのに。
さっき温まったはずの体が急速に冷え込んでいく。塩を入れた氷水を頭から被ったみたいだ。さーっと、どんどん、どんどん冷えていく。痛いくらいの寒さに全身が包まれる。
「ごめんね。……でも、別に意地悪をしてたわけじゃないよ。今年が終わるまでには、ちゃんと伝えようと思ってた」
「……だけど!」
「あのね、紅葉。私だって、離れたくないよ。紅葉が大好きなんだよ」
切なげな幸歌の表情がつらい。私は、そんな顔をさせたいわけじゃないのに。耐え切れなくなって、私は目を逸らした。
でも、すぐさま私の頬に差し伸べられた温かい手が、それを許さない。
「……っ」
「私はずっと、紅葉の親友だよ。それは何があっても絶対変わらない。……だから、紅葉のことを遠く離れても応援するよ。ずっと、ずっと応援しているよ。あなたならきっと、素晴らしいバレリーナになれるもん」
――――だから、負けないで。
そう言って、幸歌は儚く笑った。
*
「う~~~っ。さ、寒ーいっ」
「もー、寒い寒いなんて暗示かけるから、ほんとに寒くなっちゃうんだよ」
「……わ、わかってるもん!でも、実際、さむいでしょっ」
「い、言わないでっ」
さすが12月。まだ6時過ぎだというのに、この寒さ。加えて、あたりはもう真っ暗だ。
1月にもなればさらに寒くなると思うと、恐ろしい。雪は降るのだろうか。
――――と、そんなことを思いつつ隣の幸歌を盗み見る。彼女は、マフラーに顔をうずめ、手袋をはめた手を擦っていた。
……あのあと、無理やりに話題は変えられてしまって、それ以上聞くことは出来なかった。
言ってやりたいことは山ほどあるけれど、もう決まってしまっていることならば仕方がないのだ。私たち子どもは、大人に対してあまりに無力だから。だから、もう覆せないことにこだわるよりも、幸歌と過ごす時間一分一秒を大切にして、少しでも楽しい日々を過ごす方がいい。
幸歌が遠くへ行ってしまう前に、何か出来ることはないのだろうか。唯一無二の親友に、何か残せるものはないのか。
……それに、応援すると言ってくれたのに、私は何も言葉を返せていない……。
まだまだ長く続くと思っていた日常に急に終わりを告げられて、思考は絡んで衝突して落下して……、まるでジェットコースターに乗っているみたいにモミクチャだ。ぐるんぐるんと回って、あちこち体が振り回されて、内臓がフワリと浮かぶ。ありえない、もうやめてくれと、いたる所で悲鳴が上がった。
ちらりと幸歌の横顔を見る。彼女は全く気にしていないみたいだ。どうして、そんな風にいられるんだろう。私は今も、辺りを駈けずり回って、叫んで、地団太を踏みたい衝動を抑えているのに。
何だか悔しくなってきて、幸歌をじぃっと見詰める。とことん見詰める。テレパシーを送信し始める。気付け気付けと念じながら、眉を寄せて幸歌の頬に穴が開きそうな程見詰める。
すると、ふいに幸歌がこちらを見た。私が送信したテレパシーを受信したとでも言うのか。反射的に幸歌から視線を外す。苦笑するような気配が微かにあった。
バクバクと、心臓がうるさい。黙っていろ、幸歌に聞こえてしまう。
「あー、早く帰りたいねー」
「そうだね。寒いもん」
さっきとそう変わらない単語を言い合い、お互いの顔を見つめ合って笑う。手をこすり合わせ、一方的に体を襲う寒さに耐えた。
私は背後を振り返りため息をつく。白い息がふわっと広がって消えた。
実は、教室の建物の玄関先からは一歩も動いてはいなかったりする。
電車に乗ってこの教室に通っている人もいるくらいに、各所から集まっているのだけれど、幸歌とは偶然にも帰る方向が全く同じだ。……そして、その“偶然”に当てはまる人がもう一人いるのだ。
すると、バタバタと五月蠅い足音が近づいてくる。幸歌と同時に振り返った。一つの人影が、私たちに突進してくる。
「――――遅れてごめんっ」
「遅いよ、伸一!」
開口一番、謝罪の言葉を口にしながら駆けてきた私と同じ歳の男の子――――長田伸一に言った。
彼はゲーム好きという一面を持ちながらもバレエ部門に通う、ちょっと変わった子だ。しかも、学校では同じクラス。
本当に、偶然って恐ろしい。
「だから、ごめんってば。紅葉ちゃんに頼まれてたやつ、ラフ画までだけど描いたんだよ」
「……もう! 明日学校でいいよって言ったじゃん!」
「……ラフ画?」
すると、それまでの会話を聞いていた幸歌が、首を傾げながら聞いてきた。寒いので、歩きながら説明を入れる。
「うん。……私、ちょっと前に、絵画コンクールで入賞したでしょ?」
「あーあの、全国のやつ?たしか、最優秀賞取ったよね」
「……ま、まぁ、それは置いておいて……。――――それでね、なんかその時の絵が目に留まったとかで、茅場晶彦……って言ったかな。その人が、今構想を練っているゲームに出すモンスターのデザイン案を30体くれないかって」
「さ、30!?……あ、それで長田君に頼んだんだ。ゲーム好きだもんね」
「う、うん」
私と幸歌の会話に自分の名前が出てきた所為か、伸一は少しどぎまぎしつつも相槌を入れた。
「そ。伸一に、5体頼んだ。それで、あと1体なんだけど――――」
「へぇ……それは大変。――――あれ?」
ふいに、幸歌が立ち止まる。私と伸一も釣られて足を止め、何だろうと顔を見合わせる。すると、微かに人の泣き声が――――、ううん、人ではない。
これは……、猫?
「あ、あれだ!」
伸一が指差したと思ったら、急に走り出した。私たちも、慌てて追う形で走り出す。
真っ暗な道には、定期的に街灯があるのだが、その中の一つに、ガムテープで閉ざされた段ボール箱があった。側面には、ありきたりな『拾ってください』の文字。
鳴き声の発生源は、たしかにこの中だ。
最初に走り出したのは伸一にもかかわらず、手を伸ばしたのは幸歌だ。……そういえば、伸一は猫が苦手だったような気がする。
「……わぁ、かわいい」
ガムテープに手をかけ、はがした幸歌が漏らす。私が覗き込むと、そこには――――、
「黒猫」
……黒猫。なんて、ふきつな。
そう思ったのは私だけではなかったらしい。伸一も、少し眉根を寄せている。けれど、幸歌は全く気にしていないようで、
「かわいそうに。こんな、寒いところで」
風に浚われてしまいそうな程小さい声でそう呟いたかと思うと、ダンボール箱で丸くなる黒猫を抱きかかえて立ち上がった。そして、私たちを見てにっこりと笑う。
「この子、私の家で飼うよ。ちょうど、猫ほしいねって、家族と話していたから」
「……え、でも」
「黒猫って、不幸を呼ぶとか言われてるけど、私は違うと思うんだ。実際、黒い蝶には幸せもらったし。私の名前に“幸”ついてるし」
……理由がよくわからない。
そもそも、黒い蝶なんて……、と思ってしまうけれど、ふわふわと幸歌が笑っているのでどうでもよくなる。
私は黒猫を指差した。
「じゃあ、名前、“リュヌ”ってどう?“Lune”って書いて、フランス語でそう読むの。“月”って意味だよ」
「月?」
「うん。その子、完全に真っ黒じゃないよ。…ほら、右側のおなかあたり。三日月みたいな白い模様が入ってる」
「ほんとだ」
幸歌は猫の体を器用にずらし、覗き見る。そして、また笑った。
――――その笑顔を見て、ひらめいた。
「あ……。さっきのモンスター案、残りの一体、この子モデルにしようかな」
ポロリと口から出る。それを聞いた2人は、「え」と小さく声を上げた。私は2人のその反応に、眉を八の字にする。
「……だめ、かな」
「う、ううん。いいと思うよ。てゆうか、嬉しい。……倒されるのは、かわいそうだけど」
慌てたように片手を左右に振りながら言う幸歌に、あはは、と笑ってから、
「ありがと。さっそく、家に帰ったら頑張るよ」
そう宣言してから後ろ向きに軽くスキップする。そんな私に、幸歌は笑みを浮かべながら、
「ところで、そのゲームの名前は?」
そう問われ、足を一旦止め、記憶を探る。たしか、依頼内容が書かれたプリントに、≪仮≫となっていた名前があったはずだ。――――と思いながら記憶を引っ掻き回すと、意外にも早く、引き出しから言葉が出てきた。
「≪ソードアート・オンライン≫、……だったかな」
*
「じゃあね、紅葉」
「うん」
私の家の前で、いつも私たちは別れる。幸歌の家は、もう少し歩いた先にあるからだ。
ちなみに、伸一とは少し手前で別れた。
「……ねぇ、幸歌。さっきの黒猫のモンスター、≪ノワール≫って名前、どう?これもフランス語で“黒”って意味なんだけど。――――希望があれば、名前もつけていいんだって」
「黒?」
「うん。……なんか、あの黒猫見てたら、兄さんの好きな色って黒だなーって思って」
兄さん――――和人のことだ。黒が好きなのか、いつもダーク系の服を着ている。しかも、私の髪の色と同じ漆黒の髪と瞳のせいで相乗効果が働き、“黒”というイメージがどうしても強い。
そんな理由でいったのだが、幸歌は、なぜかクスクスと笑いだす。
「ほんと、お兄さんっこだねー。今度紹介してよ。顔、かわいいんでしょ」
「それ、本人気にしてるから言わないであげて……」
「あはは、気を付けます。――――えーと、いいんじゃない?かわいいし、おもしろいし」
私はそれを聞いて、「うん」と頷く。
そして――――幸歌の左腕を、掴んだ。幸歌がビクリと肩を揺らし、目を見開いている。
けれど、言うなら今しかないから。少し油断をしていた、今しか。
私は、彼女の黒い瞳をしっかりと捕え、そして声を潜めていった。
「……さっき、幸歌は“応援してる”って言ってくれた。なら、私は“約束”する。――――私、フランスにあるコンセルヴァトワールに入る。それで、絶対世界一素敵なバレリーナになるよ」
それに、おじいちゃんが許してくれたんだし、といたずらっぽく付け足すと、いつの間にか真剣な表情になっていた幸歌が口元に笑みを作り、表情が柔らかくなった。
「だから幸歌も、歌やめないでよね。私、幸歌の歌大好きなんだから。……でも、私が独り占めするのにはもったいないからさ。……がんばってよ?」
「……うん。誰かを幸せに出来る唄が歌えるように、頑張る」
幸歌は、猫を落とさないようにしながら、器用に手袋から手を抜き取る。そして、手袋をしていたのに、氷をさわっているのかと錯覚するほど冷たい指先を、私の指を絡めた。
「「約束」」
2人の声が合わさったので思わず吹き出すと、幸歌の腕の中にいる猫が、「にゃお」と小さく鳴いた。
まるで、この猫までもが指切りをしているように。
*
私は荷物を部屋に放り投げたあと、道場の方へ向う。
少し開いた扉の隙間からこぼれてくる人工的な光と、聞き慣れた声に安堵した。
中からは「せいっ」だとか、「はっ」という、頑張っているということがハッキリと伝わってくる覇気のある声がしている。私は邪魔してはいけないなと思いつつ中に滑り込むように入った。
「……どうしよ」
思わずそんな言葉がポツリと漏れる。入ったのはいいものの、本当に、どうすればいいか考えていなかった。
右手をあてもなくブラブラする、というのを何回か繰り返す。しかし、いつまでもこうしているわけにはいかないので、意を決して口を開いた。
「――――す、スグ?」
「……え、モミ?」
直ぐに動きを止めたスグが、クルリとした大きめ目をこちらに向けた。そして、数回パチパチと音がしそうな程目を瞬かせ――――ハッとしたような表情になる。
「も、モミが帰って来てるってことは……、て、わぁぁぁ! もう7時!? な、なんで誰も教えてくれなかったの!」
「あ、うーん……。多分、お母さんたち、映画観てるからじゃないかな。忘れてる、とか」
「あの録画してたやつ!?あたし、楽しみにしてたのに!」
今にも木刀でさえ放り投げそうな勢いで、スグが詰め寄ってきた。その剣幕に私は体がのけぞる。口元が引きつりそうになるのをなんとか堪えながら、両手で軽くスグの体を押し返した。
「……う、うん。あ、じゃあ、私が消さないでって、言ってきてあげるよ」
「うん、お願い! さっさと片付けて、着替えた後そっちに行くから!」
そう言い終わるや否や、パッと身をひるがえしバタバタと駆けて行った。
「……あ」
ドタッという盛大な音とともに、こけた。
*
スグは一応、私の双子の姉だ。けれど、2人の間では、さほど上だの下だのを気にしていない。
――――生まれ落ちた時間の差はほんの数十分。
違うのはそれだけで、あとは何も変わらない。
今まで過ごした時間、日々は同じだ。
だからこそ、姉だとかは意識出来ない。むしろ、そうやって縛りをつけてしまう方が息苦しく感じてしまうかもしれない。
そんなのことをスグと生真面目に話したことはないけれど、多分、考えは一緒だと思う。
実際、スグがそのことを言ってきたことはないし。……いや、小さい頃から“姉”なんて単語を使って話しかけたことはないから、当たり前すぎて、思いついてすらいないかもしれない。
私とスグは、本当に双子なのかと思うほど、性格が見事に正反対だ。スグを“動”と表すなら、私は“静”。
……といっても、フォローはしたりされたりで――――特にイタズラをしでかした時なんかは、息はピッタリだ。
……うん、やっぱり、私たちは、いくら正反対でも、根は一緒なのかもしれない。
ふっと口元が緩んだのが、自分でもわかった。慌てて気持ちを入れ直し、引き締める。
――――と、いつのまにか居間の前まで来ていた。考えながら歩いてきたため、周りのことを確認するのがおろそかになっていたのかもれない。
内心ヒヤヒヤとしながらも、ドアの取っ手に手をのばし――――そこで、わずかに隙間があることに気が付いた。何となく、そうっと押し広げ、室内を覗き込む。
「え……、兄さん?」
どうしたんだろう。兄さんがソファに座る両親の後ろに立っている。その表情は見たことがないくらいに硬く、唇はきつく引き結ばれていた。両親は背後に立つ兄さんに気付いている様子は無い。
そのただならぬ雰囲気に、私は自然と、半歩下がった。心臓がぎゅっと鷲掴みされたみたいに息苦しくなる。
――――ここに、居てはいけない。この先の光景を、見てはいけない。
頭のなかで、私がそう叫んでいる。
警笛を鳴らしている。
今すぐ踵をかえして、とにかくここを離れたい。
……そう思っているのに――――これ以上足が動かない。まるで足が、強力な接着剤によって床へくっつけられてしまったかのように。
さっきと同じだ。大きな孤立感を感じて足が張り付いてしまった時と。……けれど決定的に違うのは、その時よりも深くて重い。
……底なしの沼に足を突っ込んでしまったみたいだ。逸る気持ちが、思考を揺さぶる。
早く、早く! ここから離れなきゃ!
そう思っているのに、足は床とピッタリと張り付いている。目は縫い止められているかのように両親と兄さんの姿から外すことが出来ない。手と声は封じられ、耳は今にも兄さんの呼吸音が聞こえてしまいそうなほど敏感になっている。
……体のすべての神経が、目の前の異質な空間に完全に飲み込まれてしまっていた。
ズブズブと体が沼へ沈んでいき、足も腕も絡め捕られて抜け出すことなど叶わない。
――――だから、聞いてしまった。
兄さんがそれを口にした瞬間を、頭に焼き付けてしまった。
「オレの、本当の両親のことを教えてほしい」
「……え?」
吐息のように掠れた音が、自分の口から漏れ出る。
――――本当の、両親。
私はその意味を、すぐに理解してしまった。
呼吸が浅く速くなっていく。息がしにくい。手で首を圧迫されて、気道が塞がれているみたいだ。キーンという音が耳元で響く。さぁーと、身震いする冷気が全身を一気に撫でていった。
けれどそれに反して、自分の心臓の音が聞こえそうなほど高鳴り、体温がどんどん上がっていく。
――――いや。やめて。それ以上、言わないで。
けれど、音になっていない声なんて届くわけがなく。
次々と、耳を塞いでしまいたくなるような真実が兄さんに――――、否、兄さんと私に告げられていく。世界を遮断してしまいたい。
「直葉と紅葉は、あなたの従妹よ。……和人」
イトコ。
それはつまり、私たちは――――。
……ああ、“兄さん”って誰なんだろう。
ぐわんぐわんと頭の中が揺れていて、もう、何が正しいかわからない。
――――私の中で、何かが壊れた。
そう、直感的に認識した。
目の前が真っ暗になる。視界ごとグラリと揺れ、次の瞬間には膝に痛みが走った。
「……ぁ」
やけにかすれた声。
それが自分のものだと認識するのに、時間がかかった。私が3人の前に転がり出てしまったという事実に気が付くのにも。
私はチカチカと光って眩みそうになる視界の中で、何とか力の抜けた足を引きずった。見上げた先で “兄さん”の瞳を捕える。
「……にい、さ……」
「……ッ」
「ねえ、にいさん……?」
否定してほしい、という消え入りそうな希望を抱きながら覗いた2つの光は異常に暗く、『これが現実だ』と、言葉はないのにもかかわらず言われているようで。
「にいさん……、兄さん、お願い……ッ」
嘘だよ、って言って。兄さんが言うなら、信じられるから。明日には綺麗に忘れてしまうから!!
私はふらつく両足を手近な椅子の背を持つことで支え、立ち上がる。痛ましそうに顔を歪める両親と、振り返った体勢のまま目を見開いて顔を青ざめさせる兄さん。
……認めたくない。こんなの、認めたくない!!
「――――ね、兄さん。今日ね、来年の発表会の役が発表されたんだよ」
……笑って。
「ほらっ、兄さんも毎年楽しみにしてくれてるでしょ? 発表会が終わるたびに、“早くモミのバレエが観たいな”なんて言ってさ……」
それで私は決まって、“兄さんは気が早いんだから”って返すんだ。
「また、観に来てくれるよね? いつもそうだもんね?」
ねえ、笑ってよ。
いつもみたいに、笑ってよ!!
「…………にいさ……、どうして……」
どうして、笑って『発表会が楽しみだな』って言ってくれないの?
「……う、ぅ……っ」
いつの間にか、双眼からボロボロと涙がこぼれていた。止まらない。けれど、拭おうとは思えなかった。
私は滲む視界の端に居るお母さんに顔を向け、
「……ね、ねえ、お母さん。今日の夜ご飯は何だっけ」
「も、紅葉……」
「あ、あれー? 朝確かに聞いたはずなんだけどな、忘れちゃった」
今日の朝の出来事を思い出す。
いつも通り目覚まし時計で目を覚まして、隣のベッドで寝るスグを揺り起こす。部屋を出たところで、大きな欠伸をしながら部屋から出てきた兄さんと鉢合わせして。そのまま一緒にリビングに行って、久しぶりに海外から帰ってきたお父さんと朝食を食べて。今日は休みだからと微笑むお母さんに見送られて登校する――――。
……変わらない朝だった。普通の朝だった。
――――確かに今朝は幸せな日常があって、兄さんは笑っていたのに。
「あっ、思い出した! エビフライだったよね、お母さん!」
「……っ」
「ねえねえ、何やってるの。もうすぐ、スグが来ちゃうよ。早く夜ご飯の支度しようよ~」
……ほら、兄さん。笑って。
「発表会の話もしたいんだからさ!」
視界が霞む。唇は震えていた。膝は今にも崩れ落ちてしまいそう。
でも、私頑張るから。
我慢するから……。
「……も、もうー、どうして黙ってるのー?」
ボロボロ、ボロボロ。
口の中に涙が入ってきちゃったよ。しょっぱいなー。
「お、おかしいよ、なんで何も言わないの……?」
――――本当におかしいのは。
「……ひっく、……う、なんで、なんで……」
崩れ去った嘘に、まだ縋っている私。
「……じゃ、じゃあさ、私もう一回リビングに入って来るよ。お母さんたちが楽しそうに話しているリビングに、もう一回入ってくるからさ」
お父さんとお母さんが映画を観ていて、その真ん中で兄さんが笑っていて。そんな明るいリビングに私が入って行く。『ただいま』、『おかえり』って言葉を交わして、戻ってきたスグと夜ご飯にするんだ。
――――ね、これで元通り。
幸せな時間に戻れるよ。
「い、良い考えでしょ? そうだよね……?」
誰も反応しなかった。お父さんも、兄さんも、茫然と私を見詰めている。お母さんといったら、口元を押さえてすすり泣いていた。……どうしてだろう?
――――あ、そっか。私がこんな顔をしているからだね。
だったらこの涙を止めなくちゃ。
でも、変だな。涙の止め方が分からないよ。
「……ぅ、……うっ」
何故だろう。笑おうとしているのに、喉から引きつった音が漏れる。
「……にいさん……、兄さん。……私は、私たちは……」
私は笑う。精一杯笑う。
「私たちは、仲の良い兄妹だよね?」
兄さんが喉を詰まらせる音が、シンと静まり返るリビングの中でいやに大きく聞こえた。私は何とか気力を振り絞って、血の気が引いた顔で目だけをこちらに寄越す兄さんを見詰める。その噛み締められた唇は細かく震え、何かをためらっているように見えた。
「……にい、さん?」
どくん、と心臓がいやに大きく打った。兄さんが、口を開く。
「なあ……」
そして――――、
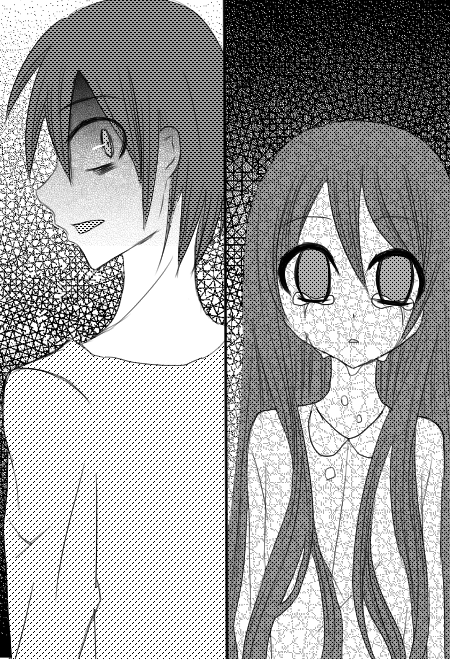
「モミ……、――――紅葉」
『ごめん』、そう声にはならない言葉の後、そっと、けれども冷酷に、――――目がそらされた。
――――目ガ、ソラサレタ。
ガラガラと壊れていく音が、明瞭に聞こえた気がした。
「――――……あ、……あぁ……っ、ああああぁぁぁぁあああああああ!!」
気づいた時には、玄関のドアを思い切り開け放っていた。鈍く刺さる外の冷たい風も、どこか遠く感じられる。
「モミ……ッ!?」
聞き慣れた女の子の声が聞こえたけれど、誰だか分からない。
……分からない。分かりたくない。もう何も受け付けたくない。
私の中でグルグル渦巻く全てのものが、ぼんやりと靄がかかってしまっていた。目や耳に入ってくる情報を、体が拒絶する。
けれど、そんな中でも射抜くような光だけが、妙にハッキリしていて。
何度目かの声が耳に届いた時、ぼんやりと、それを認識した。
――――けたたましいクラクションと、ブレーキの音を。
「……あ」
――――世界一素敵なバレリーナになるよ。
そう言った自分の声が、やけに鮮明に蘇って。
同時に、視界は黒で塗りつぶされた。
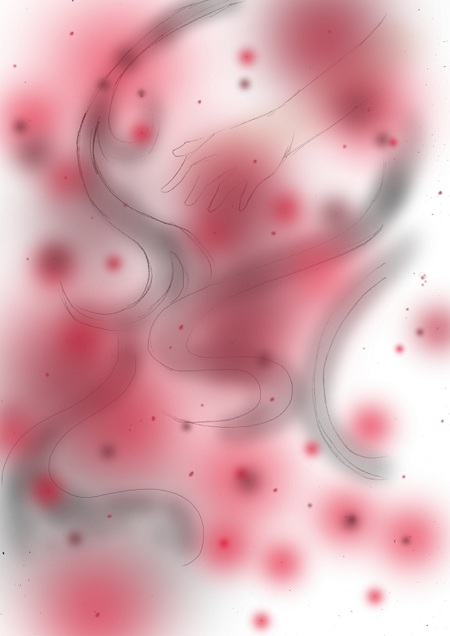
男は、車を動かすべくキーを回した。同時にモーターが動きだし、車体全体が小刻みに震え始める。
日はとっくの前に落ちていた。先ほど居た建物の明かりがわずかばかりにこぼれてきているが、車のヘッドライトだけが今は頼りだ。
目の前には鬱蒼とした森林だけが広がっていて、人間の介入を拒絶しているようにも感じられてしまう。それがひどく、男を不安にさせた。
すると、そんなものを打ち消すように後部座席のドアが開いた。同時に見えた人物の姿を確認して、無意識に顔がほころぶ。
「手伝おうか?」
「いいえ、大丈夫。ありがとう」
そう言いながら、今しがたドアを開けた女性――――男の妻である彼女は、朗らかに微笑んだ。そして車内に上半身だけを入れ、抱きかかえている子どもを、気を使っているのがありありと分かる程丁寧に、チャイルドシートへ降ろす。彼女はシートベルトが着いたかをしっかりと確かめると反対側へ周り込み、後ろのドアをゆっくりと開け、車内に乗り込んだ。
そんな愛しい妻の姿を目で追いながら口を開く。
「……ずいぶん嬉しそうだね?」
「ええ。だって、2人で描いた夢へまた一歩近づいたのよ」
「それもこれも……、“彼”のおかげだな」
「ええ、そうね。まだあんな歳なのに……」
途端憂いと情けなさが入り混じったような光を帯びさせ、妻は目を細める。苦しさが溶け込んだような表情をする妻をルームミラー越しに見た男は、唇を引き締めてすでに装着していたシートベルトを外した。体ごと後ろへ乗り出し、優しく脆いその女性のしっとりとした肌に、自身のゴツゴツとした手を寄せる。視線が絡み合い、もう少しで吐き出す息が掛かってしまいそうだ。
「気にすることない。“彼”は強い。良く出来た子だよ」
「“彼”は特別な才能を持っているのよ。私たちが思っているほど、簡単な子ではないわ。いつか、何かが起きそうで怖いのよ……」
「……ならば、そうならないように見守っていよう。この子の成長と一緒に」
強い口調で言い切ると、不安そうに瞳の奥を揺らしながらも彼女はコクリと頷いた。男は微笑み、妻の頬をもう一度撫でると、チラリと横で眠る息子を見る。
ああ、愛おしい。決して失いたくない。
腹の底から湧き上がる強い思い。グラグラと視界が揺れそうなほど、体中の血液が駆け巡る。
……今度こそ、守るのだ。自らが未熟なせいで犯してしまった罪は、もう消せはしないけれど。
男は妻に悟られぬよう拳を握りしめると、体を前へ戻した。体勢を整え、再びシートベルトを締め――――そこでハッと今朝の会話を思い出す。
「そうだ。翠さんはどうなった?」
「ああ、そうそう! あなたには言っていなかったわね」
彼女の様子を窺いながら話題を変えると、打って変って空気が明るくなった。この切り替えの早さが彼女の良い所だ、と男は苦笑いを浮かべる。しかし彼女は男の下らない心情に気付く様子は無く、代わりに身に纏う雰囲気を一層優しいものに変えると、まるで自分のことのように穏やかな声音で、
「さっき翠の旦那さんからメールが来たのだけれど、無事赤ちゃんが生まれたんですって。双子の可愛い女の子だそうよ」
「良かったじゃないか! ずいぶん心配していたからな」
「ええ! 本当によかったわ。……名前ももう決まっているらしくて、上の子が直葉ちゃん、下が
彼女は徐に鞄を探り、携帯電話の画面を開いて寄越してきた。数センチ程の長方形のそこには、2人の赤ん坊の姿が映しだされている。画面の光のせいなのか、それともその神秘的な雰囲気のせいなのか、妙に目が痛い。
「それでね、その子たちを見ていたら、……和人も来月で1歳なんだなーって思って」
ふわりと口元に笑みを浮かべながら、彼女はチャイルドシートですやすやと気持ちよさそうに眠る息子の頭を撫でる。和人は嬉しそうに、妻の手に顔を摺り寄せた。
男はそんな愛する2人の光景に、心が和むのを感じながら、視線を前へ戻した。そして、アクセルを踏み込む。
「早く、埼玉に戻ろうな」
「はい。早く、翠の幸せそうな顔が見たいわ」
その返答に、男は僅かに首を縦に振った。まあ、少しの異変も見逃すまいと、フロントガラスの向こう側を睨むように見ながらだが。
そして、もうすぐ下り坂だな、なんて思いつつブレーキを踏み込んだ――――つもりだった。
「――――っ!?」
すぐその異変に気が付いた。ガラスの向こう側ではない、……車自体に。
しかし、それを否定すべく何度もブレーキを踏む。ガタガタと鈍い音が響いているが、構わず同じ動作を何度も、何度もする。
すると、後部座席に座る彼女も異変に気が付いたようで、「どうしたの!?」と悲鳴に近い声をあげた。けれども、それに応える余裕はない。
スピードは一向に変わらない。むしろ、坂に入ったせいか、少しずつ速くなっていく。
それでも、諦めずに踏む。意味がないと分かりつつも、サイドブレーキを思いきり引いた。
――――やっと。
やっと、なんだ。
こんなところで……。
目の前に、カーブが見えた。その瞬間、思考が弾け飛ぶ。
白で塗りつぶされてしまう。
――――そして、そんな最中でも頭に浮かぶのは、和人と、“
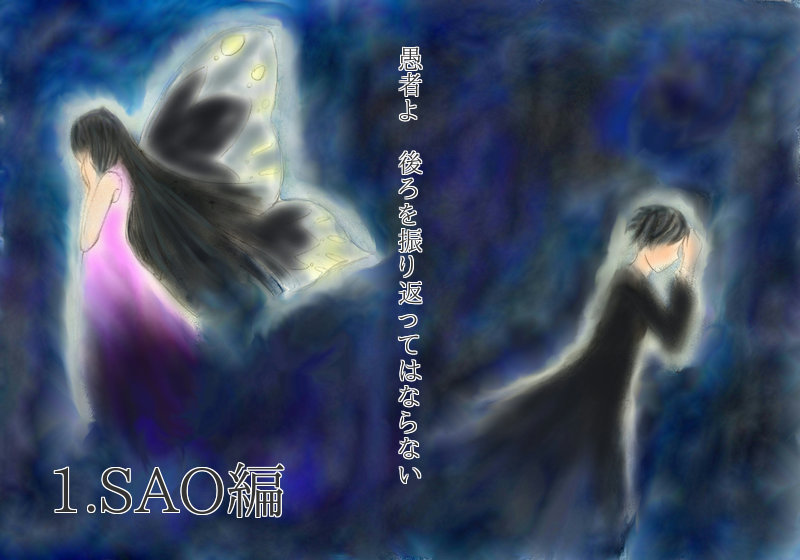
――――――――――――――――――――――――――――
愚者よ、後ろを振り返ってはならない
たとえ、己の身を滅ぼす結果になろうとも
――――――――――――――――――――――――――――
――――――――2018年 12月。
日本最大の芸術専門の大学。その隣には、付属の芸術教室があり、バレエや演劇、歌唱、絵画などを部門別に習うことが出来る。
そこに、私――――桐ケ谷紅葉は通っている。
私はバレエと演劇部門を掛け持ちしているのだが、今日も大人と混じって――――別に小学生のみのクラスもあるのだが――――バレエのレッスンをしていた。
そして今、来年の7月にある発表会での役が発表されたのだが――――少し、……否、かなり気まずい。
「――――紅葉ちゃんがオデット。いい?異論はないですよね?」
「……まぁ、小学3年生にもかかわらず、このクラスで一番上手ですし」
――――このクラス。
そう、ここは私以外全員が大人。しかも、将来を有望視されている人たちばかりだ。
その中に、私一人、小学生。
それはとても不思議な光景で、なんで私だけ、と口には出さずとも思っている。そして、天地がひっくりかえったとしても、この空間で浮いた存在であることは絶対に変わらない、とも理解している。
ちなみにオデットとは、『白鳥の湖』に出でくる、魔法によって白鳥に変えられてしまったお姫様のこと。
この役は、オディールという役との1人2役をしなければいけない、とても難しい役なのだ。……単刀直入に、簡潔に言ってしまえば――――主人公になる。
だから、何度でも言おう。
なんで私なの、と。
普通なら、小学生と大人では出来るハズがないのだ。身長差があり過ぎるのだから。
けれども、幸か不幸か私は同年代の子たちよりも頭一つ分以上身長が高い。1つ年上の兄よりもちょっと高いのだ。よって一緒に舞台の上に立っていても、ギリギリ通用してしまうのだった。
……けれど、問題はそこではないのだ。
この役は、非常に難しい役なハズなのだ。とても高度なテクニックを要求されるから、到底私みたいな子どもが出来るはずがない。本来なら、私よりずっと経験のある人がするべきなのに……。
「じゃあ、これでレッスンは終わりです」
私が、拒めるわけがない。
そんな意味を込めながら視線を先生に送っていると、いつのまにか話がまとまっていたようで、その一声でレッスン終了になってしまった。
私は部屋の隅に畳んで置いていたカーディガンを取りに行こうと、大人たちの波に逆らって歩く。するとその途中で、立ち止まって話す2人の女性とすれ違った。
「――――あの子、演劇部門の方でも主役になったそうよ」
ドクン。心臓が飛び上がった。
グラグラと地面が揺れた気がして、思わず歩みが止まる。……しかし、その間も容赦なく会話は続いていく。
「えぇ~? 本当?」
「うんうん、本当。そろそろ芸能界からお声が掛かるんじゃないかって噂もあるし」
「まったく――――恐ろしい子ね」
「本当ねぇ。……しかも、あの子いくつ教室に通っていると思う?」
片方の女性が立ちすくむ私をチラリと見やる。その口元が弧を描いた。
……ああ、近くにいるのを分かっているのに会話しているのだ。わざと聞こえるように話して、なんて嫌らしい。
「え……、バレエと演劇だけじゃないの?」
「それが違うみたいなのよね~。絵画とか、あと弓道と剣道も他の教室で習っているみたい」
「ええー、嘘ぉー。じゃあ、いつ勉強しているの? 頭も凄く良いって噂でしょ」
「それはアレよ。“天才少女”だからねぇ」
「まさに文武両道ってことかぁ。あーあ、私も才能が欲しかったぁ」
「リノは今のままでも十分素敵だよ。“普通”が一番!」
「そうね~!」
きゃらきゃらと、笑い声が耳を劈く。
私は好きでやっているのに。どうしてこんな事を言われなければいけないのだ。
こうやって疎まれ、あるいはその逆に異常にすり寄ってくる人たちもいる。しかも厄介なことに、全員に当てはまるものは上辺だけの好意だ。
こうやって自分のプライドが傷つけられれば、わざと聞こえるように嫌味を言うくせに、普段は優しい大人の仮面を身に着けている。いっそ女優や俳優にでもなってしまえばいいのに。きっとお似合いだ。
そう内心毒を吐いてしまうくらい、私の周りにいる人たちはみんな、気持ちの悪い好意を顔に張り付けている。
芸術教室の人たちだけじゃない。クラスの子も、学校の先生も、近所の人たちも。
けれど私は、そんなものはいらない。
私は、“普通”なのだから。
……“普通”、なのに。
――――他の同い年の子達と、何にも変わらないのに!!
石のような足を引きずりながら歩き出した。まるで背後の笑い声に追い立てられているみたい。……私は、何も悪くはないはずなのに。
鬱々とした気分のまま教室の扉を開けて廊下に出た。カーディガンの上から、ヒヤリとした空気が肌を刺す。なんとなく、この空間までもが自分の敵のような気がしてきた。圧倒的な破壊力を持った強烈で鋭い竜巻が、私の胸に穴を空けて行き、ぽっかりと空いたそこからドロドロと液体が漏れ出て行く。突き抜ける痛みと強い漂流感に、ぎゅっと両手を握りしめた。顔の筋肉が強張り、あまりの空虚さに足を進めることが出来ない。足が樹の幹になったみたいだ。筋肉が仕事を忘れたと言わんばかりに動かなかった。
濁流が治まるのをただひたすらに耐えようと、私は背中を丸める。
――――しかしその時、打ち消すように肩に軽い衝撃があった。
「もーみじっ」
「あ……、待っていてくれたの?」
サッと、目の前の景色が晴れた気がした。それはもう、太陽の光が差し込んできたみたいに。体の硬直が嘘のように、すうっと消える。
……私の周りには嘘をロウで固めたような人たちばかりだけれど、こうして純粋な好意を向けてくれる人もいるんだ。
私は、胸がじんわりと温かくなるのをハッキリと感じながら、目の前の人物――――如月幸歌をまじまじとみた。
幸歌は、笑窪がよく似合う笑顔を浮かべながら、
「って言っても、私もさっきレッスン終わったばかりだよ?」
と、イタズラっぽく言った。
私は、その笑顔に釣られるようにして笑う。
幸歌は、私より3つ年上の小学6年生にもかかわらず、対等に接してくれる。親友だと、胸を張ってはっきりと宣言できる存在でもあるだろう。
彼女は少し前まではバレエ部門にも入っていたので、そのつながりで仲が良くなった。今でこそ声楽部門の方に専念するためバレエはやめてしまっているが、関係が崩れたわけではない。
むしろつながっている糸が、太く、強くなったようだ。
そして、今日もいつものように、レッスン終わりで疲れたと悲鳴を上げている体をなだめながら、2人で廊下を歩く。
「幸歌、発表会のやつ、ソロに選ばれたんだって?」
「あーうん。……そうなんだけど、ね……」
めずらしく歯切れの悪い言葉に、私は首をかしげた。
幸歌の表情を見れば、眉根を寄せ、どこか困ったような顔をしている。
しかし、唇を1度ギュッと引き締めると、覚悟を決めました、と言わんばかりの雰囲気で口を開いた。
「実は私、断っちゃった」
「へ……っ、えぇっ!?」
イタズラを告白するみたいな軽い調子でとんでもない事を告げられ、思わず大声を上げた。廊下で反響し前を歩く人たちが振り返るが、構ってなどいられない。
――――全く予想していなかった。
断るなんて、そんな。あんなに発表会を楽しみにしていたのに!!
衝撃的な事に口をあんぐりと開け棒立ちしていると、依然として何でもないような涼しい顔をしている幸歌が、早口にまくし立てるような口調でさらなる爆弾を投下する。
「あはは、そんな驚かないでよ。紅葉には話してなかったけど、私来年引っ越すんだ。だから、来年の7月なんてもうここにはいないの」
……は?
続けざまに大爆発が起きて、私の頭が上手く言葉の意味を拾ってくれなくなってしまった。自然と眉間に皺が寄って行き、つい問い詰めるかのようなキツイ物言いと固い声になる。
「ねえ、幸歌。もう一度言ってよ。私、聞こえなかったみたい」
「ええ~、この距離で聞こえないの? ……もう、仕方がないなぁ。本当は、そんな何度も言いたくないのに」
幸歌ののんびりとした話し方と柔らかな声音が、今日ほど苛立たしく思ったことはない。……けれど、私を焦れさせていることくらい幸歌なら気付いているだろうに、彼女は決して笑顔を崩さなかった。
そして、その優しい微笑みを湛えたまま、ひどく残酷で決定的な一言を私に突き付ける。
「引っ越すの、私。もうこの教室には通えないような、遠いところへ」
深く太いため息が意図せずとも口からこぼれた。目を固くつぶり、手の平に爪が刺さるくらい両手を握りしめる。
「……どうして、もっと早く言ってくれなかったの? 急に決まったことではないんでしょ」
……私に言う時間なら、たっぷりあったはずなのに。
さっき温まったはずの体が急速に冷え込んでいく。塩を入れた氷水を頭から被ったみたいだ。さーっと、どんどん、どんどん冷えていく。痛いくらいの寒さに全身が包まれる。
「ごめんね。……でも、別に意地悪をしてたわけじゃないよ。今年が終わるまでには、ちゃんと伝えようと思ってた」
「……だけど!」
「あのね、紅葉。私だって、離れたくないよ。紅葉が大好きなんだよ」
切なげな幸歌の表情がつらい。私は、そんな顔をさせたいわけじゃないのに。耐え切れなくなって、私は目を逸らした。
でも、すぐさま私の頬に差し伸べられた温かい手が、それを許さない。
「……っ」
「私はずっと、紅葉の親友だよ。それは何があっても絶対変わらない。……だから、紅葉のことを遠く離れても応援するよ。ずっと、ずっと応援しているよ。あなたならきっと、素晴らしいバレリーナになれるもん」
――――だから、負けないで。
そう言って、幸歌は儚く笑った。
*
「う~~~っ。さ、寒ーいっ」
「もー、寒い寒いなんて暗示かけるから、ほんとに寒くなっちゃうんだよ」
「……わ、わかってるもん!でも、実際、さむいでしょっ」
「い、言わないでっ」
さすが12月。まだ6時過ぎだというのに、この寒さ。加えて、あたりはもう真っ暗だ。
1月にもなればさらに寒くなると思うと、恐ろしい。雪は降るのだろうか。
――――と、そんなことを思いつつ隣の幸歌を盗み見る。彼女は、マフラーに顔をうずめ、手袋をはめた手を擦っていた。
……あのあと、無理やりに話題は変えられてしまって、それ以上聞くことは出来なかった。
言ってやりたいことは山ほどあるけれど、もう決まってしまっていることならば仕方がないのだ。私たち子どもは、大人に対してあまりに無力だから。だから、もう覆せないことにこだわるよりも、幸歌と過ごす時間一分一秒を大切にして、少しでも楽しい日々を過ごす方がいい。
幸歌が遠くへ行ってしまう前に、何か出来ることはないのだろうか。唯一無二の親友に、何か残せるものはないのか。
……それに、応援すると言ってくれたのに、私は何も言葉を返せていない……。
まだまだ長く続くと思っていた日常に急に終わりを告げられて、思考は絡んで衝突して落下して……、まるでジェットコースターに乗っているみたいにモミクチャだ。ぐるんぐるんと回って、あちこち体が振り回されて、内臓がフワリと浮かぶ。ありえない、もうやめてくれと、いたる所で悲鳴が上がった。
ちらりと幸歌の横顔を見る。彼女は全く気にしていないみたいだ。どうして、そんな風にいられるんだろう。私は今も、辺りを駈けずり回って、叫んで、地団太を踏みたい衝動を抑えているのに。
何だか悔しくなってきて、幸歌をじぃっと見詰める。とことん見詰める。テレパシーを送信し始める。気付け気付けと念じながら、眉を寄せて幸歌の頬に穴が開きそうな程見詰める。
すると、ふいに幸歌がこちらを見た。私が送信したテレパシーを受信したとでも言うのか。反射的に幸歌から視線を外す。苦笑するような気配が微かにあった。
バクバクと、心臓がうるさい。黙っていろ、幸歌に聞こえてしまう。
「あー、早く帰りたいねー」
「そうだね。寒いもん」
さっきとそう変わらない単語を言い合い、お互いの顔を見つめ合って笑う。手をこすり合わせ、一方的に体を襲う寒さに耐えた。
私は背後を振り返りため息をつく。白い息がふわっと広がって消えた。
実は、教室の建物の玄関先からは一歩も動いてはいなかったりする。
電車に乗ってこの教室に通っている人もいるくらいに、各所から集まっているのだけれど、幸歌とは偶然にも帰る方向が全く同じだ。……そして、その“偶然”に当てはまる人がもう一人いるのだ。
すると、バタバタと五月蠅い足音が近づいてくる。幸歌と同時に振り返った。一つの人影が、私たちに突進してくる。
「――――遅れてごめんっ」
「遅いよ、伸一!」
開口一番、謝罪の言葉を口にしながら駆けてきた私と同じ歳の男の子――――長田伸一に言った。
彼はゲーム好きという一面を持ちながらもバレエ部門に通う、ちょっと変わった子だ。しかも、学校では同じクラス。
本当に、偶然って恐ろしい。
「だから、ごめんってば。紅葉ちゃんに頼まれてたやつ、ラフ画までだけど描いたんだよ」
「……もう! 明日学校でいいよって言ったじゃん!」
「……ラフ画?」
すると、それまでの会話を聞いていた幸歌が、首を傾げながら聞いてきた。寒いので、歩きながら説明を入れる。
「うん。……私、ちょっと前に、絵画コンクールで入賞したでしょ?」
「あーあの、全国のやつ?たしか、最優秀賞取ったよね」
「……ま、まぁ、それは置いておいて……。――――それでね、なんかその時の絵が目に留まったとかで、茅場晶彦……って言ったかな。その人が、今構想を練っているゲームに出すモンスターのデザイン案を30体くれないかって」
「さ、30!?……あ、それで長田君に頼んだんだ。ゲーム好きだもんね」
「う、うん」
私と幸歌の会話に自分の名前が出てきた所為か、伸一は少しどぎまぎしつつも相槌を入れた。
「そ。伸一に、5体頼んだ。それで、あと1体なんだけど――――」
「へぇ……それは大変。――――あれ?」
ふいに、幸歌が立ち止まる。私と伸一も釣られて足を止め、何だろうと顔を見合わせる。すると、微かに人の泣き声が――――、ううん、人ではない。
これは……、猫?
「あ、あれだ!」
伸一が指差したと思ったら、急に走り出した。私たちも、慌てて追う形で走り出す。
真っ暗な道には、定期的に街灯があるのだが、その中の一つに、ガムテープで閉ざされた段ボール箱があった。側面には、ありきたりな『拾ってください』の文字。
鳴き声の発生源は、たしかにこの中だ。
最初に走り出したのは伸一にもかかわらず、手を伸ばしたのは幸歌だ。……そういえば、伸一は猫が苦手だったような気がする。
「……わぁ、かわいい」
ガムテープに手をかけ、はがした幸歌が漏らす。私が覗き込むと、そこには――――、
「黒猫」
……黒猫。なんて、ふきつな。
そう思ったのは私だけではなかったらしい。伸一も、少し眉根を寄せている。けれど、幸歌は全く気にしていないようで、
「かわいそうに。こんな、寒いところで」
風に浚われてしまいそうな程小さい声でそう呟いたかと思うと、ダンボール箱で丸くなる黒猫を抱きかかえて立ち上がった。そして、私たちを見てにっこりと笑う。
「この子、私の家で飼うよ。ちょうど、猫ほしいねって、家族と話していたから」
「……え、でも」
「黒猫って、不幸を呼ぶとか言われてるけど、私は違うと思うんだ。実際、黒い蝶には幸せもらったし。私の名前に“幸”ついてるし」
……理由がよくわからない。
そもそも、黒い蝶なんて……、と思ってしまうけれど、ふわふわと幸歌が笑っているのでどうでもよくなる。
私は黒猫を指差した。
「じゃあ、名前、“リュヌ”ってどう?“Lune”って書いて、フランス語でそう読むの。“月”って意味だよ」
「月?」
「うん。その子、完全に真っ黒じゃないよ。…ほら、右側のおなかあたり。三日月みたいな白い模様が入ってる」
「ほんとだ」
幸歌は猫の体を器用にずらし、覗き見る。そして、また笑った。
――――その笑顔を見て、ひらめいた。
「あ……。さっきのモンスター案、残りの一体、この子モデルにしようかな」
ポロリと口から出る。それを聞いた2人は、「え」と小さく声を上げた。私は2人のその反応に、眉を八の字にする。
「……だめ、かな」
「う、ううん。いいと思うよ。てゆうか、嬉しい。……倒されるのは、かわいそうだけど」
慌てたように片手を左右に振りながら言う幸歌に、あはは、と笑ってから、
「ありがと。さっそく、家に帰ったら頑張るよ」
そう宣言してから後ろ向きに軽くスキップする。そんな私に、幸歌は笑みを浮かべながら、
「ところで、そのゲームの名前は?」
そう問われ、足を一旦止め、記憶を探る。たしか、依頼内容が書かれたプリントに、≪仮≫となっていた名前があったはずだ。――――と思いながら記憶を引っ掻き回すと、意外にも早く、引き出しから言葉が出てきた。
「≪ソードアート・オンライン≫、……だったかな」
*
「じゃあね、紅葉」
「うん」
私の家の前で、いつも私たちは別れる。幸歌の家は、もう少し歩いた先にあるからだ。
ちなみに、伸一とは少し手前で別れた。
「……ねぇ、幸歌。さっきの黒猫のモンスター、≪ノワール≫って名前、どう?これもフランス語で“黒”って意味なんだけど。――――希望があれば、名前もつけていいんだって」
「黒?」
「うん。……なんか、あの黒猫見てたら、兄さんの好きな色って黒だなーって思って」
兄さん――――和人のことだ。黒が好きなのか、いつもダーク系の服を着ている。しかも、私の髪の色と同じ漆黒の髪と瞳のせいで相乗効果が働き、“黒”というイメージがどうしても強い。
そんな理由でいったのだが、幸歌は、なぜかクスクスと笑いだす。
「ほんと、お兄さんっこだねー。今度紹介してよ。顔、かわいいんでしょ」
「それ、本人気にしてるから言わないであげて……」
「あはは、気を付けます。――――えーと、いいんじゃない?かわいいし、おもしろいし」
私はそれを聞いて、「うん」と頷く。
そして――――幸歌の左腕を、掴んだ。幸歌がビクリと肩を揺らし、目を見開いている。
けれど、言うなら今しかないから。少し油断をしていた、今しか。
私は、彼女の黒い瞳をしっかりと捕え、そして声を潜めていった。
「……さっき、幸歌は“応援してる”って言ってくれた。なら、私は“約束”する。――――私、フランスにあるコンセルヴァトワールに入る。それで、絶対世界一素敵なバレリーナになるよ」
それに、おじいちゃんが許してくれたんだし、といたずらっぽく付け足すと、いつの間にか真剣な表情になっていた幸歌が口元に笑みを作り、表情が柔らかくなった。
「だから幸歌も、歌やめないでよね。私、幸歌の歌大好きなんだから。……でも、私が独り占めするのにはもったいないからさ。……がんばってよ?」
「……うん。誰かを幸せに出来る唄が歌えるように、頑張る」
幸歌は、猫を落とさないようにしながら、器用に手袋から手を抜き取る。そして、手袋をしていたのに、氷をさわっているのかと錯覚するほど冷たい指先を、私の指を絡めた。
「「約束」」
2人の声が合わさったので思わず吹き出すと、幸歌の腕の中にいる猫が、「にゃお」と小さく鳴いた。
まるで、この猫までもが指切りをしているように。
*
私は荷物を部屋に放り投げたあと、道場の方へ向う。
少し開いた扉の隙間からこぼれてくる人工的な光と、聞き慣れた声に安堵した。
中からは「せいっ」だとか、「はっ」という、頑張っているということがハッキリと伝わってくる覇気のある声がしている。私は邪魔してはいけないなと思いつつ中に滑り込むように入った。
「……どうしよ」
思わずそんな言葉がポツリと漏れる。入ったのはいいものの、本当に、どうすればいいか考えていなかった。
右手をあてもなくブラブラする、というのを何回か繰り返す。しかし、いつまでもこうしているわけにはいかないので、意を決して口を開いた。
「――――す、スグ?」
「……え、モミ?」
直ぐに動きを止めたスグが、クルリとした大きめ目をこちらに向けた。そして、数回パチパチと音がしそうな程目を瞬かせ――――ハッとしたような表情になる。
「も、モミが帰って来てるってことは……、て、わぁぁぁ! もう7時!? な、なんで誰も教えてくれなかったの!」
「あ、うーん……。多分、お母さんたち、映画観てるからじゃないかな。忘れてる、とか」
「あの録画してたやつ!?あたし、楽しみにしてたのに!」
今にも木刀でさえ放り投げそうな勢いで、スグが詰め寄ってきた。その剣幕に私は体がのけぞる。口元が引きつりそうになるのをなんとか堪えながら、両手で軽くスグの体を押し返した。
「……う、うん。あ、じゃあ、私が消さないでって、言ってきてあげるよ」
「うん、お願い! さっさと片付けて、着替えた後そっちに行くから!」
そう言い終わるや否や、パッと身をひるがえしバタバタと駆けて行った。
「……あ」
ドタッという盛大な音とともに、こけた。
*
スグは一応、私の双子の姉だ。けれど、2人の間では、さほど上だの下だのを気にしていない。
――――生まれ落ちた時間の差はほんの数十分。
違うのはそれだけで、あとは何も変わらない。
今まで過ごした時間、日々は同じだ。
だからこそ、姉だとかは意識出来ない。むしろ、そうやって縛りをつけてしまう方が息苦しく感じてしまうかもしれない。
そんなのことをスグと生真面目に話したことはないけれど、多分、考えは一緒だと思う。
実際、スグがそのことを言ってきたことはないし。……いや、小さい頃から“姉”なんて単語を使って話しかけたことはないから、当たり前すぎて、思いついてすらいないかもしれない。
私とスグは、本当に双子なのかと思うほど、性格が見事に正反対だ。スグを“動”と表すなら、私は“静”。
……といっても、フォローはしたりされたりで――――特にイタズラをしでかした時なんかは、息はピッタリだ。
……うん、やっぱり、私たちは、いくら正反対でも、根は一緒なのかもしれない。
ふっと口元が緩んだのが、自分でもわかった。慌てて気持ちを入れ直し、引き締める。
――――と、いつのまにか居間の前まで来ていた。考えながら歩いてきたため、周りのことを確認するのがおろそかになっていたのかもれない。
内心ヒヤヒヤとしながらも、ドアの取っ手に手をのばし――――そこで、わずかに隙間があることに気が付いた。何となく、そうっと押し広げ、室内を覗き込む。
「え……、兄さん?」
どうしたんだろう。兄さんがソファに座る両親の後ろに立っている。その表情は見たことがないくらいに硬く、唇はきつく引き結ばれていた。両親は背後に立つ兄さんに気付いている様子は無い。
そのただならぬ雰囲気に、私は自然と、半歩下がった。心臓がぎゅっと鷲掴みされたみたいに息苦しくなる。
――――ここに、居てはいけない。この先の光景を、見てはいけない。
頭のなかで、私がそう叫んでいる。
警笛を鳴らしている。
今すぐ踵をかえして、とにかくここを離れたい。
……そう思っているのに――――これ以上足が動かない。まるで足が、強力な接着剤によって床へくっつけられてしまったかのように。
さっきと同じだ。大きな孤立感を感じて足が張り付いてしまった時と。……けれど決定的に違うのは、その時よりも深くて重い。
……底なしの沼に足を突っ込んでしまったみたいだ。逸る気持ちが、思考を揺さぶる。
早く、早く! ここから離れなきゃ!
そう思っているのに、足は床とピッタリと張り付いている。目は縫い止められているかのように両親と兄さんの姿から外すことが出来ない。手と声は封じられ、耳は今にも兄さんの呼吸音が聞こえてしまいそうなほど敏感になっている。
……体のすべての神経が、目の前の異質な空間に完全に飲み込まれてしまっていた。
ズブズブと体が沼へ沈んでいき、足も腕も絡め捕られて抜け出すことなど叶わない。
――――だから、聞いてしまった。
兄さんがそれを口にした瞬間を、頭に焼き付けてしまった。
「オレの、本当の両親のことを教えてほしい」
「……え?」
吐息のように掠れた音が、自分の口から漏れ出る。
――――本当の、両親。
私はその意味を、すぐに理解してしまった。
呼吸が浅く速くなっていく。息がしにくい。手で首を圧迫されて、気道が塞がれているみたいだ。キーンという音が耳元で響く。さぁーと、身震いする冷気が全身を一気に撫でていった。
けれどそれに反して、自分の心臓の音が聞こえそうなほど高鳴り、体温がどんどん上がっていく。
――――いや。やめて。それ以上、言わないで。
けれど、音になっていない声なんて届くわけがなく。
次々と、耳を塞いでしまいたくなるような真実が兄さんに――――、否、兄さんと私に告げられていく。世界を遮断してしまいたい。
「直葉と紅葉は、あなたの従妹よ。……和人」
イトコ。
それはつまり、私たちは――――。
……ああ、“兄さん”って誰なんだろう。
ぐわんぐわんと頭の中が揺れていて、もう、何が正しいかわからない。
――――私の中で、何かが壊れた。
そう、直感的に認識した。
目の前が真っ暗になる。視界ごとグラリと揺れ、次の瞬間には膝に痛みが走った。
「……ぁ」
やけにかすれた声。
それが自分のものだと認識するのに、時間がかかった。私が3人の前に転がり出てしまったという事実に気が付くのにも。
私はチカチカと光って眩みそうになる視界の中で、何とか力の抜けた足を引きずった。見上げた先で “兄さん”の瞳を捕える。
「……にい、さ……」
「……ッ」
「ねえ、にいさん……?」
否定してほしい、という消え入りそうな希望を抱きながら覗いた2つの光は異常に暗く、『これが現実だ』と、言葉はないのにもかかわらず言われているようで。
「にいさん……、兄さん、お願い……ッ」
嘘だよ、って言って。兄さんが言うなら、信じられるから。明日には綺麗に忘れてしまうから!!
私はふらつく両足を手近な椅子の背を持つことで支え、立ち上がる。痛ましそうに顔を歪める両親と、振り返った体勢のまま目を見開いて顔を青ざめさせる兄さん。
……認めたくない。こんなの、認めたくない!!
「――――ね、兄さん。今日ね、来年の発表会の役が発表されたんだよ」
……笑って。
「ほらっ、兄さんも毎年楽しみにしてくれてるでしょ? 発表会が終わるたびに、“早くモミのバレエが観たいな”なんて言ってさ……」
それで私は決まって、“兄さんは気が早いんだから”って返すんだ。
「また、観に来てくれるよね? いつもそうだもんね?」
ねえ、笑ってよ。
いつもみたいに、笑ってよ!!
「…………にいさ……、どうして……」
どうして、笑って『発表会が楽しみだな』って言ってくれないの?
「……う、ぅ……っ」
いつの間にか、双眼からボロボロと涙がこぼれていた。止まらない。けれど、拭おうとは思えなかった。
私は滲む視界の端に居るお母さんに顔を向け、
「……ね、ねえ、お母さん。今日の夜ご飯は何だっけ」
「も、紅葉……」
「あ、あれー? 朝確かに聞いたはずなんだけどな、忘れちゃった」
今日の朝の出来事を思い出す。
いつも通り目覚まし時計で目を覚まして、隣のベッドで寝るスグを揺り起こす。部屋を出たところで、大きな欠伸をしながら部屋から出てきた兄さんと鉢合わせして。そのまま一緒にリビングに行って、久しぶりに海外から帰ってきたお父さんと朝食を食べて。今日は休みだからと微笑むお母さんに見送られて登校する――――。
……変わらない朝だった。普通の朝だった。
――――確かに今朝は幸せな日常があって、兄さんは笑っていたのに。
「あっ、思い出した! エビフライだったよね、お母さん!」
「……っ」
「ねえねえ、何やってるの。もうすぐ、スグが来ちゃうよ。早く夜ご飯の支度しようよ~」
……ほら、兄さん。笑って。
「発表会の話もしたいんだからさ!」
視界が霞む。唇は震えていた。膝は今にも崩れ落ちてしまいそう。
でも、私頑張るから。
我慢するから……。
「……も、もうー、どうして黙ってるのー?」
ボロボロ、ボロボロ。
口の中に涙が入ってきちゃったよ。しょっぱいなー。
「お、おかしいよ、なんで何も言わないの……?」
――――本当におかしいのは。
「……ひっく、……う、なんで、なんで……」
崩れ去った嘘に、まだ縋っている私。
「……じゃ、じゃあさ、私もう一回リビングに入って来るよ。お母さんたちが楽しそうに話しているリビングに、もう一回入ってくるからさ」
お父さんとお母さんが映画を観ていて、その真ん中で兄さんが笑っていて。そんな明るいリビングに私が入って行く。『ただいま』、『おかえり』って言葉を交わして、戻ってきたスグと夜ご飯にするんだ。
――――ね、これで元通り。
幸せな時間に戻れるよ。
「い、良い考えでしょ? そうだよね……?」
誰も反応しなかった。お父さんも、兄さんも、茫然と私を見詰めている。お母さんといったら、口元を押さえてすすり泣いていた。……どうしてだろう?
――――あ、そっか。私がこんな顔をしているからだね。
だったらこの涙を止めなくちゃ。
でも、変だな。涙の止め方が分からないよ。
「……ぅ、……うっ」
何故だろう。笑おうとしているのに、喉から引きつった音が漏れる。
「……にいさん……、兄さん。……私は、私たちは……」
私は笑う。精一杯笑う。
「私たちは、仲の良い兄妹だよね?」
兄さんが喉を詰まらせる音が、シンと静まり返るリビングの中でいやに大きく聞こえた。私は何とか気力を振り絞って、血の気が引いた顔で目だけをこちらに寄越す兄さんを見詰める。その噛み締められた唇は細かく震え、何かをためらっているように見えた。
「……にい、さん?」
どくん、と心臓がいやに大きく打った。兄さんが、口を開く。
「なあ……」
そして――――、
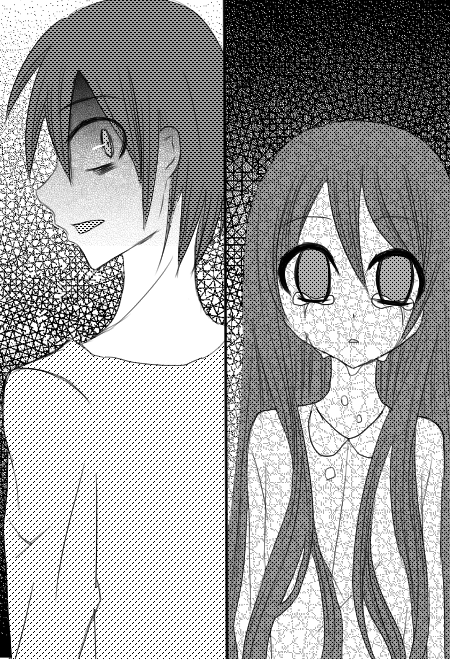
「モミ……、――――紅葉」
『ごめん』、そう声にはならない言葉の後、そっと、けれども冷酷に、――――目がそらされた。
――――目ガ、ソラサレタ。
ガラガラと壊れていく音が、明瞭に聞こえた気がした。
「――――……あ、……あぁ……っ、ああああぁぁぁぁあああああああ!!」
気づいた時には、玄関のドアを思い切り開け放っていた。鈍く刺さる外の冷たい風も、どこか遠く感じられる。
「モミ……ッ!?」
聞き慣れた女の子の声が聞こえたけれど、誰だか分からない。
……分からない。分かりたくない。もう何も受け付けたくない。
私の中でグルグル渦巻く全てのものが、ぼんやりと靄がかかってしまっていた。目や耳に入ってくる情報を、体が拒絶する。
けれど、そんな中でも射抜くような光だけが、妙にハッキリしていて。
何度目かの声が耳に届いた時、ぼんやりと、それを認識した。
――――けたたましいクラクションと、ブレーキの音を。
「……あ」
――――世界一素敵なバレリーナになるよ。
そう言った自分の声が、やけに鮮明に蘇って。
同時に、視界は黒で塗りつぶされた。
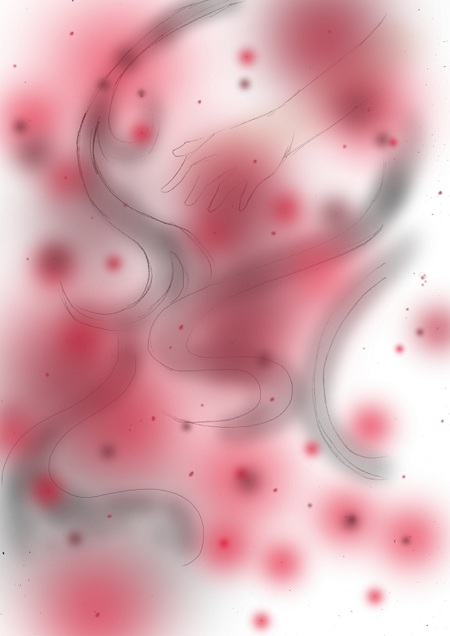
後書き
作中に出てくる“長田伸一”は、ALO編のレコン君と同一人物です
誤字・脱字等があればご報告ください。
ページ上へ戻る誤字・脱字等があればご報告ください。
感想を書く
この話の感想を書きましょう!
全て感想を見る:感想一覧
