| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
魔弾の王と戦姫~獅子と黒竜の輪廻曲~
作者:gomachan
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動第7話『闇の暗殺集団~七鎖走る!』
『ブリューヌ・ネメタクム・主要都市ランス・執務室』
七鎖―セラシュ。
それは、要人暗殺を受け持つ名うての暗殺集団。必ず7人で行動するとして知られる。
現在こそ、ブリューヌの王都はニースとされているものの、国が興る以前は、アルテシウムこそブリューヌの王都としてあり続けた。
元々そのアルテシウムが王都の時代から仕えている、セラシュはいわば王政府の密偵だった。
光を浴びる表向きの任務は警護。闇に紛れる裏の任務は諜報活動。特に諜報活動は特筆すべき点であり、日常的に官僚や大貴族、ブリューヌ全土を観察し、異常があれば報告するよう定められたと言われている。
故に彼らは影の見張り役として、ブリューヌの長きに渡る歴史と流れを、見守り続けてきた。
――全ては、ブリューヌの繁栄と平和を目指して――
例え身分が低くても、特別な役職の名目で国主に近づくことが出来たので、国主の意志を反映できる立場だった。
その特殊な任務の為、本来セラシュは功績を上げて、出世する機会に恵まれる……はずだった。
時代の流れと共に、アルテシウムからニースへ王政が移ると、治安維持の騎士団や貴族等が創設された。それに伴い、政治経済がうまく循環するようになると、セラシュもその役目を終える事となった。
活躍できる場を失った彼らはその後、新たな職に就くことが出来ず、終止符 を打てないまま、時代の輪廻の中で彷徨い続けてきた。
その彼らは今、ブリューヌの双璧を成す貴族の一室にいる。
「セラシュか」
早速、テナルディエは依頼内容を説明する。任務内容を理解、承知すると、「直ちに」と言い残して音を立てず、部屋から消えていった。
ただ一人だけ、御頭を呼び止めた。
「何故私に仕える?かつてテナルディエ家はアルテシウム王制の倒世運動を行ってきた一族。アルテシウム出身の貴様らから見れば、私は復讐の対象だ。何故?」
ブリューヌ変革期における抵抗運動から始まるガヌロン家との因縁は、遥か昔から行われている。
存在の意味とアルテシウムの伝統を破壊した大柄の男は、セラシュにとってテナルディエは戦犯の血を引く愚物でしかないはずだ。
「我ら七鎖 は影の末裔。主という実体がなければ存在出来ない者。影の我々にフェリックス=アーロン=テナルディエという実体が現れた。それだけの事」
軽く一礼すると、御頭も他のセラシュと同様に、音を立てずに部屋から出ていった。
10数える間くらいか、再び戸が開く。入ってきたのは、長年テナルディエ家に仕える占い師ドレカヴァクだ。
「虫を潰すのに、斧を用いるようでありますな。辺境の貴族を始末するのに、名うての暗殺集団を差し向けるとは」
「辺境の貴族だから……こそだ。むしろ、これくらい乗り越えてもらわねばならぬ。」
テナルディエにとって、ティグルへ与えた境遇はいわば「課題」に過ぎない。
目測通り、ティグルヴルムド=ヴォルンはジスタート軍を引き入れて戻ってきた。
そして、我がテナルディエ軍を撃退した。それも、竜を屠ったという報告を受けて。
だからこそ思考していた。次の「課題」をぶつけるにはどうしたらいいかと――
思考を巡らせたが、結局、一去した。
理由は『何者かが』ドナルベイン一派を消滅させたとの事。ヴォージュ山脈に集会所を構える連中なら、オルミュッツに偽装して周辺貴族の圧力に使えないか、もしくは連絡係としてうまく使えないかと考えていたが、甲冑を着せる予定の連中がいなくなった為、思慮していても仕方がない。
もう一つは、時折陰湿さや狡猾さを持つテナルディエらしからぬ理由だった。
「私は品性まで売った覚えはない」
これは失礼と、くぐもった笑いを漏らして一礼した。
(いずれにせよ、ライトメリッツの戦姫を引きはがす必要があるな)
テナルディエとしては、アルサスの小僧をブリューヌの渦中に投げ込みたいところだ。一時的にライトメリッツの力を必要としていたらしいが、今後はブリューヌの為に軍を引いてもらいたいと思っている。
戦姫には、やはり戦姫しかないのか。
「戦姫の方はどうなさるので?」
「それは私の方で対処する。それから……新たな竜と、例のものはいつ頃用意できる?」
「竜の方は、いくばくかの金銭と一月程の時間を要します。ただ……」
「ただ?」
「例のものといえば……デュランダルの兄弟剣と、カヴァクなる工芸品は半年程の時間を要します」
「仕方がない。だが……頼む」
それからテナルディエは鈴を鳴らし、従者を呼びつけると金貨を持ってくるよう命ずる。やがて人頭大の袋を持ってきて、ドレカヴァクに渡すよう指示する。
それから分厚い手を振って、ドレカヴァクに退出を命ずる。音もなく退出したドレカヴァクの姿を確認すると、入れ替わるように一人の優男が入ってきた。
「失礼します。テナルディエさん」
明快な口調で親しげに話しかけるこの男、ノア=カートライト。その表情はいつも笑みを浮かばせている。
この屋敷で、不遜な態度を示せば、家族ともども即刻処刑されてしまうだろう。例外として、そのような不遜な態度をとれるのは、ノアとドレカヴァク、以下数名のみだった。
「ザイアンは何をしている?」
「ザイアン様は釈放されたものの、ネメタクム帰領へは至らず……正確には、しばらくは戻らないそうです」
そうか、とそう小さくつぶやき、情を表に出さず頭の中で振り切って本題に入る。
この結果が分かっていたからこそ、衝撃は表に出さなかった。それがザイアンの為ともなり、ヴォルンの可能性を拡大する為の計画だ。
事実、ノアは今回のアルサス遠征において、ただの監視役だった。ガヌロンの動向を探る密偵として――
「ノア。貴様に一つ、やってほしいことがある。頼まれてくれるか?」
苛烈者として知られるテナルディエが、一歩引いた態度で依頼するなど、従者が見たら到底信じられない。
それほどまで、このノア=カートライトはテナルディエの全幅の信頼を置かれている。
「懲罰以外なら、なんなりと」
「ここブリューヌへ、七戦騎を全員終結させるのだ」
七戦騎とは、テナルディエ軍の精鋭であり、ブリューヌ転覆計画を執行する為の特殊部隊だ。
「ヴォルンさんにぶつける気ですか?別にいいですけど、ガイさんの出方を伺ってからの方がいいんじゃないですか?」
獅子王凱。伝説上の霊獣を冠する名は、既にテナルディエの耳に届いていた。
時代を動かす力を持ちながら、愛だの不殺だのそんな甘っちょろい戯言をほざき続ける半端もの。
眠れる獅子の存在は出方が分からないため、とりあえず心に留めておくことにした。
「一つ申し上げておきますけど、多分、ガイさんはこっちへなびきそうにないですよ?」
弱者を糧とする獅子王 にとって、弱者の糧となろうとする獅子王 の信念は、彼にとって相反するものでしかない。
「かまわん。言われるまでもなく、七戦騎は重要な特攻部隊。ブリューヌ内乱に合わせて、私が奴らの使い方を考えておく。『慣らし』も必要だろうからな。貴様とて、シシオウ=ガイとかいう男の決着を付けたいはずだ」
「あちゃーばれましたか?」
芝居がかったノアの言葉に、テナルディエは薄く笑みを浮かべた。こういう度胸の高さは、テナルディエが彼を気に入っている要素の一つである。
「それに、ホレーショーのように所在を掴み難い連中もいる。収集には時間がかかるはずだ。恐らく、七戦騎が終結する頃には、ブリューヌ内乱も目途が立っている」
「分かりました。では失礼します」
ノアを下がらせて、テナルディエは次の展開を構築する。
銀製のグラスに映る己の顔を見ながら、テナルディエはゆっくりつぶやく。
「そういえば、ガヌロンもジスタートの戦姫と付き合いがあったな。東の連中が転がり込んだこの情勢、あの男はどう出るやら」
今まで弱者しか溢れていなかったこのブリューヌだったが、今は強者がうごめく地獄となりつつある。
以前、ノアがテナルディエの傘下に入ったときに聞きだしたことを思い出した。ジスタートより遥か東の大陸で、憎悪と復讐の輪廻が織りなす、阿鼻叫喚の代理契約戦争があったことを――
『ジスタート・オルミュッツ公国・執務室』
春咲を告げる待雪草―バトスネジユ
夏夜を彩る煌蛍―キラホタル
秋夕を伝える紅葉―アカモミジ
冬薄を見舞う粉雪―コナユキ
それだけで紅茶 は十分おいしい。
品性と教養を思わせる哲学があるほど、リュドミラ=ルリエにとって、紅茶 とは日常に密接している必需品。
今、自身の公宮の執務室で、リュドミラは紅茶を静かに飲んでいた。
優雅な時を堪能しているとき、青い髪の少女の元へ一通の書簡が届けられた。
――エレオノーラ=ヴィルターリアが、ジスタート国王の無許可にてブリューヌ領内へ進軍――
――リュドミラ=ルリエ。エレオノーラ=ヴィルターリアの公判を執行するため、ジスタート憲章に基づき、王都へ出廷を要請する――
無意識に、溜息をついた。
要するに王都へ召集がかかったのである。
そんな書簡の内容の様子に僅かな一瞥を加えただけで、オルミュッツ公主は公務の処理を続けていた。
オルミュッツ公宮の最上階。彼女の机の小さな灯りは深夜になっても消える事はない。
自分で淹れた紅茶の香りに鼻孔をくすぐられつつ、リュドミラは月の映える窓際を覗いた。
連日続く激務に愚痴を漏らすことなく、彼女はこの夜も超過公務を続けていた。
「まったく、あの女は何をしでかしたのかしら?」
……修正。愚痴をこぼしていた。
傲岸不遜の野蛮人とは、リュドミラがエレオノーラに下した評価である。そして、初めて会ったときの第一印象である。
そして、ヴォルン伯爵と言ったかしら?どこの辺境の貴族か知らないけど、エレオノーラに付き合わされるなんて。
それでも……獣の皮を被ったような人でも、裏表がない分、嫌悪感がないのもまた事実だ。
別にエレオノーラを信じているわけではないが、きっと何か事情があったはずだ。直接会って話してみれば、真実が分かるはず。
―――なぜか、リュドミラにはそう思わずにはいられなかった。―――
『昼間・アルサス・セレスタ郊外』
さて、場所は変わってアルサスへ――――それは森と山に恵まれた、ブリューヌ領内の辺境土地である。中心都市セレスタが中心にそびえ、様々な穀倉部区画と、森や山によっての天然区画で構成されている。
中心都市と言っても、市民が想像するような豪華性や、賑わいは垣間見えない。土地の特色による税収の為なのか、ここの領主様は、贅沢とは無縁の生活を送っている。むしろ、それがティグルの気性にとって丁度いいのかもしれない。それでも、森や大地の配色を考慮しているのか、美観は十分に考慮されており、領主の敷地の大部分は一般住民に開放されていた。住民の生活を支える水車や風車でさえ、美しく、規則的に整列し、陽風と澄川を全体で受けて、力強く回転している。
久しぶりの平穏。凱はセレスタを出て、ユナヴィールの村へ向かって一人で街道を歩いていた。アルサスの特色なのか、空気は澄みきっており、そよぐ風はどこかひんやりとしていて心地よかった。
かつて、アルサスの民は懸命に働きながらも、平和に暮らしてきた。にもかかわらず、テナルディエ軍は兵をアルサスへ差し向けてきた。
故に、今まで外界に関心のなかった住民は、自由に領内の村同士を行きかうことをほどんどなくした。ティグルによって行動を規制されていたわけではない。常に臨戦態勢をとる必要があると分かった以上、それに伴う緊張感と責任感が、村の住民の心を縛り付け、行動を自粛させていたのだ。
目的地に歩いていく行為が、本来なら凱にとって楽しいはずである。だが、今はアルサスどころか、ブリューヌ国内の情勢自体が危うい。
気ままに歩いていると、待ち合わせの場所についてしまったが、時間を潰す必要はなさそうだ。しばらく穀倉地帯の分け道を歩こうかと思った凱は、彼方を眺めて二つの影を見つけた。
「ティグルヴルムド卿。それにティッタ。もう来てたのか」
「あ、あれ?もうそんな時間ですか?」
あいにく、この世界には日本人の常識で言う時計は無い。独立交易都市のように、24時間式の時刻体制が導入されていない以上、彼らは概ね太陽の動きに沿って行動しているとされる。1刻がだいたい2時間。まだ分や秒の概念は存在しない。だから、「もうそんな時間ですか?」というティッタの台詞が、妙におもしろかった。
ティグルの背中で居眠りしていたのか、ティッタはあわわと取り乱していた。そんな仕草に凱はなんだか癒された。
待ち合わせの相手は、くすんだ赤い若者と、彼に従う侍女の二人だった。
◇◇◇◇◇◇◇◇
凱とティグルは並んで小さな丘に座り込み、ティッタのお弁当を食べていた。
二人とも、ティッタの料理は大の好物であり、自然に恵まれたアルサスだったことも思えば、ティッタの弁当は必然である。
野道だからといって、アルサスで生まれ育ったティグルとティッタには気にする必要もないし、その点は凱にも似たようなものといえる。
「美味しかった……!」
「ああ、ティッタの御飯は最高だよな!」
言いつつも、凱はティグルの食欲を気にしていた。小食だったわけではない。むしろ、ありすぎた。
(そういえば、早く着いた俺よりも、先に来ていたな。一体、いつからここにいたのだろう?)
そんな凱の思考は、いきなりハンカチをティグルに拭き付けてきたティッタによって、中断させられた。
「ティグル様!口元にジャムがついてますよ」
「こら、よせ。ティッタ。ガイさんが見てるだろ?」
そんな光景を見て、凱は思わず漏らし笑いをしそうになった。しばらく、ティッタの攻撃とティグルの応戦を見守ることにした。
凱の視線を気にしているのか、ティグルはなんだか恥ずかしくなった。
「そ、それにしても、狩りをするにはいい日だな。ティッタ」
ティグルは無理矢理誤魔化した。これ以上、ティッタのおもちゃにされたくない。
こういう時、女は男をすぐ子ども扱いしたがる。口元にジャムを残したままという絶好の材料を与えたティグルに非があるわけだが――
「やっといつものティグル様に戻ってくださいましたね」
「あ……いつもの俺と違っていたか?」
「いつものティグル様なら、狩りをするにはいい日だ。ぐらいのことは仰るから……」
ティッタの言葉は、昼寝と狩りを趣味とするティグルがいつも出る口癖だ。
「え……」
自覚していなかったことを指摘され、ティグルは浮かない顔をした。
凱には、やっとティグルの心が抱いているものを理解できた。
◇◇◇◇◇◇◇◇
「ティグルヴルムド卿」
しばらく沈黙が続いたために、凱はくすんだ赤い若者に声を掛けた。
「すみませんガイさん、見苦しいところを見せてしまって……あと、長くて呼びにくかったら、俺の事はティグルでいいです」
改めて紹介する。
そう凱に自分の愛称を許す少年、ティグルヴルムド=ヴォルンという。
凱の見たところ、彼は年相応の普通の少年となんら変わりはない。いや、普通を遥かに超えた、勇気ある少年だ。ディナントの戦いから始まった、常ならざる運命に翻弄されながらも、ティグルは弓一つで領民を守る為に戦ってきた。
だから、凱はこの少年の事を尊敬する貴族として、アルサスを守り抜いた戦友として、ティッタが慕う心優しき領主として、知ることが出来たことを誇りに思っている。
少年が自分から口を開くまで、青年は無理に話を聞き出そうとは思わなかった。
「あの、ガイさん」
ティグルが黙り込んでいたのは、そんなに長いことではない。だが、なぜか、この場に居合わせていた全員にとって長く感じられていた。
「嘘って、いけないことですよね」
「ウソ……つきたいのか?」
「い、いえ!つきたくないです!」
「なら別にいいんじゃないか?」
「え……」
ティッタもいつしか凱の言葉を聞き入っていた。
「ウソって、いっぱいあるんだよな。つきたくないウソ。つかなければならないウソ。それも、自分の為じゃなくて、誰かのためのね。だったら、俺もいっぱいウソをついてるさ」
「「ガイ……さんも?」」
「ああ、そうさ」
凱は自分の左手につけている獅子篭手を見せてくれた。
「こんなこと言うのもみっともないけど、アルサス防衛戦の時……俺、怖かったんだ」
「怖いんですか?ガイさんでも?」
「ああ、怖いさ。やっぱり、実戦を重ねても、怖い」
ティグルとティッタは、信じられないという表情を浮かべて、凱を見上げた。一途に信じる強い想いが、その瞳にはめ込まれている。若者たちを安心させようと、凱は微笑みを浮かべた。
「そんな目で見るなよ。ティグル、ティッタ。ところで、勇気って何だと思う?」
勇気という意味は、なんとなく直感で理解していたが、いざ正面から問われると、言葉が出てこなくなる。
「怖い気持ちを恐れずに向かう心」
そうティグルが回答した。
「そうさ。勇気ってのは、怖い気持ちを乗り越える強い心の事さ。怖さを知らない奴に、勇気なんて必要ない。だから、決して勇者にはなれない」
最後の方はよくわからなかったが、「そっか……そうなんだ」と二人はつぶやいていた。
(ディナントの戦いの野営の時、マスハス卿も言っていたな。剣や槍を扱えることが、勇気の証明にならないって)
そんな皮肉を、思い出した。
「テナルディエ軍が明日、アルサスに迫ってくる。どうしても怖かった。」
「分かります。あたしも、ティグル様をずっと待ち続ける間は、ずっと怖かったです」
「そうだろうな」
凱はティッタに向けて深くうなずいた。今だ、凱が乗り越えられない強さを、この少女は既に乗り越えてきたのだ。
「ティッタは……俺の戦いをどう思った?」
出来るだけ優しい口調で凱は、ティッタに話しかけた。
アルサス防衛戦の時、多分ヴォルン邸の2階で彼女は見えていたはずだ。
人間を遥かに超えた、力を以て――
「……嬉しかったです。本当だったら、あたしたちとガイさんって、出会うはずがなかった。そして、なんだか心に灯がともったような感じがしました。みんなみんな、強くて優しいガイさんが大好きなんです」
「ありがとな。ティッタ……でも、俺自身、この力が怖いんだ」
ティッタにはとても信じられなかった。どんなに強い相手でも、凱はいつも恐れずに立ち向かっていった。そして、眩しいくらいの笑顔でみんなを安心させていた。
「二人とも、そんな目で見るなよ。ただ……俺自身というより、俺の心に住み着いている獅子王 が怖いんだ」
「それって……」
獅子王 とは、ブリューヌやジスタートに出てくる、英雄譚等に出てくる伝説上の霊獣である。
数多の動物の頂点に立つ百獣の王である獅子をたたえて言う言葉。また、獅子のように勇ましい王。すなわち、勇者。
だが、かつて十の神々の文明を埋葬したとして、大陸の殆どでは凶兆となぞられている。
今でも、国家の要人を闇へ葬ったという歴史が語られているほど、ブリューヌとジスタートの神官達に、レグヌスは忌み嫌われている。
戦意高揚が、心の檻をこじ開けようとして、凱を凱でいられなくする。
故に、獅子王を孤独にする。
その時、孤独の寂しさに苛まれ、人肌の恋しさを求めて、いつか守るべき民すらも喰らうんじゃないか――
そう思わずにはいられない。
だから――
「俺を信じてくれているアルサスの人たちの為にも、そういう弱音は吐けない、その人の前では、俺は勇者でなければならない。普通の人を超える力を持つものとして」
やがて、凱は少し自嘲気味に言葉を続ける。
「でも、俺は……いつか、自分が獅子王 に立ち戻ってしまうんじゃないか……テナルディエ軍のように、いつか民を虐げる存在になるんじゃないか……そう思うと、怖いんだ」「そんなことはありません!」
突然声を荒げて立ち上がったティグルに、凱とティッタは驚いた。
「俺には、ガイさんの抱えている怖さや、昔、何があったかなんて……知りません。でも、現にアルサスを……ティッタを……領民を守ってくれたじゃないですか!ガイさんは……ガイさんは……不殺を貫く勇者じゃないですか!非道なテナルディエ軍とは違う!」
何気なくティグルの口からでた言葉。それを聞いた凱とティッタは目を丸くした。ただ、凱にとって、それはティグルからの叱咤激励のように感じた。
「それ比べて……俺は……俺は……」
「ティグル?」
「結局、みんなに助けられて、それ以上に……自分の無力を痛感しました。アルサスは兵を集めようとすれば、せいぜい百人程度。対してテナルディエ公爵は良くて1万、最悪は3万……昨日の宴で、ガイさんの勇戦を聞いて思いました。結局は、『ああ、俺はガイさんみたいになれない』と分かっちゃって……エレンと隣で戦ってみて、彼女の凄さを知って……ティッタには怖い思いをたくさんさせて……俺には何もできなくて……」
地面がいつしか濡れていた。見上げると、ティグルは双眸に滂沱の涙を流していた。
ティグルとて、外つ国とはいえジスタートの兵を借りてアルサスへ戻ってきた。エレンの力を借りて、リムの力を借りて、みんなの力を借りて、テナルディエ軍を撃退できた。
実の所、ティグル自身は、少しも勝ったとは思えない。
勝利したのは、ジスタートで、実際に民を……ティッタを守ったのは、シシオウ=ガイという青年だ。
俺は……民に何ができたんだ?
自分だって、逃亡寸前の、ザイアンが駆る飛竜を穿ち、貫いた。だが、それは黒き弓の力。エレンのように、竜具を手足のように操れるようでもなく。自分でも弓の全容を知らない故、自分自身の力とは言えない。最初は、この弓の力があればきっと、なんて思っていたが、結局はただの強がりだと理解して。
悔しくて、悔しくて、自分がいかに矮小な存在かが理解できた。
俺には、戦う才能がない。勇気がない。
それをわかってしまうのが、怖かった。
「ずっと昔、父上と王宮に言ったとき、弓が取り柄だと知られたら、多くの人に笑われました。ディナントの戦いの前、ザイアンにも笑われました。『弓しか使えない分際で……弓は白人の前に出れない、臆病者の武器だ』って、だって、実際そうじゃないですか。これからテナルディエ公爵と戦うって時に……こんなに震えてる」
見れば、ティグルの腕が小刻みに震えていた。
情けないくらいに、ティグルは悔し涙を流していた。多分、ティグルは本心をさらけ出している。
朝からどこか、ティグルは浮かない顔をしていた。ティッタにはそう見えていた。
少し、凱は混乱した。ティッタもだ。
ウソから始まった彼らの会話は、いつしか軌条変更していたのではないか?そう思わずにはいられない。
それでも……
一つ一つ込められたティグルの想い。そして、それを包み隠さずに本気で話してくれる気持ち。ティグルには申し訳ないが、凱はなんだか嬉しかった。
「話は戻るけど、俺は、嘘をたくさんついてるさ。みんなが俺を勇者にしてくれたから、俺を信じてくれてる人たちを……誰も不安にさせたくないんだ。みんなの前で、俺は俺でなくちゃならない……みんなが俺を勇者と信じてくれていることを……人を超える力を持つものとして」
少し、ティグルは混乱した。聞けばどこか矛盾が生じているようにも聞こえる気がしたのだ。ただ、それを理解できる明晰な思考を持ち合わせているほど、ティグルはまだ大人ではない。
それでも、凱の込めた勇気という言葉に込めた想い。そして、包み隠さず話してくれる凱の気持ちには、ティグルとしても、ティッタとしても嬉しかった。
(ティグル様……ずっと気を張り詰めていたから……お屋敷でも一度2期に上がって降りてきた時には、ひどくさえなっているように見えた……)
ティグルも、知らず知らずのうちにウソをついていた。本当は弱音を吐きたかったはずだ。
貴族としての責務がティグルを支えるものであり、そして、縛り付けるものであったからだ。
領民を、ティッタを、不安にさせたくないから、その人たちの前でずっと、笑顔を振りまいていて――
「ティグル。勇者は何を対価に動くと思う?」
「それは……」
ティグルは、自分の領地を対価にして、エレンの力を借りた。それは分かる。一公国を治める立場なら、領民と兵に報いる為には目に見える対価が必要だからだ。
では、凱は何を対価に、今回の戦いに力を貸してくれたんだろう?
「簡単さ。ただ心から「助けて」って、一言言ってくれたから。だから、俺はアルサスの人たちを守る為に力を振るった。自分の怖い気持ちにウソまでついて」
「……ガイさん!」
ティグルの心は震えた。
自分とティッタだけは、どんな時でも、何があっても、ティグルの味方だと伝えたいのが分かったからだ。それが、ティグルの胸を熱い想いで満たしていた。
思えば、凱もなんだか恥ずかしくなった。あまりにも、素の自分を出しすぎたのではないか?もう少し、大人として気の利いた言葉が選べなかったものかと――
「ウソも悪くない時があると説明するのに、ウソをつかないわけにはいかないってのも、おかしい話だよな」
凱がそういうと、ティグルは再び空を見上げた。天上に浮かぶ太陽の輝きに背を押されたかのように、ティグルはティッタに語り始めた。
「ティッタ。俺はこれからみんなに、ティッタにもいっぱいウソをつく。自分の為ではなく、みんなの為に、ティッタの為に」
「はい!ティグル様のウソは、誰かの為のウソだってことを、あたしは知ってます!」
眩しい空を見上げながら、ティグルがいかなる決意をしたのか、この時、凱もティッタも知る由はない。
そして、この瞬間こそが、『英雄へ至る伝説……そして勇者から紡がれる神話へ』の始まりであり、この輝きに満ちたアルサスこそが始まりの地であったことも……
『数刻前・中心都市セレスタ・神殿前』
話は少し巻き戻る。
宴を終えた翌日の朝から、ティグル達は町の復興に向けての作業で忙殺していた。
昨日、あれほどの惨劇にも関わらず、セレスタの住民に死者が出なかったのは不幸中の幸いだった。
事情はともあれ、ティグルヴルムド=ヴォルンはアルサスへの帰還を果たした。
だが、テナルディエ公爵のアルサス侵攻については、ティグルにとって到底納得できるものではない。領土をめぐる攻防で、負傷者まで出ているのだから。
ティグルの今後を決めるよう声を掛けたエレンは神殿へ向かい、リムに今後の予定を伝える。彼女らが率いてきた兵は、町の空き家や、神殿の内部で寝泊まりしている。
「選抜した兵はお前に任せる。国王を黙らせたらすぐ戻ってくる。それまで頼むぞ」
「エレオノーラ様は、随分と彼を信頼されているのですね?」
「お前もそうだと思ったが……ただ」
「ただ?」
「やはり、あの男……ガイの姿勢は気に入らない」
それに関しては、リムも概ね同じ意見を持っていた。
不殺。殺さず。奪わない。
個に対して全体を優先しなければならない立場のエレンにとって、凱の心情は理解できるものではない。
テナルディエ兵を延命させたことは、非常に危険な行為だ。一軍を率いる将として、結果的には味方や仲間を危険に晒す可能性は見過ごすことなど出来ない。もし、助けた敵が再び自分の命を狙うか分からない。
ジスタート軍が到着するまで、凱の撃破数は見積もって、テナルディエ軍全体の約3分の1.結果として、モルザイム平原で迎え撃った時は、当初は3倍と推測していた数字が2倍に収まった。
本来なら、自軍が有利になり、敵軍が不利になるという、喜ばしい事態のはずだった。
しかし、凱の削り取った数字の正体は、全て殺されずに倒された敵兵なのだ。全員捕虜にすることなど当然できず、首をはねるにも手間がかかる。結局彼らに対して逃がすという選択しかとれない。
つまり、再び相手に剣を持たせる機会を与えてしまったのだ。
これでは、挑んできた敵に敬意を払い、勇敢に戦って散っていった者が報われないではないか。侮辱以外の何物でもない。
自分も相手も守りたいなんていう我儘は戦場では通用しない。
殺さないという事は、当然といっていいほど損害 を負うのである。一公主であるエレンが、凱を非難するのも当然と言える。
どちらにしても、凱やエレンにしても、「相手に未来を与える」という点は一緒である。
「私は、あの男を見損なうべきなのだろうか」
正直、エレンには凱への評価に悩んでいた。
不殺主義の絶対条件は、まず相手より圧倒的に強いこと。
相手に選択肢を与えることができ、常に自分が優位に立っていないと出来ないからだ。
でなければ自分が殺されて終わりである。
表面的な凱の強さを、歴戦の戦士としても優秀なエレンだからこそ分かる。ただ、強いから殺さないという矛盾だけは分からない。
「ともかく、あいつの事は取りあえず忘れよう。警戒したところで何も始まらない」
そうなのだ。これから戦姫たる自分は、仕える王に対して戦いの正当性を主張しなければならない。
今回において王は、承認を得ていないエレンの独断専行と見なしている。ティグルを助ける為に力を貸してくれた兵や、ライトメリッツに残っている兵、領民達にも危機に見舞われる。
エレンには自国の民を守る義務がある。その為、今一度王都へ向かい、正式に参戦の許可をもらわなければならない。
「リム。ティグルの戦う理由を答えろ」
「第一に領民の安全。テナルディエ公爵の非道な行いにふさわしい処罰を与える事。彼に賠償金を支払わせること。今後の内乱における中立の立場を維持。この4点です」
「そうだ。ティグルは戦う理由をちゃんと主張している」
エレンのその言葉は、リムに不思議な沈黙をもたらした。
無論、危険を顧みず、戦いの渦中に身を置いたライトメリッツの兵達にとって、気持ちは一つである。
だが、本格的にブリューヌの内乱へ自分たちが赴くことは、『ライトメリッツの防衛戦』からの逸脱を意味している。
それは、自分たちの戦いの意義を、あらためて考えるための……沈黙だった。
NEXT
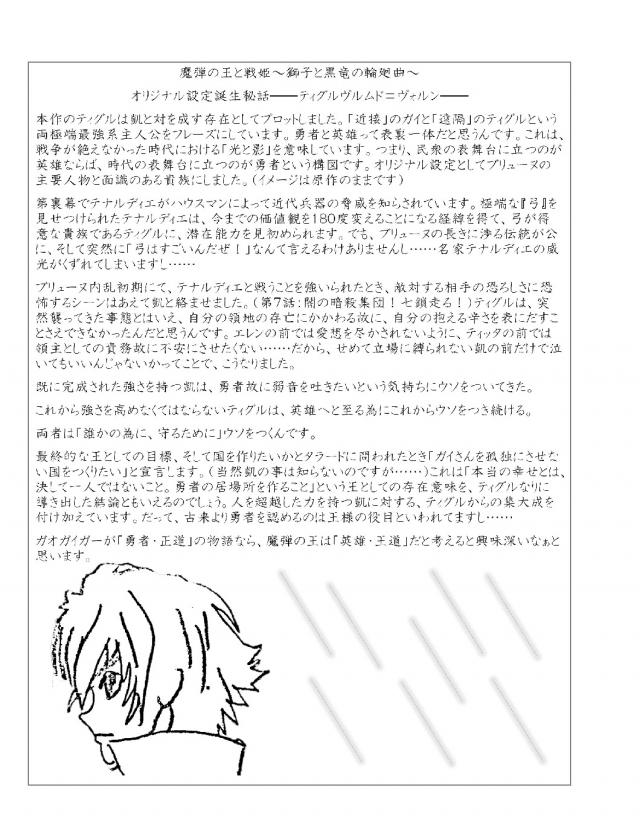
ページ上へ戻る七鎖―セラシュ。
それは、要人暗殺を受け持つ名うての暗殺集団。必ず7人で行動するとして知られる。
現在こそ、ブリューヌの王都はニースとされているものの、国が興る以前は、アルテシウムこそブリューヌの王都としてあり続けた。
元々そのアルテシウムが王都の時代から仕えている、セラシュはいわば王政府の密偵だった。
光を浴びる表向きの任務は警護。闇に紛れる裏の任務は諜報活動。特に諜報活動は特筆すべき点であり、日常的に官僚や大貴族、ブリューヌ全土を観察し、異常があれば報告するよう定められたと言われている。
故に彼らは影の見張り役として、ブリューヌの長きに渡る歴史と流れを、見守り続けてきた。
――全ては、ブリューヌの繁栄と平和を目指して――
例え身分が低くても、特別な役職の名目で国主に近づくことが出来たので、国主の意志を反映できる立場だった。
その特殊な任務の為、本来セラシュは功績を上げて、出世する機会に恵まれる……はずだった。
時代の流れと共に、アルテシウムからニースへ王政が移ると、治安維持の騎士団や貴族等が創設された。それに伴い、政治経済がうまく循環するようになると、セラシュもその役目を終える事となった。
活躍できる場を失った彼らはその後、新たな職に就くことが出来ず、
その彼らは今、ブリューヌの双璧を成す貴族の一室にいる。
「セラシュか」
早速、テナルディエは依頼内容を説明する。任務内容を理解、承知すると、「直ちに」と言い残して音を立てず、部屋から消えていった。
ただ一人だけ、御頭を呼び止めた。
「何故私に仕える?かつてテナルディエ家はアルテシウム王制の倒世運動を行ってきた一族。アルテシウム出身の貴様らから見れば、私は復讐の対象だ。何故?」
ブリューヌ変革期における抵抗運動から始まるガヌロン家との因縁は、遥か昔から行われている。
存在の意味とアルテシウムの伝統を破壊した大柄の男は、セラシュにとってテナルディエは戦犯の血を引く愚物でしかないはずだ。
「我ら
軽く一礼すると、御頭も他のセラシュと同様に、音を立てずに部屋から出ていった。
10数える間くらいか、再び戸が開く。入ってきたのは、長年テナルディエ家に仕える占い師ドレカヴァクだ。
「虫を潰すのに、斧を用いるようでありますな。辺境の貴族を始末するのに、名うての暗殺集団を差し向けるとは」
「辺境の貴族だから……こそだ。むしろ、これくらい乗り越えてもらわねばならぬ。」
テナルディエにとって、ティグルへ与えた境遇はいわば「課題」に過ぎない。
目測通り、ティグルヴルムド=ヴォルンはジスタート軍を引き入れて戻ってきた。
そして、我がテナルディエ軍を撃退した。それも、竜を屠ったという報告を受けて。
だからこそ思考していた。次の「課題」をぶつけるにはどうしたらいいかと――
思考を巡らせたが、結局、一去した。
理由は『何者かが』ドナルベイン一派を消滅させたとの事。ヴォージュ山脈に集会所を構える連中なら、オルミュッツに偽装して周辺貴族の圧力に使えないか、もしくは連絡係としてうまく使えないかと考えていたが、甲冑を着せる予定の連中がいなくなった為、思慮していても仕方がない。
もう一つは、時折陰湿さや狡猾さを持つテナルディエらしからぬ理由だった。
「私は品性まで売った覚えはない」
これは失礼と、くぐもった笑いを漏らして一礼した。
(いずれにせよ、ライトメリッツの戦姫を引きはがす必要があるな)
テナルディエとしては、アルサスの小僧をブリューヌの渦中に投げ込みたいところだ。一時的にライトメリッツの力を必要としていたらしいが、今後はブリューヌの為に軍を引いてもらいたいと思っている。
戦姫には、やはり戦姫しかないのか。
「戦姫の方はどうなさるので?」
「それは私の方で対処する。それから……新たな竜と、例のものはいつ頃用意できる?」
「竜の方は、いくばくかの金銭と一月程の時間を要します。ただ……」
「ただ?」
「例のものといえば……デュランダルの兄弟剣と、カヴァクなる工芸品は半年程の時間を要します」
「仕方がない。だが……頼む」
それからテナルディエは鈴を鳴らし、従者を呼びつけると金貨を持ってくるよう命ずる。やがて人頭大の袋を持ってきて、ドレカヴァクに渡すよう指示する。
それから分厚い手を振って、ドレカヴァクに退出を命ずる。音もなく退出したドレカヴァクの姿を確認すると、入れ替わるように一人の優男が入ってきた。
「失礼します。テナルディエさん」
明快な口調で親しげに話しかけるこの男、ノア=カートライト。その表情はいつも笑みを浮かばせている。
この屋敷で、不遜な態度を示せば、家族ともども即刻処刑されてしまうだろう。例外として、そのような不遜な態度をとれるのは、ノアとドレカヴァク、以下数名のみだった。
「ザイアンは何をしている?」
「ザイアン様は釈放されたものの、ネメタクム帰領へは至らず……正確には、しばらくは戻らないそうです」
そうか、とそう小さくつぶやき、情を表に出さず頭の中で振り切って本題に入る。
この結果が分かっていたからこそ、衝撃は表に出さなかった。それがザイアンの為ともなり、ヴォルンの可能性を拡大する為の計画だ。
事実、ノアは今回のアルサス遠征において、ただの監視役だった。ガヌロンの動向を探る密偵として――
「ノア。貴様に一つ、やってほしいことがある。頼まれてくれるか?」
苛烈者として知られるテナルディエが、一歩引いた態度で依頼するなど、従者が見たら到底信じられない。
それほどまで、このノア=カートライトはテナルディエの全幅の信頼を置かれている。
「懲罰以外なら、なんなりと」
「ここブリューヌへ、七戦騎を全員終結させるのだ」
七戦騎とは、テナルディエ軍の精鋭であり、ブリューヌ転覆計画を執行する為の特殊部隊だ。
「ヴォルンさんにぶつける気ですか?別にいいですけど、ガイさんの出方を伺ってからの方がいいんじゃないですか?」
獅子王凱。伝説上の霊獣を冠する名は、既にテナルディエの耳に届いていた。
時代を動かす力を持ちながら、愛だの不殺だのそんな甘っちょろい戯言をほざき続ける半端もの。
眠れる獅子の存在は出方が分からないため、とりあえず心に留めておくことにした。
「一つ申し上げておきますけど、多分、ガイさんはこっちへなびきそうにないですよ?」
弱者を糧とする
「かまわん。言われるまでもなく、七戦騎は重要な特攻部隊。ブリューヌ内乱に合わせて、私が奴らの使い方を考えておく。『慣らし』も必要だろうからな。貴様とて、シシオウ=ガイとかいう男の決着を付けたいはずだ」
「あちゃーばれましたか?」
芝居がかったノアの言葉に、テナルディエは薄く笑みを浮かべた。こういう度胸の高さは、テナルディエが彼を気に入っている要素の一つである。
「それに、ホレーショーのように所在を掴み難い連中もいる。収集には時間がかかるはずだ。恐らく、七戦騎が終結する頃には、ブリューヌ内乱も目途が立っている」
「分かりました。では失礼します」
ノアを下がらせて、テナルディエは次の展開を構築する。
銀製のグラスに映る己の顔を見ながら、テナルディエはゆっくりつぶやく。
「そういえば、ガヌロンもジスタートの戦姫と付き合いがあったな。東の連中が転がり込んだこの情勢、あの男はどう出るやら」
今まで弱者しか溢れていなかったこのブリューヌだったが、今は強者がうごめく地獄となりつつある。
以前、ノアがテナルディエの傘下に入ったときに聞きだしたことを思い出した。ジスタートより遥か東の大陸で、憎悪と復讐の輪廻が織りなす、阿鼻叫喚の代理契約戦争があったことを――
『ジスタート・オルミュッツ公国・執務室』
春咲を告げる待雪草―バトスネジユ
夏夜を彩る煌蛍―キラホタル
秋夕を伝える紅葉―アカモミジ
冬薄を見舞う粉雪―コナユキ
それだけで
品性と教養を思わせる哲学があるほど、リュドミラ=ルリエにとって、
今、自身の公宮の執務室で、リュドミラは紅茶を静かに飲んでいた。
優雅な時を堪能しているとき、青い髪の少女の元へ一通の書簡が届けられた。
――エレオノーラ=ヴィルターリアが、ジスタート国王の無許可にてブリューヌ領内へ進軍――
――リュドミラ=ルリエ。エレオノーラ=ヴィルターリアの公判を執行するため、ジスタート憲章に基づき、王都へ出廷を要請する――
無意識に、溜息をついた。
要するに王都へ召集がかかったのである。
そんな書簡の内容の様子に僅かな一瞥を加えただけで、オルミュッツ公主は公務の処理を続けていた。
オルミュッツ公宮の最上階。彼女の机の小さな灯りは深夜になっても消える事はない。
自分で淹れた紅茶の香りに鼻孔をくすぐられつつ、リュドミラは月の映える窓際を覗いた。
連日続く激務に愚痴を漏らすことなく、彼女はこの夜も超過公務を続けていた。
「まったく、あの女は何をしでかしたのかしら?」
……修正。愚痴をこぼしていた。
傲岸不遜の野蛮人とは、リュドミラがエレオノーラに下した評価である。そして、初めて会ったときの第一印象である。
そして、ヴォルン伯爵と言ったかしら?どこの辺境の貴族か知らないけど、エレオノーラに付き合わされるなんて。
それでも……獣の皮を被ったような人でも、裏表がない分、嫌悪感がないのもまた事実だ。
別にエレオノーラを信じているわけではないが、きっと何か事情があったはずだ。直接会って話してみれば、真実が分かるはず。
―――なぜか、リュドミラにはそう思わずにはいられなかった。―――
『昼間・アルサス・セレスタ郊外』
さて、場所は変わってアルサスへ――――それは森と山に恵まれた、ブリューヌ領内の辺境土地である。中心都市セレスタが中心にそびえ、様々な穀倉部区画と、森や山によっての天然区画で構成されている。
中心都市と言っても、市民が想像するような豪華性や、賑わいは垣間見えない。土地の特色による税収の為なのか、ここの領主様は、贅沢とは無縁の生活を送っている。むしろ、それがティグルの気性にとって丁度いいのかもしれない。それでも、森や大地の配色を考慮しているのか、美観は十分に考慮されており、領主の敷地の大部分は一般住民に開放されていた。住民の生活を支える水車や風車でさえ、美しく、規則的に整列し、陽風と澄川を全体で受けて、力強く回転している。
久しぶりの平穏。凱はセレスタを出て、ユナヴィールの村へ向かって一人で街道を歩いていた。アルサスの特色なのか、空気は澄みきっており、そよぐ風はどこかひんやりとしていて心地よかった。
かつて、アルサスの民は懸命に働きながらも、平和に暮らしてきた。にもかかわらず、テナルディエ軍は兵をアルサスへ差し向けてきた。
故に、今まで外界に関心のなかった住民は、自由に領内の村同士を行きかうことをほどんどなくした。ティグルによって行動を規制されていたわけではない。常に臨戦態勢をとる必要があると分かった以上、それに伴う緊張感と責任感が、村の住民の心を縛り付け、行動を自粛させていたのだ。
目的地に歩いていく行為が、本来なら凱にとって楽しいはずである。だが、今はアルサスどころか、ブリューヌ国内の情勢自体が危うい。
気ままに歩いていると、待ち合わせの場所についてしまったが、時間を潰す必要はなさそうだ。しばらく穀倉地帯の分け道を歩こうかと思った凱は、彼方を眺めて二つの影を見つけた。
「ティグルヴルムド卿。それにティッタ。もう来てたのか」
「あ、あれ?もうそんな時間ですか?」
あいにく、この世界には日本人の常識で言う時計は無い。独立交易都市のように、24時間式の時刻体制が導入されていない以上、彼らは概ね太陽の動きに沿って行動しているとされる。1刻がだいたい2時間。まだ分や秒の概念は存在しない。だから、「もうそんな時間ですか?」というティッタの台詞が、妙におもしろかった。
ティグルの背中で居眠りしていたのか、ティッタはあわわと取り乱していた。そんな仕草に凱はなんだか癒された。
待ち合わせの相手は、くすんだ赤い若者と、彼に従う侍女の二人だった。
◇◇◇◇◇◇◇◇
凱とティグルは並んで小さな丘に座り込み、ティッタのお弁当を食べていた。
二人とも、ティッタの料理は大の好物であり、自然に恵まれたアルサスだったことも思えば、ティッタの弁当は必然である。
野道だからといって、アルサスで生まれ育ったティグルとティッタには気にする必要もないし、その点は凱にも似たようなものといえる。
「美味しかった……!」
「ああ、ティッタの御飯は最高だよな!」
言いつつも、凱はティグルの食欲を気にしていた。小食だったわけではない。むしろ、ありすぎた。
(そういえば、早く着いた俺よりも、先に来ていたな。一体、いつからここにいたのだろう?)
そんな凱の思考は、いきなりハンカチをティグルに拭き付けてきたティッタによって、中断させられた。
「ティグル様!口元にジャムがついてますよ」
「こら、よせ。ティッタ。ガイさんが見てるだろ?」
そんな光景を見て、凱は思わず漏らし笑いをしそうになった。しばらく、ティッタの攻撃とティグルの応戦を見守ることにした。
凱の視線を気にしているのか、ティグルはなんだか恥ずかしくなった。
「そ、それにしても、狩りをするにはいい日だな。ティッタ」
ティグルは無理矢理誤魔化した。これ以上、ティッタのおもちゃにされたくない。
こういう時、女は男をすぐ子ども扱いしたがる。口元にジャムを残したままという絶好の材料を与えたティグルに非があるわけだが――
「やっといつものティグル様に戻ってくださいましたね」
「あ……いつもの俺と違っていたか?」
「いつものティグル様なら、狩りをするにはいい日だ。ぐらいのことは仰るから……」
ティッタの言葉は、昼寝と狩りを趣味とするティグルがいつも出る口癖だ。
「え……」
自覚していなかったことを指摘され、ティグルは浮かない顔をした。
凱には、やっとティグルの心が抱いているものを理解できた。
◇◇◇◇◇◇◇◇
「ティグルヴルムド卿」
しばらく沈黙が続いたために、凱はくすんだ赤い若者に声を掛けた。
「すみませんガイさん、見苦しいところを見せてしまって……あと、長くて呼びにくかったら、俺の事はティグルでいいです」
改めて紹介する。
そう凱に自分の愛称を許す少年、ティグルヴルムド=ヴォルンという。
凱の見たところ、彼は年相応の普通の少年となんら変わりはない。いや、普通を遥かに超えた、勇気ある少年だ。ディナントの戦いから始まった、常ならざる運命に翻弄されながらも、ティグルは弓一つで領民を守る為に戦ってきた。
だから、凱はこの少年の事を尊敬する貴族として、アルサスを守り抜いた戦友として、ティッタが慕う心優しき領主として、知ることが出来たことを誇りに思っている。
少年が自分から口を開くまで、青年は無理に話を聞き出そうとは思わなかった。
「あの、ガイさん」
ティグルが黙り込んでいたのは、そんなに長いことではない。だが、なぜか、この場に居合わせていた全員にとって長く感じられていた。
「嘘って、いけないことですよね」
「ウソ……つきたいのか?」
「い、いえ!つきたくないです!」
「なら別にいいんじゃないか?」
「え……」
ティッタもいつしか凱の言葉を聞き入っていた。
「ウソって、いっぱいあるんだよな。つきたくないウソ。つかなければならないウソ。それも、自分の為じゃなくて、誰かのためのね。だったら、俺もいっぱいウソをついてるさ」
「「ガイ……さんも?」」
「ああ、そうさ」
凱は自分の左手につけている獅子篭手を見せてくれた。
「こんなこと言うのもみっともないけど、アルサス防衛戦の時……俺、怖かったんだ」
「怖いんですか?ガイさんでも?」
「ああ、怖いさ。やっぱり、実戦を重ねても、怖い」
ティグルとティッタは、信じられないという表情を浮かべて、凱を見上げた。一途に信じる強い想いが、その瞳にはめ込まれている。若者たちを安心させようと、凱は微笑みを浮かべた。
「そんな目で見るなよ。ティグル、ティッタ。ところで、勇気って何だと思う?」
勇気という意味は、なんとなく直感で理解していたが、いざ正面から問われると、言葉が出てこなくなる。
「怖い気持ちを恐れずに向かう心」
そうティグルが回答した。
「そうさ。勇気ってのは、怖い気持ちを乗り越える強い心の事さ。怖さを知らない奴に、勇気なんて必要ない。だから、決して勇者にはなれない」
最後の方はよくわからなかったが、「そっか……そうなんだ」と二人はつぶやいていた。
(ディナントの戦いの野営の時、マスハス卿も言っていたな。剣や槍を扱えることが、勇気の証明にならないって)
そんな皮肉を、思い出した。
「テナルディエ軍が明日、アルサスに迫ってくる。どうしても怖かった。」
「分かります。あたしも、ティグル様をずっと待ち続ける間は、ずっと怖かったです」
「そうだろうな」
凱はティッタに向けて深くうなずいた。今だ、凱が乗り越えられない強さを、この少女は既に乗り越えてきたのだ。
「ティッタは……俺の戦いをどう思った?」
出来るだけ優しい口調で凱は、ティッタに話しかけた。
アルサス防衛戦の時、多分ヴォルン邸の2階で彼女は見えていたはずだ。
人間を遥かに超えた、力を以て――
「……嬉しかったです。本当だったら、あたしたちとガイさんって、出会うはずがなかった。そして、なんだか心に灯がともったような感じがしました。みんなみんな、強くて優しいガイさんが大好きなんです」
「ありがとな。ティッタ……でも、俺自身、この力が怖いんだ」
ティッタにはとても信じられなかった。どんなに強い相手でも、凱はいつも恐れずに立ち向かっていった。そして、眩しいくらいの笑顔でみんなを安心させていた。
「二人とも、そんな目で見るなよ。ただ……俺自身というより、俺の心に住み着いている
「それって……」
数多の動物の頂点に立つ百獣の王である獅子をたたえて言う言葉。また、獅子のように勇ましい王。すなわち、勇者。
だが、かつて十の神々の文明を埋葬したとして、大陸の殆どでは凶兆となぞられている。
今でも、国家の要人を闇へ葬ったという歴史が語られているほど、ブリューヌとジスタートの神官達に、レグヌスは忌み嫌われている。
戦意高揚が、心の檻をこじ開けようとして、凱を凱でいられなくする。
故に、獅子王を孤独にする。
その時、孤独の寂しさに苛まれ、人肌の恋しさを求めて、いつか守るべき民すらも喰らうんじゃないか――
そう思わずにはいられない。
だから――
「俺を信じてくれているアルサスの人たちの為にも、そういう弱音は吐けない、その人の前では、俺は勇者でなければならない。普通の人を超える力を持つものとして」
やがて、凱は少し自嘲気味に言葉を続ける。
「でも、俺は……いつか、自分が
突然声を荒げて立ち上がったティグルに、凱とティッタは驚いた。
「俺には、ガイさんの抱えている怖さや、昔、何があったかなんて……知りません。でも、現にアルサスを……ティッタを……領民を守ってくれたじゃないですか!ガイさんは……ガイさんは……不殺を貫く勇者じゃないですか!非道なテナルディエ軍とは違う!」
何気なくティグルの口からでた言葉。それを聞いた凱とティッタは目を丸くした。ただ、凱にとって、それはティグルからの叱咤激励のように感じた。
「それ比べて……俺は……俺は……」
「ティグル?」
「結局、みんなに助けられて、それ以上に……自分の無力を痛感しました。アルサスは兵を集めようとすれば、せいぜい百人程度。対してテナルディエ公爵は良くて1万、最悪は3万……昨日の宴で、ガイさんの勇戦を聞いて思いました。結局は、『ああ、俺はガイさんみたいになれない』と分かっちゃって……エレンと隣で戦ってみて、彼女の凄さを知って……ティッタには怖い思いをたくさんさせて……俺には何もできなくて……」
地面がいつしか濡れていた。見上げると、ティグルは双眸に滂沱の涙を流していた。
ティグルとて、外つ国とはいえジスタートの兵を借りてアルサスへ戻ってきた。エレンの力を借りて、リムの力を借りて、みんなの力を借りて、テナルディエ軍を撃退できた。
実の所、ティグル自身は、少しも勝ったとは思えない。
勝利したのは、ジスタートで、実際に民を……ティッタを守ったのは、シシオウ=ガイという青年だ。
俺は……民に何ができたんだ?
自分だって、逃亡寸前の、ザイアンが駆る飛竜を穿ち、貫いた。だが、それは黒き弓の力。エレンのように、竜具を手足のように操れるようでもなく。自分でも弓の全容を知らない故、自分自身の力とは言えない。最初は、この弓の力があればきっと、なんて思っていたが、結局はただの強がりだと理解して。
悔しくて、悔しくて、自分がいかに矮小な存在かが理解できた。
俺には、戦う才能がない。勇気がない。
それをわかってしまうのが、怖かった。
「ずっと昔、父上と王宮に言ったとき、弓が取り柄だと知られたら、多くの人に笑われました。ディナントの戦いの前、ザイアンにも笑われました。『弓しか使えない分際で……弓は白人の前に出れない、臆病者の武器だ』って、だって、実際そうじゃないですか。これからテナルディエ公爵と戦うって時に……こんなに震えてる」
見れば、ティグルの腕が小刻みに震えていた。
情けないくらいに、ティグルは悔し涙を流していた。多分、ティグルは本心をさらけ出している。
朝からどこか、ティグルは浮かない顔をしていた。ティッタにはそう見えていた。
少し、凱は混乱した。ティッタもだ。
ウソから始まった彼らの会話は、いつしか軌条変更していたのではないか?そう思わずにはいられない。
それでも……
一つ一つ込められたティグルの想い。そして、それを包み隠さずに本気で話してくれる気持ち。ティグルには申し訳ないが、凱はなんだか嬉しかった。
「話は戻るけど、俺は、嘘をたくさんついてるさ。みんなが俺を勇者にしてくれたから、俺を信じてくれてる人たちを……誰も不安にさせたくないんだ。みんなの前で、俺は俺でなくちゃならない……みんなが俺を勇者と信じてくれていることを……人を超える力を持つものとして」
少し、ティグルは混乱した。聞けばどこか矛盾が生じているようにも聞こえる気がしたのだ。ただ、それを理解できる明晰な思考を持ち合わせているほど、ティグルはまだ大人ではない。
それでも、凱の込めた勇気という言葉に込めた想い。そして、包み隠さず話してくれる凱の気持ちには、ティグルとしても、ティッタとしても嬉しかった。
(ティグル様……ずっと気を張り詰めていたから……お屋敷でも一度2期に上がって降りてきた時には、ひどくさえなっているように見えた……)
ティグルも、知らず知らずのうちにウソをついていた。本当は弱音を吐きたかったはずだ。
貴族としての責務がティグルを支えるものであり、そして、縛り付けるものであったからだ。
領民を、ティッタを、不安にさせたくないから、その人たちの前でずっと、笑顔を振りまいていて――
「ティグル。勇者は何を対価に動くと思う?」
「それは……」
ティグルは、自分の領地を対価にして、エレンの力を借りた。それは分かる。一公国を治める立場なら、領民と兵に報いる為には目に見える対価が必要だからだ。
では、凱は何を対価に、今回の戦いに力を貸してくれたんだろう?
「簡単さ。ただ心から「助けて」って、一言言ってくれたから。だから、俺はアルサスの人たちを守る為に力を振るった。自分の怖い気持ちにウソまでついて」
「……ガイさん!」
ティグルの心は震えた。
自分とティッタだけは、どんな時でも、何があっても、ティグルの味方だと伝えたいのが分かったからだ。それが、ティグルの胸を熱い想いで満たしていた。
思えば、凱もなんだか恥ずかしくなった。あまりにも、素の自分を出しすぎたのではないか?もう少し、大人として気の利いた言葉が選べなかったものかと――
「ウソも悪くない時があると説明するのに、ウソをつかないわけにはいかないってのも、おかしい話だよな」
凱がそういうと、ティグルは再び空を見上げた。天上に浮かぶ太陽の輝きに背を押されたかのように、ティグルはティッタに語り始めた。
「ティッタ。俺はこれからみんなに、ティッタにもいっぱいウソをつく。自分の為ではなく、みんなの為に、ティッタの為に」
「はい!ティグル様のウソは、誰かの為のウソだってことを、あたしは知ってます!」
眩しい空を見上げながら、ティグルがいかなる決意をしたのか、この時、凱もティッタも知る由はない。
そして、この瞬間こそが、『英雄へ至る伝説……そして勇者から紡がれる神話へ』の始まりであり、この輝きに満ちたアルサスこそが始まりの地であったことも……
『数刻前・中心都市セレスタ・神殿前』
話は少し巻き戻る。
宴を終えた翌日の朝から、ティグル達は町の復興に向けての作業で忙殺していた。
昨日、あれほどの惨劇にも関わらず、セレスタの住民に死者が出なかったのは不幸中の幸いだった。
事情はともあれ、ティグルヴルムド=ヴォルンはアルサスへの帰還を果たした。
だが、テナルディエ公爵のアルサス侵攻については、ティグルにとって到底納得できるものではない。領土をめぐる攻防で、負傷者まで出ているのだから。
ティグルの今後を決めるよう声を掛けたエレンは神殿へ向かい、リムに今後の予定を伝える。彼女らが率いてきた兵は、町の空き家や、神殿の内部で寝泊まりしている。
「選抜した兵はお前に任せる。国王を黙らせたらすぐ戻ってくる。それまで頼むぞ」
「エレオノーラ様は、随分と彼を信頼されているのですね?」
「お前もそうだと思ったが……ただ」
「ただ?」
「やはり、あの男……ガイの姿勢は気に入らない」
それに関しては、リムも概ね同じ意見を持っていた。
不殺。殺さず。奪わない。
個に対して全体を優先しなければならない立場のエレンにとって、凱の心情は理解できるものではない。
テナルディエ兵を延命させたことは、非常に危険な行為だ。一軍を率いる将として、結果的には味方や仲間を危険に晒す可能性は見過ごすことなど出来ない。もし、助けた敵が再び自分の命を狙うか分からない。
ジスタート軍が到着するまで、凱の撃破数は見積もって、テナルディエ軍全体の約3分の1.結果として、モルザイム平原で迎え撃った時は、当初は3倍と推測していた数字が2倍に収まった。
本来なら、自軍が有利になり、敵軍が不利になるという、喜ばしい事態のはずだった。
しかし、凱の削り取った数字の正体は、全て殺されずに倒された敵兵なのだ。全員捕虜にすることなど当然できず、首をはねるにも手間がかかる。結局彼らに対して逃がすという選択しかとれない。
つまり、再び相手に剣を持たせる機会を与えてしまったのだ。
これでは、挑んできた敵に敬意を払い、勇敢に戦って散っていった者が報われないではないか。侮辱以外の何物でもない。
自分も相手も守りたいなんていう我儘は戦場では通用しない。
殺さないという事は、当然といっていいほど
どちらにしても、凱やエレンにしても、「相手に未来を与える」という点は一緒である。
「私は、あの男を見損なうべきなのだろうか」
正直、エレンには凱への評価に悩んでいた。
不殺主義の絶対条件は、まず相手より圧倒的に強いこと。
相手に選択肢を与えることができ、常に自分が優位に立っていないと出来ないからだ。
でなければ自分が殺されて終わりである。
表面的な凱の強さを、歴戦の戦士としても優秀なエレンだからこそ分かる。ただ、強いから殺さないという矛盾だけは分からない。
「ともかく、あいつの事は取りあえず忘れよう。警戒したところで何も始まらない」
そうなのだ。これから戦姫たる自分は、仕える王に対して戦いの正当性を主張しなければならない。
今回において王は、承認を得ていないエレンの独断専行と見なしている。ティグルを助ける為に力を貸してくれた兵や、ライトメリッツに残っている兵、領民達にも危機に見舞われる。
エレンには自国の民を守る義務がある。その為、今一度王都へ向かい、正式に参戦の許可をもらわなければならない。
「リム。ティグルの戦う理由を答えろ」
「第一に領民の安全。テナルディエ公爵の非道な行いにふさわしい処罰を与える事。彼に賠償金を支払わせること。今後の内乱における中立の立場を維持。この4点です」
「そうだ。ティグルは戦う理由をちゃんと主張している」
エレンのその言葉は、リムに不思議な沈黙をもたらした。
無論、危険を顧みず、戦いの渦中に身を置いたライトメリッツの兵達にとって、気持ちは一つである。
だが、本格的にブリューヌの内乱へ自分たちが赴くことは、『ライトメリッツの防衛戦』からの逸脱を意味している。
それは、自分たちの戦いの意義を、あらためて考えるための……沈黙だった。
NEXT
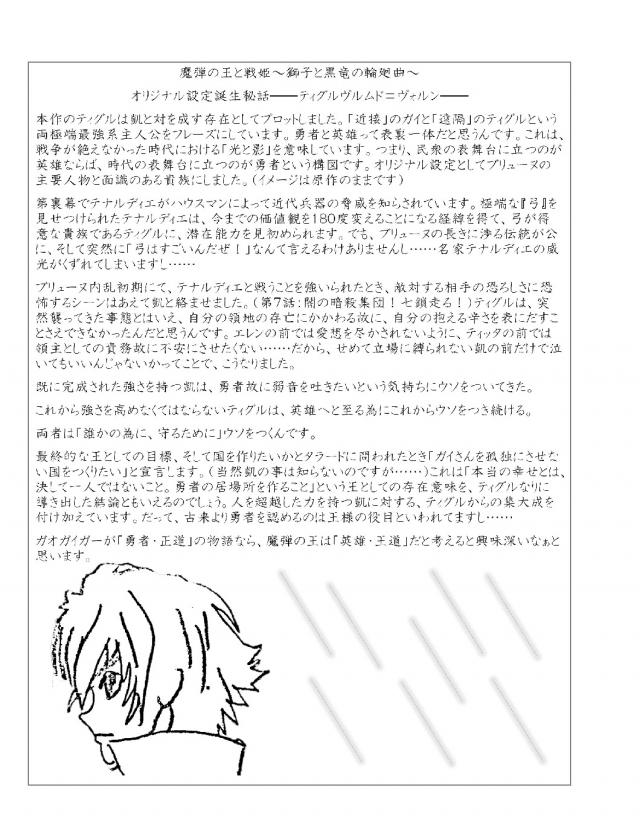
感想を書く
この話の感想を書きましょう!
全て感想を見る:感想一覧
