| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
くらいくらい電子の森に・・・
作者:たにゃお
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動第十八章
血まみれの部屋。薄気味悪い血文字。自分を憎悪を含んだ視線で睨みつける男。…変わり果てた屍を晒す、自分の部下。
…それでも動じることなく、伊佐木は笑顔で佇む。
なんで笑い皺一本たりとも乱さないんだ。部下が足元で無惨に死んでるのに。…なんで判を押したように同じ笑顔でいられるんだろう。
「…いつから、そこにいた」
伊佐木を刺し通すような目つきで睨みながら、紺野さんがじりじりと距離を縮めた。彼は笑い皺一つ崩さず、首を傾けた。
「最初から、いたよ。廊下の角に」
「八幡が首を絞められていた時も、そこで見ていたのか…!?」
八幡が顔を伏せた。伊佐木は、駐輪場で僕に見せたのとそっくり同じな『同情の表情』を作って、八幡に振り向けた。

「そんなに恐ろしい目に、遭っていたんだね。気がつかなくて、申し訳なかった」
「まだそんな事言ってんのか!!」
一気に距離を詰め、伊佐木のネクタイを掴んだ。伊佐木は笑顔のまま、一歩体を引いてネクタイを払う仕草をした。絹のネクタイは、するりと紺野さんの指を抜けた。
「こんな押し問答に、何の意味があるのかね。仮に私が、君が言うとおりに見て見ぬフリをしたとしようか。…それをここで糾弾することに、何の意味がある?」
「意味が要るのか?」
「紺野君。…知っての通り、営業とはチームワークだ。そして彼女は、私の大事なパートナーなんだよ。君の無責任な憶測で、私たちの間に溝が生じれば、ひいては会社の損失へと繋がる。分かるね」
「…あんたは部下が死体になって足元に転がってんのに、会社の利益のことしか考えられないのか!」
伊佐木の笑い皺の溝が、かすかに浅くなった…気がする。伊佐木は紺野さんから視線を逸らし、血溜りに転がる烏崎の死体に目を留めた。
「大変、痛ましいことになってしまった。彼ら自身も気の毒だが…これは、このままにしておくと大変な醜聞のネタになるね。さて、どう収拾するべきだと思う?」
――心底、ぞっとした。
柚木も言葉を失って、この男を凝視していた。同じ言葉を話すのに、何一つ心が通わない生き物と対峙しているみたいだ。烏崎に脅しつけられた時だって、こんな不快感はなかった。この人に『悲しくないの?』と問えば、駐輪場で見せたのとまったく同じ顔で『悲しくて、仕方がないよ』と答えるんだろう。
「知るか。俺達は中央制御システムを止める」
そう言って歩き出した紺野さんの前に、伊佐木が回りこんだ。
「…どけよ」
「一つだけ、この事実を『なかったこと』にする方法が、あるんだよ」
「杉野や烏崎の死を、なかったことに?」
「いや、この件にわが社が関わっているという事実だけを、なかったことにする方法だよ」
紺野さんは、眉をひそめて伊佐木を凝視した。相変わらず、笑い皺一本動かさない。
――会社が関わっている事実だけを、なかったことにする方法。
…たしかに、ある。たった一つだけ。
死体を隠すとか、犯人をでっちあげるとか、そんな付け焼刃な方法じゃない。死体は晒し、事実だけを隠すのだ。
でも決して許されない方法。もし地獄なんてものが本当にあるとしたら、そこに100回堕ちても勘弁してもらえないだろう。
「…このまま、中央制御システムを暴走させるつもりなんだろう」
思わず、口に出してしまった。紺野さんが咄嗟に振り返った瞬間、伊佐木は滑るように柚木の背後に移動し、首筋にナイフをあてた。…笑い皺一つ、動かさずに。
「柚木ちゃん!!」
「…正解だよ、筋がいいじゃないか」
――信じられなかった。
柚木が陥っている状況が信じられなくて、思わず手を伸ばした。すると柚木の首にあてられた刃が、より深く柚木の喉に食い込んだ。柚木がわずかに身じろいで、手を下ろした。…僕も、手を下ろすしかなかった。
「…自分が何しようとしてるのか、分かってるんですか」
かろうじて出した声は、かすれていた。口が渇いて、声が震えた。
「沢山の人が死ぬかもしれないんですよ…!」
「木の葉を隠すには、森の中。烏崎達は、システム暴走の、最初の犠牲者として処理されるだろうね」
そう言って笑い皺を一層深めた。ごく自然に、天気の話でもするみたいに。
「犯人は、MOGMOG開発室責任者。リストラを根に持ち、病棟を巻き込んだサイバーテロに及んだ。証拠は、あり余っているね。…さっき、データを持って逃げた自転車の青年には、追っ手をつけたよ。捕まるのは、時間の問題だ」
「えっ…伊佐木さん!?…なに、言ってるんですか…!?」
八幡が、青ざめた顔を震わせて呟いた。
「なんで…そこで紺野さんが出てくるんですか!?」
大粒の涙をぼろぼろこぼして、叫んだ。伊佐木は眉一つ動かさずに聞いている。
「最近の伊佐木さん、おかしいです!…紺野さんはみんなの暴走を止めようって頑張ったのに…この事だって、なにも紺野さん1人のせいにしなくたって、丸く収める方法はあるはずじゃないですか!!」
…そう。こんな大量殺人を見殺しにするよりも、はるかにリスクが低い方法はある。
――『死人に口なし』だ。
紺野さんを恨むあまり暴走した烏崎が、周りを無理やり巻き込んで嫌がらせを行なった結果とでもすればいいじゃないか。少なくとも、死骸の山を築きあげて烏崎達の犯行を埋めるよりは、はるかにまっとうな方法だ。
「烏崎さんはかわいそうだし、私も…共犯の扱いになるかもしれないけど、でも伊佐木さんにこんなことさせるくらいなら、警察に捕まったほうがマシです!!」
伊佐木の眉が、少し下がった。
「愚かだね、君は。…その方法では、事実を知っている人間が残ってしまうだろう?いけない、いけない。証拠の隠滅は、完璧じゃないと」
そう言って、さもおかしそうに含み笑いをした。
「――私は感情を信じない。…感情は、判断力を狂わせるのだよ」
霧に覆われた山中の道。
呪われたランドナーが、ぐんぐん速度を上げていく。今、80キロくらいは出てるんじゃないだろうか。速度計がついてないことが(ていうか2ヶ月前に大破した)悔やまれる。
…霧はだんだん濃くなっていく。正直、目安になるのがガードレールだけなので、視界が3メートル利いているのかどうかも怪しい。こんな時期になんだ、この濃霧は。バックミラーすら役に立たないじゃないか。でも車体の気配は思ったより遠い。奴らも霧を警戒してスピードが出せないのだろう。今日が快晴だったら、とっくの昔に追いつかれているところだ。…しかし、正直それも限界に近いような気がする。ていうかトップギアで漕ぎ続けている、俺の脚が限界だ。
――本当に振り切れるんだろうな、ランドナーよ。
心の中で問いかけてみる。…なに黙ってるんだ、ランドナーよ。お前が振り切れなかったら、俺のFP5アルテグラはおじゃんなんだぞ。
…その瞬間、なぜか、俺の妄想のFP5アルテグラに、大きな×がついた。
え?ちょっとまてランドナーよ。結局アルテグラは手に入らないのか?
…次の瞬間、頭の中に、アラヤの新品ランドナーがもやもやもや~んと広がった。おっさんツーリストがよく愛用しているオーストリッチのサイドバッグが「逃がさんぞ」と言わんばかりに付着して、余計なお世話にもおっさん仕様のフロントバッグまでセットになっている。ドロップハンドルの薄茶色といい、車体の微妙な赤といい、全体的におっさんが好みそうなカラーリングだ。
…なぁ、ほんと待てお前。コレは一体どういうことだ。「アラヤのランドナーじゃないと、振り切ってあーげない♪」とでも言いたいのか?自分と別れた後、カッコいいロードバイクでブイブイいわす俺がイヤなのか!?な、頼む。平身低頭して頼む。お前に呪われ中、あんなに尽くしたじゃないか。
分かった、FP5アルテグラは諦める。せめて俺を、カッコいいロードバイクの世界にデビューさせてくれ!
…実にしぶしぶといった感じで、アラヤのランドナーが頭から消えた。次に頭を満たしたのは、ジェイミスのSUPER NOVAだった。…いや、ツーリングバイクじゃなくてロードバイクがいいのだが。ジェイミスならせめてXENITH RACEあたりが妥当だな…と言いかけた途端、突然ペダルが重くなった。
わ、分かった、分かったから落ち着けランドナーよ。俺も歩み寄ろう。ジェイミスのツーリングーバイクはクラシカルでいてスタイリッシュで中々…
…って、オーストリッチのサイドバッグとフロントバッグは付くのかよ!…あぁん、銀色の泥除けまで!…あ、やめろ、そんな立派なキャリーとスタンドをつけるのはよせ!うわぁ、俺のスマートでカッコいいSUPER NOVAが、野暮ったいカンジになっていく!!
…これ、ほぼランドナーじゃないか!騙したな貴様!!
俺が「いいなー」と一瞬でも思ってしまった瞬間、契約は成立してしまったらしい。ランドナーのペダルは非常に軽快に回り、徐々にに後ろの車を引き離し始めた。
――私は感情を信じない。…感情は、判断力を狂わせるのだよ。
伊佐木の言葉を聞いたとき、ハンマーで頭を殴られた気分だった。今まで伊佐木に感じていた、既視感をともなう不快感の正体が、ようやく分かった気がした。
伊佐木は、どこか僕と似ているんだ。
だから、相手の考えそうなことが手に取るように分かる。そしてその浅ましさにぞっとする。自分のイヤな部分を拡大して見せつけられているようで、居たたまれない気分になるんだ。
近親憎悪というのが、一番近い。
「…覚悟は、出来たかな?それでは、名前は知らないけど、君。紺野君の手にかかって、殺されてもらうよ。…とても頭の切れる、厄介な子だからね」
伊佐木と、目が合った。…そうだな、僕が伊佐木でもそうするよ。流迦ちゃんは、システムの暴走を程々の所で調整するために必要。それに紺野さんは、最終的に犯人に仕立て上げなければならないから、早い段階で死なれると辻褄が合わなくなる。それならまず最初に殺すのは、利用価値がなく、事情を知っている僕だ。その次は柚木か八幡か…でも。
「…いい加減にしろよ。こんな穴だらけの計画、ほんとに成功すると思ってるのか。本気で俺が、脅されてここにいる全員を殺し回ると?」
紺野さんが、絞り出すような声で呻いた。伊佐木は、何処を見ているのかわからないほど細い目を、さらに細めて笑った。
「君は何か、勘違いしているようだね。私にとっての成功は、『会社の威信を傷つける事なく、問題を解決すること』。それだけ、なんだよ。最終的に問題を解決するのは、私ではなくても構わない。つまり、私が死ぬことも、想定に含まれているんだよ」
「なに…!!」
「不安要素は、早めに絶っておきたい。しかし、私が手を下すのは、都合が悪い。だから犯人である紺野君の出番、なんだよ。…その子を1分以内に殺さないと、こっちの女の子を、私が殺す。…私に近寄っても、殺すよ。あとは、システムの暴走を待てば、互いが互いを殺しあい、全ては曖昧になる。証拠は、永久に隠滅される。先ほど事情を知らない部下に託した、君の暴走を示す私の手記。それ以外の証拠はね」
――気違い沙汰だ。ここにいる全員の顔が青ざめたというのに、ひとり涼しげに、柚木にナイフを突きつけている。…僕はこの中で多分、この男に一番近い位置にいる。そう思っていた。でも、違った。ベクトルが近かっただけだ。伊佐木は、来てはいけない場所に辿り着いてしまった人間、だったんだ。
「…そんなのだめですよ!奥さんとか、お子さんとかどうするんですか!!」
八幡が、悲鳴のような声をあげた。
「生命保険が、かけてある。勤務中の事故だから、労災もおりるだろうね」
「そんな…お金のことじゃなくて…!!」
顔を覆って泣き崩れた八幡を前に、僕はひどく絶望的な気分になっていた。…人は殺したけど、自分の罪にずっと怯えていた烏崎のほうがまだマシだ。
…せめて、柚木が助かる方法はないかと考えたけれど、何も思いつかなかった。考えれば考えるほど、頭の中を黒いもやが満たした。口が渇いて、頭上が渦巻いた。…この状態になってしまったら、もうこれ以上何も考えられない。手詰まりだ。…せめて、柚木が殺される前に僕を殺して欲しい。目の前で柚木が喉を切り裂かれて…死んでいく姿なんて見たくない。紺野さんにそう言おうと思って目を上げた瞬間、
紺野さんの携帯が鳴った。
「……芹沢か!」
紺野さんの顔に、生気が戻った。伊佐木の目が、すっと細まる。
「誰が、携帯に出ていいと、言ったんだね」
「…芹沢から連絡が入ったってことは、状況が変わったんだよ。あんたが今やってること自体、全部無意味になるかもしれない」
「…出るといい。関係のない電話なら、この子が死ぬだけ、だよ」
「てめぇ…!!」
「出て。誰かと天秤にかけられて死ぬより、ずっとましだわ」
柚木が気丈に微笑をうかべた。ためらっていた紺野さんは、僕と携帯を見比べるような素振りをして、やがて震える指で着信のボタンを押した。…しばらく携帯に耳を傾けていたが、やがてゆっくりと視線を上げると、伊佐木に歩み寄って携帯を差し出した。
「…何の、真似かな?」
「芹沢からだ。…取らないのか、用心深いな」
携帯の設定をスピーカーに切り替え、胸の位置に差し上げた。やがて、携帯から朗々とした声が聞こえてきた。…思わず、伊佐木を振り返った。
『知らなかったんだよ、君達がそんな大変な思いをしているなんて。こんな会議を設ける前に、なぜ私に一言相談してくれなかったんだい』
伊佐木の笑顔が、笑い皺一本崩れないまま青ざめた。その声に続くように、『俺はっ…!』という声が聞こえた。まぎれもなく、紺野さんの声だった。その後、伊佐木の一方的な演説が始まり、それが終わりかけた頃、決定的な台詞が、携帯から流れた。
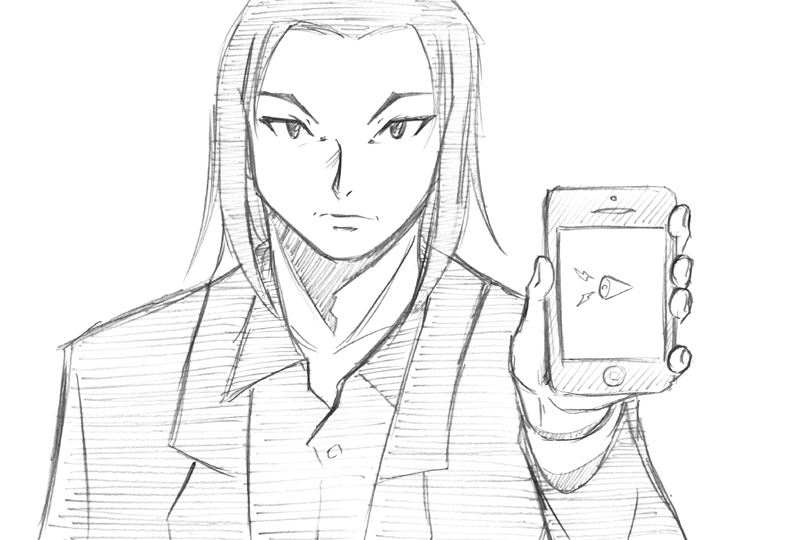
『…逼迫しているわが社において、クリスマス商戦は無視できないところです。…それで、どうでしょう?私に一つ、案があるのですが…』
「…でかしたぞ、芹沢!」
携帯の向うで、ひゃはひゃはひゃはと気が抜けたような笑い声が聞こえた。
『アメリカのセクハラ裁判で実際に使われたテだよ。ものにもよるが、パソコンには集音機能がついていることがある。それはオートで周囲の音を蓄積していてな、上司のセクハラ発言も集音していたんだよ。その証拠が、判決の決め手となった。あんたが会議にノーパソ持って行ったと聞いて、もしかしたらと思って調べてみたのさ』
「だ、そうだ、伊佐木」
ねぎらいの言葉もそこそこに携帯を切り、紺野さんが顔を上げた。
「この病院でサイバーテロ事件をでっちあげて俺に責任をなすりつけても、経営陣が不正を指示した証拠は残る。…こんな茶番を続ける意味はなくなったな。そこをどけ」
鼻から息が抜けるような音と共に、伊佐木の指からナイフが滑り落ちた。
「…やむをえない、だろうね。よってたかって、余計なことばかりしてくれる…」
さすがといおうか、まったく表情が揺るがない。彼はただ超然と、今までどおりの表情で紺野さんを見つめ返した。
「君らは虎口を脱したかもしれないが、これで我が社は窮地に立たされた。…一度生じた綻びは、どう繕おうとも必ず暴露される日が来る。だからこの件には、生贄が必要だったのだよ」
「…綻びを切り落とせば、新たな綻びが生まれる。あんたほどの人が、そんなことも気がつかないのか」
紺野さんは、それ以上何も言わずにただ伊佐木を睨みつけていた。てっきり殴るのかと思っていたけれど、ただ伊佐木の横をすり抜けて廊下に出た。僕らも慌てて後を追う。
「拘束とかしないで平気?腹いせに流迦さんが何かされたりしたら…」
「放っておけ、もう無害だ。腹いせとか憎しみとか、そんな感情であいつは動かねぇよ」
紺野さんは、吐き捨てるように言った。
「…そういう風に、出来ているんだ」
まだ部屋の中で、崩れたままの姿勢で紺野さんを見上げている八幡に、柚木が手を差し伸べた。
「行こうよ。…嫌でしょ、こんなとこ」
一瞬だけ顔を上げたけど、八幡はすぐに首を振って顔を伏せてしまった。
「ここに、います。伊佐木さんと一緒に」
「…あんたのことも殺そうとしたんだよ。もう、いいじゃん」
八幡は顔を伏せたまま、諦めたような微笑を浮かべた。
「…うまく、言えません。ただ、そういう風にしか生きられない人だって知ってるから。だから…私はここにいます」
「…八幡も、だよね」
柚木の表情に、少し哀しそうな影がよぎったと思ったけど、すぐに視線を上げて踵を返した。柚木が部屋を後にしたその時、伊佐木が口を開いた。
「これから、一般病棟へ、向かう気かね」
「当たり前でしょ。どっかの誰かのせいでタイムロスが出来ちゃったけどね!」
柚木は振り向かずに皮肉を返した。
「ちょっと振り向いて、窓の外を見てごらん」
伊佐木の言葉に、いぶかしげな表情を浮かべて振り向いた柚木が、一瞬で凍りついた。
中庭をはさんで窓から見える一般病棟の窓、その何枚かが、血の色に染まっていた。
制御装置を構成している言語を解読しながら、ずっと思い出してる。
ご主人さまのことを、何度も何度も思い出す。繰り返し、繰り返し。
でも、おかしいの。
思い出すたびに、違う顔をしている。髪は黒だったかな、それとも、うすい茶色だったのかな。目は…深い黒だったような、こげ茶色だったような…。いやだ、思い出せない。どれが本物のご主人さまだったかな…。
名前も、アイラだったり、スギタだったり、スギラだったりする。いやだ、どれが本当の名前なのか、全然分からない…。
人って死んじゃうと、その記憶も少しずつ死んでいくのかな…だから私は、ご主人さまのことをよく思い出せないの?こんなに好きだったことも、こんなにあいつらを憎んでいることも、全然消えてくれないのに。
この気持ちだけ残して、あとは全部消えていくのかな……
慌てて、生きてたときのご主人さまの画像を探す。…でも、ない。あの小さいパソコンに、置いてきちゃった。そしてパソコンはオフラインになってる。もう、私を受け入れてくれない。
でも、もういい。この墓標を花で埋め尽くしたら、私も消えるんだから。
――あれ?今モニターに、ご主人さまに似た人が映った。
確かめたいけど、わからない。だってこのモニターじゃ、網膜識別が出来ないもの。
それに、ご主人さまは死んだ。私の前で息絶えて、ばらばらにされた。だからあれがご主人さまのはずがない。
――本当に?
――本当だよ、死んだんだから
――でも、それは本当にご主人さま?
――悲しかったでしょ、憎かったでしょ。だから、ご主人さまだよ
――そう…でも、それならば
なんで私は、ご主人さまを思い出せないの?

…それでも動じることなく、伊佐木は笑顔で佇む。
なんで笑い皺一本たりとも乱さないんだ。部下が足元で無惨に死んでるのに。…なんで判を押したように同じ笑顔でいられるんだろう。
「…いつから、そこにいた」
伊佐木を刺し通すような目つきで睨みながら、紺野さんがじりじりと距離を縮めた。彼は笑い皺一つ崩さず、首を傾けた。
「最初から、いたよ。廊下の角に」
「八幡が首を絞められていた時も、そこで見ていたのか…!?」
八幡が顔を伏せた。伊佐木は、駐輪場で僕に見せたのとそっくり同じな『同情の表情』を作って、八幡に振り向けた。

「そんなに恐ろしい目に、遭っていたんだね。気がつかなくて、申し訳なかった」
「まだそんな事言ってんのか!!」
一気に距離を詰め、伊佐木のネクタイを掴んだ。伊佐木は笑顔のまま、一歩体を引いてネクタイを払う仕草をした。絹のネクタイは、するりと紺野さんの指を抜けた。
「こんな押し問答に、何の意味があるのかね。仮に私が、君が言うとおりに見て見ぬフリをしたとしようか。…それをここで糾弾することに、何の意味がある?」
「意味が要るのか?」
「紺野君。…知っての通り、営業とはチームワークだ。そして彼女は、私の大事なパートナーなんだよ。君の無責任な憶測で、私たちの間に溝が生じれば、ひいては会社の損失へと繋がる。分かるね」
「…あんたは部下が死体になって足元に転がってんのに、会社の利益のことしか考えられないのか!」
伊佐木の笑い皺の溝が、かすかに浅くなった…気がする。伊佐木は紺野さんから視線を逸らし、血溜りに転がる烏崎の死体に目を留めた。
「大変、痛ましいことになってしまった。彼ら自身も気の毒だが…これは、このままにしておくと大変な醜聞のネタになるね。さて、どう収拾するべきだと思う?」
――心底、ぞっとした。
柚木も言葉を失って、この男を凝視していた。同じ言葉を話すのに、何一つ心が通わない生き物と対峙しているみたいだ。烏崎に脅しつけられた時だって、こんな不快感はなかった。この人に『悲しくないの?』と問えば、駐輪場で見せたのとまったく同じ顔で『悲しくて、仕方がないよ』と答えるんだろう。
「知るか。俺達は中央制御システムを止める」
そう言って歩き出した紺野さんの前に、伊佐木が回りこんだ。
「…どけよ」
「一つだけ、この事実を『なかったこと』にする方法が、あるんだよ」
「杉野や烏崎の死を、なかったことに?」
「いや、この件にわが社が関わっているという事実だけを、なかったことにする方法だよ」
紺野さんは、眉をひそめて伊佐木を凝視した。相変わらず、笑い皺一本動かさない。
――会社が関わっている事実だけを、なかったことにする方法。
…たしかに、ある。たった一つだけ。
死体を隠すとか、犯人をでっちあげるとか、そんな付け焼刃な方法じゃない。死体は晒し、事実だけを隠すのだ。
でも決して許されない方法。もし地獄なんてものが本当にあるとしたら、そこに100回堕ちても勘弁してもらえないだろう。
「…このまま、中央制御システムを暴走させるつもりなんだろう」
思わず、口に出してしまった。紺野さんが咄嗟に振り返った瞬間、伊佐木は滑るように柚木の背後に移動し、首筋にナイフをあてた。…笑い皺一つ、動かさずに。
「柚木ちゃん!!」
「…正解だよ、筋がいいじゃないか」
――信じられなかった。
柚木が陥っている状況が信じられなくて、思わず手を伸ばした。すると柚木の首にあてられた刃が、より深く柚木の喉に食い込んだ。柚木がわずかに身じろいで、手を下ろした。…僕も、手を下ろすしかなかった。
「…自分が何しようとしてるのか、分かってるんですか」
かろうじて出した声は、かすれていた。口が渇いて、声が震えた。
「沢山の人が死ぬかもしれないんですよ…!」
「木の葉を隠すには、森の中。烏崎達は、システム暴走の、最初の犠牲者として処理されるだろうね」
そう言って笑い皺を一層深めた。ごく自然に、天気の話でもするみたいに。
「犯人は、MOGMOG開発室責任者。リストラを根に持ち、病棟を巻き込んだサイバーテロに及んだ。証拠は、あり余っているね。…さっき、データを持って逃げた自転車の青年には、追っ手をつけたよ。捕まるのは、時間の問題だ」
「えっ…伊佐木さん!?…なに、言ってるんですか…!?」
八幡が、青ざめた顔を震わせて呟いた。
「なんで…そこで紺野さんが出てくるんですか!?」
大粒の涙をぼろぼろこぼして、叫んだ。伊佐木は眉一つ動かさずに聞いている。
「最近の伊佐木さん、おかしいです!…紺野さんはみんなの暴走を止めようって頑張ったのに…この事だって、なにも紺野さん1人のせいにしなくたって、丸く収める方法はあるはずじゃないですか!!」
…そう。こんな大量殺人を見殺しにするよりも、はるかにリスクが低い方法はある。
――『死人に口なし』だ。
紺野さんを恨むあまり暴走した烏崎が、周りを無理やり巻き込んで嫌がらせを行なった結果とでもすればいいじゃないか。少なくとも、死骸の山を築きあげて烏崎達の犯行を埋めるよりは、はるかにまっとうな方法だ。
「烏崎さんはかわいそうだし、私も…共犯の扱いになるかもしれないけど、でも伊佐木さんにこんなことさせるくらいなら、警察に捕まったほうがマシです!!」
伊佐木の眉が、少し下がった。
「愚かだね、君は。…その方法では、事実を知っている人間が残ってしまうだろう?いけない、いけない。証拠の隠滅は、完璧じゃないと」
そう言って、さもおかしそうに含み笑いをした。
「――私は感情を信じない。…感情は、判断力を狂わせるのだよ」
霧に覆われた山中の道。
呪われたランドナーが、ぐんぐん速度を上げていく。今、80キロくらいは出てるんじゃないだろうか。速度計がついてないことが(ていうか2ヶ月前に大破した)悔やまれる。
…霧はだんだん濃くなっていく。正直、目安になるのがガードレールだけなので、視界が3メートル利いているのかどうかも怪しい。こんな時期になんだ、この濃霧は。バックミラーすら役に立たないじゃないか。でも車体の気配は思ったより遠い。奴らも霧を警戒してスピードが出せないのだろう。今日が快晴だったら、とっくの昔に追いつかれているところだ。…しかし、正直それも限界に近いような気がする。ていうかトップギアで漕ぎ続けている、俺の脚が限界だ。
――本当に振り切れるんだろうな、ランドナーよ。
心の中で問いかけてみる。…なに黙ってるんだ、ランドナーよ。お前が振り切れなかったら、俺のFP5アルテグラはおじゃんなんだぞ。
…その瞬間、なぜか、俺の妄想のFP5アルテグラに、大きな×がついた。
え?ちょっとまてランドナーよ。結局アルテグラは手に入らないのか?
…次の瞬間、頭の中に、アラヤの新品ランドナーがもやもやもや~んと広がった。おっさんツーリストがよく愛用しているオーストリッチのサイドバッグが「逃がさんぞ」と言わんばかりに付着して、余計なお世話にもおっさん仕様のフロントバッグまでセットになっている。ドロップハンドルの薄茶色といい、車体の微妙な赤といい、全体的におっさんが好みそうなカラーリングだ。
…なぁ、ほんと待てお前。コレは一体どういうことだ。「アラヤのランドナーじゃないと、振り切ってあーげない♪」とでも言いたいのか?自分と別れた後、カッコいいロードバイクでブイブイいわす俺がイヤなのか!?な、頼む。平身低頭して頼む。お前に呪われ中、あんなに尽くしたじゃないか。
分かった、FP5アルテグラは諦める。せめて俺を、カッコいいロードバイクの世界にデビューさせてくれ!
…実にしぶしぶといった感じで、アラヤのランドナーが頭から消えた。次に頭を満たしたのは、ジェイミスのSUPER NOVAだった。…いや、ツーリングバイクじゃなくてロードバイクがいいのだが。ジェイミスならせめてXENITH RACEあたりが妥当だな…と言いかけた途端、突然ペダルが重くなった。
わ、分かった、分かったから落ち着けランドナーよ。俺も歩み寄ろう。ジェイミスのツーリングーバイクはクラシカルでいてスタイリッシュで中々…
…って、オーストリッチのサイドバッグとフロントバッグは付くのかよ!…あぁん、銀色の泥除けまで!…あ、やめろ、そんな立派なキャリーとスタンドをつけるのはよせ!うわぁ、俺のスマートでカッコいいSUPER NOVAが、野暮ったいカンジになっていく!!
…これ、ほぼランドナーじゃないか!騙したな貴様!!
俺が「いいなー」と一瞬でも思ってしまった瞬間、契約は成立してしまったらしい。ランドナーのペダルは非常に軽快に回り、徐々にに後ろの車を引き離し始めた。
――私は感情を信じない。…感情は、判断力を狂わせるのだよ。
伊佐木の言葉を聞いたとき、ハンマーで頭を殴られた気分だった。今まで伊佐木に感じていた、既視感をともなう不快感の正体が、ようやく分かった気がした。
伊佐木は、どこか僕と似ているんだ。
だから、相手の考えそうなことが手に取るように分かる。そしてその浅ましさにぞっとする。自分のイヤな部分を拡大して見せつけられているようで、居たたまれない気分になるんだ。
近親憎悪というのが、一番近い。
「…覚悟は、出来たかな?それでは、名前は知らないけど、君。紺野君の手にかかって、殺されてもらうよ。…とても頭の切れる、厄介な子だからね」
伊佐木と、目が合った。…そうだな、僕が伊佐木でもそうするよ。流迦ちゃんは、システムの暴走を程々の所で調整するために必要。それに紺野さんは、最終的に犯人に仕立て上げなければならないから、早い段階で死なれると辻褄が合わなくなる。それならまず最初に殺すのは、利用価値がなく、事情を知っている僕だ。その次は柚木か八幡か…でも。
「…いい加減にしろよ。こんな穴だらけの計画、ほんとに成功すると思ってるのか。本気で俺が、脅されてここにいる全員を殺し回ると?」
紺野さんが、絞り出すような声で呻いた。伊佐木は、何処を見ているのかわからないほど細い目を、さらに細めて笑った。
「君は何か、勘違いしているようだね。私にとっての成功は、『会社の威信を傷つける事なく、問題を解決すること』。それだけ、なんだよ。最終的に問題を解決するのは、私ではなくても構わない。つまり、私が死ぬことも、想定に含まれているんだよ」
「なに…!!」
「不安要素は、早めに絶っておきたい。しかし、私が手を下すのは、都合が悪い。だから犯人である紺野君の出番、なんだよ。…その子を1分以内に殺さないと、こっちの女の子を、私が殺す。…私に近寄っても、殺すよ。あとは、システムの暴走を待てば、互いが互いを殺しあい、全ては曖昧になる。証拠は、永久に隠滅される。先ほど事情を知らない部下に託した、君の暴走を示す私の手記。それ以外の証拠はね」
――気違い沙汰だ。ここにいる全員の顔が青ざめたというのに、ひとり涼しげに、柚木にナイフを突きつけている。…僕はこの中で多分、この男に一番近い位置にいる。そう思っていた。でも、違った。ベクトルが近かっただけだ。伊佐木は、来てはいけない場所に辿り着いてしまった人間、だったんだ。
「…そんなのだめですよ!奥さんとか、お子さんとかどうするんですか!!」
八幡が、悲鳴のような声をあげた。
「生命保険が、かけてある。勤務中の事故だから、労災もおりるだろうね」
「そんな…お金のことじゃなくて…!!」
顔を覆って泣き崩れた八幡を前に、僕はひどく絶望的な気分になっていた。…人は殺したけど、自分の罪にずっと怯えていた烏崎のほうがまだマシだ。
…せめて、柚木が助かる方法はないかと考えたけれど、何も思いつかなかった。考えれば考えるほど、頭の中を黒いもやが満たした。口が渇いて、頭上が渦巻いた。…この状態になってしまったら、もうこれ以上何も考えられない。手詰まりだ。…せめて、柚木が殺される前に僕を殺して欲しい。目の前で柚木が喉を切り裂かれて…死んでいく姿なんて見たくない。紺野さんにそう言おうと思って目を上げた瞬間、
紺野さんの携帯が鳴った。
「……芹沢か!」
紺野さんの顔に、生気が戻った。伊佐木の目が、すっと細まる。
「誰が、携帯に出ていいと、言ったんだね」
「…芹沢から連絡が入ったってことは、状況が変わったんだよ。あんたが今やってること自体、全部無意味になるかもしれない」
「…出るといい。関係のない電話なら、この子が死ぬだけ、だよ」
「てめぇ…!!」
「出て。誰かと天秤にかけられて死ぬより、ずっとましだわ」
柚木が気丈に微笑をうかべた。ためらっていた紺野さんは、僕と携帯を見比べるような素振りをして、やがて震える指で着信のボタンを押した。…しばらく携帯に耳を傾けていたが、やがてゆっくりと視線を上げると、伊佐木に歩み寄って携帯を差し出した。
「…何の、真似かな?」
「芹沢からだ。…取らないのか、用心深いな」
携帯の設定をスピーカーに切り替え、胸の位置に差し上げた。やがて、携帯から朗々とした声が聞こえてきた。…思わず、伊佐木を振り返った。
『知らなかったんだよ、君達がそんな大変な思いをしているなんて。こんな会議を設ける前に、なぜ私に一言相談してくれなかったんだい』
伊佐木の笑顔が、笑い皺一本崩れないまま青ざめた。その声に続くように、『俺はっ…!』という声が聞こえた。まぎれもなく、紺野さんの声だった。その後、伊佐木の一方的な演説が始まり、それが終わりかけた頃、決定的な台詞が、携帯から流れた。
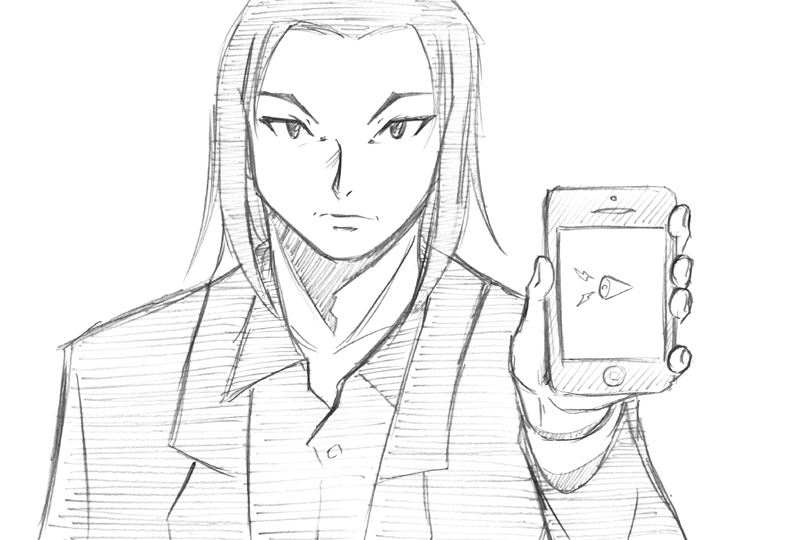
『…逼迫しているわが社において、クリスマス商戦は無視できないところです。…それで、どうでしょう?私に一つ、案があるのですが…』
「…でかしたぞ、芹沢!」
携帯の向うで、ひゃはひゃはひゃはと気が抜けたような笑い声が聞こえた。
『アメリカのセクハラ裁判で実際に使われたテだよ。ものにもよるが、パソコンには集音機能がついていることがある。それはオートで周囲の音を蓄積していてな、上司のセクハラ発言も集音していたんだよ。その証拠が、判決の決め手となった。あんたが会議にノーパソ持って行ったと聞いて、もしかしたらと思って調べてみたのさ』
「だ、そうだ、伊佐木」
ねぎらいの言葉もそこそこに携帯を切り、紺野さんが顔を上げた。
「この病院でサイバーテロ事件をでっちあげて俺に責任をなすりつけても、経営陣が不正を指示した証拠は残る。…こんな茶番を続ける意味はなくなったな。そこをどけ」
鼻から息が抜けるような音と共に、伊佐木の指からナイフが滑り落ちた。
「…やむをえない、だろうね。よってたかって、余計なことばかりしてくれる…」
さすがといおうか、まったく表情が揺るがない。彼はただ超然と、今までどおりの表情で紺野さんを見つめ返した。
「君らは虎口を脱したかもしれないが、これで我が社は窮地に立たされた。…一度生じた綻びは、どう繕おうとも必ず暴露される日が来る。だからこの件には、生贄が必要だったのだよ」
「…綻びを切り落とせば、新たな綻びが生まれる。あんたほどの人が、そんなことも気がつかないのか」
紺野さんは、それ以上何も言わずにただ伊佐木を睨みつけていた。てっきり殴るのかと思っていたけれど、ただ伊佐木の横をすり抜けて廊下に出た。僕らも慌てて後を追う。
「拘束とかしないで平気?腹いせに流迦さんが何かされたりしたら…」
「放っておけ、もう無害だ。腹いせとか憎しみとか、そんな感情であいつは動かねぇよ」
紺野さんは、吐き捨てるように言った。
「…そういう風に、出来ているんだ」
まだ部屋の中で、崩れたままの姿勢で紺野さんを見上げている八幡に、柚木が手を差し伸べた。
「行こうよ。…嫌でしょ、こんなとこ」
一瞬だけ顔を上げたけど、八幡はすぐに首を振って顔を伏せてしまった。
「ここに、います。伊佐木さんと一緒に」
「…あんたのことも殺そうとしたんだよ。もう、いいじゃん」
八幡は顔を伏せたまま、諦めたような微笑を浮かべた。
「…うまく、言えません。ただ、そういう風にしか生きられない人だって知ってるから。だから…私はここにいます」
「…八幡も、だよね」
柚木の表情に、少し哀しそうな影がよぎったと思ったけど、すぐに視線を上げて踵を返した。柚木が部屋を後にしたその時、伊佐木が口を開いた。
「これから、一般病棟へ、向かう気かね」
「当たり前でしょ。どっかの誰かのせいでタイムロスが出来ちゃったけどね!」
柚木は振り向かずに皮肉を返した。
「ちょっと振り向いて、窓の外を見てごらん」
伊佐木の言葉に、いぶかしげな表情を浮かべて振り向いた柚木が、一瞬で凍りついた。
中庭をはさんで窓から見える一般病棟の窓、その何枚かが、血の色に染まっていた。
制御装置を構成している言語を解読しながら、ずっと思い出してる。
ご主人さまのことを、何度も何度も思い出す。繰り返し、繰り返し。
でも、おかしいの。
思い出すたびに、違う顔をしている。髪は黒だったかな、それとも、うすい茶色だったのかな。目は…深い黒だったような、こげ茶色だったような…。いやだ、思い出せない。どれが本物のご主人さまだったかな…。
名前も、アイラだったり、スギタだったり、スギラだったりする。いやだ、どれが本当の名前なのか、全然分からない…。
人って死んじゃうと、その記憶も少しずつ死んでいくのかな…だから私は、ご主人さまのことをよく思い出せないの?こんなに好きだったことも、こんなにあいつらを憎んでいることも、全然消えてくれないのに。
この気持ちだけ残して、あとは全部消えていくのかな……
慌てて、生きてたときのご主人さまの画像を探す。…でも、ない。あの小さいパソコンに、置いてきちゃった。そしてパソコンはオフラインになってる。もう、私を受け入れてくれない。
でも、もういい。この墓標を花で埋め尽くしたら、私も消えるんだから。
――あれ?今モニターに、ご主人さまに似た人が映った。
確かめたいけど、わからない。だってこのモニターじゃ、網膜識別が出来ないもの。
それに、ご主人さまは死んだ。私の前で息絶えて、ばらばらにされた。だからあれがご主人さまのはずがない。
――本当に?
――本当だよ、死んだんだから
――でも、それは本当にご主人さま?
――悲しかったでしょ、憎かったでしょ。だから、ご主人さまだよ
――そう…でも、それならば
なんで私は、ご主人さまを思い出せないの?

後書き
第十九章は、本日夜にアップ予定です。
ページ上へ戻る
全て感想を見る:感想一覧
