| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
嗤うせぇるすガキども
作者:プラウダ風紀いいんかい?
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動これが漢の戦車道 最終話
勝者である謎の美少女戦車隊のウイニングランも終わり、N山競戦車場は再び静かになった。
そしていよいよ捕虜となった戦犯どもの軍事裁判イベントだ。
ホラー号の面々が、黒衣の軍装の怖い連中に引き立てられてパドックに連れてこられた。
ほとんど全員が負け組になった観衆には、こいつらがどうなるかだけが残された楽しみだ。
「これより、捕虜どもの軍事裁判を行う!」
そう宣言したのは、一般親衛隊の制服なのにミニスカで網タイツ、ロン毛の美人なのに
酷薄そうな印象のある女性の大隊指揮官(少佐)。
そのとなりにはなぜか、一般親衛隊とは犬猿の仲である武装親衛隊の迷彩服を着た将校、ちびデブメガネが立っていた。
そして、「法廷」には、分厚いアクリルで作られた水槽らしきものが5つ並んでいる。
もはやヤケクソで大歓声をあげる大観衆。
テレビ中継席ではアナウンサーが、これから行われる「軍事法廷」についてしゃべっている。
「今回、ホラー号は自ら白旗を揚げて降伏しましたので『戦死』ではなく『捕虜』となります。
そして会場臨時法廷におきまして、『婦女子に対する非人道的行為』の疑いで軍事裁判にかけられます。
なお、彼らにはすでに『敗北時罰金を10倍とする』ことが確定しております」
観客どもがブーイングを飛ばし続ける。
ブッ殺せコールが巻き起こり、皆が親指を下に向けて立てている。
「おい、今回の罰金、全部お前持ちだからな」
戦争親父が、ぼそりと鹿次に宣告する。
罰金一千万……。ノルマが倍になってしまった。
俺、どうしたらいいんだよお。と心の中だけで嘆く鹿次の顔色は土気色。
「そして、これから会場役員による取り調べが行われます。楽しみですね~。
これから行われる取り調べに耐えれば耐えるほど罰金が減額され、0円になった暁には無罪放免となりますが、ギブアップしたときにはその時点の罰金が残り、かつ、刑罰が課せられます」
なんなんだよそれ。だったらおとなしく撃破されていれば良かった。と悔やむ鹿次。
だが、いまさらになって後悔してももう遅い。
今回の観衆の怒りを収めるにはいけにえが必要なのだ。
「さあ、立てぃ!」
今度は迷彩服の人外みたいな武装親衛隊どもが、ホラー号のクルーを下着一丁にひんむいて、アクリルの水槽に放り込んで、上から穴の開いたふたをする。
そして一般親衛隊が、ぐらぐら煮立ったお湯がいっぱいの、巨大な釜を乗せたトレーラーをキューベルワーゲンで牽引してきた。中にはでかい電気ヒーターが突っ込んである。
たぶん、処刑が終わったあと、芋煮会でもやるのであろう。
これは、バラエティ番組なんかよく見る「熱湯風呂」って奴だろうか。
鹿次でなくとも、そうとしか思えない。
「ではこれから、戦犯どもの入った水槽に、この釜の中のお湯を注ぎます。
戦犯が1分耐えるごとに、罰金が100万円減ります。
10分全員が耐えて、罰金が0円になりましたら、無罪放免と言うことになります」
そして戦争親父たちであっても、その後病院で生死の境をさまようことは見え見えだ。
釜にポンプのついた太いホースが5本放り込まれる。
同時にホースの出口が、鹿次たちの納まる水槽のふたに突っ込まれる。
「では、これより尋問を始める。
自白したい奴はいないか?」
アルゲマイネ女王様が、念のために確認する。
鹿次はつい「自白自白自白!!」と叫びそうになったが、一千万の重みが思いとどまらせた。
他の連中も、一緒に耐えてくれるようだ。
「ふむ、自白しないというのなら尋問を続ける」
女王様が宣言すると、小太りの武装親衛隊ちびデブメガネの三重苦の少佐殿が、
「哀れな捕虜どもが素っ裸で立ち向かってきたのに熱湯を浴びせるのはもうたまらない」とほざきながら、ポンプを全部作動させた。
水槽にドバドバと熱湯がつぎこまれる。
漢どもは、声も立てずに平然と水かさを増すお湯をながめている。
漢ではない鹿次はぎゃーぎゃー泣き叫んでいる。
「それでは、いまから時計を動かす」
女王様がリモコンで一周10分の巨大タイマーを作動させた。
大きな秒針と分針が回り出す。
「ふふふ、この程度で俺たちが音を上げると思ったか?」
「まことにいい湯加減だ」
「おい、ぬるいぞ。もっと熱くしてくれ」
「ただの湯ではなくて温泉で、源泉掛け流しなら言うことはないんだがな」
鹿次以外の4人は、余裕綽々である。
本当に10分耐えきってみせるかもしれない。
しかし……。
「うぎゃー!! ギブギブギブ――――!!!」
10秒もたたないうちに絶叫して飛び出してきたのがいる。
もちろん、鹿次だ。
「水! みずみずみずぅーっ!!」
叫びながら転げ回る鹿次。
しかたねーなという顔をしながら、ホースで水をぶっかける武装親衛隊少佐。
その間に、アルゲマイネの女王様は、判決文を読み上げる。
「被告、ホラー号乗員はすでに確定した罰金一千万円に加え、銃殺刑に処す。
刑は直ちに執行される。銃殺隊は直ちに受刑者を刑場に引っ立てよ!」
熱湯風呂につかりながら、天を仰ぐホラー号の面々。
一方で鹿次は、何が起きているのか理解できないまま、武装親衛隊の人外どもに「刑場」へと引きずられていく。
刑場では手回しの良いことに、すでに5本の杭が打ってある。
え? 何? なに? ときょろきょろと周囲を見渡す鹿次以外の4人は、
粛々と後ろ手に、杭に縛り付けられる。
その段にいたってようやくこれが銃殺を模した何かだと気がつく鹿次。
あああ~。俺って何て愚かだったんだ。
おとなしく砲撃を食らっていれば、せいぜい高圧電流か催涙ガスか炭塵爆発レベルで済んだのに……。と、何度も後悔する鹿次。
しかし、覆水盆に返らず。自業自得である。
「せめて目隠しをおねがいしますだー」
この期におよんで、まだ見苦しい鹿次。
いよいよ、衆人環視の中で彼らの「銃殺刑」が執行される。
一般親衛隊の制服を着た人間が6人、彼らの前に並ぶ。
その中の偉い奴みたいなのは、実際の将校のように「死亡確認」をする役なんだろう。
「これより、戦争犯罪人5名を婦女子暴行のかどで銃殺に処す。
銃殺隊、前進」
将校役の合図で、黒衣の軍装に身を包む5人の男が、手に短銃らしきものを持ったまま、一歩前に進む。
「ぎゃあああ! 殺さないで殺さないで殺さないで~~~」
鹿次の悲鳴に、冷えた笑い声で報いる観衆。
いまや彼らの憎悪は堂々とした態度の戦争親父から、見苦しく泣き叫んでばかりの鹿次に矛先を転じていた。
なんであんな男の風上にも置けない奴が戦車に乗ってるんだ?
皆がそう思っている。戦車道を舐めていると。
「構え!」
銃殺隊が5人の心臓にむけて、短銃を構えた。
「執行!」
短銃の先から、細いワイヤーを引っ張った太い針が飛び出す。
短銃のグリップには、らせん状の電源コードがついていて、銃殺隊のベルトにつけられた高圧バッテリーにつながっている。
単発型ワイヤー針スタンガン、テイザーM26。
犯罪者制圧用に飛び道具として開発された、自動拳銃みたいに見える代物である。
もちろん性能は、護身用スタンガンと何ら変わるところがない。
電極付きの針が、あわれなホラー号乗組員の胴体に次々突き刺さる。
高圧電流をくらい、さしもの猛者、戦争親父も絶叫する。
ひとしきり野郎どもの苦悶に満ちた叫び声が、闘技場いっぱいに響き渡る。
他のクルーが次々と頭を垂れて気絶していく中、戦争親父は目を血走らせて雄叫びを上げる。
「見ておくがいい! 戦いに、敗れるとは、ごういう、ごどだああぁぁ―――――っ!!」
叫び終わると同時に、ついに壮絶に力尽きる戦争親父。
いっぽう鹿次はといえば、なさけないことに針が刺さる前に失神&失禁していた……。
「刑場」に、意識を失った5人の身体が並べられる。
将校役が、一人一人を検分して、意識がないのを確認する。
彼はうなずくと、「執行完了!」と宣言する。
観客席を埋めつくす観衆は、一斉に拍手。
これですべてが終わったかに思われた。
5分もしたころ、まず一番頑健な戦争親父が目を覚ます。
時間差こそあれ、次々と起き上がるクルーたち。
「あーあ、ひでえ目にあった」
「まったくだ」
「銃殺刑なんて、公営競戦車道始まって以来なんじゃね?」
「おい新入り、いつまでも白目むいておねんねしてんじゃねー! さっさと起き……」
ドライバーが、鹿次の様子がおかしいことに気がついたのは、このときだった。
「おい、テメエ! しっかりしやがれ」
「どうしたんだよ」
「親父! こいつ息してねえ!」
戦争親父がすばやく駆け寄り、鹿次の胸に耳を当てている。
「やばい! 心臓が止まってるぞ!
おい、AEDもってこい。あとは人工呼吸と心臓マッサージだ!」
一人が競技本部にAEDを取りに行く。
戦争親父は、鹿次の胸に両手を当てて、懸命に押す。
「代われ! 肋骨が折れても構わん! 押しまくれ!!」
「救急車じゃ間にあわねえ! ドクターヘリの手配だ!」
「観客の中に医者はいねえか!? 非常事態だ!!」
競技場は、急に慌ただしくなる。
アルゲマイネもヴァッフェンも、その扮装のまま本来の職務に戻る。
N山競戦車場は、大混乱のきわみにおちいった……。
──数日後。
梵野興業株式会社の社長室に、子どもがふたり呼ばれていた。
まだ幼いと言っていい、姉弟のような二人連れだった。
優しそうな顔の社長は、中学1年ぐらいの少女と小学生らしい男児に、おだやかに話しかける。
「叔父さんは、本当にお気の毒なことをしました」
男の子がそれを聞いて、しゃくり上げ始める。
姉とおぼしき女の子が、彼をなだめる。
「たった3人のお身内だったそうですね」
「はい、親を亡くした私たちに、実の子どもであるかのように接してくれた、優しい叔父でした」
少女がそう言うと、男の子は声を上げて泣き出した。
強面そうな重役たちも、今日はなにかしんみりして悲しげだ。
「さいわいここに、黒木君……叔父さんが遺された生命保険金がある。
彼には返さなければならないお金があったから、それは引いたけど
それでもかなり残りがあった。これからの生活に役立ててください」
社長は必要があればいつでも仁王様になれる人物だったが、今日ばかりは優しい大人で通すつもりのようだ。少なくともこの子どもたちの前では。
子どもら二人は、保険金と鹿次の骨壺を大事そうにおしいただいて、社長室を辞去した。
何度も何度もお辞儀をして……。
「……それにしても黒木のあほんだらあ、あんな小さな子供ら遺して、あんな死に方しやがって」
一番情け知らずに見える坊主頭の巨漢が、ぼそりとつぶやいた。
子どもらが下に向かうエレベーターに乗った頃合いだと思った社長は、三白眼の仁王様になっていた。
「まったく使えねえ奴だったな。今度からはもっとしっかり吟味しねえとならねえぞ」
社長室は先ほどとうって変わって、ブリザード吹きすさぶ男の戦場と化していた。
「だが、あのスペシャルマッチでは、こっちも大いに稼がせてもらった。
カスが一匹死んだくれえ、どうということはねえ」
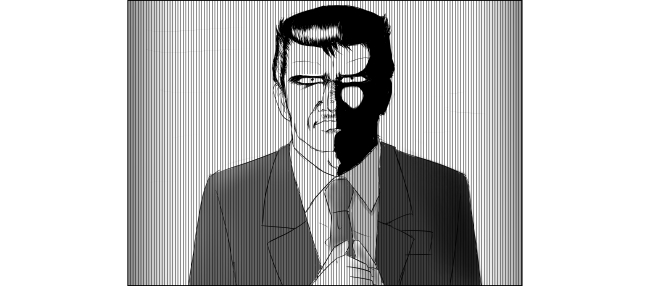
社長の頭の中からは、もう鹿次のことはとっくに消え去っていた。
『マスターが10億円は召し上げるが、保険金はお前らで分けろ。ってことだ』
『でも、10億円でも焼け石に冷却スプレーなのよね。魔界の累積赤字は』
ここは、「この地球」の茨城県の大洗海岸。
いまは海水浴シーズンも終わり、無人の「海の家」が寂しくたたずんでいる。
そこにいるのは子どもがふたり。白木の箱を持っている。
年かさの女の子が、箱から「黒木鹿次の霊」と書かれた白い陶器を取り出した。
男の子の方が、白木の箱を子どもとは思えない力で、こっぱみじんに踏みつぶす。
女の子は思い切り振りかぶり、体格からは考えられない速さで骨壺を海に投げる。
骨壺は、100mは沖合に飛んで、「ポチャン」と音を立てて沈んだ。
『なんだよ、なにかいいたいことでもあるのか?』
少年悪魔が、空中に向かって話しかける。
『ふん、地獄にも天国にも連れて行ってやらないよ。お前が選んだ道だ』
『ふーん。あんたどこにも行けないでウロウロしてるんだ。
じゃあ、とむらってあげる』
小娘悪魔は空中に魔方陣を描き、弔いの言葉を紡ぐ。
『クロキシシジノタマシイヨ、ウチュウニトンデ
エイエンノカナシミノナカニタダヨイタマエ』
魔方陣から強烈な光が発して、その先にあった者を「宇宙の地平線」まで飛ばした。
誰かさんへの呪いの言葉とともに。
-こんなどこが二次なのかわからない、オリジナルが書ける力量が必要な男戦車道ものなんかもう二度と書きたくないくらい嫌だ- おしまい
感想を書く
この話の感想を書きましょう!
全て感想を見る:感想一覧
