| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
Chocolate Time
作者:Simpson
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動第2章 秘密の恋人
2-1 恋人同士
恋人同士
8月4日。金曜日。
朝食のテーブルで、ケンジとマユミは平常通りを装っていた。しかし、二人の心の中は、すぐ隣に座った人への想いでいっぱいだった。
「マユミ、今日はよく食べるわね……」
母親が怪訝な顔で言った。
「成長期だからね」
「何言ってるの。あんたもう高二じゃない。そんなに食べて今から成長するのは体重だけよ」
マユミの横でケンジはクスッと笑った。
「昨日まで朝ご飯なんかほとんど食べなかったくせに……」
母親はマユミの前にドレッシングを置いた。マユミはそれを手にとって、生野菜に掛けた。
「何か嬉しい事でもあったの?」
「うん。あたしの人生で、たぶん最高の出来事がね」マユミは無邪気にウィンクをした。横にいたケンジは、思わず飲みかけたコーヒーを噴き出しそうになった。
「へえ……。いったいどんな事なのかしらね」
母親が、それ以上マユミに食い下がる気配はなかったので、とりあえずほっとしてケンジはコーヒーを飲み干した。
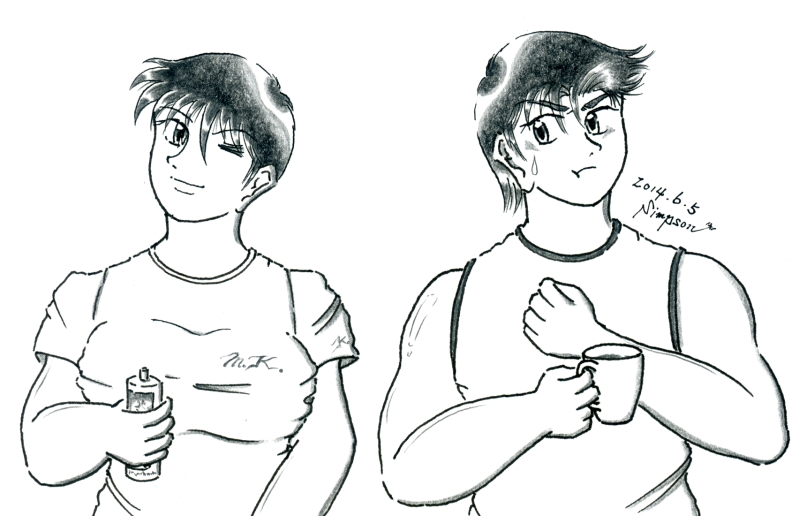
学校に到着し、自転車を降りた所で、ケンジは胸ポケットのケータイが震えるのを感じた。
彼はそれを取り出し、画面を見た。マユミからのメールだった。
『ケン兄、今夜はあたしの部屋に来て。一緒にチョコレートタイムしよう』
ケンジは自分の顔が一気に上気するのを感じた。そして思わず頬の筋肉が緩んだ。
「どうしたんだ? ケンジ」
不意にケンジの背後から声がした。ケンジはびくっと身体を震わせて振り向いた。
「なんだ、拓志か」
「なんだ、はないだろ? おまえ何顔赤くしてんの?」
「え?」
「ケータイ見ながら、何にやにやしてんだよ」
「べ、別に」
ケンジは大きなバッグを担いで、焦ったようにさっさと部室に向かって走り去った。
夕方、部活が終わって、部員たちがプールに併設されたジムのミーティングスペースに集まっていた。
「ケンジ、おまえ今日、えらく調子よかったじゃないか」
ケンジの隣に座った康男が言った。
「タイムもずいぶん伸びてたようだが」
「たまにはそんな日もなきゃ」ケンジは爽やかに笑った。
康男は怪訝な顔をした。「なんだ、その幸福そうな顔は」
ケンジたちの向かいに座った拓志が身を乗り出した。「何かいい事あったのか?」
「確かにいつもと雰囲気違うな」康男も言った。「言え! 何があった」
「言えないね」
「もしかして、彼女でもできたか?」
「ふふん……」
「『ふふん』? 何だ、余裕かませやがって」
「やっぱ彼女か」拓志が鋭い目でケンジを睨み付けながら言った。「そうか、さっきのはその彼女からのメールだったんだな」
康男が言った。「卑怯者。抜け駆けしやがって」
「何が抜け駆けだ。俺はおまえたちとそんな取り決めをした覚えはない」
「こうなったら、」康男がムキになった。「俺、本気でマユミちゃんに告白してやる」
「おお、おまえもその気になったか」拓志が面白そうに言った。「しろしろ、告白」
「ムダだよ」ケンジが言った。
「は?」
「残念だが、マユにはもう彼氏がいるんだ」
「何だと?」
「おまえ、こないだそんな事一言も言わなかったじゃないか。マユミちゃんにそんなのがいるなんて」
「そうだそうだ」
「って事は、マユミちゃんに彼氏ができたのも、つい最近……って事か?」
「ま、そんなとこだな」
「おまえら兄妹、同時期に恋人をゲットした、ってか」
「そ、そういう事にしとけ」ケンジが少し焦ったように言った。
「何が『そういう事』だ」康男が心底面白くなさそうにほおづえをついた。
その時、コーチがドアを開けて入ってきた。
部員たちは背中を伸ばした。
「突然だが、」
コーチは部員たちの前に立つと、いきなり口を開いた。
「うちの部活にカナダから留学生がやってくる」
集まった部員たちの中にざわめきが広がった。
「男子部員には残念だが、ケネス・シンプソンという男だ」
「セクハラ発言」後ろの方に座った女子部員の一人が隣に座ったマネージャの友人に声を潜めて言った。
「楽しみじゃん」そのマネージャはにこにこしながら応えた。「イケメンだったら食べちゃおかな」
「現在高校二年。彼は中学の時、カナダの水泳の全国大会で三位に入賞したという凄いやつだ。得意種目はバタフライ」
コーチはそう言って、ケンジに目を向けた。「海棠、いい刺激になるぞ」
ケンジは軽く肩をすくめた。
「しばらくは学校の学生寮に寝泊まりするが、帰国する三日前からホームステイする予定だ。部員の家に」
「誰んちですか?」康男がさっと手を挙げて言った。
「まだ未定だ。本人が来て、うちの部活に馴染んだら決める」
また康男が手を挙げた。「俺、英語話せません」
部員の間にまたざわめきが広がった。口々に、「俺も」「あたしも」と言い合っている。
「ああ、それは心配いらん。彼は普通に日本語を話す。ちょっと癖はあるがな」
「カナダから来るのに、日本語を話すって……」拓志が横のケンジに小声で言った。
「ま、いいじゃないか。無駄な気を遣わなくて済むって事だし」
拓志は眉間にしわを寄せてケンジを見た。
「おまえ、今日はほんとに楽観的だな、いつもと違って……」
その日の晩、入浴を済ませたケンジは、約束通りマユミの部屋を訪ねた。
「マユ……」恥じらいながら顔を赤くして、後ろ手にドアを閉めたケンジは、ベッドに座ったマユミに近づいた。そして手に持っていたチョコレートの箱を差し出した。
「ケン兄」マユミはにっこりと笑った。「コーヒー淹れてくるね」
マユミはケンジをベッドに座らせると、階下に下りて、トレイに二つのカップを載せて戻ってきた。
並んで座った二人は、チョコレートをつまみながら同じように頬を赤く染めていた。
「ケン兄」
「何だ?」
「なんか、昨日からケン兄が別人に見える」
「別人?」
「うん。もうお兄ちゃんとしては見られない」マユミは笑った。
「そう言われれば俺も」
「ケン兄も?」
「うん。って言うか、俺、結構前からおまえを妹として見られなくなってた」
「どういう事?」
「じ、実はさ……」ケンジはもじもじしながらうつむいて言った。「俺、マユとエッチしたい、ってずっと思ってた」
「そうなの?」
「うん。ごめん……」
「謝る事ないよ。あたし嬉しい」
「だ、だって、俺、いやらしい目でおまえを見てたって事なんだぞ?」
「ケン兄がさ、女なら誰でもいいからエッチしたい、って思ってたのなら、ちょっと軽蔑しちゃうけど、あたし限定だったんでしょ?」
ケンジは頷いた。
「でも、どうして?」
「おまえ、かわいいし、その……優しいし、いい匂いだし、柔らかそうだし、あったかそうだし、それに、」
マユミは笑いをこらえながら次の言葉を促した「それに?」
「お、俺さ、前に偶然おまえが部屋で着替えてるところ、見ちゃって……」
「え? 覗いてたの?」
「だ、だから偶然だって」
「ケン兄だから許す」マユミは笑った。「で、あたしの身体を見て興奮したって事?」
「興奮、って言うか……まあ、興奮なんだろうな。身体がすごく熱くなって……」
「そういう時って、男のコは一人でやっちゃうわけ?」
「うん」ケンジは真剣な顔をマユミに向けた。「一人でやって、一人でイく。そして虚しい気分に浸る」
「あははは! 大変だね、男のコって」

ケンジはコーヒーのカップを持ち上げた。
「女子は、そんな風にはならないのか?」
「そんな風?」
「かっこいいオトコに抱かれるのを想像して、興奮して、自分で身体を刺激して慰める、とか……」
「あんまり聞かないし、あたしもそんな事、した事なかった。でもね、」
マユミは恥じらったように上目遣いで言った。「ケン兄に抱かれる事を想像して、最近自分でやったりしてたんだ」
「えっ? そ、そうなのか?」
「うん」
「お、俺とエッチしたかった、って事?」
「そうだよー」マユミは照れくさそうにケンジの右腕に自分の両腕を絡めた。「だから、昨夜はとっても嬉しくて、幸せだった。願いがなかった、って事だから」
「お、俺もだ、マユ。俺も昨夜は天に昇るような気持ちだったよ」
「そう……良かった。あたしたち、想い合ってたんだね、壁一つ隔てたところで」
「そうだな」
穏やかに長いため息をついた後、ケンジは言った。「でも、マユ、」
「なに?」
「おまえが以前つき合ってたとかいう先輩から胸を触られた時は拒絶したのに、なんで昨日は俺を受け入れてくれたんだ?」
「ケン兄に抱かれたい、って思ってたから、ってさっき言ったでしょ?」
「でも、いきなりキスされたりしたら、恐怖感とか感じるんじゃないのか? 俺、あの後おまえにひっぱたかれる、って覚悟してたぞ」
マユミは微笑みながらケンジの手を取った。「ケン兄だから……」
「え?」
「ろくに話もした事のない相手に、いきなり抱きつかれたら、たぶん女の子はみんなびっくりしちゃって、拒絶しちゃうよ。でも、ケン兄とは生まれる時からずっと一緒だし、今までいっぱい話したりしたじゃん」
「そういう事なのか?」
「それは大きいと思うよ。よく知らない相手からいきなり触られるのは、やっぱりイヤだけど、ケン兄みたいにその人がその時、どんな顔をして、どんな事を言って、どういう事するのか、って事がわかっていれば安心だよ」
「安心……なんだ」ケンジはほっとしたように小さなため息をついた。
「ケン兄の反応は予想できるもん。ずっと一緒に暮らしてるからね。うん、やっぱり安心感だね」マユミは微笑んだ。
「そうなんだな……」ケンジは頭を掻いた。
「男のコはそうじゃないんでしょ?」マユミは悪戯っぽい笑みを浮かべて、ケンジの顔を覗き込んだ。「あんまり親しくなくても、エッチしたいって思えばできちゃうんでしょ?」
「うん。おそらく」
「だよね。だから性犯罪がなくならないんだよね」
「お、俺はそんな事しないからな」
「わかってるよ」マユミは優しく言った。
それからマユミはチョコレートの空き箱と、空になった二つのカップが載ったトレイを持ち、自分の机に運んだ。そして振り向き、ケンジの目を見た。「ケン兄、今夜も……」
ケンジは緊張したような笑みを浮かべて頷いた。
部屋の灯りを消し、ケンジとマユミ兄妹は着ていた服を全て脱ぎ去り、マユミのベッドに横になっていた。
「マユ、まだ痛いんじゃないのか?」
「大丈夫。ケン兄と何度かエッチするうちに痛みなんて、感じなくなるよ、きっと。だから」
「何度か、って……、いいのか? 俺、おまえをそんなに何度も抱いても」
「あたし、もうケン兄以外の男子なんて目に入らないもん」
「マユ……」
「自分の身体がケン兄仕様になっていくなんて、もう最高じゃない」
「マユっ!」ケンジは思わずマユミの身体を抱きしめた。
「だから、きて、ケン兄……」
ケンジは腕をほどき、マユミを仰向けにした。そして両脚の膝に手を掛けた。
「はあ……」マユミは熱いため息をついた。
ケンジはマユミの両脚をゆっくり開かせると、その股間に顔を埋めた。
「あっ! やっ、やだ、ケン兄、何するの? やめて!」
顔を上げたケンジが言った。「どうして? おまえのここ、舐めて気持ち良くしてやるんだよ」
「は、恥ずかしいよ、そんなの……」
「たぶん、気持ちいいって。心配いらないよ」
ケンジは優しく言った。
「ケン兄……」
「どうしても気持ち悪くて我慢できなかったら、言いな。すぐやめるから」
「わ、わかった……」マユミは少し震える声で言った後、昨夜と同じように両手で自分の顔を覆った。

マユミの部屋のカーテンは厚手なので、外からの光があまり入らない。灯りを消すと、部屋の中は思いの外暗くなって、ケンジはマユミのその部分をつぶさに観察する事はできなかった。彼は目を閉じ、舌をそっとマユミの谷間に宛がって、ぺろぺろと舐め始めた。
「あっ!」マユミが小さく叫んだ。
それからケンジは、愛らしい茂みの下にあるフードに隠れていた小さな粒を舌で探り出し、ゆっくりと舐めた。
「あっ、あっ! ケ、ケン兄!」
ケンジは口を離して目を上げた。マユミは、まだ顔を手で覆っているようだった。
「マユ、どう? 気持ちいい?」
「ケン兄、なんかすごいよ。あたし、感じてきたみたい、とっても気持ちいい……」
「そうか」
ケンジはその言葉に勢いづいて、再び彼女の谷間やいつしか露わになって硬くなっているクリトリスに舌を這わせ続けた。
マユミは身体をくねらせ、喘ぎ声を上げ続けた。
谷間から雫が漏れ出したのに気づいたケンジは、今、妹のマユミが自分の刺激で気持ち良くなっている事を確信し、満ち足りた気分に浸っていた。そしてその行為を続けているうちに、ケンジの全身も熱を帯び、その中心にあるものはすでに天を指して先端から透明な液を漏らし始めていた。
ケンジは身体を起こした。そして小さく言った。「マユ、入ってもいい? おまえに」
「うん。ケン兄、きて、あたしの中にきて」
「よし。じゃあ、マユ、昨夜は俺のペースだったから、今度はおまえがリードしなよ」
「え? ど、どういう事?」
「マユが上になってさ」ケンジはそう言うと、マユミの背中を抱え上げ、自分は仰向けになって身体に跨がらせた。「騎乗位って言うんだって。こういうの」
「さすがオトコの人って詳しいね」
ケンジは自分のペニスを手で掴み、上に向けて固定した。
「そのままおまえが自分の中に入れてみなよ」
「わ、わかった。でも、何だか恥ずかしいな……」
マユミは股間に手を添えて、ケンジの硬く、熱くなった持ち物を自分の秘部に導き、少しずつ腰を落としていった。
ケンジのペニスの先端がぬるり、とマユミの谷間を押し開いた。
「あ、いい、マユ、いい気持ちだ」
「あたしもだよ、ケン兄」
「痛くないか?」
「うん。平気。それで、これからどうすればいい?」
「もっと奥まで入れられる?」
「う、うん。がんばってみる……」
マユミは脚をふるふると小さく震わせながら、腰を少しずつケンジの身体に沈ませていった。
「痛かったら抜いていいから」
「だ、大丈夫……」
暗がりの中、マユミが苦しそうな顔をしているのが、ケンジの目に映った。
マユミは意を決したように、一気に腰を落とした。「んんっ!」
ケンジの最高に怒張したペニスが、ぬるりと根元までマユミの身体に埋まり込んだ。
「あ、あああ……」ケンジも身体を仰け反らせ、喘いだ。
「ケン兄、ケン兄っ!」
「お、俺の上で動いて、お、おまえの一番気持ちのいい所を刺激するんだ」
マユミは腰を前後、上下にぎこちなく動かした。
「ああ、な、何だか気持ちいい、あ、ああああ、ケン兄」
ケンジのペニスに貫かれたまま、マユミは腰をさらに大きく動かし始めた。二人の結合部分の隙間から、マユミが分泌した液が流れ出し、二人の股間をぬるぬるにしていた。そしてマユミが腰を動かす度にそれがぬちゃぬちゃと淫靡な音を立てた。その音を聞きながら、ケンジは絶頂を予感し始めた。

「マ、マユっ! お、俺、も、もう……」
「出ちゃうの? ケン兄。いいよ。あたしも気持ち良くなってるから、ああああ……」
マユミは腰の動きをますます大きくした。そして彼女は苦しそうな表情で自分の乳房を両手で鷲づかみにすると、一度腰を持ち上げ、再び勢いをつけてケンジのペニスを自分の奥深くに迎え入れた。
「いっ!」
「んんっ! うぐっ!」喉の奥でケンジが呻いた。
びゅくっ! びゅるるっ! びゅる、びゅる、びゅくびゅくびゅくっ!
「ああああ! ケン兄ーっ!」マユミの身体ががくがくと震えた。ケンジの身体は大きく海老ぞりになりびくん、びくんと脈動しながらまた体中の熱い想いをマユミの中に放出し続けた。
ページ上へ戻る朝食のテーブルで、ケンジとマユミは平常通りを装っていた。しかし、二人の心の中は、すぐ隣に座った人への想いでいっぱいだった。
「マユミ、今日はよく食べるわね……」
母親が怪訝な顔で言った。
「成長期だからね」
「何言ってるの。あんたもう高二じゃない。そんなに食べて今から成長するのは体重だけよ」
マユミの横でケンジはクスッと笑った。
「昨日まで朝ご飯なんかほとんど食べなかったくせに……」
母親はマユミの前にドレッシングを置いた。マユミはそれを手にとって、生野菜に掛けた。
「何か嬉しい事でもあったの?」
「うん。あたしの人生で、たぶん最高の出来事がね」マユミは無邪気にウィンクをした。横にいたケンジは、思わず飲みかけたコーヒーを噴き出しそうになった。
「へえ……。いったいどんな事なのかしらね」
母親が、それ以上マユミに食い下がる気配はなかったので、とりあえずほっとしてケンジはコーヒーを飲み干した。
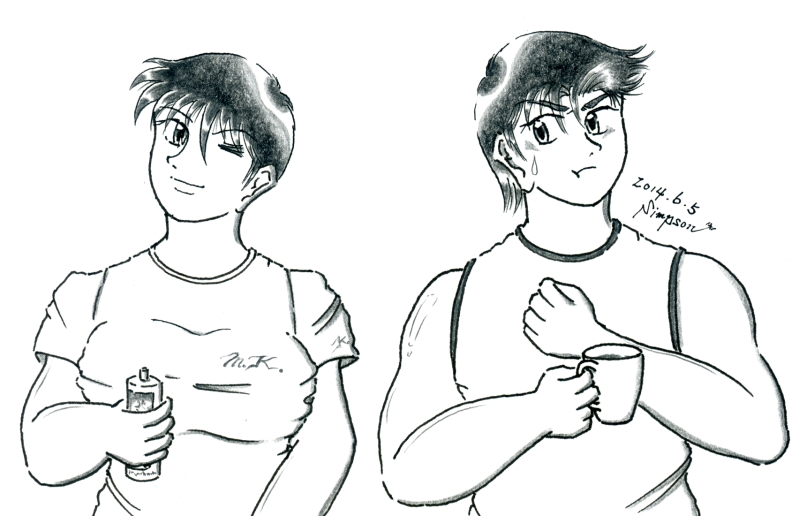
学校に到着し、自転車を降りた所で、ケンジは胸ポケットのケータイが震えるのを感じた。
彼はそれを取り出し、画面を見た。マユミからのメールだった。
『ケン兄、今夜はあたしの部屋に来て。一緒にチョコレートタイムしよう』
ケンジは自分の顔が一気に上気するのを感じた。そして思わず頬の筋肉が緩んだ。
「どうしたんだ? ケンジ」
不意にケンジの背後から声がした。ケンジはびくっと身体を震わせて振り向いた。
「なんだ、拓志か」
「なんだ、はないだろ? おまえ何顔赤くしてんの?」
「え?」
「ケータイ見ながら、何にやにやしてんだよ」
「べ、別に」
ケンジは大きなバッグを担いで、焦ったようにさっさと部室に向かって走り去った。
夕方、部活が終わって、部員たちがプールに併設されたジムのミーティングスペースに集まっていた。
「ケンジ、おまえ今日、えらく調子よかったじゃないか」
ケンジの隣に座った康男が言った。
「タイムもずいぶん伸びてたようだが」
「たまにはそんな日もなきゃ」ケンジは爽やかに笑った。
康男は怪訝な顔をした。「なんだ、その幸福そうな顔は」
ケンジたちの向かいに座った拓志が身を乗り出した。「何かいい事あったのか?」
「確かにいつもと雰囲気違うな」康男も言った。「言え! 何があった」
「言えないね」
「もしかして、彼女でもできたか?」
「ふふん……」
「『ふふん』? 何だ、余裕かませやがって」
「やっぱ彼女か」拓志が鋭い目でケンジを睨み付けながら言った。「そうか、さっきのはその彼女からのメールだったんだな」
康男が言った。「卑怯者。抜け駆けしやがって」
「何が抜け駆けだ。俺はおまえたちとそんな取り決めをした覚えはない」
「こうなったら、」康男がムキになった。「俺、本気でマユミちゃんに告白してやる」
「おお、おまえもその気になったか」拓志が面白そうに言った。「しろしろ、告白」
「ムダだよ」ケンジが言った。
「は?」
「残念だが、マユにはもう彼氏がいるんだ」
「何だと?」
「おまえ、こないだそんな事一言も言わなかったじゃないか。マユミちゃんにそんなのがいるなんて」
「そうだそうだ」
「って事は、マユミちゃんに彼氏ができたのも、つい最近……って事か?」
「ま、そんなとこだな」
「おまえら兄妹、同時期に恋人をゲットした、ってか」
「そ、そういう事にしとけ」ケンジが少し焦ったように言った。
「何が『そういう事』だ」康男が心底面白くなさそうにほおづえをついた。
その時、コーチがドアを開けて入ってきた。
部員たちは背中を伸ばした。
「突然だが、」
コーチは部員たちの前に立つと、いきなり口を開いた。
「うちの部活にカナダから留学生がやってくる」
集まった部員たちの中にざわめきが広がった。
「男子部員には残念だが、ケネス・シンプソンという男だ」
「セクハラ発言」後ろの方に座った女子部員の一人が隣に座ったマネージャの友人に声を潜めて言った。
「楽しみじゃん」そのマネージャはにこにこしながら応えた。「イケメンだったら食べちゃおかな」
「現在高校二年。彼は中学の時、カナダの水泳の全国大会で三位に入賞したという凄いやつだ。得意種目はバタフライ」
コーチはそう言って、ケンジに目を向けた。「海棠、いい刺激になるぞ」
ケンジは軽く肩をすくめた。
「しばらくは学校の学生寮に寝泊まりするが、帰国する三日前からホームステイする予定だ。部員の家に」
「誰んちですか?」康男がさっと手を挙げて言った。
「まだ未定だ。本人が来て、うちの部活に馴染んだら決める」
また康男が手を挙げた。「俺、英語話せません」
部員の間にまたざわめきが広がった。口々に、「俺も」「あたしも」と言い合っている。
「ああ、それは心配いらん。彼は普通に日本語を話す。ちょっと癖はあるがな」
「カナダから来るのに、日本語を話すって……」拓志が横のケンジに小声で言った。
「ま、いいじゃないか。無駄な気を遣わなくて済むって事だし」
拓志は眉間にしわを寄せてケンジを見た。
「おまえ、今日はほんとに楽観的だな、いつもと違って……」
その日の晩、入浴を済ませたケンジは、約束通りマユミの部屋を訪ねた。
「マユ……」恥じらいながら顔を赤くして、後ろ手にドアを閉めたケンジは、ベッドに座ったマユミに近づいた。そして手に持っていたチョコレートの箱を差し出した。
「ケン兄」マユミはにっこりと笑った。「コーヒー淹れてくるね」
マユミはケンジをベッドに座らせると、階下に下りて、トレイに二つのカップを載せて戻ってきた。
並んで座った二人は、チョコレートをつまみながら同じように頬を赤く染めていた。
「ケン兄」
「何だ?」
「なんか、昨日からケン兄が別人に見える」
「別人?」
「うん。もうお兄ちゃんとしては見られない」マユミは笑った。
「そう言われれば俺も」
「ケン兄も?」
「うん。って言うか、俺、結構前からおまえを妹として見られなくなってた」
「どういう事?」
「じ、実はさ……」ケンジはもじもじしながらうつむいて言った。「俺、マユとエッチしたい、ってずっと思ってた」
「そうなの?」
「うん。ごめん……」
「謝る事ないよ。あたし嬉しい」
「だ、だって、俺、いやらしい目でおまえを見てたって事なんだぞ?」
「ケン兄がさ、女なら誰でもいいからエッチしたい、って思ってたのなら、ちょっと軽蔑しちゃうけど、あたし限定だったんでしょ?」
ケンジは頷いた。
「でも、どうして?」
「おまえ、かわいいし、その……優しいし、いい匂いだし、柔らかそうだし、あったかそうだし、それに、」
マユミは笑いをこらえながら次の言葉を促した「それに?」
「お、俺さ、前に偶然おまえが部屋で着替えてるところ、見ちゃって……」
「え? 覗いてたの?」
「だ、だから偶然だって」
「ケン兄だから許す」マユミは笑った。「で、あたしの身体を見て興奮したって事?」
「興奮、って言うか……まあ、興奮なんだろうな。身体がすごく熱くなって……」
「そういう時って、男のコは一人でやっちゃうわけ?」
「うん」ケンジは真剣な顔をマユミに向けた。「一人でやって、一人でイく。そして虚しい気分に浸る」
「あははは! 大変だね、男のコって」

ケンジはコーヒーのカップを持ち上げた。
「女子は、そんな風にはならないのか?」
「そんな風?」
「かっこいいオトコに抱かれるのを想像して、興奮して、自分で身体を刺激して慰める、とか……」
「あんまり聞かないし、あたしもそんな事、した事なかった。でもね、」
マユミは恥じらったように上目遣いで言った。「ケン兄に抱かれる事を想像して、最近自分でやったりしてたんだ」
「えっ? そ、そうなのか?」
「うん」
「お、俺とエッチしたかった、って事?」
「そうだよー」マユミは照れくさそうにケンジの右腕に自分の両腕を絡めた。「だから、昨夜はとっても嬉しくて、幸せだった。願いがなかった、って事だから」
「お、俺もだ、マユ。俺も昨夜は天に昇るような気持ちだったよ」
「そう……良かった。あたしたち、想い合ってたんだね、壁一つ隔てたところで」
「そうだな」
穏やかに長いため息をついた後、ケンジは言った。「でも、マユ、」
「なに?」
「おまえが以前つき合ってたとかいう先輩から胸を触られた時は拒絶したのに、なんで昨日は俺を受け入れてくれたんだ?」
「ケン兄に抱かれたい、って思ってたから、ってさっき言ったでしょ?」
「でも、いきなりキスされたりしたら、恐怖感とか感じるんじゃないのか? 俺、あの後おまえにひっぱたかれる、って覚悟してたぞ」
マユミは微笑みながらケンジの手を取った。「ケン兄だから……」
「え?」
「ろくに話もした事のない相手に、いきなり抱きつかれたら、たぶん女の子はみんなびっくりしちゃって、拒絶しちゃうよ。でも、ケン兄とは生まれる時からずっと一緒だし、今までいっぱい話したりしたじゃん」
「そういう事なのか?」
「それは大きいと思うよ。よく知らない相手からいきなり触られるのは、やっぱりイヤだけど、ケン兄みたいにその人がその時、どんな顔をして、どんな事を言って、どういう事するのか、って事がわかっていれば安心だよ」
「安心……なんだ」ケンジはほっとしたように小さなため息をついた。
「ケン兄の反応は予想できるもん。ずっと一緒に暮らしてるからね。うん、やっぱり安心感だね」マユミは微笑んだ。
「そうなんだな……」ケンジは頭を掻いた。
「男のコはそうじゃないんでしょ?」マユミは悪戯っぽい笑みを浮かべて、ケンジの顔を覗き込んだ。「あんまり親しくなくても、エッチしたいって思えばできちゃうんでしょ?」
「うん。おそらく」
「だよね。だから性犯罪がなくならないんだよね」
「お、俺はそんな事しないからな」
「わかってるよ」マユミは優しく言った。
それからマユミはチョコレートの空き箱と、空になった二つのカップが載ったトレイを持ち、自分の机に運んだ。そして振り向き、ケンジの目を見た。「ケン兄、今夜も……」
ケンジは緊張したような笑みを浮かべて頷いた。
部屋の灯りを消し、ケンジとマユミ兄妹は着ていた服を全て脱ぎ去り、マユミのベッドに横になっていた。
「マユ、まだ痛いんじゃないのか?」
「大丈夫。ケン兄と何度かエッチするうちに痛みなんて、感じなくなるよ、きっと。だから」
「何度か、って……、いいのか? 俺、おまえをそんなに何度も抱いても」
「あたし、もうケン兄以外の男子なんて目に入らないもん」
「マユ……」
「自分の身体がケン兄仕様になっていくなんて、もう最高じゃない」
「マユっ!」ケンジは思わずマユミの身体を抱きしめた。
「だから、きて、ケン兄……」
ケンジは腕をほどき、マユミを仰向けにした。そして両脚の膝に手を掛けた。
「はあ……」マユミは熱いため息をついた。
ケンジはマユミの両脚をゆっくり開かせると、その股間に顔を埋めた。
「あっ! やっ、やだ、ケン兄、何するの? やめて!」
顔を上げたケンジが言った。「どうして? おまえのここ、舐めて気持ち良くしてやるんだよ」
「は、恥ずかしいよ、そんなの……」
「たぶん、気持ちいいって。心配いらないよ」
ケンジは優しく言った。
「ケン兄……」
「どうしても気持ち悪くて我慢できなかったら、言いな。すぐやめるから」
「わ、わかった……」マユミは少し震える声で言った後、昨夜と同じように両手で自分の顔を覆った。

マユミの部屋のカーテンは厚手なので、外からの光があまり入らない。灯りを消すと、部屋の中は思いの外暗くなって、ケンジはマユミのその部分をつぶさに観察する事はできなかった。彼は目を閉じ、舌をそっとマユミの谷間に宛がって、ぺろぺろと舐め始めた。
「あっ!」マユミが小さく叫んだ。
それからケンジは、愛らしい茂みの下にあるフードに隠れていた小さな粒を舌で探り出し、ゆっくりと舐めた。
「あっ、あっ! ケ、ケン兄!」
ケンジは口を離して目を上げた。マユミは、まだ顔を手で覆っているようだった。
「マユ、どう? 気持ちいい?」
「ケン兄、なんかすごいよ。あたし、感じてきたみたい、とっても気持ちいい……」
「そうか」
ケンジはその言葉に勢いづいて、再び彼女の谷間やいつしか露わになって硬くなっているクリトリスに舌を這わせ続けた。
マユミは身体をくねらせ、喘ぎ声を上げ続けた。
谷間から雫が漏れ出したのに気づいたケンジは、今、妹のマユミが自分の刺激で気持ち良くなっている事を確信し、満ち足りた気分に浸っていた。そしてその行為を続けているうちに、ケンジの全身も熱を帯び、その中心にあるものはすでに天を指して先端から透明な液を漏らし始めていた。
ケンジは身体を起こした。そして小さく言った。「マユ、入ってもいい? おまえに」
「うん。ケン兄、きて、あたしの中にきて」
「よし。じゃあ、マユ、昨夜は俺のペースだったから、今度はおまえがリードしなよ」
「え? ど、どういう事?」
「マユが上になってさ」ケンジはそう言うと、マユミの背中を抱え上げ、自分は仰向けになって身体に跨がらせた。「騎乗位って言うんだって。こういうの」
「さすがオトコの人って詳しいね」
ケンジは自分のペニスを手で掴み、上に向けて固定した。
「そのままおまえが自分の中に入れてみなよ」
「わ、わかった。でも、何だか恥ずかしいな……」
マユミは股間に手を添えて、ケンジの硬く、熱くなった持ち物を自分の秘部に導き、少しずつ腰を落としていった。
ケンジのペニスの先端がぬるり、とマユミの谷間を押し開いた。
「あ、いい、マユ、いい気持ちだ」
「あたしもだよ、ケン兄」
「痛くないか?」
「うん。平気。それで、これからどうすればいい?」
「もっと奥まで入れられる?」
「う、うん。がんばってみる……」
マユミは脚をふるふると小さく震わせながら、腰を少しずつケンジの身体に沈ませていった。
「痛かったら抜いていいから」
「だ、大丈夫……」
暗がりの中、マユミが苦しそうな顔をしているのが、ケンジの目に映った。
マユミは意を決したように、一気に腰を落とした。「んんっ!」
ケンジの最高に怒張したペニスが、ぬるりと根元までマユミの身体に埋まり込んだ。
「あ、あああ……」ケンジも身体を仰け反らせ、喘いだ。
「ケン兄、ケン兄っ!」
「お、俺の上で動いて、お、おまえの一番気持ちのいい所を刺激するんだ」
マユミは腰を前後、上下にぎこちなく動かした。
「ああ、な、何だか気持ちいい、あ、ああああ、ケン兄」
ケンジのペニスに貫かれたまま、マユミは腰をさらに大きく動かし始めた。二人の結合部分の隙間から、マユミが分泌した液が流れ出し、二人の股間をぬるぬるにしていた。そしてマユミが腰を動かす度にそれがぬちゃぬちゃと淫靡な音を立てた。その音を聞きながら、ケンジは絶頂を予感し始めた。

「マ、マユっ! お、俺、も、もう……」
「出ちゃうの? ケン兄。いいよ。あたしも気持ち良くなってるから、ああああ……」
マユミは腰の動きをますます大きくした。そして彼女は苦しそうな表情で自分の乳房を両手で鷲づかみにすると、一度腰を持ち上げ、再び勢いをつけてケンジのペニスを自分の奥深くに迎え入れた。
「いっ!」
「んんっ! うぐっ!」喉の奥でケンジが呻いた。
びゅくっ! びゅるるっ! びゅる、びゅる、びゅくびゅくびゅくっ!
「ああああ! ケン兄ーっ!」マユミの身体ががくがくと震えた。ケンジの身体は大きく海老ぞりになりびくん、びくんと脈動しながらまた体中の熱い想いをマユミの中に放出し続けた。
感想を書く
この話の感想を書きましょう!
全て感想を見る:感想一覧
