| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
Chocolate Time
作者:Simpson
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動第3章 揺れる想い
3-1 すれ違い
すれ違い
8月6日。日曜日。
夜、ケンジの後にシャワーを済ませたマユミは、いそいそとケンジの部屋を訪ねた。
「マユ」ケンジは嬉しそうに両手を広げて、その妹の柔らかな身体をぎゅっと抱きしめた。
「マユー」ケンジはまたそう呟きながら、くんくんとマユミの首筋やうなじの匂いを嗅いだ。
「やだー、ケン兄くすぐったいよ」
「いい匂いだ、マユ」
「シャンプーの匂いでしょ?」マユミは笑いながらケンジのベッドに腰掛けた。
「アイスコーヒー、作っといたから」ケンジがそう言って、氷で冷やされたコーヒーのデキャンタを手に持ち、二つのグラスに注ぎ入れた。
エアコンの風が、マユミの頬を撫でた。
「ねえねえ、ケン兄」
コーヒーを飲む手を止めて、マユミが唐突に言った。
「何だ? マユ」
「ケン兄さ、エッチなDVD持ってる、って言ってたよね?」
「なっ!」ケンジは一瞬絶句して顔を赤らめた。「何だよ、いきなり」
「あたし、観てみたい、それ」
「えっ?」
「ねえ、観せてよ。あたし観た事ないから興味ある」
「で、でも、おまえ気持ち悪い、って思うかも知れないぞ」
「いいの。それでも。ね、ケン兄、お願い」
ケンジはしぶしぶ机の上のノートパソコンを開き、机の奥に隠していたラベルのないディスクを取り出してセットした。
「自分で買ったわけじゃないんだね。それ、コピー?」
「う、うん。友だちから借りて焼いた」
画面に艶めかしいピンク色のロゴが表示され、いきなり男女のキスシーンがアップになった。
椅子に座らせたマユミの隣に立ったケンジは、ごくりと唾を飲み込んだ。
「わあ……すごい、濃厚だね。昨夜のケン兄のキスもこんなだったね。マネしたんだ」
「う、うん……」
それから画面の中の男女は服を脱がせ合い、最初に男優が女優の秘部を舐め始めた。
『ああん……気持ちいい、あ、あああ……』
それから今度は男女が逆になり、大きく反り返った男優のペニスを、女優が長い髪を掻き上げながら咥え、じゅるじゅると淫猥な音をたてながら吸ったり舐めたりした。
「ケン兄のの方がおっきいね」
「な、何言ってるんだ、マユ。は、恥ずかしいコト言わないでくれ」
男優が脚を伸ばした上に、女優が後ろ向きで跨がり、その谷間にペニスが挿入され始めた。
『ああ、ああああ……』女優は仰け反り、甘い声をあげた。
「あたしもケン兄のが入ってくる時、とっても気持ちいいよ」
「そ、そうなのか……」
女優が腰を上下に大きく動かし始めた。背後から手を回し、男優が女優のクリトリスを激しく指で擦り始めた。女優はさらに大きな声で喘いだ。ケンジは焦って画面のボリュームつまみを下げ、音を小さくした。
「こんな事されたら痛いだけだよ、あたし……」
「これは演技だからな。そこって、すごくデリケートなんだろ?」
「うん。こんなに乱暴に擦られたら痛くてエッチどころじゃなくなるよ、きっと」そしてマユミはケンジの顔を見上げた。「ケン兄は優しく触ってくれるよね、いつも」
ケンジは頭を掻いた。
「なんで? なんでデリケートだって知ってるの?」
「立ち読みした」
「立ち読み?」
「うん。本屋でこっそり『本当に気持ちのいいエッチ』っていう本。女医さんが書いたとかいう本」
「そうなんだー。すごいね。ケン兄ってやっぱりフェミニストなんだね」
マユミは嬉しそうに言った。
画面上では、いつしか仰向けになった女優に男優が覆い被さり、正常位で挿入したペニスを大きく出し入れしていた。時折男優は下になった女優の唇を吸ったり、背を丸めて乳首を咥え込んだりした。その度に女優は身体をくねくねとよじらせ、大きな喘ぎ声を出した。
「確かにオーバーアクションかも……」
「だろ?」
出し抜けに男優は身体を離し、焦ったように女優の頭の横ににじり寄って膝立ちになると、ペニスを右手で握り、彼女の顔に向けた。
うっとりとした表情の女優の顔に向かって、白い液が何度も容赦なく迸り、その瞼や唇、頬にまつわりついた。
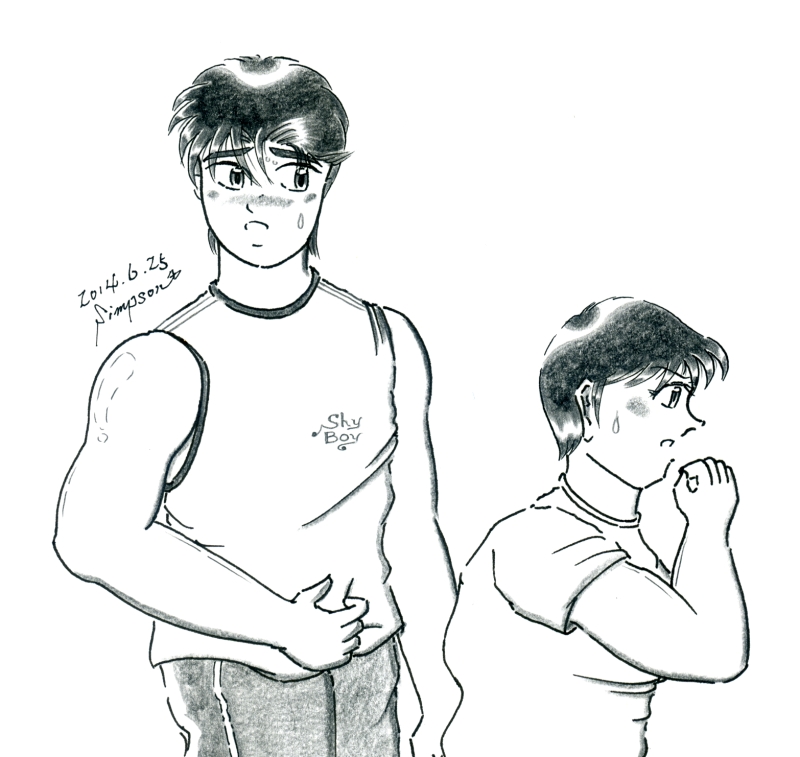
「うわあ……」マユミは凍り付いたように身動き一つせず、その画面に見入っていた。
ケンジが先に口を開いた。
「俺、イヤだな、こんなコトするの」
「そうなの?」マユミは意外そうな顔をケンジに向けた。
「相手の顔に放出するなんて……」
「男の人にとっては、女性を凌辱してるみたいで興奮するんじゃない?」
「俺、マユを凌辱したいなんて思ってないから」
「いつかやってみて」
「ええっ?!」
「どんな感じなのか、あたし経験してみたい」
「いやだ。断る。絶対やらないからな、俺」ケンジは赤い顔をして言った。
「そんなに目一杯否定しなくても……」マユミは呆れたように笑って立ち上がった。
ケンジはDVDディスクを取り出し、元のように引き出しの奥にしまった後、パソコンをシャットダウンさせて、マユミに向き直った。
「俺は、マユの身体を自分の一人エッチの道具になんかしたくないんだよ」
そして彼はマユミの頬を両手で包みこんでそっとキスをした。
「ごめんね、ケン兄」
ベッドに座り直してケンジとマユミは語り合っていた。
「何が?」
「今、生理中だから、エッチできないね」
ケンジは肩をすくめた。「気にするな。おまえを気持ち良くする方法はいっぱいある」
「ケン兄も出したいんじゃない? あの男優さんみたいに」
「マユの匂いを嗅いだり、おっぱい吸ったりする事はできるだろ? 最後はティッシュに出せばいいわけだし」
「やっぱりゴムがあった方がいいね……」
「そうだな……近いうちに買ってくるよ、俺」
「がんばってね」マユミはウィンクをした。
◆
明くる8月7日。月曜日。
週明け。夕方の海棠家の食卓はケンジの所にだけ箸が揃えて置かれたままだった。
「ケン兄遅いね」
「今度の土曜日、大会だからね」母親が言った。「今週は部活の時間も延長だって言ってたわ。あんた知らなかったの?」
「知ってたけど……」
「ふうん……」母親は怪訝な顔でマユミを見た。
「何よ」
「ちょっと前まであんた、ケンジの事心配したりする事なんかなかったのに、って思ったのよ」
「そ、そりゃ、に、肉親だもん。心配するよ」
「確かにここんとこあんたたち妙に仲良しだもんね。何かあったの?」
「え? べ、別に何もないよ」
「高二になってからあんたケンジの事脂臭い、オトコ臭いって避けてたりしたのに、唐突に親密になってるような……」
「ケ、ケン兄の部屋は、確かにオトコ臭いね……」マユミは野菜ミックスグレープジュースを慌てて飲み干した。
「その割には、あんた近頃、よくケンジに誘われて部屋に行ってない?」
「う、うん」
「ケンジの部屋で何してるの?」
「ケン兄がもらったチョコレートとか、一緒に食べてるんだよ」
「コーヒーも時々下から持ってってるわね。一緒に飲んでるの? ケンジの部屋で」
「うん」
「オトコ臭いの、気にならないわけ?」
「気にならない事はないけど……」
「用もないのにケンジの部屋に行ってるの? ただのチョコレートタイムするために?」
「よ、用事だったら、いろいろあるよ。こ、こないだはTシャツ借りなきゃいけなかったし」
「Tシャツ? ケンジの? なんで?」
「た、体育祭で着なきゃいけないんだ」
「なんでケンジのを借りなきゃいけないのよ。あんただって持ってるでしょ? 2、3枚」
「も、もういいでしょっ!」マユミは頬を赤らめて叫び、食器を持って立ち上がった。「ごちそうさまっ!」
マユミはさっさと、二階に上がっていった。
「よくわからない子だわね。我が子ながら」
「おまえ、よくあんなに追い詰めるような言い方ができるな……」父親が呆れたように言った。
「え? 私、そんなに追い詰めてた?」
遅く帰ったケンジが入浴を済ませて二階に上がってくるのをマユミは待ち構えていた。ケンジの部屋の前でマユミは言った。「ケン兄、一緒にコーヒー飲もうよ」
ケンジの返事はちょっと意外なものだった。「あ、う、うん。マユ、今日は遠慮するよ」
マユミは一瞬絶句してケンジの顔を見た。「そ、そうか、疲れてるんだね」
「悪い。もうくたくたで……。俺、寝る。じゃあなマユ、おやすみ」
マユミの返事も聞かずケンジは自分の部屋に入った。閉じたドアの前に立ったマユミは一つため息をついて、自分の部屋に入っていった。

火曜日も水曜日もケンジの反応は同じだった。マユミは日に日にケンジへの想いが募り、夜はケンジの身体の温もりを想っては自らを慰めるのだった。
そして木曜日。
「……ケン兄、」
「マユ、ごめん。最近相手してやれなくて」
「あたし、寂しい。何だかケン兄がほんとに遠くへいっちゃう気がしてきた」
「大げさだよマユ。大会が終わったらまた一緒にチョコレートタイムしよう」
「あたし、待てない。そんなに」
ケンジは少しむっとして言った。
「俺だって、おまえといれば癒される。でも、大会も大事なんだ。わかってくれよ」
「癒してあげるよ。いつでもあたし、ケン兄を癒してあげられるから」マユミは少し涙声になっていた。
「もう少し我慢してくれ。マユ、お願いだ」ケンジはそう言ってマユミの肩に手を置いた。
しかしマユミはその手を振り払うと強い口調で言った。「もういいよ! ケン兄。あたしの気持ちなんかわかってくれないんだ」そして彼女は自分の部屋に戻り、ドアを一方的に閉めた。
◆
「あんたたち、ケンカでもしてんの?」
金曜日の夕食時、母親が切り出した。明日の大会に備えて、前日の今日はケンジの帰りは早く、いつものように家族四人で食卓を囲んでいた。
「え?」マユミが手を止めた。「な、なんで?」
「今朝から会話がほとんどないじゃない。ついこの前はデートしたりして、超仲良さげだったのに」
「デートじゃないから」
「あのね、兄妹ってのは一生で一番長くつき合う人間なんだからね。いがみ合ったりしたらきついわよ。って、こないだ言わなかったっけ?」
「べ、別にケンカなんか、してないよ。なあ、マユ」
「う、うん。そうだよ」
「ならいいけど……」
しばらくの沈黙の後、ケンジが躊躇いがちに口を開いた。「そうそう、明日の大会、おまえも来てくれるだろ? マユ」
「……行けないかも」
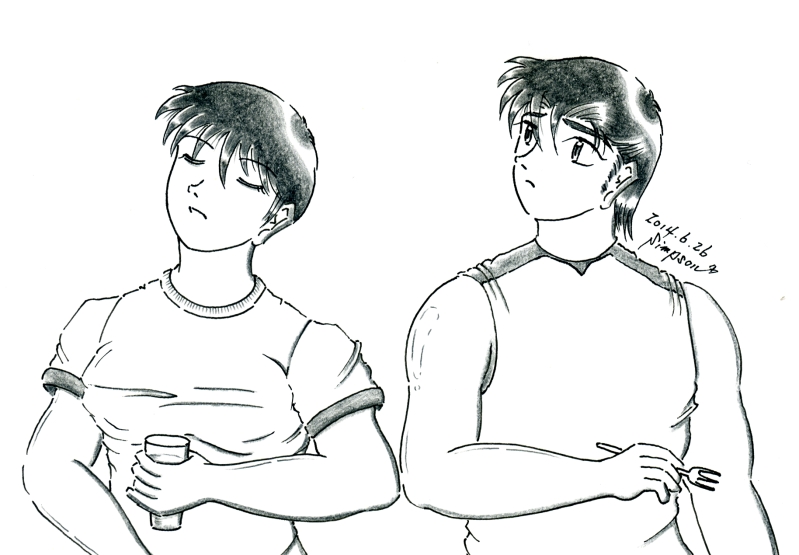
母親が口を挟んだ。「なんで? あんたの学校の水泳部も何人か出場するんでしょ?」母親が怪訝な顔で言った。
「うちからは出ないよ。弱いから」
それだけ言うとマユミはさっさと食器を片付けて二階へ上がっていった。
「やっぱりあんたたちケンカしてるんじゃない」
母親の言葉に応えもせず、ケンジは一つため息をついて立ち上がった。「明日早いから、俺、もう寝るよ」
◆
土曜日。ケンジは競泳の大会に出場するため、暗い内から家を出た。遅く起きたマユミは母親と向かい合って朝食をとっていた。
「あんたも行くでしょ? ケンジの水泳の大会」
「友だちと約束があるから行かない」
「何それ。冷たい妹ね。いつも必ず行ってたじゃない。ケンジが出る大会。仲良しのお兄ちゃんの事が気にならないの?」
マユミは表情を曇らせた。「別に……仲良しなんかじゃないから」
「母さん10時頃には家を出るから」
「あたしその前に出かける」
「もう、勝手にしなさい」
しばらく黙ったままトーストをかじっていたマユミが唐突に口を開いた。「そう言えば、ケン兄が外国人を明日連れてくるって本当?」
「そうなのよ。ホームステイをうちで引き受ける事になってね。何でもケンジの学校に部活留学でやってきている男の子らしいわよ」
「ケニーくんの事かな……」
「なに? あんた知ってるの?」
「うん。一度会った事がある。街で」
「そう。カナダの全国中学生大会で三位だったとか言う子だって?」
「そうなの? 凄いんだね、あの人」
「帰国前の三日間、うちにホームステイ事になったらしいわ」
マユミは驚いて顔を上げた。
「み、三日間も?!」
「そうなのよ。二泊三日」母親はため息をついて続けた。「英語なんてみんなしゃべれないのに、どうしろっていうのかしらね」
「それは心配いらないよ」
「なんで?」
「その人日本語ぺらぺらだから」
「そう。良かった……」
「じゃ、じゃあ、ケニーくん、二晩もケン兄の部屋に泊まるわけ?」
「あんたの部屋に泊めるわけにはいかないでしょっ」
「最低……」
「なに? あんたその男の子を部屋に泊めたいわけ?」
「そんなわけないでしょ! もう、ほんっとに最低」
◆
その大会では、ケンジは全く冴えない記録しか出せず、解散前のミーティングでは、監督教師やコーチは逆に心配して彼をわざわざ部員から離れたところまで呼び、声をかけた。
「まるで別人のようだったぞ、海棠」
「すみません……」ケンジはうつむいていた。
「明らかにメンタル的な問題だな」コーチが腕組みをして言った。「心配事があるんなら、相談に乗ってやってもいいが……」
「い、いえ、大丈夫です。必ず来週には復活します。約束します」ケンジは目を上げて言った。
「ま、おまえのことだから、よほどのことでもない限り、今日のような調子を引きずるとは思えんが……」
監督の教師はケンジの肩に手を置いて続けた。「来週になってもこんな感じだったら、何か手を打たなきゃな」
その監督の鋭い眼差しが、ケンジの目を射貫き、ケンジは一瞬肩をびくつかせ動揺した。
ケンジが部員たちの集団に戻ると、マネージャのアヤカが心配そうな顔でケンジに近づいた。
「海棠君……」
ケンジは言葉もなくため息をついた。
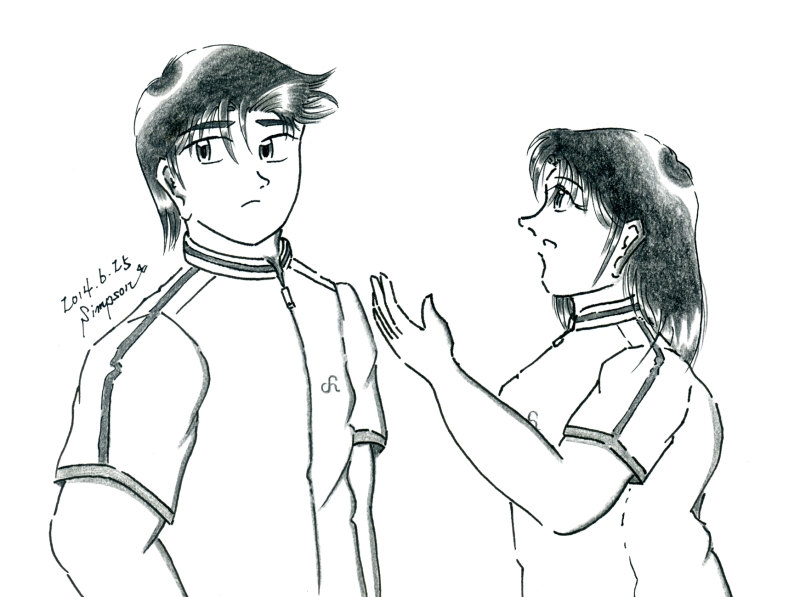
「何かあったの? 今日の記録……」
ケンジは無理して微笑み、その視線を受け止めた。「大丈夫。ただ調子が悪かっただけさ」
「にしても、フォームも精彩を欠いてたし、表情も冴えないみたい」
「心配いらないよ。来週はいつも通りだ」
ケンジはそれでも明らかにばつが悪そうに瞳を泳がせ、焦ったように彼女から離れた。
ミーティングが終わった後、ケネスがケンジを呼び止めた。
「ケンジ、明日から世話になるけど、よろしゅうな」
そして軽く肩をたたいた。
「あ、ああ。遠慮するな。気楽な気持ちで来いよ」
「土産も持って行くさかいな」
「土産? なんだよ、それ」
「今は秘密や。っちゅうても、別に秘密にするようなもんでもあれへんけどな」
ケネスはにこにこ笑いながら自分の荷物を肩に担いだ。
「……」
ケンジはじっとしてうつむいていた。
「どないしたん?」
ケネスはケンジの顔を覗き込んだ。
ケンジは一つため息をついてケネスに顔を向けた。「ケニー」
「何? どないしたんや?」
「……」
「歩きながら話そやないか。もう遅いで。家族も心配するやろ」
「……そうだな」
ケネスは来日してから学校の学生寮に寝泊まりしていた。学校へ向かうルートをケネスと並んで、自転車を押しながらケンジも歩いた。
大会会場を後にして、二つ目の交差点を過ぎたあたりで、ケンジが唐突に口を開いた。
「仮に、仮にだぞ、」
ケネスはちょっとびっくりしてケンジに顔を向けた。
ケンジは少し顔を赤くして続けた。「お、俺に彼女ができたとして、その子が好きで、そ、その、か、身体を求めたくなったとしたら」
「彼女、できそうなんか? ケンジ」
ケンジは慌てて言った。「だ、だから、仮に、って言っただろ。彼女なんか、いないけどさ……」
「ほんで、求めたくなったとしたら、何やねん」
「その気持ちって、本当の『好き』っていう気持ちなのかな」
ケネスは少し考えてから言った。
「そやな、男っちゅう生きモンは、ある意味性欲の塊やからなー。ヤりたい気持ちを恋心と錯覚してまうことはあるかもしれへんな。特に高校生ぐらいやったら」
「やっぱり……そうだよな」
ケンジはまた小さなため息をついた。
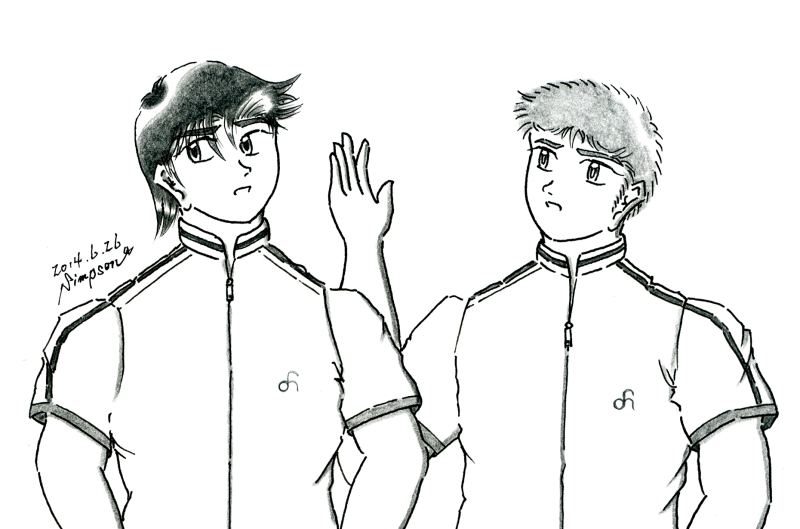
ケネスはそんな彼の表情をちらりと見て、ぽつりと言った。
「問題は、ヤった後の気持ちやな」
「ヤった後?」
「そや。性欲抜きで、自分が相手をどう思てるか、ってことは、事後にしかわからへんやろ? いわゆる『賢者タイム』」
「お前、そんなことよく知ってるな。日本に住んでもいないくせに」
「男子の性行動は世界共通やないか。それに的を射た素晴らしい言葉やで、『賢者タイム』」
ケンジは呆れたように眉尻を下げた。
「その子がほんまに好きやったら、コトが終わった後に抱きしめてても、心は熱いままや。それで確かめられるんちゃう?」
「そうだな……」
ケンジは少しだけ微笑んで、ケネスを見た。「すまん、ケニー、変なこと訊いちゃって」
「わいは一人身やけど、こないな意見でも少しは役に立ったか?」
「ああ、なんかちょっと安心した。ありがとう」
ケネスははた、と立ち止まった。「……って」
「ん? どうした? ケニー」ケンジも立ち止まり、ケネスの顔を見た。
彼は顎に手を当てて眉を寄せ、ケンジの顔をまじまじと見返した。
「ケンジは確かめられるんか? そんな事後の気持ち」
「えっ?」
「実際女のコとエッチせなんだら、わからへんやろ? そないなこと。おまえ、コトが終わって確かめること、できるんか? っちゅうか、実はケンジ、お互い愛し合って、何べんもエッチしとる相手が実はおるんとちゃうか?」
ケンジは激しく動揺した。「だっ、だっ、だから、か、かか、仮にって言っただろっ!」
「……ムキになっとる」
「か、帰るぞ、遅くなっちまう」ケンジは焦ったように再び自転車を押して、勝手に歩き始めた。
ケネスも遅れてケンジを追いかけ、そのまま二人は連れだって学校の学生寮への道をたどっていった。
ページ上へ戻る夜、ケンジの後にシャワーを済ませたマユミは、いそいそとケンジの部屋を訪ねた。
「マユ」ケンジは嬉しそうに両手を広げて、その妹の柔らかな身体をぎゅっと抱きしめた。
「マユー」ケンジはまたそう呟きながら、くんくんとマユミの首筋やうなじの匂いを嗅いだ。
「やだー、ケン兄くすぐったいよ」
「いい匂いだ、マユ」
「シャンプーの匂いでしょ?」マユミは笑いながらケンジのベッドに腰掛けた。
「アイスコーヒー、作っといたから」ケンジがそう言って、氷で冷やされたコーヒーのデキャンタを手に持ち、二つのグラスに注ぎ入れた。
エアコンの風が、マユミの頬を撫でた。
「ねえねえ、ケン兄」
コーヒーを飲む手を止めて、マユミが唐突に言った。
「何だ? マユ」
「ケン兄さ、エッチなDVD持ってる、って言ってたよね?」
「なっ!」ケンジは一瞬絶句して顔を赤らめた。「何だよ、いきなり」
「あたし、観てみたい、それ」
「えっ?」
「ねえ、観せてよ。あたし観た事ないから興味ある」
「で、でも、おまえ気持ち悪い、って思うかも知れないぞ」
「いいの。それでも。ね、ケン兄、お願い」
ケンジはしぶしぶ机の上のノートパソコンを開き、机の奥に隠していたラベルのないディスクを取り出してセットした。
「自分で買ったわけじゃないんだね。それ、コピー?」
「う、うん。友だちから借りて焼いた」
画面に艶めかしいピンク色のロゴが表示され、いきなり男女のキスシーンがアップになった。
椅子に座らせたマユミの隣に立ったケンジは、ごくりと唾を飲み込んだ。
「わあ……すごい、濃厚だね。昨夜のケン兄のキスもこんなだったね。マネしたんだ」
「う、うん……」
それから画面の中の男女は服を脱がせ合い、最初に男優が女優の秘部を舐め始めた。
『ああん……気持ちいい、あ、あああ……』
それから今度は男女が逆になり、大きく反り返った男優のペニスを、女優が長い髪を掻き上げながら咥え、じゅるじゅると淫猥な音をたてながら吸ったり舐めたりした。
「ケン兄のの方がおっきいね」
「な、何言ってるんだ、マユ。は、恥ずかしいコト言わないでくれ」
男優が脚を伸ばした上に、女優が後ろ向きで跨がり、その谷間にペニスが挿入され始めた。
『ああ、ああああ……』女優は仰け反り、甘い声をあげた。
「あたしもケン兄のが入ってくる時、とっても気持ちいいよ」
「そ、そうなのか……」
女優が腰を上下に大きく動かし始めた。背後から手を回し、男優が女優のクリトリスを激しく指で擦り始めた。女優はさらに大きな声で喘いだ。ケンジは焦って画面のボリュームつまみを下げ、音を小さくした。
「こんな事されたら痛いだけだよ、あたし……」
「これは演技だからな。そこって、すごくデリケートなんだろ?」
「うん。こんなに乱暴に擦られたら痛くてエッチどころじゃなくなるよ、きっと」そしてマユミはケンジの顔を見上げた。「ケン兄は優しく触ってくれるよね、いつも」
ケンジは頭を掻いた。
「なんで? なんでデリケートだって知ってるの?」
「立ち読みした」
「立ち読み?」
「うん。本屋でこっそり『本当に気持ちのいいエッチ』っていう本。女医さんが書いたとかいう本」
「そうなんだー。すごいね。ケン兄ってやっぱりフェミニストなんだね」
マユミは嬉しそうに言った。
画面上では、いつしか仰向けになった女優に男優が覆い被さり、正常位で挿入したペニスを大きく出し入れしていた。時折男優は下になった女優の唇を吸ったり、背を丸めて乳首を咥え込んだりした。その度に女優は身体をくねくねとよじらせ、大きな喘ぎ声を出した。
「確かにオーバーアクションかも……」
「だろ?」
出し抜けに男優は身体を離し、焦ったように女優の頭の横ににじり寄って膝立ちになると、ペニスを右手で握り、彼女の顔に向けた。
うっとりとした表情の女優の顔に向かって、白い液が何度も容赦なく迸り、その瞼や唇、頬にまつわりついた。
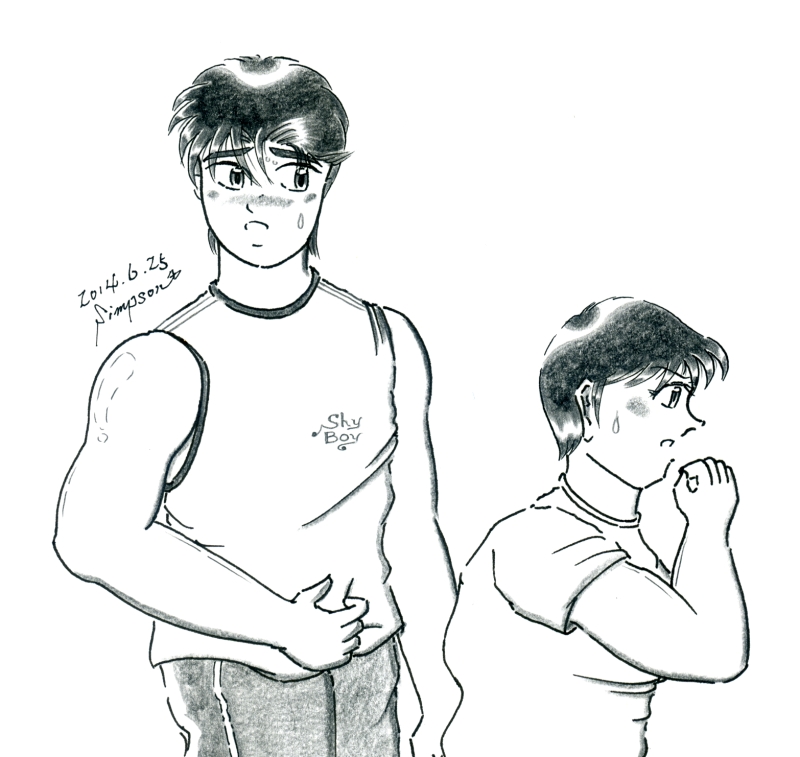
「うわあ……」マユミは凍り付いたように身動き一つせず、その画面に見入っていた。
ケンジが先に口を開いた。
「俺、イヤだな、こんなコトするの」
「そうなの?」マユミは意外そうな顔をケンジに向けた。
「相手の顔に放出するなんて……」
「男の人にとっては、女性を凌辱してるみたいで興奮するんじゃない?」
「俺、マユを凌辱したいなんて思ってないから」
「いつかやってみて」
「ええっ?!」
「どんな感じなのか、あたし経験してみたい」
「いやだ。断る。絶対やらないからな、俺」ケンジは赤い顔をして言った。
「そんなに目一杯否定しなくても……」マユミは呆れたように笑って立ち上がった。
ケンジはDVDディスクを取り出し、元のように引き出しの奥にしまった後、パソコンをシャットダウンさせて、マユミに向き直った。
「俺は、マユの身体を自分の一人エッチの道具になんかしたくないんだよ」
そして彼はマユミの頬を両手で包みこんでそっとキスをした。
「ごめんね、ケン兄」
ベッドに座り直してケンジとマユミは語り合っていた。
「何が?」
「今、生理中だから、エッチできないね」
ケンジは肩をすくめた。「気にするな。おまえを気持ち良くする方法はいっぱいある」
「ケン兄も出したいんじゃない? あの男優さんみたいに」
「マユの匂いを嗅いだり、おっぱい吸ったりする事はできるだろ? 最後はティッシュに出せばいいわけだし」
「やっぱりゴムがあった方がいいね……」
「そうだな……近いうちに買ってくるよ、俺」
「がんばってね」マユミはウィンクをした。
◆
明くる8月7日。月曜日。
週明け。夕方の海棠家の食卓はケンジの所にだけ箸が揃えて置かれたままだった。
「ケン兄遅いね」
「今度の土曜日、大会だからね」母親が言った。「今週は部活の時間も延長だって言ってたわ。あんた知らなかったの?」
「知ってたけど……」
「ふうん……」母親は怪訝な顔でマユミを見た。
「何よ」
「ちょっと前まであんた、ケンジの事心配したりする事なんかなかったのに、って思ったのよ」
「そ、そりゃ、に、肉親だもん。心配するよ」
「確かにここんとこあんたたち妙に仲良しだもんね。何かあったの?」
「え? べ、別に何もないよ」
「高二になってからあんたケンジの事脂臭い、オトコ臭いって避けてたりしたのに、唐突に親密になってるような……」
「ケ、ケン兄の部屋は、確かにオトコ臭いね……」マユミは野菜ミックスグレープジュースを慌てて飲み干した。
「その割には、あんた近頃、よくケンジに誘われて部屋に行ってない?」
「う、うん」
「ケンジの部屋で何してるの?」
「ケン兄がもらったチョコレートとか、一緒に食べてるんだよ」
「コーヒーも時々下から持ってってるわね。一緒に飲んでるの? ケンジの部屋で」
「うん」
「オトコ臭いの、気にならないわけ?」
「気にならない事はないけど……」
「用もないのにケンジの部屋に行ってるの? ただのチョコレートタイムするために?」
「よ、用事だったら、いろいろあるよ。こ、こないだはTシャツ借りなきゃいけなかったし」
「Tシャツ? ケンジの? なんで?」
「た、体育祭で着なきゃいけないんだ」
「なんでケンジのを借りなきゃいけないのよ。あんただって持ってるでしょ? 2、3枚」
「も、もういいでしょっ!」マユミは頬を赤らめて叫び、食器を持って立ち上がった。「ごちそうさまっ!」
マユミはさっさと、二階に上がっていった。
「よくわからない子だわね。我が子ながら」
「おまえ、よくあんなに追い詰めるような言い方ができるな……」父親が呆れたように言った。
「え? 私、そんなに追い詰めてた?」
遅く帰ったケンジが入浴を済ませて二階に上がってくるのをマユミは待ち構えていた。ケンジの部屋の前でマユミは言った。「ケン兄、一緒にコーヒー飲もうよ」
ケンジの返事はちょっと意外なものだった。「あ、う、うん。マユ、今日は遠慮するよ」
マユミは一瞬絶句してケンジの顔を見た。「そ、そうか、疲れてるんだね」
「悪い。もうくたくたで……。俺、寝る。じゃあなマユ、おやすみ」
マユミの返事も聞かずケンジは自分の部屋に入った。閉じたドアの前に立ったマユミは一つため息をついて、自分の部屋に入っていった。

火曜日も水曜日もケンジの反応は同じだった。マユミは日に日にケンジへの想いが募り、夜はケンジの身体の温もりを想っては自らを慰めるのだった。
そして木曜日。
「……ケン兄、」
「マユ、ごめん。最近相手してやれなくて」
「あたし、寂しい。何だかケン兄がほんとに遠くへいっちゃう気がしてきた」
「大げさだよマユ。大会が終わったらまた一緒にチョコレートタイムしよう」
「あたし、待てない。そんなに」
ケンジは少しむっとして言った。
「俺だって、おまえといれば癒される。でも、大会も大事なんだ。わかってくれよ」
「癒してあげるよ。いつでもあたし、ケン兄を癒してあげられるから」マユミは少し涙声になっていた。
「もう少し我慢してくれ。マユ、お願いだ」ケンジはそう言ってマユミの肩に手を置いた。
しかしマユミはその手を振り払うと強い口調で言った。「もういいよ! ケン兄。あたしの気持ちなんかわかってくれないんだ」そして彼女は自分の部屋に戻り、ドアを一方的に閉めた。
◆
「あんたたち、ケンカでもしてんの?」
金曜日の夕食時、母親が切り出した。明日の大会に備えて、前日の今日はケンジの帰りは早く、いつものように家族四人で食卓を囲んでいた。
「え?」マユミが手を止めた。「な、なんで?」
「今朝から会話がほとんどないじゃない。ついこの前はデートしたりして、超仲良さげだったのに」
「デートじゃないから」
「あのね、兄妹ってのは一生で一番長くつき合う人間なんだからね。いがみ合ったりしたらきついわよ。って、こないだ言わなかったっけ?」
「べ、別にケンカなんか、してないよ。なあ、マユ」
「う、うん。そうだよ」
「ならいいけど……」
しばらくの沈黙の後、ケンジが躊躇いがちに口を開いた。「そうそう、明日の大会、おまえも来てくれるだろ? マユ」
「……行けないかも」
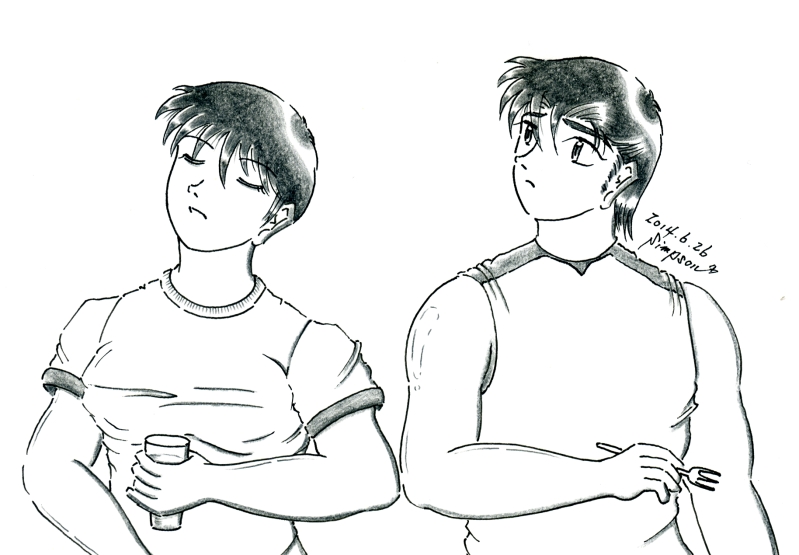
母親が口を挟んだ。「なんで? あんたの学校の水泳部も何人か出場するんでしょ?」母親が怪訝な顔で言った。
「うちからは出ないよ。弱いから」
それだけ言うとマユミはさっさと食器を片付けて二階へ上がっていった。
「やっぱりあんたたちケンカしてるんじゃない」
母親の言葉に応えもせず、ケンジは一つため息をついて立ち上がった。「明日早いから、俺、もう寝るよ」
◆
土曜日。ケンジは競泳の大会に出場するため、暗い内から家を出た。遅く起きたマユミは母親と向かい合って朝食をとっていた。
「あんたも行くでしょ? ケンジの水泳の大会」
「友だちと約束があるから行かない」
「何それ。冷たい妹ね。いつも必ず行ってたじゃない。ケンジが出る大会。仲良しのお兄ちゃんの事が気にならないの?」
マユミは表情を曇らせた。「別に……仲良しなんかじゃないから」
「母さん10時頃には家を出るから」
「あたしその前に出かける」
「もう、勝手にしなさい」
しばらく黙ったままトーストをかじっていたマユミが唐突に口を開いた。「そう言えば、ケン兄が外国人を明日連れてくるって本当?」
「そうなのよ。ホームステイをうちで引き受ける事になってね。何でもケンジの学校に部活留学でやってきている男の子らしいわよ」
「ケニーくんの事かな……」
「なに? あんた知ってるの?」
「うん。一度会った事がある。街で」
「そう。カナダの全国中学生大会で三位だったとか言う子だって?」
「そうなの? 凄いんだね、あの人」
「帰国前の三日間、うちにホームステイ事になったらしいわ」
マユミは驚いて顔を上げた。
「み、三日間も?!」
「そうなのよ。二泊三日」母親はため息をついて続けた。「英語なんてみんなしゃべれないのに、どうしろっていうのかしらね」
「それは心配いらないよ」
「なんで?」
「その人日本語ぺらぺらだから」
「そう。良かった……」
「じゃ、じゃあ、ケニーくん、二晩もケン兄の部屋に泊まるわけ?」
「あんたの部屋に泊めるわけにはいかないでしょっ」
「最低……」
「なに? あんたその男の子を部屋に泊めたいわけ?」
「そんなわけないでしょ! もう、ほんっとに最低」
◆
その大会では、ケンジは全く冴えない記録しか出せず、解散前のミーティングでは、監督教師やコーチは逆に心配して彼をわざわざ部員から離れたところまで呼び、声をかけた。
「まるで別人のようだったぞ、海棠」
「すみません……」ケンジはうつむいていた。
「明らかにメンタル的な問題だな」コーチが腕組みをして言った。「心配事があるんなら、相談に乗ってやってもいいが……」
「い、いえ、大丈夫です。必ず来週には復活します。約束します」ケンジは目を上げて言った。
「ま、おまえのことだから、よほどのことでもない限り、今日のような調子を引きずるとは思えんが……」
監督の教師はケンジの肩に手を置いて続けた。「来週になってもこんな感じだったら、何か手を打たなきゃな」
その監督の鋭い眼差しが、ケンジの目を射貫き、ケンジは一瞬肩をびくつかせ動揺した。
ケンジが部員たちの集団に戻ると、マネージャのアヤカが心配そうな顔でケンジに近づいた。
「海棠君……」
ケンジは言葉もなくため息をついた。
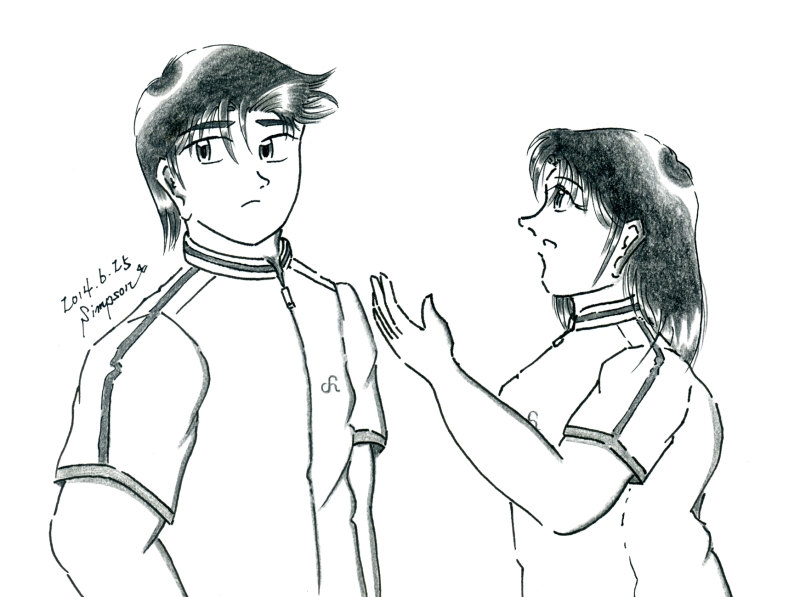
「何かあったの? 今日の記録……」
ケンジは無理して微笑み、その視線を受け止めた。「大丈夫。ただ調子が悪かっただけさ」
「にしても、フォームも精彩を欠いてたし、表情も冴えないみたい」
「心配いらないよ。来週はいつも通りだ」
ケンジはそれでも明らかにばつが悪そうに瞳を泳がせ、焦ったように彼女から離れた。
ミーティングが終わった後、ケネスがケンジを呼び止めた。
「ケンジ、明日から世話になるけど、よろしゅうな」
そして軽く肩をたたいた。
「あ、ああ。遠慮するな。気楽な気持ちで来いよ」
「土産も持って行くさかいな」
「土産? なんだよ、それ」
「今は秘密や。っちゅうても、別に秘密にするようなもんでもあれへんけどな」
ケネスはにこにこ笑いながら自分の荷物を肩に担いだ。
「……」
ケンジはじっとしてうつむいていた。
「どないしたん?」
ケネスはケンジの顔を覗き込んだ。
ケンジは一つため息をついてケネスに顔を向けた。「ケニー」
「何? どないしたんや?」
「……」
「歩きながら話そやないか。もう遅いで。家族も心配するやろ」
「……そうだな」
ケネスは来日してから学校の学生寮に寝泊まりしていた。学校へ向かうルートをケネスと並んで、自転車を押しながらケンジも歩いた。
大会会場を後にして、二つ目の交差点を過ぎたあたりで、ケンジが唐突に口を開いた。
「仮に、仮にだぞ、」
ケネスはちょっとびっくりしてケンジに顔を向けた。
ケンジは少し顔を赤くして続けた。「お、俺に彼女ができたとして、その子が好きで、そ、その、か、身体を求めたくなったとしたら」
「彼女、できそうなんか? ケンジ」
ケンジは慌てて言った。「だ、だから、仮に、って言っただろ。彼女なんか、いないけどさ……」
「ほんで、求めたくなったとしたら、何やねん」
「その気持ちって、本当の『好き』っていう気持ちなのかな」
ケネスは少し考えてから言った。
「そやな、男っちゅう生きモンは、ある意味性欲の塊やからなー。ヤりたい気持ちを恋心と錯覚してまうことはあるかもしれへんな。特に高校生ぐらいやったら」
「やっぱり……そうだよな」
ケンジはまた小さなため息をついた。
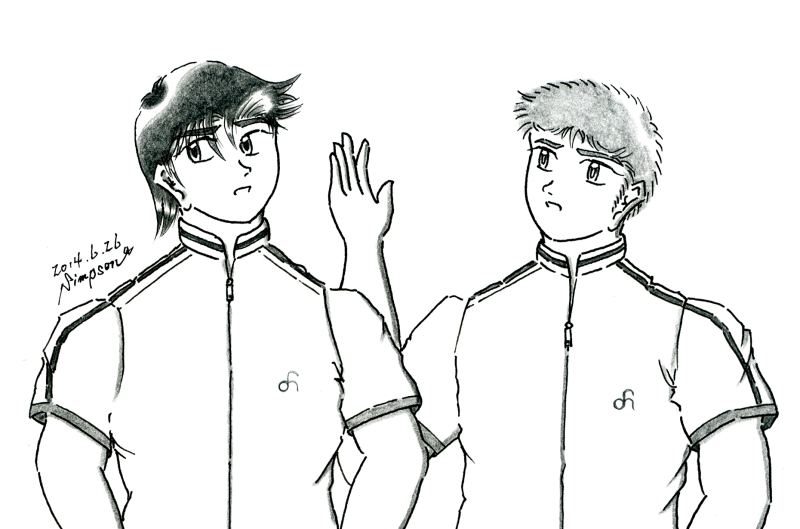
ケネスはそんな彼の表情をちらりと見て、ぽつりと言った。
「問題は、ヤった後の気持ちやな」
「ヤった後?」
「そや。性欲抜きで、自分が相手をどう思てるか、ってことは、事後にしかわからへんやろ? いわゆる『賢者タイム』」
「お前、そんなことよく知ってるな。日本に住んでもいないくせに」
「男子の性行動は世界共通やないか。それに的を射た素晴らしい言葉やで、『賢者タイム』」
ケンジは呆れたように眉尻を下げた。
「その子がほんまに好きやったら、コトが終わった後に抱きしめてても、心は熱いままや。それで確かめられるんちゃう?」
「そうだな……」
ケンジは少しだけ微笑んで、ケネスを見た。「すまん、ケニー、変なこと訊いちゃって」
「わいは一人身やけど、こないな意見でも少しは役に立ったか?」
「ああ、なんかちょっと安心した。ありがとう」
ケネスははた、と立ち止まった。「……って」
「ん? どうした? ケニー」ケンジも立ち止まり、ケネスの顔を見た。
彼は顎に手を当てて眉を寄せ、ケンジの顔をまじまじと見返した。
「ケンジは確かめられるんか? そんな事後の気持ち」
「えっ?」
「実際女のコとエッチせなんだら、わからへんやろ? そないなこと。おまえ、コトが終わって確かめること、できるんか? っちゅうか、実はケンジ、お互い愛し合って、何べんもエッチしとる相手が実はおるんとちゃうか?」
ケンジは激しく動揺した。「だっ、だっ、だから、か、かか、仮にって言っただろっ!」
「……ムキになっとる」
「か、帰るぞ、遅くなっちまう」ケンジは焦ったように再び自転車を押して、勝手に歩き始めた。
ケネスも遅れてケンジを追いかけ、そのまま二人は連れだって学校の学生寮への道をたどっていった。
感想を書く
この話の感想を書きましょう!
全て感想を見る:感想一覧
