| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
RSリベリオン・セイヴァー外伝 「オオカミと巫女]
作者:伊波ヨシアキ
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動オオカミと巫女
前書き

俺は、この夏休みを利用して弥生と神無さんの実家「玄那神社」へ出向いていた。
蝉の鳴き声がこだまする山道を、汗だくになりながら地図を片手に歩き続けた。
玄那神社は、この集落からやや離れた山中にある。
「はぁ……早く、つかないかな?」
バスで行けるとこまでは行けたものの、やはりここから先は徒歩である。その徒歩がどうしても長すぎる。
――こんなことなら、一夏みたいにバイクで来りゃあよかった……
俺も一様、一夏のようにバイク乗りである。こんなことになら、愛用のオフロードバイクで山道をスラスラとツーリング感覚で向かえばよかった。
しかし、いまから神聖な場所へ向かうんだし、失礼があっては何だと思えば逆に徒歩で向かった方がいいのかもしれない。
「今から、弥生の家へ行くのか……」
今まで、俺は知り合いの家に遊びに行っても女の子の家に入ったことは一度もない! ましてや、女友達すら一人もいないから無理はない。
そう、年端の離れていない女の子の家って、いったいどんなところだろうか? 想像するたびに緊張して胸が苦しくなる。
ま、まぁ……これまで弥生とは一緒の部屋で寝てたり臨海学校のときもハードルの高いことをしてきたんだ。今更、夏休みの期間、彼女の家でお世話になる……なんて、今までよりハイレベルじゃん!?
考えてみると、いつでも彼女に付きっ切り、その上二人っきりっぽいし……あ、でも寝る時はたぶん別の部屋を貸してくれそうだからそれはそれでいいが……
しかし、そんな所へこんな俺が果たして耐えきれるであろうか?
「……」
自信のない顔をして、俺は歩いて数十分後、ようやく大きな鳥居と天まで届くかのように高く長い石段が姿を見せた。
「おお……これは立派なもんだぜ?」
石段を見上げながら、俺はえっちらと汗をポタポタ落としながら石段を登っていった。周囲からの深緑の木々からミンミンゼミの鳴き声が甲高く鳴き乱れる。うるさいというよりも、幻想的で嫌いではなかった。
――弥生って、巫女だから境内で掃き掃除とかしてんのかな……?
弥生の巫女といえば……例の和風レオタードの装束しか印象がない。もしや……神社で奉仕をしている時でも、あのきわどい格好で……?
「や、やばっ……!?」
突然、タラリと鼻血が流れ落ちる。慌てて鼻元をつまんでどうにか凌いだ。
「やれやれ……この年になると異常なまでの性欲が湧き出てしまうんだから、正直辛いよ?」
そう、思春期の時はそんな感情を毛嫌いしていたのだが、高校を卒業して徐々に社会人になっていくたびに、次第と興味を示し始めてしまったのだ。
「さて……」
俺はようやく石段を登り切ると、目の前には広い境内と神々しい立派な本殿が出迎えてくれた。
確か、弥生の家は社務所兼自宅だったな? しばらくお世話になるんだから、授与所で店番ぐらいは手伝わないとな?
何度も深呼吸をする俺は、落ち着いて境内を見渡した。すると、境内の片隅で何やら男女の会話が聞こえてくるではないか?
男女の内、男は見知らぬが対する女は弥生の声だった……
「あの……ですから、大変申し訳ありませんが……このたびのお見合いは御断りさせていただきます……」
「どうしてです? 僕は、こんなにもあなたのことを愛しているんです。その気持ちは本物だ!」
「本当にごめんなさい。でも……」
「……また、御伺いに上がります。それまでにどうか考え直しておいてください!」
男は不機嫌になって、彼女に背を向けるとそのまま境内から立ち去っていく。
「……?」
男が、俺の方へ歩いてくる。真正面から見ていただけでわかりずらかったものの、その素顔はかなりの美青年であった。背も俺よりスラッと長く、スーツ姿がとても似合う男である。
しかし、男は俺と目があった途端にさらに機嫌の悪い態度をとりだした。
「何だね……? 何を見ている!?」
「あ、いや……」
突然絡んでくるから俺は言葉に詰まった。
「フンッ……下衆が!」
と、男は俺をにらみつけた後、また歩きだして鳥居をくぐって石段を降りていった……
「な、何だよ? アイツ……!」
八つ当たりされたかのようで、実に気に食わない奴だ……
「……あ、狼君!」
と、俺に気付いて弥生が元気よくこちらへ元気に駆け出してきた。巫女装束は一般的な緋袴をはいた普通の装束だったので、やや残念だ……
「弥生?」
「いらっしゃい! 暑かったでしょ?」
「あ、ああ……」
急に親しくする彼女に、俺は少し驚いた。いつもはこんなにはしゃぐような娘じゃない。
まるで、嫌なことから解放されてはしゃぐ子供のようだった。
「早く上がって? お茶出すから……」
俺は、社務所にある来客用の和室へ案内され、菓子と冷たいジュースを頂いた。氷が入ったジュースは、俺の乾いた喉を潤してくれる。
「この八月中、お世話になるよ? いろいろと迷惑かけちゃうと思うけど……」
汗まみれの髪をボリボリかきながら、それを挨拶にして彼女に言う。
「ううん? お姉ちゃんが蒼真さんのところへしばらく行くから、私も寂しかったところなの。狼君が居てくれると、心細くないからよかった!」
「……」
――やはり、あの男と何か関係があるのか?
先ほど境内で酷く当たってきた男を思いだした。俺はつい気になってしまい、おもわずそのことを彼女に尋ねてしまう。
「弥生……あの、先ほどの人は?」
「え……?」
「さっき、神社で変な奴とすれ違ったけど……?」
「……もしかして、工藤さん?」
表情を曇らせて、弥生は恐る恐る尋ねた。聞いてはいけないことを聞いてしまったのだろうか? 俺は、そんな彼女を見て慌てて詫びた。
「すまん! 嫌なこと聞いたか?」
「……いいよ? 最近よく私の元へ来る人だから」
――もしかして、アイツが弥生の婚約者?
俺は、目を丸くした。そして、再び口を滑らせてそのことを言う。
「まさか……婚約者?」
「どうして、それを?」
「ごめん……蒼真さんから聞いたんだ?」
「……」
弥生は黙った。しかし、俺はどうしても知りたかった。あの臨海での以降、俺と彼女の距離は次第に親密になり、今回もそれがあってこの8月いっぱいを彼女の実家で過ごすということにもなったのだ。
「……隠していたわけじゃないの。ただ、狼君と会う前からあの人に誘いを受け続けられていたの。きっぱりお断りしても、諦めずに何度も……」
「どうして、そんな奴と婚約者に?」
「狼君と出会う二カ月前、その頃の私とお姉ちゃんは神社の経営に苦しんでいたの。そこへ、偶然参拝客として来た工藤さんに突然告白されて……結婚してくれるなら資金を援助するっていうから、私達は迷ったけど、例の臨海学校の件以来、お姉ちゃんが工藤さんに御断りの返事を言ったの。私も、突然あったばかりの人と結婚なんてしたくはないし、それにお姉ちゃんと離れ離れになってお嫁に行くのは嫌だから、私自身も彼にお断りを言っておいたのですが……」
「……それ以来、執念深く通いだしてきたと?」
俺の問に弥生は静かに頷いた。
「もしかして……ストーカーか?」
俺はボソッと呟いた。
「今のところ、気味の悪い事はされていませんが……よく短気な方ですから、怒ると怖いんです」
「まぁ……確かに、ああいう奴は怒ると面倒な奴っぽいな?」
「どうしようもない相手なら、警察に頼んでストーカー被害だって訴えればいいんじゃないか?」
この女尊男卑の御時世、男が少しでも女性にしつこい行為を働けば、それを痴漢や酷いときは暴行の罪で逮捕させることができるのだ。
「でも……そんな事をして逆恨みが酷くなると怖いです。何せ、工藤さんは大手企業の御曹司ですから」
「ああ……そうきたか?」
確かにそれも怖い一例だ。何せ、相手は大富豪の坊ちゃまだ。どうせ、務所へ放り込まれてもソイツの両親が大金の賄賂を警察へ渡せば取引としてソイツの罪は抹消されるのだ。
こう言う裏社会の現状は世界各国では当たり前のように流行っている。その中でも日本の場合はもっとも可愛い方だ。
中には警察が「人身売買」に携わっていたという国もある。どれもこれも、ISの到来によって引き起こされた原因の一つでもあるのだ。
まぁ……早い話、犯人が大富豪の御曹司なら警察に相談しても無駄だということだ。
「……」
俺は腕を組みながら唸り続けた。何か、良い方法はないだろうか? 今、俺が感が得られる方法としては、蒼真さんか魁人さんに頼んで「裏社会」の力でどうにかするしかない。しかし、そんなことをすれば逆にリスクも発生してしまいかねない。
俺も、出来るだけ裏社会の連中とは関わりたくない。しかし、今弥生の身が危うい時に自分のことなど考えている暇はない。
「やっぱ、ここは魁人さんに……」
「あ、あの……!」
と、弥生は俺にこういう。
「え……?」
そんな彼女に俺も少しびっくりした。
「もし……狼君がよかったなら。工藤さんが諦めてくれるよう私の……こ、恋人ってことにしてくださいませんか?」
「え?」
俺は少し驚いたが、しかし彼女からはすでに臨海学校で告白されているため、今さら恋人を装う必要などない。
「えっと……それって、臨海学校のときに」
「あっ! そ、そうでしたよね……? じゃあ、え、えっと……」
しばらく体をモジモジさせながら、弥生は良き案を考える。すると……
「ろ、狼君!!」
「は、はい!」
突然立ち上がって弥生は顔を真っ赤にしながらもこう案を出した。
「私と、狼君が……『夫婦 』になっているって、設定はどうでしょうか?」
「へっ?」
めおと? なにそれ?
「めおとって……?」
「ふ……ふ……」
何やら言い出せにくいことなのか? 弥生はいまだにモジモジしながらその言葉にためらう。
「ふ……夫婦の意味です!」
「え?」
しばらく俺は茫然とした表情を取り、そして後から目を丸くさせた。
「いぃ……!?」
弥生は、俺に対してまさかの発言をした。俺も最初は驚いたが、しかし徐々にそれの発言に義務感を感じざるを得なくなる。
「だめ……ですか?」
泣きそうな声で悲しむ弥生だが、そんな彼女に俺は慌てて答える。
「そ、そんなことないよ!? そもそも、俺だって夏休みの間をここで満喫させてもらうために来たんだし、居候させたもらうんだから喜んで協力するよ? そ、それと……」
「……?」
「……大切な人が、目の前で困ってんなら放っておけないじゃないか?」
俺は照れながらそう言いぬいた。
「……」
しかし、あまりにもこっぱずかしいこと言ったことで俺たちはお互い顔を赤くしてソッポを向いてしまった。
その後、俺は弥生に案内されて部屋へ案内された。与えられた部屋は綺麗に掃除されていて、畳の香りが漂う風流な和室であった。
「ここが、狼君のお部屋になる場所です」
「いいの? こんな立派な和室を一人で使っちゃって?」
「いいんですよ? ウチには部屋が結構余っていますから」
「じゃあ……しばらく、お世話になります」
俺は、少し恥ずかしがりながらも弥生へぺこりとお辞儀をする。
「はいっ♪」
「ところで……俺は、これからどうすんだ? やることがあるなら、手伝わせてくれよ?」
荷物を下ろし終えたところで、俺は彼女へ振り返った。
「え? でも……狼君は大事なお客様ですし」
「かといって、このまま居候の身でいるのはどうもな?」
「じゃあ……軽い雑用でもお願いしようかしら?」
「ああ、いいよ? 男手が足りないなら喜んで」
「でも、無理はしなくていいですからね?」
弥生は、俺を連れて境内にでるとすぐそばにある授与所へと案内した。
「授与所では、主に御守りや御札などの整理と参拝客への授与などを主に行っておりまして、もし時々で構いませんので、もし御暇がございましたら手伝って頂けたら嬉しいです」
「わかったよ? ああ、力仕事でもいいからさ」
「せんぱーい!!」
すると、赤い第二鳥居の方から元気の良い声を上げて駆け出してくる一人の少女が見えた。
「弥生先輩!」
やや、活発な風格を思わせる弥生と同い年ほどの女子高生が、息を切らして俺たちの元へ駆け寄ってきた。
「あ、櫻ちゃん?」
弥生はその少女の名を言うと、櫻と言うその少女は息を荒げて駆けつけると、驚いた口調でこういう。
「例の工藤って言う人が弥生ちゃんのところへ来たって言うから急いできたの?」
「大丈夫、もう行ったよ?」
「んもう! あのストーカー……油断も隙もありゃしないったら」
と、そんな彼女は次に弥生の隣にいる俺に気付いた。
「……で? そっちの人は誰ですか?」
やや、警戒気味な顔をして俺を睨むように見える彼女に、俺はムッとした。
「弥生、誰だこの娘?」
俺も彼女に問う。
「狼君、この娘は私の後輩の朋絵櫻ちゃんっていうの。夏休みになると手伝いに来てくれるの。櫻ちゃん、この人は鎖火狼君っていうの。とっても良い人だから仲良くしてね?」
並行して紹介する弥生だが、そんな彼女に櫻はやや不機嫌な態度を取る。
「ふぅん……? 先輩、もしかして彼氏ですか? この人……」
「え!?」
図星をつかれたことに弥生はとっさに赤くなった。
「やっぱり! 工藤って金持ち野郎がつけまとってくる最中に別の彼氏をつくったんですか!? 信用できます? この人……」
「大丈夫、狼君はとっても良い人だから……」
「そんなんじゃだめです! 先輩は優しすぎるんです!!」
と、櫻は一方的に認めない体制を構え続けた挙句、俺へ振り向くとその細い指をビシッと向けだした。
「先輩の彼氏って名乗るなら? それに相応しい器を持っているかどうかを私が見極めさせて頂きます!!」
そう櫻は俺に挑みこんできた。やれやれ、面倒な相手と目を付けられてしまったものだ……
「……ごめんなさいね? 狼君」
授与所の中で、隣で正座している弥生は申し訳なさそうに詫びた。
「あ、いや……別に気にしてないよ?」
「櫻ちゃんは、ああ見えてとても良い娘ですから、そんなに嫌わないで上げて?」
「うん……」
と、いっても無理な相談だ。彼女が俺を敵視しているのなら……
その後も、櫻は俺の背後から監視するかのように奉仕を続けている。昼食の時間だって……
「狼君、こっちに気てご飯食べよ?」
弥生が隣に座るよう指定してくれたのに、そこへ櫻のやつが割り込んできやがった。
「先輩! ドーナッツ焼いてきたから一緒にたべましょ!」
と、こんな具合に俺と弥生の間を邪魔するイレギュラーとなってしまう。
「あ、ちょっと……!」
級に割りこんできた彼女に、俺はイラつく。
「ふふん……先輩にいやらしい事なんてさせやしないんだからね?」
と、勝ち誇ったように彼女は言い捨てる。こいつは、凰よりも厄介な娘のようだ……
*
こうした、彼女の妨害行為が一週間も続いた。
そんな中、流石にまずいと危機感を感じたのは弥生の方である。彼女は、彼女なりのやり方で櫻を授与所へと呼び出し、奉仕がてらにこう会話をした。
「櫻ちゃんは……狼君の事が、嫌いかな?」
「え?」
ニッコリと笑みを浮かべて問う弥生に櫻は正直に答えた。
「だって……あの人、何考えているのかわからないんです。だって、先輩は優しすぎる性格だから、どっかの男に騙されないかって……」
櫻と弥生は、かれこれ小学生からの古い付き合いである。ざっくばらんな櫻とは正反対の弥生であったが、それでも二人はとても仲が良く、櫻は弥生を姉のように慕い、弥生も彼女を妹のように可愛がっている。
しかし、言いたいことを言えないのが欠点の弥生は、いつも周囲に流されながら生きているので、それに櫻はかなり不安を抱いた。大好きな姉貴分の弥生の元へ変な男が近寄ってきたら……
「狼君は、とっても優しい人だよ? 何度も私を助けてくれたし、それにとってもカッコいいし。それに彼とも長い付き合いだからね?」
「……」
しかし、櫻としてはどうも疑わしかった。彼女からして弥生は騙されているのではないかと思い込んでいる。
「じゃあ……今から、狼君と一緒にお買い物へ行ってきてくれないかな?」
「えぇ!?」
「私なら大丈夫、この境内の一帯に結界を張っておいたから、工藤さんが来ても大丈夫だよ?」
「うぅ……」
ほかならぬ弥生の頼みならしかたがないと、彼女はしぶしぶ巫女装束から私服に着替えると、境内で掃除をしている狼を呼び出して共に行くことになった。
「じゃ、じゃあ……よろしくね? 朋絵ちゃん」
「きやすく、呼ばないでよ! 私は、まだ鎖火さんを信用したわけじゃないんだからね!?」
と、やはり俺の前ではピリピリしているようだ。やれやれ、先が思いやられるな?
俺と櫻は、バスに乗ってここから少し離れた隣の小さな町へと出向いた。とはいえ、玄那神社から片道一時間もある場所だ。
町へ着いた途端に櫻は俺にメモ用紙を私て指示を出した。
「鎖火さんは、日用品を買ってきてくれない? 私は食品を買いにスーパーへ行って来るから」
二手に分かれた方が早く済むということか、それなら同感だ。
「わかったよ? じゃあ、行くから……」
「道草とか食わないで下さいよ?」
「わ、わかってるよ……?」
えらく、信用がないようだ。
俺は、しぶしぶと日用雑貨を買いに薬局へ向かった。
*
一方の櫻はというと、食品売り場で頼まれた物を買い終えた後に狼と合流するバス停へと向かって歩き出していた。
「ああ……早く帰って弥生先輩とアイス食べよ?」
炎天下にさらされて額が汗で浮かび上がる。バテそうな体を必死で支えながら彼は徐々にバス停へと近づいていく。
……が。
――……?
花屋の前に白いスポーツカーが泊まってあった。見る限り高級感を漂わせるフォルムと艶のある美しいボディーだ。
「凄い……こんな田舎町にもこんなすごい車が来るんだ?」
しかし、しばらくして店内から怒号が聞こえた。
「赤薔薇が売っていないだと!? ふざけるな!!」
「す、すみません……」
スーツ姿の男が若い店員へ大声で怒鳴っている光景が嫌でも目に入った。スラッした長身にとびっきりのイケメン。そんな人目で女性を魅了させるような美青年がどうして花屋で怒りをあらわにしているのか?
「もうしわけございません。赤い薔薇は品切れでして……」
「品切れだと!? 貴様……客である私の要望に応えられないというのか!?」
と、さらに怒鳴り散らす青年に、店員はペコペコと頭を下げるばかりだ。
――何よ、アイツ……!
それを近くで見ている櫻はたまったものじゃない。あまりにも店員が可哀相でならず、彼女は後ろから青年に呼びかけた。
「ちょっと! ないモンはないんだし仕方ないじゃない? 別のお花を買えばいいでしょ?」
「何だ? キサマ! この私が誰だか知らんようだな?」
すると、青年は櫻を睨みながら歩み寄ると、彼女に名刺をぶっきら棒に渡した。
「……?」
受け取った名刺を見て、櫻は目を丸くした。『工藤テクノロジー』と書かれた名刺。それは、日本有数のIS企業だからだ。さらに、その名前を見て櫻は彼に指をさした。
「ああ! 工藤って……アンタが、弥生先輩をつけ狙うストーカーね!?」
「なっ!? ストーカーだと!? キサマ……この私をそこまで愚弄するか!?」
「どうでもいいわよ? それよりも、弥生先輩は迷惑しているの! 早いとこ諦めてもらえるかしら!?」
「な、なにを……薄汚い下流家庭のゴミが!」
と、怒りに我を忘れた工藤は片手が伸びて櫻の髪をガシッとつかみ上げた。
「ちょ、ちょっ女の子になにすんのよ!?」
「ふん! 俺はIS企業の人間だ。IS委員会も馬鹿じゃない。女だからって調子乗るな!」
そういうと、工藤は櫻に乱暴を始めた。彼女の髪をつかんだまま地面へ倒した。
「や、やめて……!」
胸倉をつかまれた櫻は、これ以上強がることはできず、いまからひどい目にあわされるんだと涙ぐんでいた。
「愚民がぁ!」
と、工藤は今にも泣きそうな櫻へ拳を振り下ろした……が。
「やめろって!?」
しかし、そんな暴行をふるおうとしていた工藤の片腕を、何者かがガシッと掴んだ。
「なんだ! 貴様は!?」
「く、鎖火……さん?」
そこには、先ほどまで軽蔑していたあの青年が、窮地に現れてくれたのだった。
「なにムキになってんだよ? 相手は学生の娘じゃないか?」
「むぅ? 貴様……境内の時にあったあの男か?」
「だからなんだよ?」
「フン! このガキといい、貴様といい、どれもこれも私の視界を腐らせるゴミめ!」
「なんとでも言え? だがな、暴力だけはやめろ! そんなことでもしたら、一流企業の名が泣くぜ?」
「……!!」
しばし、工藤はこれでもかというほどの怖い目つきで俺を見た。俺も少しビクッとしたが、それでも時期になれる。所詮、自分の思い通りにならないと気が済まないようなガキだ。
いるんだよな? こういう、中身だけガキになった大人ってのがさ……
「チッ……!」
工藤は、舌打ちと放つと行ってしまった。
「大丈夫か?」
俺は振り返って、尻餅をつく櫻へ手を伸ばした。
「あ、ありがとう……」
きょとんとしながら、彼女は俺の手を取って立ち上がった。
「ケガはない?」
「う、うん……」
「じゃあ帰ろう? 弥生も心配してんだしさ?」
「……」
櫻は、コクリとうなずくとそのまま俺の後に続いて待ち合わせのバス停へと歩いた。
「……ねぇ?」
「ああ?」
バスの中で、揺れながら櫻は隣に座る俺にこう問いかける。
「……どうして、あの時助けたのよ?」
「は?」
「だって、相手はIS企業の御曹司だし、権力使ってきたら……」
「ああ、構やしねぇよ……?」
だが、一般の人間なら堂々とたてつこうとはしない。今や、IS企業は政治家と同様の立場に当たり、自由に国家権力を横暴することができるのだ。だから、早い話RSを所持し、なおかつ裏政府ともつながりがある俺だからできたことだ。
おそらく、工藤の奴はこのあとすぐに国家権力を駆使して俺に襲い掛かるだろうが、その行為は反撃寸前でストップがかけられるだろう。
「単なる威嚇だろ? ああいう怒鳴りながら威張るやつなんて気の小さい奴さ」
「ふぅん……」
「そんな奴に……弥生を渡されてたまるかってんだ」
そう俺は、静かに怒った。
「……」
そんな俺の光景を、ただジッと彼女だけは……櫻だけは見続けていた。
それからというもの、なぜか櫻は俺に対して弥生に関するフィルターをかけることが極力少なくなった。
俺が、弥生の隣で飯を食っていても黙って見届けているし、弥生と一緒に授与所で奉仕を続けていてもこちらに背を向けて境内を掃き掃除している。
いつもなら、弥生と仲良くしているところで強制的に割り込んでくるっていうのに、どうしちまったんだ?
まぁ、何はともあれこれでようやく弥生と親密になれることができた。
それからしばらくして……俺が初めて大人に近づいたのが、ある休みの日だった。
*
休みの日とはいえ、神様の御奉仕は忘れずに弥生は健気に巫女として神職を果たしていた。
そんな彼女の姿をみつつ、俺も共に奉仕を行い手伝っていた。
「弥生、授与所のお守り整理は終わったぞ?」
「あ、じゃあ先に上がってください。私も、境内の掃き掃除が終わったらすぐに行きますから」
「そう? 手伝おうか?」
「いいえ? もうじき終わりますから」
「じゃあ……先に行っているね?」
俺は、とりあえず先に家へ戻った。戻ったら戻ったで、簡単な家事はやっておいて後は彼女らを待つばかりだ……
しかし。
「……?」
かれこれ二時間は経った。しかし、弥生は一向に帰ってこない。
――まさか……!
まさか、また工藤の奴に絡まれてんじゃ……!?
そう思ったら、居ても経ってもいられなくなり、気が付いた時には境内を飛び出して石垣を駆け下りていた。
「鎖火さん?」
そのとき、俺の背後から私服に着替えて帰ろうとする櫻がいた。
「どうしたんですか?」
やけに騒がしいと、よからぬ顔をして俺に問う。
「弥生を見なかったか?」
「先輩なら、裏の森へ行っていますけど?」
「裏の森?」
「何かあったんですか?」
「いや……弥生がちっとも帰ってこないから」
「ああ、それなら心配はいりません。先輩はあそこでずっとご奉仕を続けています。しかし、鎖火さんが来ない限り、あの人のご奉仕は終わらないんです」
「どういうことだ?」
俺を首を傾げた。すると、櫻はさらに意味深なことを言う。
「先輩は恥じらうかもしれませんが、それでも……本心では求めているものがあるんです」
「え? それって……」
「先輩が……鎖火さんを……に、してたなんて……」
そして、最後はそう呟いて彼女は帰って行った。
――何だったんだ?
俺はそう思いつつも、弥生を心配して裏側の森へと向かった。
だが、先ほどからどうも櫻が言い残した言葉が頭から離れられないでいる。まさか、まだ俺に隠している霊能力者としての秘密があるのでは?
そう思えば思うほど、俺は彼女を探す足を速めた。
「弥生! どこにいるんだ?」
裏側の森に入って、俺はあたりを探し回った。すると、そんな俺の耳元へ徐々に彼女らしきうめき声が聞こえる。
「弥生……?」
足を進めるたびに、その声は徐々に大きくなる。そのまま俺は急いで森の中を走り回った。
そして、ある光景を目にピタリと足がとまると、そこに飛び込んできた光景に俺は茫然となだめていたのだった……
「浪君っ……あうっ! うぅ……」
彼女の中指が、水音を立てながら己の膣を優しく撫でまわすかのように突き回している。
太ももが、内に引き締まるも膣をいじる指は止まらない。
自慰だ……
――う、うそだろ!?
あの大和撫子の彼女が、こんなエッチな行為をするなんてさすがの俺でも想像できなかったのだ。
しかし、そのいやらし気な声に誘われて俺は自然と足が前へ動き出していった。そして、俺は彼女の目の前へと姿を現したのだ。
「だ、誰っ……?」
何者かの陰に気づいて、弥生は目の前を見上げた。そして、その陰の主を目に弥生はとっさに顔を真っ赤にして、泣きそうになる。
「ろ、狼君……!?」
「弥生……」
「う、うぅ……」
とっさに、弥生は火が付いたかのように泣き出してしまった。
「見ないで……見ないで! こんな恥ずかしい姿、見ないでください……」
そんな、頬を赤く染めて泣きじゃくる恥じらいの顔を目に俺は胸が苦しくなり、気がついた時には彼女を思い切り胸に抱きしめていた。
「弥生……弥生!」
「狼君……」
「俺が、こんなことで弥生を嫌いになるわけないじゃないか! それに、あのとき……俺の名前を言いながらしていたじゃないか?」
「そ、それは……だってぇ……」
また、泣き出しそうになる顔だが、それでも俺は嬉しかった。どんな形であれ、俺のことを思ってくれているんだと……
「狼君のことが……好き、なんだもん……狼君のことを思うと、胸が苦しくなって……」
「そこまで、俺のことを思ってくれてたのか?」
「ごめんね? こんないやらしいことに狼君の名前を使っちゃって……」
「いいよ。むしろうれしいさ! 俺も、弥生のことが……」
そして、俺は彼女の唇へ、自分の唇を重ねていた。互いの口を求めるように双方の舌が絡み合い、口元から大量の唾液が伝ってたれ落ちる。
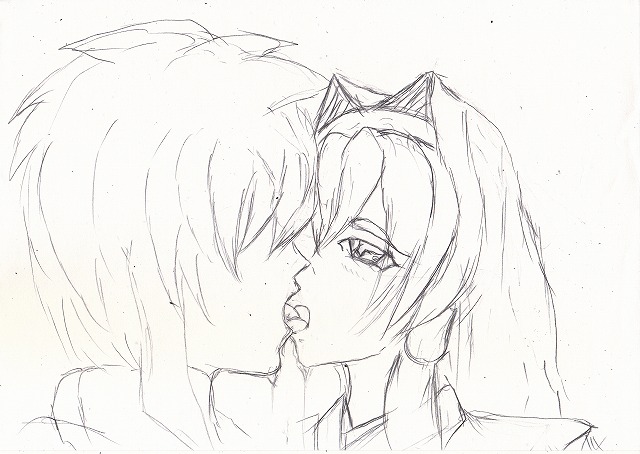
「私の初めて……狼君とやってるなんて、夢じゃないよね?」
「ああ、夢じゃないよ?」
そして、さらに俺たちは激しく口をかわし続けた。
「狼君……その、大変恥ずかしいお願いなんですけど、ズボンを……おろしてくださいませんか」
「いいのか? ここは、神社の近くだし?」
「構いません。境内の外なら……私、もう我慢できないんです!」
うずうずと恥ずかし気におねだりする彼女に、俺の性欲も限界に達した。
「じゃ、じゃあ……」
俺は、ズボンを下した。弥生と、彼女のキスで勃起したペニスがとびかかるように弥生の目先に飛び出した。
「す、すごい……! これが殿方の、狼君のオチンチン……」
やや赤黒い亀頭から発する臭いに、弥生の感覚は鈍りだしていく。
「あ、うぅ……すごい、狼君のオチンチン……」
すると、弥生の滑らかな白い手が俺のペニスの根元を擽るように摩りだした。
「うぅ……や、弥生!?」
これって……噂に聞いた「手コキ」、だよな?
「あ、あつい……狼君の、熱いですぅ」
「うぅ……ヤバッ!」
想像以上の刺激が伝わってくる。いや、興奮といったほうがいい。彼女のきれいなスベスベの白い手が俺の根元を……
――手コキって、今まで興味なかったけど……マジでヤバい!
たかが手なんかで……と、思っていたが実際は想像以上だった。
だんだんと、亀頭から我慢汁であふれ出てくる。すると、弥生はあと少しというところで手コキをやめてしまった。
「まだ……出しちゃダメですからね?」
弥生は、俺の亀頭へ口元を近づけさせる。
「弥生……なにを?」
「あむっ……」
弥生の口内が俺の亀頭をやんわりと包み込んだ。その一瞬、彼女の舌が裏筋に触れると雷に打たれたかのような衝撃がペニスから伝わってくるではないか。
――蒼真さんのお部屋で見つけたエッチな本の通りにやってるけど、狼君は気持ちよくなってくれているよね……?

前に、蒼真の散らかった部屋を掃除していたとき、偶然ベッドの裏側から幾冊ものエロ本を発掘した。
「あ、うぅ……!」
その何とも言えない快楽に俺は耐えしのごうとするが、どうあがいてもこれは我慢できない。
「ろ、ろうふん……ふるひくないれふか?」
咥えたまた喋られると、余計に気持ちよさが増してくる。舌が動かすからそれがベロベロと裏筋に当たるように舐められてそれどころじゃない!
「や、弥生……もう、ヤバすぎる!」
――えっと……狼君のオチンチンから精液を絞ればいいんだよね?
すると、弥生は吸引力を上げて俺のペニスを締め付けた。
「うぅ……! や、弥生の口に締め付けられて……」
そして、俺の我慢はとうとう限界に達した……
「ッ!?」
弥生の口内にドピュッと白い濃厚な液が溢れ出した。
――狼君の、精液……
不思議な味がして、やや苦みのあるもののそれを蒼真のエロ本通りにやってのける。
「んぐっ……!」
喉を鳴らして、口に広がる精液を一口で飲み干した。
「……狼君の、飲んじゃった♪」
やや、達成感が感じられて機嫌のいい口調で弥生は言った。
「ハァッ……ハアァー……」
呼吸を整え、俺は性欲が満たされたことを感じた。
翌日
昨日の出来事が信じられないくらいだ。まさか、御奉仕は御奉仕でも、弥生が俺に御奉仕するなんて……
そして、起きたついでにズボンとトランクスをめくって中身を見ると……
――夢だけど、夢じゃなかった!
……俺は、童貞を捨て去っていたのだった。
そんな俺は、朝から機嫌よく寝間着から私服へ着替えると、一目散に弥生が立つ台所へ向かった。
「弥生!」
「ろ、狼君!?」
巫女装束の上にエプロンを付けた彼女は、みそ汁を作っている最中だった。そして、俺を見てとっさに顔を赤くして照れてしまう。
「……今日も御奉仕、頑張ろうな?」
「は、はい!」
頬を赤くしながらも、弥生は万弁の笑顔で返した。
そのあと、八時丁度に櫻や臨時で雇われた学生を連れてやってきた。近づきつつある夏祭りに向けて、いろいろと準備が必要なのである。しかし、今回は男手となる俺も加わることで多少は苦労しないと弥生は話していた。
今日は、祭りの準備もかねてご奉仕をしなくてはならないから準備は村人の人たちも手伝ってくれるらしい。
そんな中、俺は境内の片隅にある物置小屋の整理を行った。埃だらけの中を雑巾で拭いたりしてせっせと掃除を続ける。
「はぁ……」
そんな一方で境内を掃き掃除している弥生は昨日のことが忘れられず集中しようにもできずに困っていた。
「どうしたんですか? 先輩」
と、そこへいつもと違う雰囲気を悟って櫻が歩み寄ってきた。
「櫻ちゃん? ちょっと、ね……」
「さっきから、鎖火さんのことをジッと見ていますけど~?」
と、ニヤニヤして彼女は弥生に問うと、弥生は慌てて否定しだした。
「ち、ちがうよ~!」
「鎖火さんのことが、好きなんですね?」
「べ、別に……そうというかなんというか……」
――図星か……
櫻は、弥生が狼のことが好きなんだということはあらかじめ知ってはいる。彼女も、最初は狼を毛嫌いしていたが、工藤から自分を救ってくれたことに、まんざら捨てたものじゃないと感心し、今では狼と弥生を応援する立場に変わっていた。昨日の出来事などが特にそうであった。
「あの、すみません?」
背後から聞こえた声に二人が振り返ると、そこには若い夫婦の参拝客が歩み寄ってきて訪ねてきた。若夫婦の内、妻のほうは可愛い赤ん坊を両手で大事そうに抱きかかえていた。
「うわぁ~ 可愛い赤ちゃんですね?」
櫻は無邪気な顔でこちらを見つめる赤ん坊に頬を緩ませた。
「ええ、半年前に生まれたんです」
「男の子……ですか?」
「ええ! 雄介っていいます」
笑みをこぼして我が子を紹介する若夫婦を見て、櫻と弥生も笑顔になりながらこの若夫婦に案内をした。
この玄那神社には、子宝の神様が祭ってあるのでよく新婚の夫婦がこの神社を訪れることが多い。そして、今回の若夫婦もそんなに珍しいものではなかった。
そして、夫婦を見送る中、弥生はその若夫婦の後姿を自分と、狼の姿と重ね合わせた。
「……」
境内で我が子を抱きながら狼と共に子をあやす。そんな妄想が絶え間なく続いて離れない。
――いいなぁ、赤ちゃんか……
「先輩……」
そんな寂し気な弥生の後姿を見て、櫻はふと決意してように弥生の手を引っ張った。
「先輩!」
「え、どうしたの?」
境内ではなんですから、とりあえず外でお話ししたいんです!」
「え、なにかな……?」
やや、驚くも弥生は櫻と共に境内を出て昨日の森の中へと連れてこられた。
「どうしたの? 櫻ちゃん」
「先輩……鎖火さんのことが好きなんですよね?」
「ど、どうしたの? 急に……」
「単刀直入に言います! 先輩……赤ちゃんが欲しいでしょ?」
「え!?」
弥生はまるで心を見透かされているかのように驚いた。
「否定はしません。けど……もし、弥生先輩は本当に鎖火さんの赤ちゃんがどうしても欲しいんだったら、私は敬愛なる先輩のために一肌脱ごうと思います!」
と、熱意あふれる目をして櫻は弥生の前絵に迫った。弥生も、これ以上ごまかすことはできないことを知って、静かに顔を赤くしてうなずいた。
「うん……本当は、私も狼君の赤ちゃんが欲しいの」
「でも、もし鎖火さんが嫌って言ったら?」
「それなら、諦めるしかないけど……でもぉ」
「それでも欲しいんですよね? 赤ちゃん」
「うん……」
「それなら! この私にとっておきの案があります!!」
「え?」
*
夏祭り当日、俺は祭りの準備を村人たちと共に手伝っていた。大小さまざまな出し物や屋台のテントを組み立てたりと、引っ張りだこだった。
何せ、俺意外に若い奴は五本の指で数えるぐらいであり、俺はその中の貴重な戦力としていろいろと扱き使われている。
「ふぅ……やっと終わったか?」
汗だくになって、近くの水舎の水を両手ですくって顔を洗った。冷たい井戸水は日焼けした俺の皮膚を気持ちよく冷やしてくれる。
「さて、もうひと頑張りといくか?」
「あ、あの……狼君?」
「弥生?」
すると、背後から歩み寄る弥生に俺は振り向いた。今でも、彼女は俺を見るたびに顔を赤くしながらモジモジし続けている。
「弥生か? どうした?」
「あ、あの……えっと……その……」
「……?」
何か言いたそうな口だが、なかなか言い出せない。いつものことだから俺はそこのところはゆっくりと待ってやる。
「……今夜、狼君のお部屋へお邪魔してもいいです……か?」
「え?」
「だ、駄目でしたら……」
「いいよ?」
「え? 本当!」
「ああ、別にいいけど?」
「じゃあ、今夜の八時に狼君のお部屋へ来ますね? 寝ちゃダメですからね? 絶対ですよ?」
と、それだけ言うと、はしゃぐかのように彼女は駆けていった。いつものおしとやかな彼女とは違う一面であった。いや……弥生は、俺が彼女の家へ遊びに来てからというもの彼女の雰囲気は時折変わったりしている。
IS学園にいるときは年下の女の子なのに年上で成人の俺よりもしっかりしていて大人びた風格を持った少女だった。もちろん、文武両道で俺よりも運動神経はいい上に勉強もできる優等生だ。
俺と比べたら月と鼈だ。こんな俺をどうした彼女は好きになってくれたんだろうと、いまだに理解できないのだ。
しかし、彼女が俺を心から愛してくれるのであれば、俺もその気持ちに十分こたえるつもりだ。
俺だって、弥生に対していささか劣等感を感じるとは言えども、彼女のことが好きだからそれほど嫉妬などは感じたことはない。優しいし、いつも俺を日常的に助けてくれる。
――昨日のことといい、今夜はそれに関係したことを話しに来るのかな?
下心などは出ていなかった。そんな欲情よりも、今後の関係がどうなってしまうのかという思いのほうが強かった。
祭りの準備は夕暮れ時には大方終えて、あとは本番を待つばかりである。
「あ、鎖火さん?」
と、俺が片づけを終えて物置小屋から出てきたところを櫻が表れて、俺の前まで駆け寄ってきた。
最初は敵意むき出しの彼女だったが、今ではそれほど悪くはなく、仲のいい男友達という感覚で見てくれている。
「朋絵ちゃん?」
「さっき、弥生先輩から声をかけられたんですか?」
「え? まぁね……」
「別に、悪い話じゃないみたいですから安心してください」
「え?」
「それじゃ! 私はこれで……」
と、それだけ言い残すと櫻は先に持ち場へ戻った。
「何なんだ……?」
だが、別にせずに俺はこのまま作業を再開する。
祭りは、夕暮れどきに始まった。幾店もの屋台が境内に並び、訪れる客を招いて夢中にさせる。
俺も、ようやく手伝いから解放されてくたくたになったところを、村長の爺さんたちに誘われてやや晩酌を迫られた。
軽く御猪口の酒を啜り、隙を見ては逃げ出してきたところだ。この村の老人たちはみないい人ばかりだが、酒が口に入ると途轍もなく盛り上がるから、酔ってほんわかな感覚になるよりも逆に疲れてしまう。
だから、俺は隙を見て逃げ出してきたのだった。それに、前々から楽しみにしていた弥生の舞もこの目で見ておきたいのだ。
とりあえず、夜店を何件か回って時間をつぶして、このまま暗くなるのを待った。
あたりが夕闇に沈むころ、雅楽の音色と共に舞台から一人の巫女の弥生が立ち、華麗な舞を周囲に披露した。
――綺麗だ……
神聖な装束に身を包んだ彼女の舞は、見るものを魅了することは間違いない。その舞を見とれているうちに時間はあっという間に過ぎ去っていく。
*
「ふぅ~祭りは疲れるな?」
訪れに来る客たちならともかく、準備に徹する者にとっては重労働であった。
疲れ切った体を、湯船に沈めて入浴を済ませた後、俺は寝間着に着替えると自室へ帰った。
布団を敷いて明日に備え今日は寝ようと思ったのだが、今日の昼に弥生が言っていたことを思い出してそのまま置き続けていた。
ちょうど、八時になるところだからもうじき来るだろうか?
八時になるまで、俺は適当にゴロンと布団の上に横たわって眠くならないように気を付けながら彼女が来るのを待ち続けた。
「ろ、狼君……?」
後ろから弥生の声が聞こえた。丁度、八時ジャストだ。障子の戸を引いて弥生が入ってきて、俺も起き上がって彼女のほうへと振り向いた……が。
「や、弥生!?」
「狼君……」
そこには……あの、興奮の止まない巫女レオタードの姿でいる弥生が立っていた。

「ど、どうしたんだよ? その格好……」
「狼君……本当は、この装束が好きなんだよね?」
と、いうと彼女は俺の隣に腰を下ろしと足を崩して、寄り添ってきた。
「や、弥生……?」
「……」
しかし、弥生はただ、その姿のまま俺の隣で足を崩しているばかりで、しばしの沈黙が続くのだが、そんな気まずい静けさを打ち消したのが、彼女のある一言だった。
「あの……狼君?」
「な、なに……?」
「最初に、狼君が来たとき、『夫婦 』のふりをしてもらいたいと仰いましたよね? 私」
「そう……だったね?」
「急なことを言いますけど、狼君は……『夫婦』について真面目に考えたことはありますか?」
「えっ?」
「狼君、私は……欲しいんです」
「欲しいって?」
「狼君の……」
「俺の? 俺の、何が欲しいんだ?」
俺、弥生が気に入るような物とか持ってたかな……?
「欲しいっていうのは……『物』ではなくて、狼君の……」
「俺の?」
「狼君の……『赤ちゃん』が欲しいんです!」
「俺のあか……え!?」
俺は目を丸く見開いて突然立ち上がって俺の前で仁王立ちする彼女は、顔を赤くしながらこう叫んだ。
「私の……私の、おなかに狼君の赤ちゃんの種をください!」
弥生は、泣きそうで恥じらう顔をしながら引き締まったレオタード越しに浮かんだ、可愛いおへそのくぼみに手を添えた。
「しょ、正気か!? お前……マジで俺と?」
「本気です! 私……私……狼君の赤ちゃんがどうしても欲しいんです!」
「……」
俺は驚いて返す言葉が出なかったが、しかし時期に俺は彼女にこう返した。
「……別に、今じゃなくてもいいだろ? IS学園を卒業したらさ?」
まだ、彼女はIS学園で学生を演じなくてはならない。それまでに妊娠させてしまったら、彼女が学園にいられなくなるのは当然だ。
「でも……でも! 待てないんです。あなたのことが……好きになってしまったから」
「だからって……」
「臨海学校のとき、命に代えてまで私を助けてくれたあなたに、私はますます狼君への好意が強くなって、それ以来、狼君がいないと、生きていけないぐらいに大好きになっちゃって……私は、あなたのことが、大好きで大好きで……」
「弥生……」
そこまで、俺のことを思っていたとは思わなかった。そして今、彼女の本気を思い知らされてさすがの俺も参っている。だが、夫婦とやらになるのはもう少し待ってもらいたい。
「ごめん。もう少し待って? 別に弥生のことが嫌いってわけじゃないんだ。むしろ、俺もお前が好きなんだ。だけど……結婚とか、そういうのはもう少し待ってくれないかな? 心の準備ってやつがまだだし、それに今の俺にはちょっと自信がないんだ。弥生の夫として生きていくのが」
「そんなことありません。狼君は十分に私と一緒に暮らしていけます」
「弥生……ごめんな? もう少しの間だけ、辛抱してくれ?」
「狼……」
すると、悲しい顔をして、ついにはすすり泣きをしてしまう彼女に、俺は慌てながらもどうにかしてやることはできない。
「……わかりました。でも、せめて」
と、彼女は俺の顔へまじかに迫った。
「……今宵は、抱いてください?」
「弥生……」
俺は、自然に彼女の体に手が触れて、気づいたころには彼女を思い切り抱きしめていた。
レオタードのような装束の生地から伝わる温もりとほのかな香りが俺の心を締め付ける。
「狼君……私、キスだけじゃ満足いきません」
「ああ……俺もだ」
すると、俺は己が要望を彼女に提案した。
「その……せっかく、その格好なんだしさ? えっと、『顔面乗馬』ってやつ……して、もらいたいんだけど?」
「が、顔面……乗馬!?」
蒼真のコレクションから様々な用語を会得している彼女は、「顔面乗馬」という用語も当然知っていたが、それはとても羞恥心あふれる行為であったのだ。
「え、えっと……別に変態的な意味っていうよりも、弥生の匂いを嗅ぎたいっていうか……それも変態的な意味だよな……」
苦笑いする俺だが、そんな俺に彼女は本気になった。
「わ、わかりました! 布団の上で寝そべってください!」
「え?」
「狼君の好きなように致します。ですから……」
「……」
緊張するも、俺は布団に寝転んで、天井を見た。
「で、では……いきますね?」
すると、弥生は恥じらいながら俺の天井の視界に彼女の股が差し掛かる。
――え、エロい……
女の子の股を見て、俺は今にも勃起しそうだ……いや、もうしている。
「う、うぅ……」
ゆっくりと、俺の顔面へしゃがみ込む弥生の大股が間近に迫ってきている。そして……
「!?」
一瞬弥生のアソコに口をふさがれて息苦しさを感じたが。次第にアソコから彼女の匂いがやんわりと漂ってきた。

「はうっ……!」
口を動かせば動かすほど、弥生のアソコが刺激を受けて、こそばゆく感じているようだ。
しかし、俺はそんなことなど構うことなく、むさぼるように口を動かして食べたいかのように彼女の温もりに満ちたアソコを口元でハミハミと動かしながら揉み解していく。
「だ、だめっ……狼君。そんなに口動かしちゃヤッ……」
「おいしいよ? 弥生のアソコは、いい匂いがして温かい……」
すると、舌を付けたわけでもないのに次第と彼女のアソコから割れ目のあとが浮かび上がると、湿っぽさを感じた。
彼女は今、とても興奮しているのだ。息遣いも荒くなりだして、いやらしい声を上げて、気づいたらもっとむさぼってくれと言わんかのように俺の口へアソコをグイグイ押し込んでくるのだ。
「や、弥生……!」
やばい。こうなったら、俺も勃起したのちに射精しちまいそうだ!
「ろ、狼君の……」
弥生は、片手を後ろに回すと俺の股間からイチモツの膨らみを摩りだした。
「こんなに大きくなっちゃって……狼君のオチンチン」
「弥生……」
「ほら? そろそろ入れちゃお?」
「い、入れるって……?」
「狼君のオチンチンを、私の……お、オマンコに」
「ちょ、ちょっと待った! そんなことしたら……」
まさか、中出しするつもりじゃ……
「大丈夫です。ほら?」
弥生は、片方の裾からある一つの何かを取り出した。小さな輪の内にビニール状の柔らかな素材が貼り付けられている。
「コンドーム?」
「そう、狼君が駄目って言ったときに備えて持っていました」
「そうか。なら、安心だ……」
「じゃあ……付けてあげますね?」
と、彼女は俺のペニスの亀頭へ細く白い指で突かせながら、その感触に耐えつつもゆっくりとコンドームをはめていく。
「これでいいかな……?」
「俺もわからないけど……大丈夫だと思うよ?」
「じゃ、じゃあ……入れるね?」
俺のペニスが、彼女の膣へ挿入される。途端、俺のペニスが弥生の処女膜を食い破って一気に締め付けられる。
「痛っ……!」
弥生は、その痛さに苦しんで、俺のペニスを伝って彼女の膣から血がたれ流れた。
「だ、大丈夫か……?」
「はい……私、とても幸せです。大好きな殿方と、こうして一つに繋がっているんですから……」
「弥生……!」
俺は興奮して、彼女の膣の中へ飲み込まれたペニスを動かして暴れ回る。

「あっ……うぅ……!」
「や、弥生……!」
そして、俺のペニスはもう限界に達する。
「で、出る……出るぞ! 弥生!?」
「き、きてぇ……? 狼君!」
「うぅ……!」
そして、コンドームは俺の射精まみれになって汚れた。
「き、気持ちぃよぉ……」
快楽に満ちた笑みを浮かべる弥生は、俺のペニスから離れた。
「ご、ごめん……乱暴なことしたかな?」
「ううん? とても、気持ちよかったです……あの、狼君?」
「ん?」
「そのぉ……もう一回、したいな? って……」
彼女は満足いかないようだ。
「ああ……俺も、いいよ? もう一回だ!」
俺たちは、服を脱いで、衣類が散乱する布団の上で互いに抱き合いながら再び横たわった。
「はい、コンドームのおかわりです♪」
弥生はふたたび代わりのコンドームを取り出した。
「う、うん……」
苦笑いしながらも、俺はそれをペニスにはめて再び彼女の膣へ挿入した。

そして、俺たちは互いの名を呼びあいながらこの長い夜を過ごした……
永遠に続かなくたっていい。ただ、今この時だけが……どうか夢であってほしくないことを俺は思った。
「狼君、これからも私と一緒にいてくださいね?」
「ああ、これからもずっと一緒さ。もう、お前を手放したりはしない……」
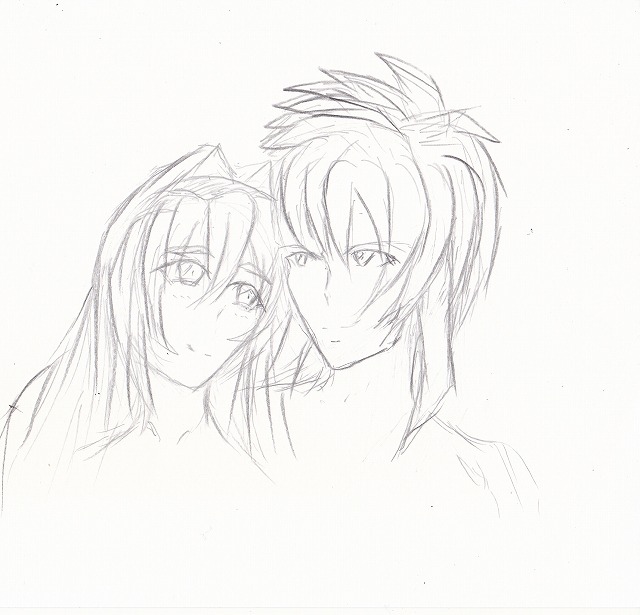
蝉の鳴き声がこだまする山道を、汗だくになりながら地図を片手に歩き続けた。
玄那神社は、この集落からやや離れた山中にある。
「はぁ……早く、つかないかな?」
バスで行けるとこまでは行けたものの、やはりここから先は徒歩である。その徒歩がどうしても長すぎる。
――こんなことなら、一夏みたいにバイクで来りゃあよかった……
俺も一様、一夏のようにバイク乗りである。こんなことになら、愛用のオフロードバイクで山道をスラスラとツーリング感覚で向かえばよかった。
しかし、いまから神聖な場所へ向かうんだし、失礼があっては何だと思えば逆に徒歩で向かった方がいいのかもしれない。
「今から、弥生の家へ行くのか……」
今まで、俺は知り合いの家に遊びに行っても女の子の家に入ったことは一度もない! ましてや、女友達すら一人もいないから無理はない。
そう、年端の離れていない女の子の家って、いったいどんなところだろうか? 想像するたびに緊張して胸が苦しくなる。
ま、まぁ……これまで弥生とは一緒の部屋で寝てたり臨海学校のときもハードルの高いことをしてきたんだ。今更、夏休みの期間、彼女の家でお世話になる……なんて、今までよりハイレベルじゃん!?
考えてみると、いつでも彼女に付きっ切り、その上二人っきりっぽいし……あ、でも寝る時はたぶん別の部屋を貸してくれそうだからそれはそれでいいが……
しかし、そんな所へこんな俺が果たして耐えきれるであろうか?
「……」
自信のない顔をして、俺は歩いて数十分後、ようやく大きな鳥居と天まで届くかのように高く長い石段が姿を見せた。
「おお……これは立派なもんだぜ?」
石段を見上げながら、俺はえっちらと汗をポタポタ落としながら石段を登っていった。周囲からの深緑の木々からミンミンゼミの鳴き声が甲高く鳴き乱れる。うるさいというよりも、幻想的で嫌いではなかった。
――弥生って、巫女だから境内で掃き掃除とかしてんのかな……?
弥生の巫女といえば……例の和風レオタードの装束しか印象がない。もしや……神社で奉仕をしている時でも、あのきわどい格好で……?
「や、やばっ……!?」
突然、タラリと鼻血が流れ落ちる。慌てて鼻元をつまんでどうにか凌いだ。
「やれやれ……この年になると異常なまでの性欲が湧き出てしまうんだから、正直辛いよ?」
そう、思春期の時はそんな感情を毛嫌いしていたのだが、高校を卒業して徐々に社会人になっていくたびに、次第と興味を示し始めてしまったのだ。
「さて……」
俺はようやく石段を登り切ると、目の前には広い境内と神々しい立派な本殿が出迎えてくれた。
確か、弥生の家は社務所兼自宅だったな? しばらくお世話になるんだから、授与所で店番ぐらいは手伝わないとな?
何度も深呼吸をする俺は、落ち着いて境内を見渡した。すると、境内の片隅で何やら男女の会話が聞こえてくるではないか?
男女の内、男は見知らぬが対する女は弥生の声だった……
「あの……ですから、大変申し訳ありませんが……このたびのお見合いは御断りさせていただきます……」
「どうしてです? 僕は、こんなにもあなたのことを愛しているんです。その気持ちは本物だ!」
「本当にごめんなさい。でも……」
「……また、御伺いに上がります。それまでにどうか考え直しておいてください!」
男は不機嫌になって、彼女に背を向けるとそのまま境内から立ち去っていく。
「……?」
男が、俺の方へ歩いてくる。真正面から見ていただけでわかりずらかったものの、その素顔はかなりの美青年であった。背も俺よりスラッと長く、スーツ姿がとても似合う男である。
しかし、男は俺と目があった途端にさらに機嫌の悪い態度をとりだした。
「何だね……? 何を見ている!?」
「あ、いや……」
突然絡んでくるから俺は言葉に詰まった。
「フンッ……下衆が!」
と、男は俺をにらみつけた後、また歩きだして鳥居をくぐって石段を降りていった……
「な、何だよ? アイツ……!」
八つ当たりされたかのようで、実に気に食わない奴だ……
「……あ、狼君!」
と、俺に気付いて弥生が元気よくこちらへ元気に駆け出してきた。巫女装束は一般的な緋袴をはいた普通の装束だったので、やや残念だ……
「弥生?」
「いらっしゃい! 暑かったでしょ?」
「あ、ああ……」
急に親しくする彼女に、俺は少し驚いた。いつもはこんなにはしゃぐような娘じゃない。
まるで、嫌なことから解放されてはしゃぐ子供のようだった。
「早く上がって? お茶出すから……」
俺は、社務所にある来客用の和室へ案内され、菓子と冷たいジュースを頂いた。氷が入ったジュースは、俺の乾いた喉を潤してくれる。
「この八月中、お世話になるよ? いろいろと迷惑かけちゃうと思うけど……」
汗まみれの髪をボリボリかきながら、それを挨拶にして彼女に言う。
「ううん? お姉ちゃんが蒼真さんのところへしばらく行くから、私も寂しかったところなの。狼君が居てくれると、心細くないからよかった!」
「……」
――やはり、あの男と何か関係があるのか?
先ほど境内で酷く当たってきた男を思いだした。俺はつい気になってしまい、おもわずそのことを彼女に尋ねてしまう。
「弥生……あの、先ほどの人は?」
「え……?」
「さっき、神社で変な奴とすれ違ったけど……?」
「……もしかして、工藤さん?」
表情を曇らせて、弥生は恐る恐る尋ねた。聞いてはいけないことを聞いてしまったのだろうか? 俺は、そんな彼女を見て慌てて詫びた。
「すまん! 嫌なこと聞いたか?」
「……いいよ? 最近よく私の元へ来る人だから」
――もしかして、アイツが弥生の婚約者?
俺は、目を丸くした。そして、再び口を滑らせてそのことを言う。
「まさか……婚約者?」
「どうして、それを?」
「ごめん……蒼真さんから聞いたんだ?」
「……」
弥生は黙った。しかし、俺はどうしても知りたかった。あの臨海での以降、俺と彼女の距離は次第に親密になり、今回もそれがあってこの8月いっぱいを彼女の実家で過ごすということにもなったのだ。
「……隠していたわけじゃないの。ただ、狼君と会う前からあの人に誘いを受け続けられていたの。きっぱりお断りしても、諦めずに何度も……」
「どうして、そんな奴と婚約者に?」
「狼君と出会う二カ月前、その頃の私とお姉ちゃんは神社の経営に苦しんでいたの。そこへ、偶然参拝客として来た工藤さんに突然告白されて……結婚してくれるなら資金を援助するっていうから、私達は迷ったけど、例の臨海学校の件以来、お姉ちゃんが工藤さんに御断りの返事を言ったの。私も、突然あったばかりの人と結婚なんてしたくはないし、それにお姉ちゃんと離れ離れになってお嫁に行くのは嫌だから、私自身も彼にお断りを言っておいたのですが……」
「……それ以来、執念深く通いだしてきたと?」
俺の問に弥生は静かに頷いた。
「もしかして……ストーカーか?」
俺はボソッと呟いた。
「今のところ、気味の悪い事はされていませんが……よく短気な方ですから、怒ると怖いんです」
「まぁ……確かに、ああいう奴は怒ると面倒な奴っぽいな?」
「どうしようもない相手なら、警察に頼んでストーカー被害だって訴えればいいんじゃないか?」
この女尊男卑の御時世、男が少しでも女性にしつこい行為を働けば、それを痴漢や酷いときは暴行の罪で逮捕させることができるのだ。
「でも……そんな事をして逆恨みが酷くなると怖いです。何せ、工藤さんは大手企業の御曹司ですから」
「ああ……そうきたか?」
確かにそれも怖い一例だ。何せ、相手は大富豪の坊ちゃまだ。どうせ、務所へ放り込まれてもソイツの両親が大金の賄賂を警察へ渡せば取引としてソイツの罪は抹消されるのだ。
こう言う裏社会の現状は世界各国では当たり前のように流行っている。その中でも日本の場合はもっとも可愛い方だ。
中には警察が「人身売買」に携わっていたという国もある。どれもこれも、ISの到来によって引き起こされた原因の一つでもあるのだ。
まぁ……早い話、犯人が大富豪の御曹司なら警察に相談しても無駄だということだ。
「……」
俺は腕を組みながら唸り続けた。何か、良い方法はないだろうか? 今、俺が感が得られる方法としては、蒼真さんか魁人さんに頼んで「裏社会」の力でどうにかするしかない。しかし、そんなことをすれば逆にリスクも発生してしまいかねない。
俺も、出来るだけ裏社会の連中とは関わりたくない。しかし、今弥生の身が危うい時に自分のことなど考えている暇はない。
「やっぱ、ここは魁人さんに……」
「あ、あの……!」
と、弥生は俺にこういう。
「え……?」
そんな彼女に俺も少しびっくりした。
「もし……狼君がよかったなら。工藤さんが諦めてくれるよう私の……こ、恋人ってことにしてくださいませんか?」
「え?」
俺は少し驚いたが、しかし彼女からはすでに臨海学校で告白されているため、今さら恋人を装う必要などない。
「えっと……それって、臨海学校のときに」
「あっ! そ、そうでしたよね……? じゃあ、え、えっと……」
しばらく体をモジモジさせながら、弥生は良き案を考える。すると……
「ろ、狼君!!」
「は、はい!」
突然立ち上がって弥生は顔を真っ赤にしながらもこう案を出した。
「私と、狼君が……『
「へっ?」
めおと? なにそれ?
「めおとって……?」
「ふ……ふ……」
何やら言い出せにくいことなのか? 弥生はいまだにモジモジしながらその言葉にためらう。
「ふ……夫婦の意味です!」
「え?」
しばらく俺は茫然とした表情を取り、そして後から目を丸くさせた。
「いぃ……!?」
弥生は、俺に対してまさかの発言をした。俺も最初は驚いたが、しかし徐々にそれの発言に義務感を感じざるを得なくなる。
「だめ……ですか?」
泣きそうな声で悲しむ弥生だが、そんな彼女に俺は慌てて答える。
「そ、そんなことないよ!? そもそも、俺だって夏休みの間をここで満喫させてもらうために来たんだし、居候させたもらうんだから喜んで協力するよ? そ、それと……」
「……?」
「……大切な人が、目の前で困ってんなら放っておけないじゃないか?」
俺は照れながらそう言いぬいた。
「……」
しかし、あまりにもこっぱずかしいこと言ったことで俺たちはお互い顔を赤くしてソッポを向いてしまった。
その後、俺は弥生に案内されて部屋へ案内された。与えられた部屋は綺麗に掃除されていて、畳の香りが漂う風流な和室であった。
「ここが、狼君のお部屋になる場所です」
「いいの? こんな立派な和室を一人で使っちゃって?」
「いいんですよ? ウチには部屋が結構余っていますから」
「じゃあ……しばらく、お世話になります」
俺は、少し恥ずかしがりながらも弥生へぺこりとお辞儀をする。
「はいっ♪」
「ところで……俺は、これからどうすんだ? やることがあるなら、手伝わせてくれよ?」
荷物を下ろし終えたところで、俺は彼女へ振り返った。
「え? でも……狼君は大事なお客様ですし」
「かといって、このまま居候の身でいるのはどうもな?」
「じゃあ……軽い雑用でもお願いしようかしら?」
「ああ、いいよ? 男手が足りないなら喜んで」
「でも、無理はしなくていいですからね?」
弥生は、俺を連れて境内にでるとすぐそばにある授与所へと案内した。
「授与所では、主に御守りや御札などの整理と参拝客への授与などを主に行っておりまして、もし時々で構いませんので、もし御暇がございましたら手伝って頂けたら嬉しいです」
「わかったよ? ああ、力仕事でもいいからさ」
「せんぱーい!!」
すると、赤い第二鳥居の方から元気の良い声を上げて駆け出してくる一人の少女が見えた。
「弥生先輩!」
やや、活発な風格を思わせる弥生と同い年ほどの女子高生が、息を切らして俺たちの元へ駆け寄ってきた。
「あ、櫻ちゃん?」
弥生はその少女の名を言うと、櫻と言うその少女は息を荒げて駆けつけると、驚いた口調でこういう。
「例の工藤って言う人が弥生ちゃんのところへ来たって言うから急いできたの?」
「大丈夫、もう行ったよ?」
「んもう! あのストーカー……油断も隙もありゃしないったら」
と、そんな彼女は次に弥生の隣にいる俺に気付いた。
「……で? そっちの人は誰ですか?」
やや、警戒気味な顔をして俺を睨むように見える彼女に、俺はムッとした。
「弥生、誰だこの娘?」
俺も彼女に問う。
「狼君、この娘は私の後輩の朋絵櫻ちゃんっていうの。夏休みになると手伝いに来てくれるの。櫻ちゃん、この人は鎖火狼君っていうの。とっても良い人だから仲良くしてね?」
並行して紹介する弥生だが、そんな彼女に櫻はやや不機嫌な態度を取る。
「ふぅん……? 先輩、もしかして彼氏ですか? この人……」
「え!?」
図星をつかれたことに弥生はとっさに赤くなった。
「やっぱり! 工藤って金持ち野郎がつけまとってくる最中に別の彼氏をつくったんですか!? 信用できます? この人……」
「大丈夫、狼君はとっても良い人だから……」
「そんなんじゃだめです! 先輩は優しすぎるんです!!」
と、櫻は一方的に認めない体制を構え続けた挙句、俺へ振り向くとその細い指をビシッと向けだした。
「先輩の彼氏って名乗るなら? それに相応しい器を持っているかどうかを私が見極めさせて頂きます!!」
そう櫻は俺に挑みこんできた。やれやれ、面倒な相手と目を付けられてしまったものだ……
「……ごめんなさいね? 狼君」
授与所の中で、隣で正座している弥生は申し訳なさそうに詫びた。
「あ、いや……別に気にしてないよ?」
「櫻ちゃんは、ああ見えてとても良い娘ですから、そんなに嫌わないで上げて?」
「うん……」
と、いっても無理な相談だ。彼女が俺を敵視しているのなら……
その後も、櫻は俺の背後から監視するかのように奉仕を続けている。昼食の時間だって……
「狼君、こっちに気てご飯食べよ?」
弥生が隣に座るよう指定してくれたのに、そこへ櫻のやつが割り込んできやがった。
「先輩! ドーナッツ焼いてきたから一緒にたべましょ!」
と、こんな具合に俺と弥生の間を邪魔するイレギュラーとなってしまう。
「あ、ちょっと……!」
級に割りこんできた彼女に、俺はイラつく。
「ふふん……先輩にいやらしい事なんてさせやしないんだからね?」
と、勝ち誇ったように彼女は言い捨てる。こいつは、凰よりも厄介な娘のようだ……
*
こうした、彼女の妨害行為が一週間も続いた。
そんな中、流石にまずいと危機感を感じたのは弥生の方である。彼女は、彼女なりのやり方で櫻を授与所へと呼び出し、奉仕がてらにこう会話をした。
「櫻ちゃんは……狼君の事が、嫌いかな?」
「え?」
ニッコリと笑みを浮かべて問う弥生に櫻は正直に答えた。
「だって……あの人、何考えているのかわからないんです。だって、先輩は優しすぎる性格だから、どっかの男に騙されないかって……」
櫻と弥生は、かれこれ小学生からの古い付き合いである。ざっくばらんな櫻とは正反対の弥生であったが、それでも二人はとても仲が良く、櫻は弥生を姉のように慕い、弥生も彼女を妹のように可愛がっている。
しかし、言いたいことを言えないのが欠点の弥生は、いつも周囲に流されながら生きているので、それに櫻はかなり不安を抱いた。大好きな姉貴分の弥生の元へ変な男が近寄ってきたら……
「狼君は、とっても優しい人だよ? 何度も私を助けてくれたし、それにとってもカッコいいし。それに彼とも長い付き合いだからね?」
「……」
しかし、櫻としてはどうも疑わしかった。彼女からして弥生は騙されているのではないかと思い込んでいる。
「じゃあ……今から、狼君と一緒にお買い物へ行ってきてくれないかな?」
「えぇ!?」
「私なら大丈夫、この境内の一帯に結界を張っておいたから、工藤さんが来ても大丈夫だよ?」
「うぅ……」
ほかならぬ弥生の頼みならしかたがないと、彼女はしぶしぶ巫女装束から私服に着替えると、境内で掃除をしている狼を呼び出して共に行くことになった。
「じゃ、じゃあ……よろしくね? 朋絵ちゃん」
「きやすく、呼ばないでよ! 私は、まだ鎖火さんを信用したわけじゃないんだからね!?」
と、やはり俺の前ではピリピリしているようだ。やれやれ、先が思いやられるな?
俺と櫻は、バスに乗ってここから少し離れた隣の小さな町へと出向いた。とはいえ、玄那神社から片道一時間もある場所だ。
町へ着いた途端に櫻は俺にメモ用紙を私て指示を出した。
「鎖火さんは、日用品を買ってきてくれない? 私は食品を買いにスーパーへ行って来るから」
二手に分かれた方が早く済むということか、それなら同感だ。
「わかったよ? じゃあ、行くから……」
「道草とか食わないで下さいよ?」
「わ、わかってるよ……?」
えらく、信用がないようだ。
俺は、しぶしぶと日用雑貨を買いに薬局へ向かった。
*
一方の櫻はというと、食品売り場で頼まれた物を買い終えた後に狼と合流するバス停へと向かって歩き出していた。
「ああ……早く帰って弥生先輩とアイス食べよ?」
炎天下にさらされて額が汗で浮かび上がる。バテそうな体を必死で支えながら彼は徐々にバス停へと近づいていく。
……が。
――……?
花屋の前に白いスポーツカーが泊まってあった。見る限り高級感を漂わせるフォルムと艶のある美しいボディーだ。
「凄い……こんな田舎町にもこんなすごい車が来るんだ?」
しかし、しばらくして店内から怒号が聞こえた。
「赤薔薇が売っていないだと!? ふざけるな!!」
「す、すみません……」
スーツ姿の男が若い店員へ大声で怒鳴っている光景が嫌でも目に入った。スラッした長身にとびっきりのイケメン。そんな人目で女性を魅了させるような美青年がどうして花屋で怒りをあらわにしているのか?
「もうしわけございません。赤い薔薇は品切れでして……」
「品切れだと!? 貴様……客である私の要望に応えられないというのか!?」
と、さらに怒鳴り散らす青年に、店員はペコペコと頭を下げるばかりだ。
――何よ、アイツ……!
それを近くで見ている櫻はたまったものじゃない。あまりにも店員が可哀相でならず、彼女は後ろから青年に呼びかけた。
「ちょっと! ないモンはないんだし仕方ないじゃない? 別のお花を買えばいいでしょ?」
「何だ? キサマ! この私が誰だか知らんようだな?」
すると、青年は櫻を睨みながら歩み寄ると、彼女に名刺をぶっきら棒に渡した。
「……?」
受け取った名刺を見て、櫻は目を丸くした。『工藤テクノロジー』と書かれた名刺。それは、日本有数のIS企業だからだ。さらに、その名前を見て櫻は彼に指をさした。
「ああ! 工藤って……アンタが、弥生先輩をつけ狙うストーカーね!?」
「なっ!? ストーカーだと!? キサマ……この私をそこまで愚弄するか!?」
「どうでもいいわよ? それよりも、弥生先輩は迷惑しているの! 早いとこ諦めてもらえるかしら!?」
「な、なにを……薄汚い下流家庭のゴミが!」
と、怒りに我を忘れた工藤は片手が伸びて櫻の髪をガシッとつかみ上げた。
「ちょ、ちょっ女の子になにすんのよ!?」
「ふん! 俺はIS企業の人間だ。IS委員会も馬鹿じゃない。女だからって調子乗るな!」
そういうと、工藤は櫻に乱暴を始めた。彼女の髪をつかんだまま地面へ倒した。
「や、やめて……!」
胸倉をつかまれた櫻は、これ以上強がることはできず、いまからひどい目にあわされるんだと涙ぐんでいた。
「愚民がぁ!」
と、工藤は今にも泣きそうな櫻へ拳を振り下ろした……が。
「やめろって!?」
しかし、そんな暴行をふるおうとしていた工藤の片腕を、何者かがガシッと掴んだ。
「なんだ! 貴様は!?」
「く、鎖火……さん?」
そこには、先ほどまで軽蔑していたあの青年が、窮地に現れてくれたのだった。
「なにムキになってんだよ? 相手は学生の娘じゃないか?」
「むぅ? 貴様……境内の時にあったあの男か?」
「だからなんだよ?」
「フン! このガキといい、貴様といい、どれもこれも私の視界を腐らせるゴミめ!」
「なんとでも言え? だがな、暴力だけはやめろ! そんなことでもしたら、一流企業の名が泣くぜ?」
「……!!」
しばし、工藤はこれでもかというほどの怖い目つきで俺を見た。俺も少しビクッとしたが、それでも時期になれる。所詮、自分の思い通りにならないと気が済まないようなガキだ。
いるんだよな? こういう、中身だけガキになった大人ってのがさ……
「チッ……!」
工藤は、舌打ちと放つと行ってしまった。
「大丈夫か?」
俺は振り返って、尻餅をつく櫻へ手を伸ばした。
「あ、ありがとう……」
きょとんとしながら、彼女は俺の手を取って立ち上がった。
「ケガはない?」
「う、うん……」
「じゃあ帰ろう? 弥生も心配してんだしさ?」
「……」
櫻は、コクリとうなずくとそのまま俺の後に続いて待ち合わせのバス停へと歩いた。
「……ねぇ?」
「ああ?」
バスの中で、揺れながら櫻は隣に座る俺にこう問いかける。
「……どうして、あの時助けたのよ?」
「は?」
「だって、相手はIS企業の御曹司だし、権力使ってきたら……」
「ああ、構やしねぇよ……?」
だが、一般の人間なら堂々とたてつこうとはしない。今や、IS企業は政治家と同様の立場に当たり、自由に国家権力を横暴することができるのだ。だから、早い話RSを所持し、なおかつ裏政府ともつながりがある俺だからできたことだ。
おそらく、工藤の奴はこのあとすぐに国家権力を駆使して俺に襲い掛かるだろうが、その行為は反撃寸前でストップがかけられるだろう。
「単なる威嚇だろ? ああいう怒鳴りながら威張るやつなんて気の小さい奴さ」
「ふぅん……」
「そんな奴に……弥生を渡されてたまるかってんだ」
そう俺は、静かに怒った。
「……」
そんな俺の光景を、ただジッと彼女だけは……櫻だけは見続けていた。
それからというもの、なぜか櫻は俺に対して弥生に関するフィルターをかけることが極力少なくなった。
俺が、弥生の隣で飯を食っていても黙って見届けているし、弥生と一緒に授与所で奉仕を続けていてもこちらに背を向けて境内を掃き掃除している。
いつもなら、弥生と仲良くしているところで強制的に割り込んでくるっていうのに、どうしちまったんだ?
まぁ、何はともあれこれでようやく弥生と親密になれることができた。
それからしばらくして……俺が初めて大人に近づいたのが、ある休みの日だった。
*
休みの日とはいえ、神様の御奉仕は忘れずに弥生は健気に巫女として神職を果たしていた。
そんな彼女の姿をみつつ、俺も共に奉仕を行い手伝っていた。
「弥生、授与所のお守り整理は終わったぞ?」
「あ、じゃあ先に上がってください。私も、境内の掃き掃除が終わったらすぐに行きますから」
「そう? 手伝おうか?」
「いいえ? もうじき終わりますから」
「じゃあ……先に行っているね?」
俺は、とりあえず先に家へ戻った。戻ったら戻ったで、簡単な家事はやっておいて後は彼女らを待つばかりだ……
しかし。
「……?」
かれこれ二時間は経った。しかし、弥生は一向に帰ってこない。
――まさか……!
まさか、また工藤の奴に絡まれてんじゃ……!?
そう思ったら、居ても経ってもいられなくなり、気が付いた時には境内を飛び出して石垣を駆け下りていた。
「鎖火さん?」
そのとき、俺の背後から私服に着替えて帰ろうとする櫻がいた。
「どうしたんですか?」
やけに騒がしいと、よからぬ顔をして俺に問う。
「弥生を見なかったか?」
「先輩なら、裏の森へ行っていますけど?」
「裏の森?」
「何かあったんですか?」
「いや……弥生がちっとも帰ってこないから」
「ああ、それなら心配はいりません。先輩はあそこでずっとご奉仕を続けています。しかし、鎖火さんが来ない限り、あの人のご奉仕は終わらないんです」
「どういうことだ?」
俺を首を傾げた。すると、櫻はさらに意味深なことを言う。
「先輩は恥じらうかもしれませんが、それでも……本心では求めているものがあるんです」
「え? それって……」
「先輩が……鎖火さんを……に、してたなんて……」
そして、最後はそう呟いて彼女は帰って行った。
――何だったんだ?
俺はそう思いつつも、弥生を心配して裏側の森へと向かった。
だが、先ほどからどうも櫻が言い残した言葉が頭から離れられないでいる。まさか、まだ俺に隠している霊能力者としての秘密があるのでは?
そう思えば思うほど、俺は彼女を探す足を速めた。
「弥生! どこにいるんだ?」
裏側の森に入って、俺はあたりを探し回った。すると、そんな俺の耳元へ徐々に彼女らしきうめき声が聞こえる。
「弥生……?」
足を進めるたびに、その声は徐々に大きくなる。そのまま俺は急いで森の中を走り回った。
そして、ある光景を目にピタリと足がとまると、そこに飛び込んできた光景に俺は茫然となだめていたのだった……
「浪君っ……あうっ! うぅ……」
彼女の中指が、水音を立てながら己の膣を優しく撫でまわすかのように突き回している。
太ももが、内に引き締まるも膣をいじる指は止まらない。
自慰だ……
――う、うそだろ!?
あの大和撫子の彼女が、こんなエッチな行為をするなんてさすがの俺でも想像できなかったのだ。
しかし、そのいやらし気な声に誘われて俺は自然と足が前へ動き出していった。そして、俺は彼女の目の前へと姿を現したのだ。
「だ、誰っ……?」
何者かの陰に気づいて、弥生は目の前を見上げた。そして、その陰の主を目に弥生はとっさに顔を真っ赤にして、泣きそうになる。
「ろ、狼君……!?」
「弥生……」
「う、うぅ……」
とっさに、弥生は火が付いたかのように泣き出してしまった。
「見ないで……見ないで! こんな恥ずかしい姿、見ないでください……」
そんな、頬を赤く染めて泣きじゃくる恥じらいの顔を目に俺は胸が苦しくなり、気がついた時には彼女を思い切り胸に抱きしめていた。
「弥生……弥生!」
「狼君……」
「俺が、こんなことで弥生を嫌いになるわけないじゃないか! それに、あのとき……俺の名前を言いながらしていたじゃないか?」
「そ、それは……だってぇ……」
また、泣き出しそうになる顔だが、それでも俺は嬉しかった。どんな形であれ、俺のことを思ってくれているんだと……
「狼君のことが……好き、なんだもん……狼君のことを思うと、胸が苦しくなって……」
「そこまで、俺のことを思ってくれてたのか?」
「ごめんね? こんないやらしいことに狼君の名前を使っちゃって……」
「いいよ。むしろうれしいさ! 俺も、弥生のことが……」
そして、俺は彼女の唇へ、自分の唇を重ねていた。互いの口を求めるように双方の舌が絡み合い、口元から大量の唾液が伝ってたれ落ちる。
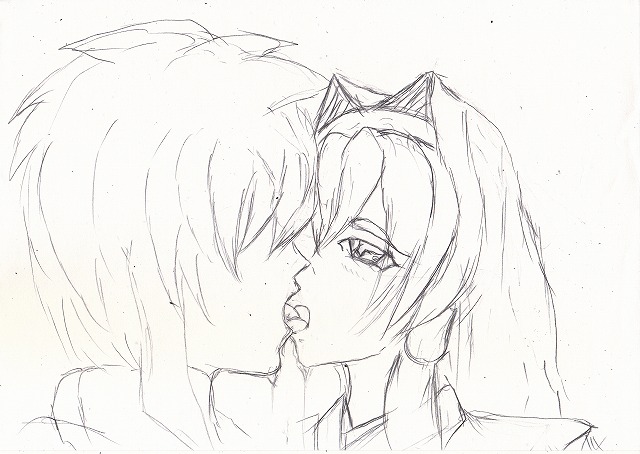
「私の初めて……狼君とやってるなんて、夢じゃないよね?」
「ああ、夢じゃないよ?」
そして、さらに俺たちは激しく口をかわし続けた。
「狼君……その、大変恥ずかしいお願いなんですけど、ズボンを……おろしてくださいませんか」
「いいのか? ここは、神社の近くだし?」
「構いません。境内の外なら……私、もう我慢できないんです!」
うずうずと恥ずかし気におねだりする彼女に、俺の性欲も限界に達した。
「じゃ、じゃあ……」
俺は、ズボンを下した。弥生と、彼女のキスで勃起したペニスがとびかかるように弥生の目先に飛び出した。
「す、すごい……! これが殿方の、狼君のオチンチン……」
やや赤黒い亀頭から発する臭いに、弥生の感覚は鈍りだしていく。
「あ、うぅ……すごい、狼君のオチンチン……」
すると、弥生の滑らかな白い手が俺のペニスの根元を擽るように摩りだした。
「うぅ……や、弥生!?」
これって……噂に聞いた「手コキ」、だよな?
「あ、あつい……狼君の、熱いですぅ」
「うぅ……ヤバッ!」
想像以上の刺激が伝わってくる。いや、興奮といったほうがいい。彼女のきれいなスベスベの白い手が俺の根元を……
――手コキって、今まで興味なかったけど……マジでヤバい!
たかが手なんかで……と、思っていたが実際は想像以上だった。
だんだんと、亀頭から我慢汁であふれ出てくる。すると、弥生はあと少しというところで手コキをやめてしまった。
「まだ……出しちゃダメですからね?」
弥生は、俺の亀頭へ口元を近づけさせる。
「弥生……なにを?」
「あむっ……」
弥生の口内が俺の亀頭をやんわりと包み込んだ。その一瞬、彼女の舌が裏筋に触れると雷に打たれたかのような衝撃がペニスから伝わってくるではないか。
――蒼真さんのお部屋で見つけたエッチな本の通りにやってるけど、狼君は気持ちよくなってくれているよね……?

前に、蒼真の散らかった部屋を掃除していたとき、偶然ベッドの裏側から幾冊ものエロ本を発掘した。
「あ、うぅ……!」
その何とも言えない快楽に俺は耐えしのごうとするが、どうあがいてもこれは我慢できない。
「ろ、ろうふん……ふるひくないれふか?」
咥えたまた喋られると、余計に気持ちよさが増してくる。舌が動かすからそれがベロベロと裏筋に当たるように舐められてそれどころじゃない!
「や、弥生……もう、ヤバすぎる!」
――えっと……狼君のオチンチンから精液を絞ればいいんだよね?
すると、弥生は吸引力を上げて俺のペニスを締め付けた。
「うぅ……! や、弥生の口に締め付けられて……」
そして、俺の我慢はとうとう限界に達した……
「ッ!?」
弥生の口内にドピュッと白い濃厚な液が溢れ出した。
――狼君の、精液……
不思議な味がして、やや苦みのあるもののそれを蒼真のエロ本通りにやってのける。
「んぐっ……!」
喉を鳴らして、口に広がる精液を一口で飲み干した。
「……狼君の、飲んじゃった♪」
やや、達成感が感じられて機嫌のいい口調で弥生は言った。
「ハァッ……ハアァー……」
呼吸を整え、俺は性欲が満たされたことを感じた。
翌日
昨日の出来事が信じられないくらいだ。まさか、御奉仕は御奉仕でも、弥生が俺に御奉仕するなんて……
そして、起きたついでにズボンとトランクスをめくって中身を見ると……
――夢だけど、夢じゃなかった!
……俺は、童貞を捨て去っていたのだった。
そんな俺は、朝から機嫌よく寝間着から私服へ着替えると、一目散に弥生が立つ台所へ向かった。
「弥生!」
「ろ、狼君!?」
巫女装束の上にエプロンを付けた彼女は、みそ汁を作っている最中だった。そして、俺を見てとっさに顔を赤くして照れてしまう。
「……今日も御奉仕、頑張ろうな?」
「は、はい!」
頬を赤くしながらも、弥生は万弁の笑顔で返した。
そのあと、八時丁度に櫻や臨時で雇われた学生を連れてやってきた。近づきつつある夏祭りに向けて、いろいろと準備が必要なのである。しかし、今回は男手となる俺も加わることで多少は苦労しないと弥生は話していた。
今日は、祭りの準備もかねてご奉仕をしなくてはならないから準備は村人の人たちも手伝ってくれるらしい。
そんな中、俺は境内の片隅にある物置小屋の整理を行った。埃だらけの中を雑巾で拭いたりしてせっせと掃除を続ける。
「はぁ……」
そんな一方で境内を掃き掃除している弥生は昨日のことが忘れられず集中しようにもできずに困っていた。
「どうしたんですか? 先輩」
と、そこへいつもと違う雰囲気を悟って櫻が歩み寄ってきた。
「櫻ちゃん? ちょっと、ね……」
「さっきから、鎖火さんのことをジッと見ていますけど~?」
と、ニヤニヤして彼女は弥生に問うと、弥生は慌てて否定しだした。
「ち、ちがうよ~!」
「鎖火さんのことが、好きなんですね?」
「べ、別に……そうというかなんというか……」
――図星か……
櫻は、弥生が狼のことが好きなんだということはあらかじめ知ってはいる。彼女も、最初は狼を毛嫌いしていたが、工藤から自分を救ってくれたことに、まんざら捨てたものじゃないと感心し、今では狼と弥生を応援する立場に変わっていた。昨日の出来事などが特にそうであった。
「あの、すみません?」
背後から聞こえた声に二人が振り返ると、そこには若い夫婦の参拝客が歩み寄ってきて訪ねてきた。若夫婦の内、妻のほうは可愛い赤ん坊を両手で大事そうに抱きかかえていた。
「うわぁ~ 可愛い赤ちゃんですね?」
櫻は無邪気な顔でこちらを見つめる赤ん坊に頬を緩ませた。
「ええ、半年前に生まれたんです」
「男の子……ですか?」
「ええ! 雄介っていいます」
笑みをこぼして我が子を紹介する若夫婦を見て、櫻と弥生も笑顔になりながらこの若夫婦に案内をした。
この玄那神社には、子宝の神様が祭ってあるのでよく新婚の夫婦がこの神社を訪れることが多い。そして、今回の若夫婦もそんなに珍しいものではなかった。
そして、夫婦を見送る中、弥生はその若夫婦の後姿を自分と、狼の姿と重ね合わせた。
「……」
境内で我が子を抱きながら狼と共に子をあやす。そんな妄想が絶え間なく続いて離れない。
――いいなぁ、赤ちゃんか……
「先輩……」
そんな寂し気な弥生の後姿を見て、櫻はふと決意してように弥生の手を引っ張った。
「先輩!」
「え、どうしたの?」
境内ではなんですから、とりあえず外でお話ししたいんです!」
「え、なにかな……?」
やや、驚くも弥生は櫻と共に境内を出て昨日の森の中へと連れてこられた。
「どうしたの? 櫻ちゃん」
「先輩……鎖火さんのことが好きなんですよね?」
「ど、どうしたの? 急に……」
「単刀直入に言います! 先輩……赤ちゃんが欲しいでしょ?」
「え!?」
弥生はまるで心を見透かされているかのように驚いた。
「否定はしません。けど……もし、弥生先輩は本当に鎖火さんの赤ちゃんがどうしても欲しいんだったら、私は敬愛なる先輩のために一肌脱ごうと思います!」
と、熱意あふれる目をして櫻は弥生の前絵に迫った。弥生も、これ以上ごまかすことはできないことを知って、静かに顔を赤くしてうなずいた。
「うん……本当は、私も狼君の赤ちゃんが欲しいの」
「でも、もし鎖火さんが嫌って言ったら?」
「それなら、諦めるしかないけど……でもぉ」
「それでも欲しいんですよね? 赤ちゃん」
「うん……」
「それなら! この私にとっておきの案があります!!」
「え?」
*
夏祭り当日、俺は祭りの準備を村人たちと共に手伝っていた。大小さまざまな出し物や屋台のテントを組み立てたりと、引っ張りだこだった。
何せ、俺意外に若い奴は五本の指で数えるぐらいであり、俺はその中の貴重な戦力としていろいろと扱き使われている。
「ふぅ……やっと終わったか?」
汗だくになって、近くの水舎の水を両手ですくって顔を洗った。冷たい井戸水は日焼けした俺の皮膚を気持ちよく冷やしてくれる。
「さて、もうひと頑張りといくか?」
「あ、あの……狼君?」
「弥生?」
すると、背後から歩み寄る弥生に俺は振り向いた。今でも、彼女は俺を見るたびに顔を赤くしながらモジモジし続けている。
「弥生か? どうした?」
「あ、あの……えっと……その……」
「……?」
何か言いたそうな口だが、なかなか言い出せない。いつものことだから俺はそこのところはゆっくりと待ってやる。
「……今夜、狼君のお部屋へお邪魔してもいいです……か?」
「え?」
「だ、駄目でしたら……」
「いいよ?」
「え? 本当!」
「ああ、別にいいけど?」
「じゃあ、今夜の八時に狼君のお部屋へ来ますね? 寝ちゃダメですからね? 絶対ですよ?」
と、それだけ言うと、はしゃぐかのように彼女は駆けていった。いつものおしとやかな彼女とは違う一面であった。いや……弥生は、俺が彼女の家へ遊びに来てからというもの彼女の雰囲気は時折変わったりしている。
IS学園にいるときは年下の女の子なのに年上で成人の俺よりもしっかりしていて大人びた風格を持った少女だった。もちろん、文武両道で俺よりも運動神経はいい上に勉強もできる優等生だ。
俺と比べたら月と鼈だ。こんな俺をどうした彼女は好きになってくれたんだろうと、いまだに理解できないのだ。
しかし、彼女が俺を心から愛してくれるのであれば、俺もその気持ちに十分こたえるつもりだ。
俺だって、弥生に対していささか劣等感を感じるとは言えども、彼女のことが好きだからそれほど嫉妬などは感じたことはない。優しいし、いつも俺を日常的に助けてくれる。
――昨日のことといい、今夜はそれに関係したことを話しに来るのかな?
下心などは出ていなかった。そんな欲情よりも、今後の関係がどうなってしまうのかという思いのほうが強かった。
祭りの準備は夕暮れ時には大方終えて、あとは本番を待つばかりである。
「あ、鎖火さん?」
と、俺が片づけを終えて物置小屋から出てきたところを櫻が表れて、俺の前まで駆け寄ってきた。
最初は敵意むき出しの彼女だったが、今ではそれほど悪くはなく、仲のいい男友達という感覚で見てくれている。
「朋絵ちゃん?」
「さっき、弥生先輩から声をかけられたんですか?」
「え? まぁね……」
「別に、悪い話じゃないみたいですから安心してください」
「え?」
「それじゃ! 私はこれで……」
と、それだけ言い残すと櫻は先に持ち場へ戻った。
「何なんだ……?」
だが、別にせずに俺はこのまま作業を再開する。
祭りは、夕暮れどきに始まった。幾店もの屋台が境内に並び、訪れる客を招いて夢中にさせる。
俺も、ようやく手伝いから解放されてくたくたになったところを、村長の爺さんたちに誘われてやや晩酌を迫られた。
軽く御猪口の酒を啜り、隙を見ては逃げ出してきたところだ。この村の老人たちはみないい人ばかりだが、酒が口に入ると途轍もなく盛り上がるから、酔ってほんわかな感覚になるよりも逆に疲れてしまう。
だから、俺は隙を見て逃げ出してきたのだった。それに、前々から楽しみにしていた弥生の舞もこの目で見ておきたいのだ。
とりあえず、夜店を何件か回って時間をつぶして、このまま暗くなるのを待った。
あたりが夕闇に沈むころ、雅楽の音色と共に舞台から一人の巫女の弥生が立ち、華麗な舞を周囲に披露した。
――綺麗だ……
神聖な装束に身を包んだ彼女の舞は、見るものを魅了することは間違いない。その舞を見とれているうちに時間はあっという間に過ぎ去っていく。
*
「ふぅ~祭りは疲れるな?」
訪れに来る客たちならともかく、準備に徹する者にとっては重労働であった。
疲れ切った体を、湯船に沈めて入浴を済ませた後、俺は寝間着に着替えると自室へ帰った。
布団を敷いて明日に備え今日は寝ようと思ったのだが、今日の昼に弥生が言っていたことを思い出してそのまま置き続けていた。
ちょうど、八時になるところだからもうじき来るだろうか?
八時になるまで、俺は適当にゴロンと布団の上に横たわって眠くならないように気を付けながら彼女が来るのを待ち続けた。
「ろ、狼君……?」
後ろから弥生の声が聞こえた。丁度、八時ジャストだ。障子の戸を引いて弥生が入ってきて、俺も起き上がって彼女のほうへと振り向いた……が。
「や、弥生!?」
「狼君……」
そこには……あの、興奮の止まない巫女レオタードの姿でいる弥生が立っていた。

「ど、どうしたんだよ? その格好……」
「狼君……本当は、この装束が好きなんだよね?」
と、いうと彼女は俺の隣に腰を下ろしと足を崩して、寄り添ってきた。
「や、弥生……?」
「……」
しかし、弥生はただ、その姿のまま俺の隣で足を崩しているばかりで、しばしの沈黙が続くのだが、そんな気まずい静けさを打ち消したのが、彼女のある一言だった。
「あの……狼君?」
「な、なに……?」
「最初に、狼君が来たとき、『
「そう……だったね?」
「急なことを言いますけど、狼君は……『夫婦』について真面目に考えたことはありますか?」
「えっ?」
「狼君、私は……欲しいんです」
「欲しいって?」
「狼君の……」
「俺の? 俺の、何が欲しいんだ?」
俺、弥生が気に入るような物とか持ってたかな……?
「欲しいっていうのは……『物』ではなくて、狼君の……」
「俺の?」
「狼君の……『赤ちゃん』が欲しいんです!」
「俺のあか……え!?」
俺は目を丸く見開いて突然立ち上がって俺の前で仁王立ちする彼女は、顔を赤くしながらこう叫んだ。
「私の……私の、おなかに狼君の赤ちゃんの種をください!」
弥生は、泣きそうで恥じらう顔をしながら引き締まったレオタード越しに浮かんだ、可愛いおへそのくぼみに手を添えた。
「しょ、正気か!? お前……マジで俺と?」
「本気です! 私……私……狼君の赤ちゃんがどうしても欲しいんです!」
「……」
俺は驚いて返す言葉が出なかったが、しかし時期に俺は彼女にこう返した。
「……別に、今じゃなくてもいいだろ? IS学園を卒業したらさ?」
まだ、彼女はIS学園で学生を演じなくてはならない。それまでに妊娠させてしまったら、彼女が学園にいられなくなるのは当然だ。
「でも……でも! 待てないんです。あなたのことが……好きになってしまったから」
「だからって……」
「臨海学校のとき、命に代えてまで私を助けてくれたあなたに、私はますます狼君への好意が強くなって、それ以来、狼君がいないと、生きていけないぐらいに大好きになっちゃって……私は、あなたのことが、大好きで大好きで……」
「弥生……」
そこまで、俺のことを思っていたとは思わなかった。そして今、彼女の本気を思い知らされてさすがの俺も参っている。だが、夫婦とやらになるのはもう少し待ってもらいたい。
「ごめん。もう少し待って? 別に弥生のことが嫌いってわけじゃないんだ。むしろ、俺もお前が好きなんだ。だけど……結婚とか、そういうのはもう少し待ってくれないかな? 心の準備ってやつがまだだし、それに今の俺にはちょっと自信がないんだ。弥生の夫として生きていくのが」
「そんなことありません。狼君は十分に私と一緒に暮らしていけます」
「弥生……ごめんな? もう少しの間だけ、辛抱してくれ?」
「狼……」
すると、悲しい顔をして、ついにはすすり泣きをしてしまう彼女に、俺は慌てながらもどうにかしてやることはできない。
「……わかりました。でも、せめて」
と、彼女は俺の顔へまじかに迫った。
「……今宵は、抱いてください?」
「弥生……」
俺は、自然に彼女の体に手が触れて、気づいたころには彼女を思い切り抱きしめていた。
レオタードのような装束の生地から伝わる温もりとほのかな香りが俺の心を締め付ける。
「狼君……私、キスだけじゃ満足いきません」
「ああ……俺もだ」
すると、俺は己が要望を彼女に提案した。
「その……せっかく、その格好なんだしさ? えっと、『顔面乗馬』ってやつ……して、もらいたいんだけど?」
「が、顔面……乗馬!?」
蒼真のコレクションから様々な用語を会得している彼女は、「顔面乗馬」という用語も当然知っていたが、それはとても羞恥心あふれる行為であったのだ。
「え、えっと……別に変態的な意味っていうよりも、弥生の匂いを嗅ぎたいっていうか……それも変態的な意味だよな……」
苦笑いする俺だが、そんな俺に彼女は本気になった。
「わ、わかりました! 布団の上で寝そべってください!」
「え?」
「狼君の好きなように致します。ですから……」
「……」
緊張するも、俺は布団に寝転んで、天井を見た。
「で、では……いきますね?」
すると、弥生は恥じらいながら俺の天井の視界に彼女の股が差し掛かる。
――え、エロい……
女の子の股を見て、俺は今にも勃起しそうだ……いや、もうしている。
「う、うぅ……」
ゆっくりと、俺の顔面へしゃがみ込む弥生の大股が間近に迫ってきている。そして……
「!?」
一瞬弥生のアソコに口をふさがれて息苦しさを感じたが。次第にアソコから彼女の匂いがやんわりと漂ってきた。

「はうっ……!」
口を動かせば動かすほど、弥生のアソコが刺激を受けて、こそばゆく感じているようだ。
しかし、俺はそんなことなど構うことなく、むさぼるように口を動かして食べたいかのように彼女の温もりに満ちたアソコを口元でハミハミと動かしながら揉み解していく。
「だ、だめっ……狼君。そんなに口動かしちゃヤッ……」
「おいしいよ? 弥生のアソコは、いい匂いがして温かい……」
すると、舌を付けたわけでもないのに次第と彼女のアソコから割れ目のあとが浮かび上がると、湿っぽさを感じた。
彼女は今、とても興奮しているのだ。息遣いも荒くなりだして、いやらしい声を上げて、気づいたらもっとむさぼってくれと言わんかのように俺の口へアソコをグイグイ押し込んでくるのだ。
「や、弥生……!」
やばい。こうなったら、俺も勃起したのちに射精しちまいそうだ!
「ろ、狼君の……」
弥生は、片手を後ろに回すと俺の股間からイチモツの膨らみを摩りだした。
「こんなに大きくなっちゃって……狼君のオチンチン」
「弥生……」
「ほら? そろそろ入れちゃお?」
「い、入れるって……?」
「狼君のオチンチンを、私の……お、オマンコに」
「ちょ、ちょっと待った! そんなことしたら……」
まさか、中出しするつもりじゃ……
「大丈夫です。ほら?」
弥生は、片方の裾からある一つの何かを取り出した。小さな輪の内にビニール状の柔らかな素材が貼り付けられている。
「コンドーム?」
「そう、狼君が駄目って言ったときに備えて持っていました」
「そうか。なら、安心だ……」
「じゃあ……付けてあげますね?」
と、彼女は俺のペニスの亀頭へ細く白い指で突かせながら、その感触に耐えつつもゆっくりとコンドームをはめていく。
「これでいいかな……?」
「俺もわからないけど……大丈夫だと思うよ?」
「じゃ、じゃあ……入れるね?」
俺のペニスが、彼女の膣へ挿入される。途端、俺のペニスが弥生の処女膜を食い破って一気に締め付けられる。
「痛っ……!」
弥生は、その痛さに苦しんで、俺のペニスを伝って彼女の膣から血がたれ流れた。
「だ、大丈夫か……?」
「はい……私、とても幸せです。大好きな殿方と、こうして一つに繋がっているんですから……」
「弥生……!」
俺は興奮して、彼女の膣の中へ飲み込まれたペニスを動かして暴れ回る。

「あっ……うぅ……!」
「や、弥生……!」
そして、俺のペニスはもう限界に達する。
「で、出る……出るぞ! 弥生!?」
「き、きてぇ……? 狼君!」
「うぅ……!」
そして、コンドームは俺の射精まみれになって汚れた。
「き、気持ちぃよぉ……」
快楽に満ちた笑みを浮かべる弥生は、俺のペニスから離れた。
「ご、ごめん……乱暴なことしたかな?」
「ううん? とても、気持ちよかったです……あの、狼君?」
「ん?」
「そのぉ……もう一回、したいな? って……」
彼女は満足いかないようだ。
「ああ……俺も、いいよ? もう一回だ!」
俺たちは、服を脱いで、衣類が散乱する布団の上で互いに抱き合いながら再び横たわった。
「はい、コンドームのおかわりです♪」
弥生はふたたび代わりのコンドームを取り出した。
「う、うん……」
苦笑いしながらも、俺はそれをペニスにはめて再び彼女の膣へ挿入した。

そして、俺たちは互いの名を呼びあいながらこの長い夜を過ごした……
永遠に続かなくたっていい。ただ、今この時だけが……どうか夢であってほしくないことを俺は思った。
「狼君、これからも私と一緒にいてくださいね?」
「ああ、これからもずっと一緒さ。もう、お前を手放したりはしない……」
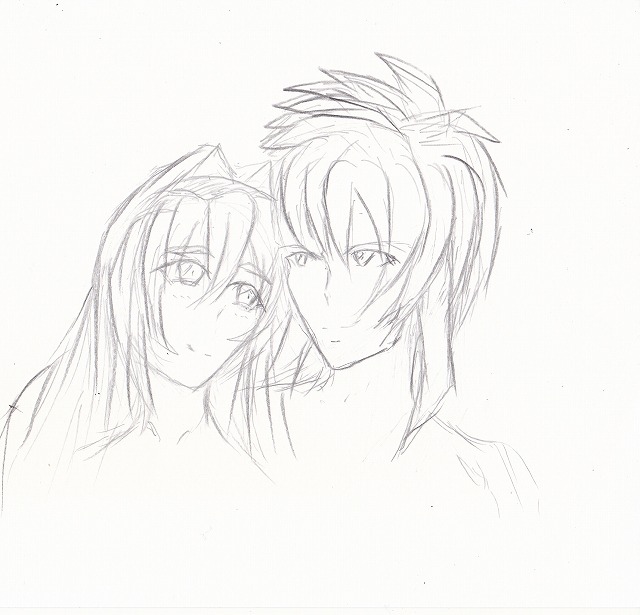
後書き
RS二期も近々考案中であります。
ページ上へ戻る
全て感想を見る:感想一覧
