| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っていた。
作者:デュースL
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動第十五話
「な、何だこれは!?」
巨樹の中に展開されている十九階層へ降りる螺旋階段に、ナチュルの驚愕に染まった叫びが木霊した。
彼女に護衛をしてもらっているレイナは、ナチュルの真後ろをついて来ていた状態であり、十八階層入り口で突然止まったせいで顔をナチュルの背中にぶつけた。
軽く額を擦りながらレイナは、未だ信じられないとばかりに目を見開いているナチュルに問いかけた。
「どうしたんですか?」
「モンスターよ、十八階層 にモンスターがいるわ。それも気持ち悪いくらい」
「えっ?」
耳を疑うような返事に堪らず聞き返し、脚から地面に根が生えたように動かないナチュルの背後から顔を覗かせたレイナの両目が見開かれた。
花だ。紺碧色の湖畔とそこに浮かぶ大島を塗り潰すような、夥しい花が蠢いていた。
あまりの数が一斉に蠢くせいで巨大な一体のモンスターにも見えるその景色はおぞましいものがある。
遠目から見ても解るほど毒々しい極彩色に染まった何枚もの花弁、中央には牙の並んだ巨大な口が存在する。食虫植物という、読んで字の如く虫を食べる花が世界には存在するのだが、それを巨大化させて明確な口や牙を持たせたら、あんな感じになるのではないだろうか。色が禍々しいことも相まってモンスターと呼ぶに相応しい姿だ。
階層内に響き渡る破鐘の咆哮に混ざって、街に住み込んでいた冒険者たちの悲鳴が聞こえてくる。無理もない、ナチュルの言う通り十八階層はモンスターが出現しない層のはずだ。誰もモンスターの大群が押し寄せてくるとは思うまい。加え断崖の上に築かれた街は天然の要塞だ、軽々と上ってくる醜悪な花たちに襲われればホラーである。
だが、リヴィアの街は安全階層にあるからとはいえ、未知で満ち溢れたダンジョン内に存在することに変わりない。いついかなるときも不測の事態が起こるのは、十分予測が立つ。証拠にリヴィアの街は今日までに三百を軽く越える壊滅を受け入れてきて、三百を軽く越える復活を遂げてきた街だ。壊滅を受け入れ続けたのは冒険者、復活を実現してきたのも冒険者。ゆえにリヴィアの街に住む冒険者は、第一級冒険者も舌を巻くほどのしぶとさを持つ。壊されれば呆気なく捨てて逃げ、帰ってきてしれっと復興するのがリヴィアの街の冒険者だ。
それに、ダンジョン内に築かれた街に商品が置いてあるということは、当然ながら地上から輸入してきている。つまり、物資を運び入れているのもこの街の冒険者である。地上から十八階層まで軽々と行き来できるほどの実力を持った冒険者が大半だ。十七階層か十九階層に出現するモンスターならば、この街に常駐する冒険者は難なく倒してみせるだろう。
しかし、そんな彼らが絶叫を上げて逃げ惑うほど、今回は例年に無いほどの異常事態 だったのだ。
まず、安全階層である十八階層に怪物の宴 と遜色ないほど大群で押し寄せてきたこと。そして押し寄せてきたモンスターがそもそもこの階層にそぐわない力を持っていたこと。これが最大の問題だった。
実は、リヴィアの街に殺到している花は地上でも確認されている。怪物祭 の騒動の裏側で【ロキ・ファミリア】が遭遇した新種モンスターなのだ。Lv.5のティオネ、ティオナ、アイズと強力無比な魔力を誇るレフィーヤの活躍により最小限の被害に抑えられたが、それは彼女らが最前線に立ち続けている一級の中の一級の実力者であったからであり、二十階層にも満たない階層を行き来できる程度の冒険者では荷が重い相手なのだ。
加え、湖畔の中心にある断崖に築かれているという立地条件が負の方面にはたらき、その湖畔を埋め尽くさんばかりに群がられては逃走するのもままならない。
地獄絵図と言わずして何と言おう。ただ、不幸中の幸い、リヴィアの街には【ロキ・ファミリア】の先鋭たちが居たお陰で、混乱のさなかでも何とか抵抗できていることだ。
しかし、翻ってレイナとナチュルの現状こそ、まさに地獄絵図だった。
十九階層に降りるための階段があるのは中央樹の根元。十八階層の中心に聳え立つ巨木の西のすぐが、今モンスターによって蹂躙されている湖畔なのだ。紺碧色の美しい色を湛えていたはずの湖畔は今では、毒々しい色へと変貌している。その脅威が目の前にある状態なのだ。
よって、十八階層に上ってきたレイナたちに、少なからぬ花たちが一斉に振り向いた。
「……まずい、逃げるわよ!!」
「はい!!」
ナチュルはもちろんのこと、前世で六十階層以降にも潜り続けていたレイナすらも初めてみるモンスターだった。ナチュルは中層の攻略推奨レベルをクリアしているものの夥しい数の初見モンスターと戦うことを恐れ、レイナは自分でも見たこと無いモンスターに言い様のない嫌な予感を感じ取り、弾かれたように十八階層の連絡路に向けて逃走を開始した。
十九階層に戻らないのは、二人で手一杯になるくらいのモンスターが跋扈している中を逃げれるか解らない上に、この花たちが階層を跨いでくる可能性も十分考えられること、そして何より逃げた先には安全地帯など存在しないからである。
十八階層ならば、十七階層の大広間にモンスターが再び屯している可能性はあるものの抜けきれる望みはあるし、もし花たちが追いかけ続けてきても階層で徘徊しているモンスターたちの処理は間に合うし、地上に帰還することが出来るからだ。
『アアアアアアアアアアアアアアアアアアアア!!!!』
背中を突き刺すような咆哮とともに、花たちは湖畔の水を盛大にぶちまけながら逃走する二人を追いかけ始めた。
背後から追いかけてくる気配に二人とも人知れず顔を歪め、地を蹴る力を更に強める。しかし、花たちも一筋縄ではいかずズルズル体を引きずるように移動しているくせにやけにスピードが速く、徐々にだが確実に二人に追いつこうとしていた。
それを肩越しに一瞥したナチュルは逡巡する素振りを見せたが、持っていたバックパックを握る手に力を込め、言葉を紡いだ。
「レイナちゃん、あなたは先に逃げてなさい」
「は、はぁ!? ナチュルさんはっ!?」
ステイタスの加護が薄いレイナの体力は、十九階層を切り抜けるときにはすでに半ばほど消費されていた。それも十七階層に逃げるための全力疾走で切れつつあった。それが浮き彫りになって息が切れているレイナは顔を上気させながら叫んだ。
一方ナチュルはLv.3と高いステイタスのお陰で汗こそ掻いているものの息は切れていない。そして共に逃げるレイナは息も絶え絶え、加え十三歳という若さだ。それだけでナチュルとして十分な踏ん切りだった。
「私が囮になるわ」
「ふざ、ふざけないでくださいっ!! あれだけの数を相手に一人なんて、そんなの囮にもなりません!!」
「なぁに、Lv.3の私に掛かれば大丈夫でしょ。子供は大人の言うこと聞きなさい」
そもそも、ナチュルには負い目がある。いくらLv.2のトロールを単独で倒したと言えど、それが即ち中層と渡り合えるかと言うと全く違う。中層はモンスターの強さもさることながら、頭数が増えることが最も厄介なところだ。一対一ならまだしも、多対一で渡り合おうなんてLv.2の冒険者でも無理なのに、Lv.1にとって無謀にもほどがある。
Lv.3の自分がいるから何とかなるでしょ、と持ち前の悪癖がレイナの命の危機に追いやったのだ。責任は取らなくてはならない。
子供を安心させるような余裕な笑みを浮かべて勝気なセリフを返すナチュルだが、レイナには己の恐怖を隠すためのポーカーフェイスにしか見えなかった。
「聞けませんっ! そんなこと───」
「真っ直ぐ進みなさい。後ろを振り向くんじゃないわよ」
悲鳴に近いレイナの叫び声を遮るように言い残したナチュルは、道脇に生え並ぶ結晶郡にはち切れそうなバックパックを乱雑に放り捨て、踵を返してレイナの視界から失せた。
ナチュルの残滓を追う様にレイナが言いつけを破り首を回した。
すでに凶悪な花たちに肉薄し、紅い燐光を点す薙刀を猛然と振りかぶろうとしていた。
「【爆ぜろ】!!!!」
喉が裂けんばかりに放たれた砲声と共に、鍛冶師の体から洪水のような量の魔力が迸った。
【エクスプロージョン】の最高出力は果たして、彼女に噛み付こうと口をばっくりと空けた花たちに走った一閃の後、遅れて大量の大爆発を引き起こした。薙刀で口を斬られた花たちは零距離で発生した紅蓮の爆炎に一瞬で灰と化し、直接触れていなかったものの爆発した近くにいた花も巻き込まれ痛ましい悲鳴を上げる固体もいれば、口の奥に埋め込まれている魔石に爆炎が届き焼き尽くされたために粉々になった固体もいた。
詠唱式が極めて短く、少量の精神力でも十分な火力を叩き出す【エクスプロージョン】だが、対象と何かしらの接触がなければ発動しないという特性上、その爆風はナチュル本人にも牙を向く諸刃の剣だ。精神力の調整をすれば無害で済ませられるが、今の爆発に注ぎ込まれた精神力はナチュルの意識を一瞬飛ばしてしまうほどだった。
どうせ使うなら考え無しにぶっ放してやる、大雑把な彼女らしく最後まで大雑把にぶっ放された爆風は彼女の体を叩きのめした。
「っっうっぐっっ!?」
体内で何かが粉砕する音が立て続けに奏でられた。僅かに遅れて喉にせり上がってきた大量の血が、彼女の艶やかな唇から溢れ出す。精神力枯渇状態 に限りなく近い症状のせいだけでなく、全身を激しく殴打した爆風によって走った激痛によって、明後日の方向に体を吹き飛ばされながらナチュルの脳は拒否反応を起こし強制的に意識を絶った。
彼女が容赦なく振りかざした諸刃の剣によって、追いかけていた三十体を越える花のうち二十体ほどを散らしてみせた。それだけで渾身の【エクスプロージョン】の威力を察することが出来る。
これはナチュルの言った囮としての意味に於いて、この上なく覿面だった。
ナチュルを無視して立ち止まったレイナに襲い掛かろうとしていた花、花弁が焼き爛れた花、最後尾にいた花、それら全ての花の注意の矛先がナチュルに向いた。
仲間を殺された憤怒からではない。彼らの最も過敏な魔力を使ったからだ。
ぐるんと、それまでの体勢を覆し、己の魔法の爆煙を引いて吹き飛ばされたナチュルに、数多の顔の無い頭部が向けられた。
「ナチュルっ!?!?」
ボールのように飛んでいったエルフの名を咄嗟に叫んだレイナ。しかし木々の枝を背で叩き折りながら意識を絶ったナチュルはその呼びかけに応えることはできず、爆風に乗ってきた焼かれた際に発生する臭いが充満した。
レイナの悲鳴も虚しく、花たちは触手を鞭のように振り上げながら瀕死のナチュルを滅多打ちにすべく彼女の後を追った。
◆
馬鹿だ、とレイナは思った。
天蓋いっぱい生える結晶郡が星のように輝き、光を照らしている最中、花たちはその光を浴びて狂喜するように咆哮を上げ、絶大な爆発に身を巻き込まれたナチュルに追い討ちを掻けようと殺到する。
耳に届くあらゆる音が遠のく。傍で光を発する結晶が、足元に広がっている草原が、鼻につく噎せ返るような不快な悪臭が、破れてしまいそうなほど激しくなる鼓動が、五感全てが遥か彼方へ遠のいた。
彼女に残ったのは、漠然とした意識だけ。時の流れすらも置き去りにするほど圧縮された意識の中にあった何が、ゆっくりと首を擡げた。
何かは意識のスクリーンにあらゆる記憶を映し出した。そこには、前世で救えなかった数多くの人々が死んでいく瞬間だった。もう嫌だ、自分が強くなって救えるのならいくらでも強くなりたい。トラウマのフラッシュバックだった。
またか、とレイナは嘆いた。
自分の至らなさゆえに、また自分は誰かが死んでいくのを眺めていなければならないのか。むしろ今までよりもっと質が悪い。訳があったとはいえ、自分の本性を隠して続けて躊躇ったから彼女ナチュルを死の淵際に追いやってしまったのだ。
何かが意識という殻を、内側から徐々に、徐々に、さながら卵から孵る雛鳥のように破っていく。
そして、何かは崩潰した意識に目をくれることもなく、その意思を存分に伸ばした。
生ける伝説クレア・パールスの、本当の意味での覚醒がなされた瞬間だった。
◆
レイナの目が変わった。およそ十三歳が浮かべてはならないような、どこまでも静謐で研ぎ澄まされた光が、レイナの瞳を湛えていた。
レイナの中で何かが変わってからコンマ一秒とも経っていない。そして、ほんの少し前まで押し止めていた衝動に身を委ねた。
「【ヒリング・パルス】」
それは、後に《神の恵み》と謳われた最高レベルの治癒魔法だった。
体に蓄積したダメージの九割を回復させ、体を蝕むあらゆる異常を治癒、加え消費精神力によってレンジを広げることが出来る、クレア・パールス専用魔法。更に彼女クレアの場合発展アビリティ【癒力】によって実質蓄積したダメージ全てを回復させることができる。
あらゆる治癒魔法にどんな状態でも完治させる、なんて利便性が高すぎるものはない。せいぜい五割程度の回復しか見込めず、現在オラリオ最強の魔道師ですらも不可能の芸当だ。
それを、たった魔法名を発するだけで実現してしまう。これを《神の恵み》と言わずして何と言えるだろうか。
ただし、これはクレア・パールスが目の前で死んでいった人々に嘆き、自分にその力があればと滂沱の涙を零し切歯扼腕した末にめぐって来た奇跡だ。その思いを元に己を研鑽し続けた彼女の姿を神の恩恵ファルナが認めたのだ。
《神の恵み》を授かったナチュルの体は、淡く柔らかい緑の燐光によって瞬く間に傷を回復させ、一秒後にはすでに万全の状態にまで治癒されていた。
そしてその温かみに触れた彼女の意識は否応無く目覚めさせられた。
「……ハッ!?」
極僅かな気絶に陥っていたナチュルを襲ったのは、不安定な浮遊感だった。ステイタスによって強化された五感と、気絶する直前の記憶によって己の現状を反射的に把握したナチュルは、空中で体を回転させて着地の姿勢を取り、靴底で草の絨毯を抉りながら無事に着地を成功させた。
そして気絶した直前に味わった激痛に備えたが痛覚らしき痛覚は全く無く、見るも無残な姿になっているであろう自分の体を恐る恐る見下ろした、が。
「……なにも、ない……?」
完膚だった。小さな掠り傷すら残っていない。しかし、彼女の記憶を裏づけるように、彼女が纏っていた着流しが爛れており、上半身ははだけ掛けたボロボロの下着だけの状態だった。
あまりに不可解な現状に柳眉を顰めたナチュルだったが、長く尖った耳が捉えたおぞましい咆哮に意識を前方に向けた。
すぐに木々の間を食い破るようにして花の群れが姿を表した。気絶したナチュルだったが冒険者として─薙刀へ対する愛が深いためかもしれない─己の得物を硬く握り締めていたため、直ちに八相の構えを取った。
しかし。
『アアァァァ────!?!?』
嫌悪しか喚起しない花は生え渡る牙から粘液を咆哮と共に撒き散らし、遂に噛み付こうとしたその瞬間、背筋が凍るほど正確に垂直の一閃が花の脳天から突き抜けた。
瞬きも許されない刹那、花はぼろぼろと黒い灰へ返り、積もった塵の中に不気味な極彩色を放つ大きな魔石が綺麗に真っ二つに断ち切られていた。
そして、花の背後に隠れていたレイナの姿が露になる。何で逃げなかったの、という言葉を彼女の理性が許さなかった。
自分の瞳とあったレイナの瞳が、あまりにも静かだったために。底まで見えそうなほど澄み渡った湖を覗き込んだような、言い様のない何かが言及どころか身動きすら許さなかったのだ。
全身を鎖で雁字搦めにされたように動けなくなったナチュルの眼前のレイナに、再び魔力を感知した花たちが一斉に振り向いた。が、しかし、花が振り向いている最中に音もなく動いたレイナは、ナチュルが気付いたときにはレイナの近くにいた花のすぐ傍に立っており、そう思ったときには薙刀が振り切られていた。
『────』
もはや断絶魔を与えることすら許されなかった。魔石ごと断ち切られた花の花弁が一気に枯れたかのように灰へ返り始めた頃にはもうレイナは次の標的に迫っていた。
『』
何で、何でレイナはあんなにも速く動けるんだ。ナチュルは呆然とする意識の中でようやくその疑問符を掲げることが出来た。しかし、一瞬後に自分が呈した疑問に自分が答えた。
無駄が無いのだ。あまりに淀みなく、あらゆる無駄を削いでいるため、化け物じみたステイタスが無くともLv.5相当、いや、それ以上の速度の移動を可能にしているのだ。
そして、薙刀に無理が掛かっていない。まるで自分の四肢のように、極自然と薙刀が走っているのだ。凄絶なほど滑らかに空気を薙ぎ続ける薙刀は、ナチュルの目には黄金に輝いて見えた。
自分の探していた黄金比は、目の前にあった。だが、レイナが振るう薙刀は自分が新米のときに作った駄作。過去の自分を殴りつけてやりたいくらい拙い出来であるはずの薙刀が、黄金比を奏でていた。
いや、違う、薙刀の黄金比は薙刀に無かったんだ。真に注目すべきは薙刀の使い手。その使い手が柄を握るだけで、どんな薙刀も黄金比となりうるものだった。
しかし、同時にナチュルは思った。その黄金比を手に入れるまでに、一体どれほどの努力が必要なのだろうかと。薙刀の軌跡を生み出すその腕に掛けられた途方もない試行錯誤と努力が垣間見え、ぞっとする意識。
そんなの、無理だ。どんなことをすれば、その努力を続けることが出来たんだ。そもそも、駆け出しの十三歳の少女では努力に費やす時間の絶対値が圧倒的に足りないはずだ。私が知る限り、史上で最も薙刀の黄金比に近づいた人物は一人しかいない。あの伝説の人を超えるほどの何かを、レイナは持っているのか。
目まぐるしく切り替わる疑問符に付いてこれなくなったナチュルはそこで思考を打ち切った。そして、その黄金比を目に焼き付けるためにレイナに意識を集中させた。
一輪と一輪の間を最短距離で駆け抜け、最短且つ最大の遠心力が乗せられた一撃を放ち、体を翻して掛ける。
途中で妨害に入る十を軽く超える触手の数々がその華奢な体に襲い掛かる。触手に包み込まれレイナの体が隠れた瞬間、何かが爆発したように蠕動する触手が内側から膨張し、一気に破裂、空中に緑の血潮をぶちまけるがレイナの衣服はおろか艶やかな黒髪に一滴たりともかからない。
はなから妨害なんて無かったように最短距離を突き進み、一閃。その繰り返しだった。
そして瞬きをしたころには、二十を超えていたはずの花たちは一匹残らず全て灰と割れた魔石に姿を変え、辺り一体に静けさを齎した。
ひゅん、と鋭く柄を振り血を払い落としたレイナと再び瞳が合う。だけど、そこには先ほどの深淵のような光は無く、清楚とした女の子の穏やかな光が戻っていた。ただし、少し気まずそうに焦点をずらしているが。
「地上に帰ったときに訳は全て話します。今はまだ、聞かないで下さい」
それでは帰りましょうか、と地面に三点着地した状態で固まっていたナチュルに、小さく白く細い腕が差し出される。
Lv.3に迫る力を持つ花の群れを全て一撃で葬った、Lv.1の少女の手。その掌から伝わってくる熱は温かく、少し儚げだった。
巨樹の中に展開されている十九階層へ降りる螺旋階段に、ナチュルの驚愕に染まった叫びが木霊した。
彼女に護衛をしてもらっているレイナは、ナチュルの真後ろをついて来ていた状態であり、十八階層入り口で突然止まったせいで顔をナチュルの背中にぶつけた。
軽く額を擦りながらレイナは、未だ信じられないとばかりに目を見開いているナチュルに問いかけた。
「どうしたんですか?」
「モンスターよ、
「えっ?」
耳を疑うような返事に堪らず聞き返し、脚から地面に根が生えたように動かないナチュルの背後から顔を覗かせたレイナの両目が見開かれた。
花だ。紺碧色の湖畔とそこに浮かぶ大島を塗り潰すような、夥しい花が蠢いていた。
あまりの数が一斉に蠢くせいで巨大な一体のモンスターにも見えるその景色はおぞましいものがある。
遠目から見ても解るほど毒々しい極彩色に染まった何枚もの花弁、中央には牙の並んだ巨大な口が存在する。食虫植物という、読んで字の如く虫を食べる花が世界には存在するのだが、それを巨大化させて明確な口や牙を持たせたら、あんな感じになるのではないだろうか。色が禍々しいことも相まってモンスターと呼ぶに相応しい姿だ。
階層内に響き渡る破鐘の咆哮に混ざって、街に住み込んでいた冒険者たちの悲鳴が聞こえてくる。無理もない、ナチュルの言う通り十八階層はモンスターが出現しない層のはずだ。誰もモンスターの大群が押し寄せてくるとは思うまい。加え断崖の上に築かれた街は天然の要塞だ、軽々と上ってくる醜悪な花たちに襲われればホラーである。
だが、リヴィアの街は安全階層にあるからとはいえ、未知で満ち溢れたダンジョン内に存在することに変わりない。いついかなるときも不測の事態が起こるのは、十分予測が立つ。証拠にリヴィアの街は今日までに三百を軽く越える壊滅を受け入れてきて、三百を軽く越える復活を遂げてきた街だ。壊滅を受け入れ続けたのは冒険者、復活を実現してきたのも冒険者。ゆえにリヴィアの街に住む冒険者は、第一級冒険者も舌を巻くほどのしぶとさを持つ。壊されれば呆気なく捨てて逃げ、帰ってきてしれっと復興するのがリヴィアの街の冒険者だ。
それに、ダンジョン内に築かれた街に商品が置いてあるということは、当然ながら地上から輸入してきている。つまり、物資を運び入れているのもこの街の冒険者である。地上から十八階層まで軽々と行き来できるほどの実力を持った冒険者が大半だ。十七階層か十九階層に出現するモンスターならば、この街に常駐する冒険者は難なく倒してみせるだろう。
しかし、そんな彼らが絶叫を上げて逃げ惑うほど、今回は例年に無いほどの
まず、安全階層である十八階層に
実は、リヴィアの街に殺到している花は地上でも確認されている。
加え、湖畔の中心にある断崖に築かれているという立地条件が負の方面にはたらき、その湖畔を埋め尽くさんばかりに群がられては逃走するのもままならない。
地獄絵図と言わずして何と言おう。ただ、不幸中の幸い、リヴィアの街には【ロキ・ファミリア】の先鋭たちが居たお陰で、混乱のさなかでも何とか抵抗できていることだ。
しかし、翻ってレイナとナチュルの現状こそ、まさに地獄絵図だった。
十九階層に降りるための階段があるのは中央樹の根元。十八階層の中心に聳え立つ巨木の西のすぐが、今モンスターによって蹂躙されている湖畔なのだ。紺碧色の美しい色を湛えていたはずの湖畔は今では、毒々しい色へと変貌している。その脅威が目の前にある状態なのだ。
よって、十八階層に上ってきたレイナたちに、少なからぬ花たちが一斉に振り向いた。
「……まずい、逃げるわよ!!」
「はい!!」
ナチュルはもちろんのこと、前世で六十階層以降にも潜り続けていたレイナすらも初めてみるモンスターだった。ナチュルは中層の攻略推奨レベルをクリアしているものの夥しい数の初見モンスターと戦うことを恐れ、レイナは自分でも見たこと無いモンスターに言い様のない嫌な予感を感じ取り、弾かれたように十八階層の連絡路に向けて逃走を開始した。
十九階層に戻らないのは、二人で手一杯になるくらいのモンスターが跋扈している中を逃げれるか解らない上に、この花たちが階層を跨いでくる可能性も十分考えられること、そして何より逃げた先には安全地帯など存在しないからである。
十八階層ならば、十七階層の大広間にモンスターが再び屯している可能性はあるものの抜けきれる望みはあるし、もし花たちが追いかけ続けてきても階層で徘徊しているモンスターたちの処理は間に合うし、地上に帰還することが出来るからだ。
『アアアアアアアアアアアアアアアアアアアア!!!!』
背中を突き刺すような咆哮とともに、花たちは湖畔の水を盛大にぶちまけながら逃走する二人を追いかけ始めた。
背後から追いかけてくる気配に二人とも人知れず顔を歪め、地を蹴る力を更に強める。しかし、花たちも一筋縄ではいかずズルズル体を引きずるように移動しているくせにやけにスピードが速く、徐々にだが確実に二人に追いつこうとしていた。
それを肩越しに一瞥したナチュルは逡巡する素振りを見せたが、持っていたバックパックを握る手に力を込め、言葉を紡いだ。
「レイナちゃん、あなたは先に逃げてなさい」
「は、はぁ!? ナチュルさんはっ!?」
ステイタスの加護が薄いレイナの体力は、十九階層を切り抜けるときにはすでに半ばほど消費されていた。それも十七階層に逃げるための全力疾走で切れつつあった。それが浮き彫りになって息が切れているレイナは顔を上気させながら叫んだ。
一方ナチュルはLv.3と高いステイタスのお陰で汗こそ掻いているものの息は切れていない。そして共に逃げるレイナは息も絶え絶え、加え十三歳という若さだ。それだけでナチュルとして十分な踏ん切りだった。
「私が囮になるわ」
「ふざ、ふざけないでくださいっ!! あれだけの数を相手に一人なんて、そんなの囮にもなりません!!」
「なぁに、Lv.3の私に掛かれば大丈夫でしょ。子供は大人の言うこと聞きなさい」
そもそも、ナチュルには負い目がある。いくらLv.2のトロールを単独で倒したと言えど、それが即ち中層と渡り合えるかと言うと全く違う。中層はモンスターの強さもさることながら、頭数が増えることが最も厄介なところだ。一対一ならまだしも、多対一で渡り合おうなんてLv.2の冒険者でも無理なのに、Lv.1にとって無謀にもほどがある。
Lv.3の自分がいるから何とかなるでしょ、と持ち前の悪癖がレイナの命の危機に追いやったのだ。責任は取らなくてはならない。
子供を安心させるような余裕な笑みを浮かべて勝気なセリフを返すナチュルだが、レイナには己の恐怖を隠すためのポーカーフェイスにしか見えなかった。
「聞けませんっ! そんなこと───」
「真っ直ぐ進みなさい。後ろを振り向くんじゃないわよ」
悲鳴に近いレイナの叫び声を遮るように言い残したナチュルは、道脇に生え並ぶ結晶郡にはち切れそうなバックパックを乱雑に放り捨て、踵を返してレイナの視界から失せた。
ナチュルの残滓を追う様にレイナが言いつけを破り首を回した。
すでに凶悪な花たちに肉薄し、紅い燐光を点す薙刀を猛然と振りかぶろうとしていた。
「【爆ぜろ】!!!!」
喉が裂けんばかりに放たれた砲声と共に、鍛冶師の体から洪水のような量の魔力が迸った。
【エクスプロージョン】の最高出力は果たして、彼女に噛み付こうと口をばっくりと空けた花たちに走った一閃の後、遅れて大量の大爆発を引き起こした。薙刀で口を斬られた花たちは零距離で発生した紅蓮の爆炎に一瞬で灰と化し、直接触れていなかったものの爆発した近くにいた花も巻き込まれ痛ましい悲鳴を上げる固体もいれば、口の奥に埋め込まれている魔石に爆炎が届き焼き尽くされたために粉々になった固体もいた。
詠唱式が極めて短く、少量の精神力でも十分な火力を叩き出す【エクスプロージョン】だが、対象と何かしらの接触がなければ発動しないという特性上、その爆風はナチュル本人にも牙を向く諸刃の剣だ。精神力の調整をすれば無害で済ませられるが、今の爆発に注ぎ込まれた精神力はナチュルの意識を一瞬飛ばしてしまうほどだった。
どうせ使うなら考え無しにぶっ放してやる、大雑把な彼女らしく最後まで大雑把にぶっ放された爆風は彼女の体を叩きのめした。
「っっうっぐっっ!?」
体内で何かが粉砕する音が立て続けに奏でられた。僅かに遅れて喉にせり上がってきた大量の血が、彼女の艶やかな唇から溢れ出す。
彼女が容赦なく振りかざした諸刃の剣によって、追いかけていた三十体を越える花のうち二十体ほどを散らしてみせた。それだけで渾身の【エクスプロージョン】の威力を察することが出来る。
これはナチュルの言った囮としての意味に於いて、この上なく覿面だった。
ナチュルを無視して立ち止まったレイナに襲い掛かろうとしていた花、花弁が焼き爛れた花、最後尾にいた花、それら全ての花の注意の矛先がナチュルに向いた。
仲間を殺された憤怒からではない。彼らの最も過敏な魔力を使ったからだ。
ぐるんと、それまでの体勢を覆し、己の魔法の爆煙を引いて吹き飛ばされたナチュルに、数多の顔の無い頭部が向けられた。
「ナチュルっ!?!?」
ボールのように飛んでいったエルフの名を咄嗟に叫んだレイナ。しかし木々の枝を背で叩き折りながら意識を絶ったナチュルはその呼びかけに応えることはできず、爆風に乗ってきた焼かれた際に発生する臭いが充満した。
レイナの悲鳴も虚しく、花たちは触手を鞭のように振り上げながら瀕死のナチュルを滅多打ちにすべく彼女の後を追った。
◆
馬鹿だ、とレイナは思った。
天蓋いっぱい生える結晶郡が星のように輝き、光を照らしている最中、花たちはその光を浴びて狂喜するように咆哮を上げ、絶大な爆発に身を巻き込まれたナチュルに追い討ちを掻けようと殺到する。
耳に届くあらゆる音が遠のく。傍で光を発する結晶が、足元に広がっている草原が、鼻につく噎せ返るような不快な悪臭が、破れてしまいそうなほど激しくなる鼓動が、五感全てが遥か彼方へ遠のいた。
彼女に残ったのは、漠然とした意識だけ。時の流れすらも置き去りにするほど圧縮された意識の中にあった何が、ゆっくりと首を擡げた。
何かは意識のスクリーンにあらゆる記憶を映し出した。そこには、前世で救えなかった数多くの人々が死んでいく瞬間だった。もう嫌だ、自分が強くなって救えるのならいくらでも強くなりたい。トラウマのフラッシュバックだった。
またか、とレイナは嘆いた。
自分の至らなさゆえに、また自分は誰かが死んでいくのを眺めていなければならないのか。むしろ今までよりもっと質が悪い。訳があったとはいえ、自分の本性を隠して続けて躊躇ったから彼女ナチュルを死の淵際に追いやってしまったのだ。
何かが意識という殻を、内側から徐々に、徐々に、さながら卵から孵る雛鳥のように破っていく。
そして、何かは崩潰した意識に目をくれることもなく、その意思を存分に伸ばした。
生ける伝説クレア・パールスの、本当の意味での覚醒がなされた瞬間だった。
◆
レイナの目が変わった。およそ十三歳が浮かべてはならないような、どこまでも静謐で研ぎ澄まされた光が、レイナの瞳を湛えていた。
レイナの中で何かが変わってからコンマ一秒とも経っていない。そして、ほんの少し前まで押し止めていた衝動に身を委ねた。
「【ヒリング・パルス】」
それは、後に《神の恵み》と謳われた最高レベルの治癒魔法だった。
体に蓄積したダメージの九割を回復させ、体を蝕むあらゆる異常を治癒、加え消費精神力によってレンジを広げることが出来る、クレア・パールス専用魔法。更に彼女クレアの場合発展アビリティ【癒力】によって実質蓄積したダメージ全てを回復させることができる。
あらゆる治癒魔法にどんな状態でも完治させる、なんて利便性が高すぎるものはない。せいぜい五割程度の回復しか見込めず、現在オラリオ最強の魔道師ですらも不可能の芸当だ。
それを、たった魔法名を発するだけで実現してしまう。これを《神の恵み》と言わずして何と言えるだろうか。
ただし、これはクレア・パールスが目の前で死んでいった人々に嘆き、自分にその力があればと滂沱の涙を零し切歯扼腕した末にめぐって来た奇跡だ。その思いを元に己を研鑽し続けた彼女の姿を神の恩恵ファルナが認めたのだ。
《神の恵み》を授かったナチュルの体は、淡く柔らかい緑の燐光によって瞬く間に傷を回復させ、一秒後にはすでに万全の状態にまで治癒されていた。
そしてその温かみに触れた彼女の意識は否応無く目覚めさせられた。
「……ハッ!?」
極僅かな気絶に陥っていたナチュルを襲ったのは、不安定な浮遊感だった。ステイタスによって強化された五感と、気絶する直前の記憶によって己の現状を反射的に把握したナチュルは、空中で体を回転させて着地の姿勢を取り、靴底で草の絨毯を抉りながら無事に着地を成功させた。
そして気絶した直前に味わった激痛に備えたが痛覚らしき痛覚は全く無く、見るも無残な姿になっているであろう自分の体を恐る恐る見下ろした、が。
「……なにも、ない……?」
完膚だった。小さな掠り傷すら残っていない。しかし、彼女の記憶を裏づけるように、彼女が纏っていた着流しが爛れており、上半身ははだけ掛けたボロボロの下着だけの状態だった。
あまりに不可解な現状に柳眉を顰めたナチュルだったが、長く尖った耳が捉えたおぞましい咆哮に意識を前方に向けた。
すぐに木々の間を食い破るようにして花の群れが姿を表した。気絶したナチュルだったが冒険者として─薙刀へ対する愛が深いためかもしれない─己の得物を硬く握り締めていたため、直ちに八相の構えを取った。
しかし。
『アアァァァ────!?!?』
嫌悪しか喚起しない花は生え渡る牙から粘液を咆哮と共に撒き散らし、遂に噛み付こうとしたその瞬間、背筋が凍るほど正確に垂直の一閃が花の脳天から突き抜けた。
瞬きも許されない刹那、花はぼろぼろと黒い灰へ返り、積もった塵の中に不気味な極彩色を放つ大きな魔石が綺麗に真っ二つに断ち切られていた。
そして、花の背後に隠れていたレイナの姿が露になる。何で逃げなかったの、という言葉を彼女の理性が許さなかった。
自分の瞳とあったレイナの瞳が、あまりにも静かだったために。底まで見えそうなほど澄み渡った湖を覗き込んだような、言い様のない何かが言及どころか身動きすら許さなかったのだ。
全身を鎖で雁字搦めにされたように動けなくなったナチュルの眼前のレイナに、再び魔力を感知した花たちが一斉に振り向いた。が、しかし、花が振り向いている最中に音もなく動いたレイナは、ナチュルが気付いたときにはレイナの近くにいた花のすぐ傍に立っており、そう思ったときには薙刀が振り切られていた。
『────』
もはや断絶魔を与えることすら許されなかった。魔石ごと断ち切られた花の花弁が一気に枯れたかのように灰へ返り始めた頃にはもうレイナは次の標的に迫っていた。
『』
何で、何でレイナはあんなにも速く動けるんだ。ナチュルは呆然とする意識の中でようやくその疑問符を掲げることが出来た。しかし、一瞬後に自分が呈した疑問に自分が答えた。
無駄が無いのだ。あまりに淀みなく、あらゆる無駄を削いでいるため、化け物じみたステイタスが無くともLv.5相当、いや、それ以上の速度の移動を可能にしているのだ。
そして、薙刀に無理が掛かっていない。まるで自分の四肢のように、極自然と薙刀が走っているのだ。凄絶なほど滑らかに空気を薙ぎ続ける薙刀は、ナチュルの目には黄金に輝いて見えた。
自分の探していた黄金比は、目の前にあった。だが、レイナが振るう薙刀は自分が新米のときに作った駄作。過去の自分を殴りつけてやりたいくらい拙い出来であるはずの薙刀が、黄金比を奏でていた。
いや、違う、薙刀の黄金比は薙刀に無かったんだ。真に注目すべきは薙刀の使い手。その使い手が柄を握るだけで、どんな薙刀も黄金比となりうるものだった。
しかし、同時にナチュルは思った。その黄金比を手に入れるまでに、一体どれほどの努力が必要なのだろうかと。薙刀の軌跡を生み出すその腕に掛けられた途方もない試行錯誤と努力が垣間見え、ぞっとする意識。
そんなの、無理だ。どんなことをすれば、その努力を続けることが出来たんだ。そもそも、駆け出しの十三歳の少女では努力に費やす時間の絶対値が圧倒的に足りないはずだ。私が知る限り、史上で最も薙刀の黄金比に近づいた人物は一人しかいない。あの伝説の人を超えるほどの何かを、レイナは持っているのか。
目まぐるしく切り替わる疑問符に付いてこれなくなったナチュルはそこで思考を打ち切った。そして、その黄金比を目に焼き付けるためにレイナに意識を集中させた。
一輪と一輪の間を最短距離で駆け抜け、最短且つ最大の遠心力が乗せられた一撃を放ち、体を翻して掛ける。
途中で妨害に入る十を軽く超える触手の数々がその華奢な体に襲い掛かる。触手に包み込まれレイナの体が隠れた瞬間、何かが爆発したように蠕動する触手が内側から膨張し、一気に破裂、空中に緑の血潮をぶちまけるがレイナの衣服はおろか艶やかな黒髪に一滴たりともかからない。
はなから妨害なんて無かったように最短距離を突き進み、一閃。その繰り返しだった。
そして瞬きをしたころには、二十を超えていたはずの花たちは一匹残らず全て灰と割れた魔石に姿を変え、辺り一体に静けさを齎した。
ひゅん、と鋭く柄を振り血を払い落としたレイナと再び瞳が合う。だけど、そこには先ほどの深淵のような光は無く、清楚とした女の子の穏やかな光が戻っていた。ただし、少し気まずそうに焦点をずらしているが。
「地上に帰ったときに訳は全て話します。今はまだ、聞かないで下さい」
それでは帰りましょうか、と地面に三点着地した状態で固まっていたナチュルに、小さく白く細い腕が差し出される。
Lv.3に迫る力を持つ花の群れを全て一撃で葬った、Lv.1の少女の手。その掌から伝わってくる熱は温かく、少し儚げだった。
後書き
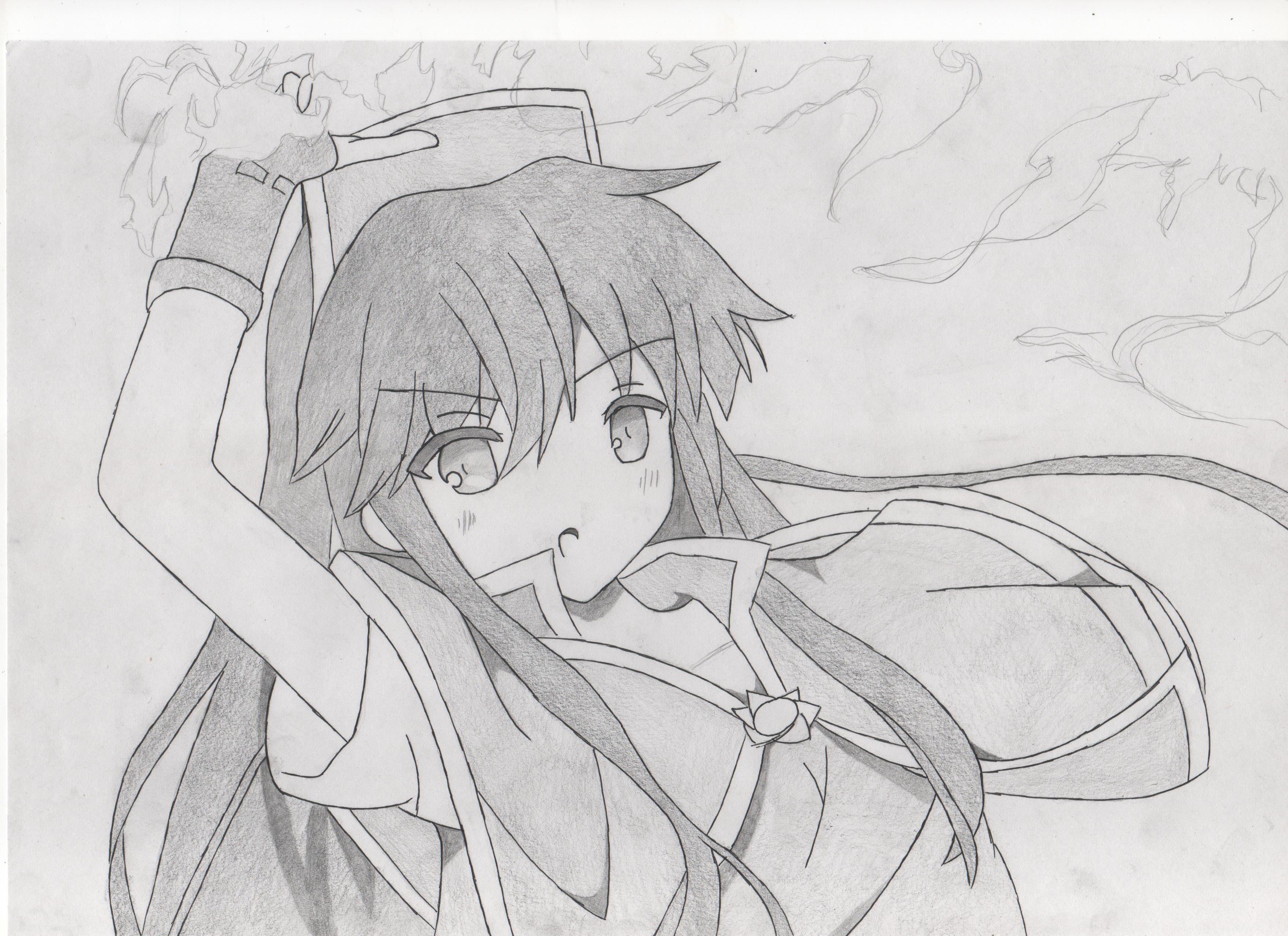
↑ファンファルレーゼを使うレイナたんです。
補足
【エクスプロージョン】
極短詠唱式にしては異様な火力を誇った魔法だったが、その制約、自身にも牙を向くことという代償があったからだ。薙刀を斬りつけながら発動することで、少量の精神力であれば柄の長さで爆風が届かず無害で済むが、大量の精神力を注ぎ込んでしまうと本文のようになってしまう。
『速攻魔法のくせに威力あって最高じゃん。ま、その代償は私たちの知るところじゃないけどね』と神様が嘲笑いそうな実態を持っていたのだった。
ちなみに素手で接触しながら発動すれば、術者の腕は呆気なく吹っ飛ぶのでくれぐれも注意をされたし。
ナチュルの大雑把な性格を上から押さえ込むような性質を孕んだ魔法は、ある意味に於いて最高の皮肉を呈していたというオチでした。
今回は第三者の視点に立ってレイナの戦闘描写をしてみました。今までは本人視点で行われていたため描写が妙に軽々しく「何かインパクトないな。本当に最強か? これ」と思われていたでしょうが、今回の描写でそれがどれほど狂っていたか解っていただけたのではと思っています。
途中に挟んだパラグラフの内容は、奉仕者クレアという意識から冒険者クレアに切り替わった、というものです。自分では理解できるかっこつけた描写をしたつもりですが、第三者の目ではかえって意味不明になってそうなので補足しました。
全て感想を見る:感想一覧
