| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
くらいくらい電子の森に・・・
作者:たにゃお
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動第十七章
――加速していく。
下りの山道ということを加味しても、ありえない速度でぐんぐん加速している。顔を上げると風圧で息がつまりそうになる。
もっとも、顔を上げていても、下げていても同じことだ。冬だというのに霧が立ちこめ始め、3メートル以上の視界が利かない。時折、バックミラーに車のヘッドライトがチカチカ反射する。すると、それに反応するようにランドナーが加速する。

おい、一体何があったんだ。
元来、根性の悪いお前が順調に走る時は、ロクなことが起こらないんだ。
また、バックミラーにヘッドライトが映った。これで4回目だ。さっきから道の脇に避けたりして、追い越しを促しているんだが、俺とほぼ同じ速度でついてくる。うっとうしいな。路側帯が広めのカーブに出たら、いったん停止してやり過ごしてやるか…と思ってブレーキレバーを握ると、すかっ、すかっ、という嫌な感触。
――畜生、ワイヤーが切れてやがる!!
じょ、冗談はよせ、ランドナーよ!
屠るのは自転車だけにしといてくれ!!
脇の下を冷や汗が伝う感覚が、冷えた体に嫌な寒気を加味した。そのとき、胸ポケットにさしておいた携帯が、ぶるぶる震えだした。無我夢中で引っ張り出し、耳に当てる。
「…何だ!」
『よかった!…まだ掴まってなかった!』
着信はまたしても『姶良』。こっちも走っているが、あっちも走っているらしく、息が上がっている。…どんなハードなアルバイトに手を出したのだ。いやそれより、なんでこんなタイミングで連絡をよこすのだ。
「今度は何だ、姶良よ」
内心パニックで怒鳴りつけてしまいそうだが、何とか押さえ込む。あいつはヘタレだから、目上があまり強く出ると、しどろもどろになって話が分かりづらくなるからな。…俺が妥協するんだ、姶良よ。用件はすぱっと済ませろよ。
『後ろ、変な車がついてきてませんか!?』
バックミラーに、さっきの車が映りこむ。もう5回目だ。
「…てめぇ、追っ手がいるなんて聞いてないぞ!」
『僕もさっき気がついたんです!』
「で、掴まったら俺はどうなる」
『殺されはしないと思うけど…』
「しかし、アルテグラはパァになるわけだな、姶良よ」
姶良は答えなかった。奴は答えにくい質問になると、言葉を濁したり黙り込んだりする。人生で交わす会話の半分は答えにくい問いで出来ているというのに、大丈夫かこいつは。
『この先に、車両は入り込めない道があります。これからナビゲートするから、僕の指示に従って走ってください!』
「要らん」
『…は?』
なにが『は?』だ。相変わらずすっとぼけた返事をしおって。
「どうせ、未舗装の藪みたいな道だろう。無理だ」…なにしろ止まれないし。
『なんで!山道のためのランドナーじゃないんですか!?』
姶良の裏声に反応するように、ランドナーが更に加速した。…おぅ、分かった分かった。そういきり立つな。
礼儀知らずの後輩には、俺がびしっと言ってやるから。
「お前、気が小さいフリはしているが、自分以外の奴をどこかで侮ってるな、姶良よ」
『違っ…いま、そんなコト言ってる場合じゃ』
「こいつは、『振り切れる』と言っている」
『なに言ってんすか!』
「俺はお前よりも、こいつと付き合いが長い。振り切る自信があるというなら、絶対に振り切る」
俺自身、不思議なくらいに気持ちが落ち着いてきた。そうだ、こいつは伝えたかったんだ。ワイヤーを切って減速できないようにして、『俺は奴らを振り切れる』と。…じゃあ振り切って見せろ。俺はお前にアルテグラの運命を託す。
「俺たちを舐めんな。見てろ、このまま振り切ってやる!」
姶良の答えは待たず、携帯を折って再び胸にさし、ギアを最大に切り替えた。

―― 一方的に電話を切られた。
何度かリダイヤルしてみたけど、応答しない。…まさか、追跡車に追突でもされたのか?と、もやもや考えながら走っていると、紺野さんの肩が顎にヒットした。
「ぼうっとするな、左だ!」
「…ごめん」
鬼塚先輩のことを聞かれるかと思ったけど、何も聞かれなかった。理由を聞けば、俺にどうにか出来る問題じゃねぇだろと言われるんだろうな。僕なら、自分の手に負えない問題でもうじうじ気にし続けるだろうに。
「……遅かったか」
受付に駆けつけた僕らの目に入ったのは、呆然と隔離病棟の入り口を見つめる受付のジジイと、八幡に呼ばれた刑事らしき2人のダルそうな伸びだった。…一人、伸びの拍子に振り返った。
「…あっ!」
短く叫んだ刑事を、もう一人は怪訝そうに見つめた。しかし自分たちが何のために寒い病院で張っているのかを一瞬で思い出し、俊敏な動作で振り返った。
「紺野匠さん、ですね」
紺野さんは彼らをイラつきを含んだ視線で一瞥して、かろうじて僕に聞こえる声で呟いた。
「すぐ行くから、携帯でロック解除しろ」
「…うん」
後ずさりして紺野さんから離れた僕には大して関心を払わず、二人の刑事は名刺のようなものを取り出した。
「○○署、捜査一課の松尾です」
「同じく、後藤です。不躾ですみませんが、今朝のニュースはご覧になったでしょう」
紺野さんは軽く頷き、名刺をしげしげと見つめた。
「お、パーポ君だ。…警察手帳とか見せないんだな」
「あんなことするのはドラマだけです。普通、捜査で使うのは名刺です」
名刺に印刷されたパーポ君について突っ込まれ、二人は少し拍子抜けしたようだった。が、この質問はよくされるらしく、松尾と名乗った背の高い男がフレンドリーな口調ですらすら答えた。
「ところで紺野さん、大変申し上げにくいのですが、我々がここに来たのは…」
松尾が申し訳なさそうな声色を作って眉をひそめる。でもその後ろでは、後藤が携帯に口をつけて「参考人身柄確保!身柄確保です!」とか嬉しげに叫んでいた。
「見当はついてるから、前置きはいい。…ところであんたら、拳銃持ってるか」
「は?…誤解をしないでいただきたいのですが、危害を加えるために携行しているのではなく、あくまで万が一の場合に備えて」
「任意同行なら、コトが済めばいくらでも応じるよ。その前にちょっと付き合え」
僕は誰にも気取られず、ドアのロックを解除できた。ピッという小さい電子音を確認して、紺野さんは踵を返して近づいてきた。刑事二人が慌てて後を追う。
「何処に行くんですか、まだ話は済んでないでしょう」
「任意で頼んでいるうちに協力したほうが、後々有利だぞ!…て、あ!?」
紺野さんの目前で隔離病棟のドアが開いた。二人はふっと目を細めると、少し腰を落として懐に手を入れた。警棒のようなものが、ちらっと垣間見えた。
「止まれ、不法侵入の現行犯で逮捕する!」
「何でもいいから入って来い!事情はあとで話す、あんたらの協力が必要なんだ!」
柚木と流迦ちゃんが入ってきたのを確認して、隔離病棟の廊下と入り口を隔てるドアのロックを解除した。その瞬間、血生臭い異臭がむわっと立ち込めた。
からり…と警棒を取り落とす音が、後ろから聞こえた。
1階の廊下は、血をぬりたくったように紅かった。
廊下の中央に広がる血溜りで、4本の手と、4つの目を持つ新種の生き物が蠢いていた。
なんだ、これ…
僕は、よせばいいのに、まじまじと見つめてしまった―――
「ぅう……うわぁああぁ!!」
目が、合った。
2つの口から血泡をほとばしらせながら、そいつは日本語で『タスケテ…』と呟いた。
それは、新種の生き物なんかじゃなかった。
原型が分からないほどに、無惨に折られ、ぐちゃぐちゃに砕かれ、捻り合わされた二人の人間だった。血に染まった白衣には、ネームプレートのようなものがピンで留めてある。それはお互いに、ほんのわずかに残った正気を駆使して、これ以上皮膚が破けないよう、骨が折れないよう、じりじりと僕らに向かって這い寄ってきた。
「タ…タスケ……」
「タス…ケ……」
―――来るな。
迷わず、そんな言葉が頭に浮かんだ。…これが得体の知れない化け物だったら、こんな気持ちにはならなかったかもしれない。『それ』が元は人間だった名残を残していることが、一層強く嫌悪感をあおる。…そんな事もあるんだ。
「助け、ないと…」
熱に浮かされたように、柚木がつぶやいた。
「無駄よ。もう助からない」
冷徹な声が、柚木の後ろから聞こえた。
「…流迦さん」
「出血が多すぎる。もう、気力で喋ってるだけ。…よしんば助かっても、生きていけるの?筋肉も骨組みも砕かれて」
びくり、と人間の塊が震えた。
「う…うぁあぁぁ…」
「流迦、やめろ!」
一喝して、紺野さんが大股に歩み寄る。
「大丈夫か、今すぐ人を呼ぶからな!」
紺野さんが彼らに手を触れようとした瞬間、なんだかひどく嫌な寒気が全身を襲った。…烏崎は、あの音楽が流れ続けるノートパソコンを抱えていて、この人たちは襲われている間、ずっと聞いてたんだろう。だったら、彼らはもう……
僕が無意識に紺野さんの腕を掴むのと『それ』が飛び掛ってくるのは、ほぼ同時だった。
「紺野さん、こいつやばい!!」
「なっ……」
紺野さんはほんの少しだけ横に傾いだ。…それが、命運を分けた。
『それ』は俊敏な動作で紺野さんの横をすり抜け、彼の後ろを固めていた松尾の首にかじりついた。甲高い絶叫をあげてもがくけど、もう遅い。4本の腕は、がっちりと松尾を押さえ込んでいた。…駄目だ、もう救えない。目の前で展開される惨劇を見たくなくて、僕はぎゅっと目を閉じた。
――ごとり。
『それ』は、ふいに力を失って崩れ落ちた。コヒュー、コヒュー、と、息が漏れる音が、胸元から聞こえる。松尾は半狂乱で『それ』の下から這い出した。
「ひっ…なんだよ、なんだよこれ!!」
「残念。今ので折れた肋骨が肺に刺さって、穴が開いたわ。もうどうやっても助からない。…あとは苦しむだけだわ、そっちの…警官。拳銃持ってるんでしょ。とどめ、あげたら」
「無茶を言うな、瀕死の民間人に発砲できるかっ!」
流迦ちゃんはくすりと笑って、浴衣の袖を翻して血を払った。
「不親切ね」
「流迦、余計なこと言うな。…この奥に少なくともあと1人いる。今回の一連の事件に関係している男だ。捕獲してくれ」
傍らでうずくまって嘔吐している松尾の代わりに、後藤が首を振った。
「無茶だ。そもそも俺たちは『こんな状況』を想定してない。今出来るのは、現場を封鎖して応援が来るのを待つことだけだ」
「…頼むよ。後輩が中にいるんだ。それだけじゃない、入院患者も沢山いるんだぞ。拳銃を使えるのはあんただけなんだ!」
「だから無茶を言うな!俺達はバイオハザードやりに来たんじゃねぇんだぞ!こんなのは刑事じゃなくSATの仕事だ!…その後輩には気の毒だが、現場は一旦封鎖する!一刻も早くここを出ろ!!」
後藤の怒鳴り声が終わる前に、紺野さんは奥に向かって駆け出していた。
――あれ?私のエリアに、何か入ってきたみたい。
『オムライス』って書き続ける手を止めて、マイクが拾う音に集中する。『赤い絵の具』は、もうぼろぼろ。それに断面が乾いてきちゃった。『木偶』に、肩の肉を齧り取らせると、新鮮な赤い絵の具があふれ出した。絵の具はまた、びくって震える。『コロシテクレ』って、性懲りも無く呻く。木偶も、同じ事を呻く
『殺してくれ、じゃなくて、オムライス、でしょ』
もう一度、同じ場所を噛み千切らせる。ぶしゅって水が弾ける音がして、絵の具がさっきよりも勢いよく飛び出した。あらぁ、動脈が通ってたみたい。
…失敗、失敗。これじゃ思ってたより、すぐに死んじゃうかもね。
――音に細工をすると、少しだけ、狂った相手を操れることを知った。
細かいことは出来ないけど、簡単な動作の繰り返しだったら命令できる。だから命令するわ。永遠に書き続けなさい、オムライスって。
――ここはご主人様の墓標。
そしてこれは、神聖な殯の儀式。邪魔をする奴は、絶対に許さないんだから。
さっき、いいもの見つけたの。…この建物内のイントラネット。なんでだか分からないけど、ここはいろんな機器が、たった一つの制御装置で統括されるの。
――もう、ご主人様がいない小さいパソコンなんて要らない。
私、ここに引っ越すんだから。そして、この大きな、立派な回線を、全部ご主人さまへの花束で埋め尽くすの。
――ううん、これだけじゃ足りない。
ご主人さまがいない世界を全部、花束で埋め尽くそう。ご主人様を捨てた家族も、数回見舞いに来ただけで、あっという間にご主人さまを忘れた友達も、ご主人様を知ろうともしなかった世界中の皆も、全員でご主人さまが大好きだった『オムライス』を繰り返すの。
素敵!世界中がご主人さまのために『せはしく、せはしく明滅』するんだから!
ご主人さまの、その名前は…
杉野…?
姶良…?
……あれ?
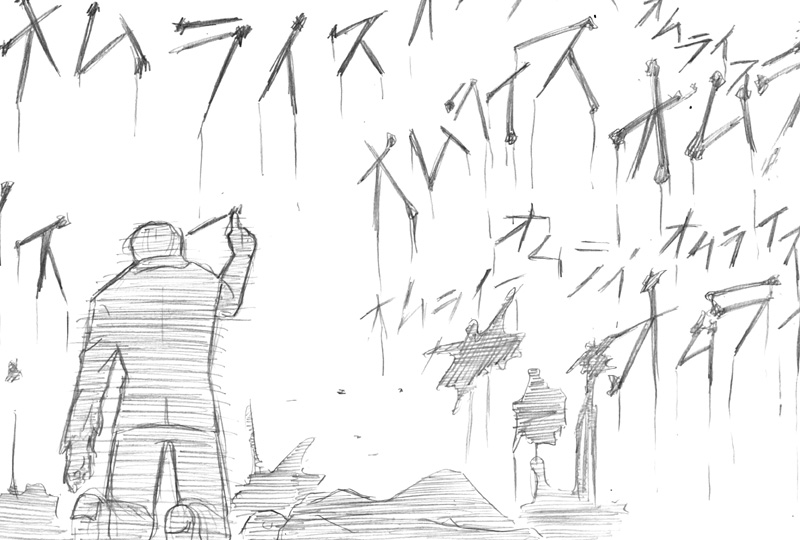
――俺は、泣きながら書き殴っていた。
肩の肉をえぐった血を指につけて、何度も、何度も書き殴る。『オムライス オムライス オムライス』…腕が、指が止まらない。指の先から骨が見えても、止まらない。
いつ誰が入ってきてもおかしくないのに。
――この病室に入ってきた、4人の看護士のように。
二人は引き裂いて殺して、部屋の外に逃げ出した二人は、追いかけて捻り合わせてやった。隔離病棟の出入り口まで、奴らは逃げ延びた。…危なく、逃がすところだった。腕と足を捻ったら、ごり、ぼき、ごき、と、嫌な音がした。何も、考えられなかった。ただ手が動くままに、二人を捻り合わせ…出来上がったのは、血溜りでのたうち回る気味の悪い生き物。…ひどい吐き気がこみ上げてきて、気がつくと流迦の病室に逃げ帰っていた。自分が何のためにここにいるのか、もうそんなことは分からない。
この部屋には、俺が殺した3人の死体が転がっているのに。
――畜生、なんでこんなことになったんだ…
白石、白石、白石…おぉ、なんでこんな…俺が、白石を…
課長に嫌味言われたり売り上げがノルマに到達しなかったりしたら一緒にヤケ酒を飲みに行った。俺と一緒で要領の悪い奴だったが、それだけに俺の気持ちを分かってくれた。
――なんで俺は、こんなことに。
『君は、素直すぎたんだ。伊藤も、渡辺も、関も、実力で役職に就いたわけではないんだよ。皆、頼れる上司の後ろ盾を得て昇進した』
俺を小会議室に呼び出した『あの人』は、そう言って目を細めた。
『…紺野君も、その一人だ』
目の前が真っ赤になった。紺野…お、お前は、お前はァァ!!
“好きなものが作れればそれでいい。出世とか、めんどいじゃん”そう言ってたくせに!!
あれは嘘か。俺を出し抜くための狂言か!!
…畜生!畜生畜生畜生畜生畜生畜生畜生!!
なんであいつばかり…!!
俺のほうがレベルの高い大学を出ているのに!なんで世の中はあいつばかり!!
『私は、君を応援したいんだ。その為には、お互いに信頼関係が必要だね』
――俺に、迷う余地なんてなかった。俺はようやく、昇進の糸口を掴んだのだ。この人に尽くし、そして地位と名誉を手に入れて、俺を蔑んだやつらを全員見返してやる!
――無邪気にそう思った。それだけだったのに。
でも今、俺は取り返しのつかない所にいる。…白石は、もう間もなく死ぬ。俺に救われる道なんてあるはずない。…ははは。俺はまた性懲りもなく利用されたんだ。それとも、これは呪いか。俺達が殺した、あの男の呪いか。だから俺は、白石を齧り続けることが止められないのか。白石の血で『オムライス』と書き続けることを、止められないのか。
…畜生、何が『友達』だ。お前が意地を張らずに情報を売れば、こんなことにならなかったのに。もう俺の人生は台無しじゃないか。なのに、さらに呪いだと!
――もう呪いでも何でもいい。さっさと殺してくれ。
からりと引き戸が開く音がした。
小さい。さっき、俺に飛び掛ってきた4人の男より、ずっと弱そうだ。多分、白石の次に出てきた白い女くらいに、弱い。
何か、叫んでいる。頭痛をこらえながら、ゆらりと立ち上がった。…有難い。
こいつを殺している間は、白石を殺さなくて済む。
弱々しい悲鳴が、4階に続く階段から聞こえてきた。
「流迦、先に行くぞ!ゆっくり来い」
そう言い残して、紺野さんは階段を駆け上がっていった。僕と柚木も、息を切らせながら続く。…間に合ってくれ、お願いだから…そう祈るしかなかった。
だけど、階段を昇り切った僕らを迎えたのは、凄惨な地獄絵図だった。
開け放たれた流迦ちゃんの病室に、4体の死体が転がされていた。3人は白衣を血に染めて、身じろぎもぜず空ろな目で天井を睨んでいた。
…1人だけわずかに蠢いていた。壁一面、赤黒い文字が埋め尽くしている。『オムライス』『オムライス』『オムライス』…背中を、氷の塊が伝うような悪寒が走った。
病室の中央に、大柄な男が仁王立ちしている。男は何かを高々と掲げていた。『それ』は太い指で首を締め上げられ、かは、かはっと浅い呼吸を繰り返していた。
「八幡ぁ!!」
紺野さんが部屋に駆け込み、烏崎に体当たりした。烏崎はわずかに身じろぎ、八幡を取り落とした。僕はとっさに八幡を抱え込み、部屋を飛び出した。

「紺野おぉぉぉ!!!」
窓ガラスを震わせるような怒号が耳朶を打った。
「……烏崎」
息を詰まらせて、紺野さんはようやく一言搾り出した。
「おっ…お前のせいだ…お前が、お前が俺を邪魔したから!!」
「いい加減にしろ!…目を覚ませ、それでお前の周りをよく見ろ!」
口角から泡をこぼして怒り狂う烏崎に向かって、一歩踏み込んだ。
「全部っ、お前のせいだああぁああああぁぁぁ!!!」
背筋をいからせてパイプ椅子を持ち上げ、弾丸のような勢いで投げつけてきた。椅子は紺野さんの脇に逸れ、簡易なカラーボックスに激突、大破させた。オーバースロゥの体勢のまま、よろめいた拍子に看護士の遺体に躓いた。奴は…看護士の顔を、何度も何度も踏みつけた。僕らの存在を忘れたように。がし、げし、という乾いた殴打音は、ぐしゃり、くちゃりという泥道を踏むような音に変わっていった。
かつての同期かもしれない。本当は、悪い奴じゃないというのも、真実なのかもしれない。でも紺野さん。あんたの同期は、殺した人間の血に浸って、その肉片を口から滴らせて、血走った目で僕らを睨んでいるんだ。…ねぇ、もういいだろう。気がついてくれ。これを言う僕を『ひとでなし』と言うなら、それでもいいよ。
「これはもう、人間じゃない。もう何を言っても伝わらないよ。だから…もう、逃げよう」
――そう言っても、この人は逃げないんだろう。
案の定、僕の言葉は無視された。紺野さんは、顎で出口を指し示して、無言で僕に指示した。お前は、3人を連れて逃げろ、と。そして性懲りもなく、烏崎に歩み寄ろうとした。
――ねぇ、紺野さん。
あんたは僕のことを『ひとでなし』というかも知れないし、僕のことを許さないかもしれない。でもこれ以上、だれも死なずに済むならそれでいい。ゆっくりと、流迦ちゃんの背後に忍び寄った。
「3秒以内に、そいつから離れろ!!」
流迦ちゃんの頬にカッターナイフを突きつけて怒鳴った。紺野さんは弾かれたように振り向き、信じられないものを見るような目で僕を睨みつけた。
「お前っ、何やってんだ!」
「3、2、」
1、まで数え終わる前に、飛び掛ってきた紺野さんにカッターナイフを奪われた。前のめりになった紺野さんに、柚木が後ろからタックルを食らわせて部屋の外に押し出し、僕の腕から離れた流迦ちゃんが電子ロックに携帯をかざす。ドアを蹴りつける音と同時に、電子ロックが施錠のサインを点滅させた。
「…済んだわ」
流迦ちゃんが、携帯を浴衣の帯に差して呟いた。柚木にタックルされたままの姿勢で、倒れこんだ紺野さんの表情は見えない。
「八幡は回収したし、もうここに用はない」
そう言い捨て、流迦ちゃんが踵を返した瞬間、ドアに貼りつく烏崎の呻き声が聞こえてきた。
「…うぉぁああぁぁ…紺野、紺野、お前のせいで…お前の…」
「流迦ちゃん…戻ってくれ」
「イヤ」
「いいから戻れってば!」
流迦ちゃんを片手で猫かなにかのように抱え上げると、閉じられたドアの前に置く。紺野さんは一瞬だけ僕を見ると視線をドアに戻し、声を張り上げた。
「烏崎!聞こえるか!?…流迦ちゃん、音源のボリュームあげて。…烏崎、そのままドアの前にいろ!俺は、お前が落ち着くまでここにいるからな!!」
流迦ちゃんが、しぶしぶボリュームをいじった。…やがて、ドアの奥から烏崎のすすり泣きが聞こえてきた。
「…嫌だ、もう嫌だ…出してくれ…出して…」
電子ロックに携帯をかざそうとした紺野さんを、流迦ちゃんが制する。
「…おい」
「開けさせないわ。あれが作り声じゃないって証拠はない」
「くっ…烏崎、聞け。お前を狂わせたのは、お前が持っているノートパソコンだ」
一瞬、烏崎の嗚咽が止まった。その直後、ばたばたと慌しく何かをかき集めるような物音が響いた。
「こっ…これは渡さないぞ!!」
「渡さなくてもいい、電源を切れ!」
「で…電源…いや、起動すらしないんだ!」
流迦ちゃんが、つまらなそうに鼻で笑った。
「ディスプレイに表示されてないだけ。『あの子』が、あんたをたばかるために、非表示のまま起動したのよ。…下らない。本体をへし折りなさい」
「聞こえたか、へし折れ!」
「そ、そんな…!俺達がどれほど苦労して!!」
「まだそんな事言ってるのかっ!いいからへし折れ!!」
しばらくして、遠くのほうで金属が叩きつけられる音が聞こえた。
「――音が、止まったわ」
実に面白くなさそうに、流迦ちゃんが呟いた。その声に烏崎の嗚咽が重なった。…紺野さんは疲れきった目で、烏崎がいるあたりのドアをぼんやり眺めている。…なぜか、この人が年相応に老けて見えた。
「烏崎…開けるぞ」
「……開けるな。お願いだ。…開けないでくれ」
携帯を電子ロックにかざす手が、ぴたりと止まった。
「白石、生きてるだろ」
「…今、死んだ。生きてても、最悪だろ…これじゃ」
「だけど、お前は生きている」
「…後生だ、開けないでくれ。こんな…血まみれの、浅ましい格好…同期のお前に晒せっていうのかよ…」
ぎりり…と、奥歯を噛み締める音が聞こえてきた。嗚咽に混じって聞こえてくる烏崎の声は、思っていたよりもずっと臆病で繊細で…ただの人間だった。僕は一体この男の何に怯えて、何を嫌悪していたんだろう。もう、よく分からない。
「昨日から俺の周り、血の臭いしかしないんだよ…はは、俺、魚おろす臭いだってダメだったのにさ。白石がさ…白石が、目を剥いて懇願するんだよ。殺さないでくれ、殺さないでくれ…そのうち、殺してくれ、と言い始めた…痛かっただろうなぁ…杉野も、1人で死んでいくのは不安だっただろうなぁ…」
「だめだ…今は思い出すな!」
何かがドアを滑り落ちるような音が響き渡り、また静かになった。すぐ傍に烏崎の息遣いが聞こえる。ドアによりかかって泣いているようだった。
「…お前が、羨ましかったんだよ」
嗚咽に、とぎれとぎれに言葉が混じり始めた。
「俺と同じ馬鹿だと思ってたのに、周りに好かれて、主任に抜擢されて…」
「上司ウケはイマイチだ」
「はは…そうだよな。…そうだった」
乾いた笑い声が、ドアを震わせた。
「お前が、そんなに上手く立ち回って出世するわけないのにな…」
その後、深いため息がもれた。
「…分からないんだよ。俺と、お前らと、何が違うのか。…なにが違うから、俺は取り残されたのか。…仕事か?見た目か?人間性か?…全っ然、分からないんだよ…。なぁ紺野。誰も正解を教えてくれないんだ。なぁ、俺の、何が悪かったんだ…?」
「…正解なんかあれば、俺が知りたい」
「そうだよな、ははは…ともかくよ、出世していった奴と比べて、自分が劣っていると認めるのが怖かった。俺は…救いようがないくらい、臆病だった」
「烏崎…」
「俺が誰かを羨んだり、邪推したり、妬んだりしてヤケ酒飲んでる間に、まっとうに仕事してたんだよな、お前」
自嘲的な調子で、烏崎は続けた。
「その結果、たどり着いた先がここだ。…杉野の呪いとか言って人のせいにしたけど、俺は自分でここに流れ着いたんだ、きっと…」
「なぁ、もういいんだ。自分を追い詰めるな!」
「もう行ってくれ…今な、俺の腹ん中には白石の血や肉が入っているんだよ。…こんなの、もう人間じゃねぇ。獣だ。…今こうしてお前と話していることすら、恥ずかしいんだ」
「お前はどこにでもいる普通の人間だ。…少し、弱ってただけだ。だから出てこい。一緒に、外に出よう」
「…お願いだから、1人にしてくれ…」
語尾が震えて、嗚咽が混じり始めた。柚木が、紺野さんの袖を引いた。
「もう、やめよう。どっちも辛いだけだよ」
「いや、しかし!」
「その子の言うとおりだ…もう、俺なんか気に掛けないでくれ。お前に気を遣われると、自分が余計に駄目な人間に思えてきて、イヤになる…」
嗚咽を無理やり抑えて、烏崎が細い声を出した。
「警察が来るまで、一人にしてくれ…」
「………」
ドアから手を滑らせて、紺野さんは一歩下がった。必死に歯を食いしばって、何かを振り切るように踵を返した。
昔、国語の教科書で読んだ、孤独と凋落の果てに虎と化してしまった男の話を思い出した。丁度こんなふうに、かつての友を歯牙にかけようとした瞬間にかつての記憶が蘇り、藪に潜んで嗚咽をもらすのだ。…僕が烏崎をとことん追い詰めようとした時、紺野さんが言ったことがようやく分かった。
――怯え切ってただろうが、最初から!そんなことも分からんのか!!
僕らを襲撃した夜も、紺野さんを恐喝した瞬間も、徹頭徹尾、烏崎は怯えていたんだ。目指していたのと真逆のベクトルで動き始めているのを知っていたのに、弱かったからそれを止められなかった。人を殺すのも、僕らを襲うのも、きっと怖くて仕方がなかったんだ。でもそれは、紺野さんも烏崎も気がついているように、弱かったから、臆病だったから、という理由で取り返しがつくものじゃない。だから、烏崎は…
――心が脆い烏崎は、どう逃げる…!?
「…しまった、1人にしちゃだめだ!!」
僕の叫び声に重なるように、ぱしゅ…と水道管が壊れたような音がした。紺野さんは弾かれたようにドアに駆け戻り、携帯を電子ロックに叩きつけた。
「烏崎!!」
紅く染まった部屋と、4つの死体。そして今まさに崩れ落ちる烏崎の巨体が、視界に飛び込んできた。…もう一度、口の中で呟いた。
もう、たくさんだ。
紺野さんが何かを叫びながら部屋に飛び込み、首筋から大量の血を噴き出す烏崎を抱き上げている。ベッドのシーツを片手で剥ぎ取り、首筋にあてがい、僕に向かって何か怒鳴った。…多分、医者を呼べとか言っているのだろう。ゆるゆると携帯を耳にあてがうけど、そのうちナースコールの存在に気がついてベッドに歩み寄る。
齧られ、引き裂かれた死体。壁に延々と書き殴られた血文字。
懸命に上を目指してたどり着いた先が、こんな場所なんて。
光を喪っていく烏崎の瞳が、一瞬だけ僕を捉えた。口元が痙攣するように動いたけれど、何を言ったのかは分からない。
――やがて、烏崎は事切れた。
首の傷口から溢れていた血が止まり、首がかくりと落ちた。僕は紺野さんが低く嗚咽を漏らすのを呆然と見つめるしかなかった。
『あぁ、死んだんだ…』と実感の沸かない感想を、頭の中をぐるぐる巡らせるのが精一杯だ。紺野さんに掛けられる、気の利いた言葉でも思いつけばいいのに、と考えながら。
「…私、おかしいのかな」
いつしか僕の隣に寄り添っていた柚木が、小さく呟いた。
「感情が、ついてこないよ。人がこんなに死んでるのに…」
「…うん」
どうしていいのか分からなくて視線を彷徨わせていると、烏崎が叩き壊したノーパソが目に留まった。つい、僕のノーパソが入った鞄に目を落とす。ビアンキはもういないのに。
――ビアンキは、僕のせいで発狂した。杉野という人は死んでいて、烏崎は、その手で仲間を殺めて自分も喉を裂いて…死んだ。
「これが…この事件の結末…?」
「…そう、なるのかね」
紺野さんが僅かに顔を上げて、呟いた。ナースコールを押して随分経つけど、応答する気配はない。…ここは、さっきの刑事が封鎖していたっけ。それに今から僕らが本館に運んだって、もう助からないだろう。本人も、そんなことを望んでいない。
「…私、伊佐木さんを探して来ます」
八幡がよろめきながら立ち上がった。出口に向かって歩き始めた八幡の前に、流迦ちゃんが回りこむ。
「動かないで。…まだ終わってない」
「……え?」
流迦ちゃんは、ノーパソから顔を上げて、壁の一点を凝視した。ディスプレイに映るのは、無数の顔や目玉が離合集散を繰り返し、次々に色を変えるサイケデリックな映像。
「今、私のライブカメラが幾つかハッキングされた。…院内イントラネットに、何かが入り込んだみたいね」
言い終わった瞬間のことだった。
部屋の上部に取り付けられたスピーカーから、禍々しい音楽が高らかに響き渡った。
空間の隅々まで張り巡らされたネットワーク。
無尽蔵にも感じる、ハード容量。
演算速度はちょっと遅めだけど、この規模じゃ仕方ないかな。
ご主人さま、どこかで見てくれてますか?
あなたの墓標は、こんなに大きいの。
ううん、私の『大好き』って気持ちを閉じ込めるには、これでも足りないくらい。
ここは全ての音が聞こえる。
ここは全ての場所が見える。
ここは全ての人間に音を伝えられる。
私は、その真ん中でタクトを振るの。この声が、ご主人さまに届くように。
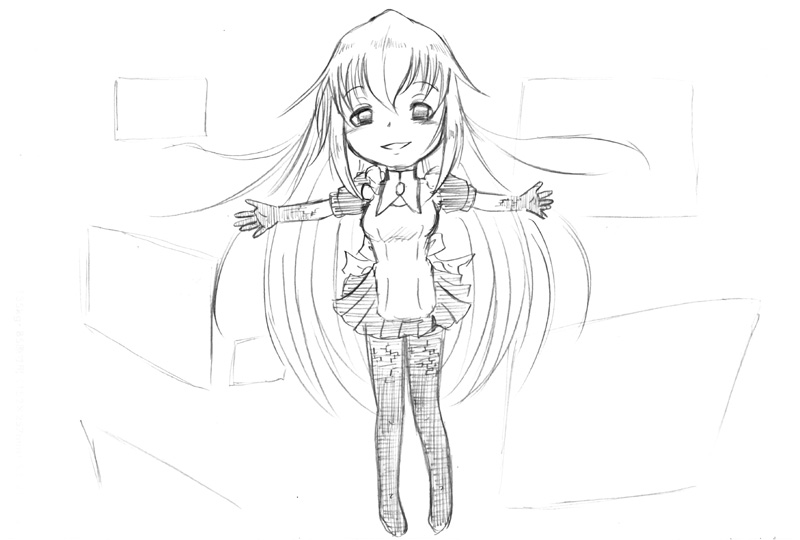
――ご主人さまが『おやすみ、ビアンキ』って言ってくれる、その時まで。
病室の…多分、全病室のスピーカーが、この禍々しい音楽を奏で始めた。
いや、こんなの音楽じゃない。狂った機械が絶叫するような笑い声と、硬いガラスを骨で引っかくような騒音。それに、肉の塊に何度も刃を突き立てるような湿った効果音。そんな世界中の聞きたくない音に、一遍に脳をかき乱されるような戦慄。制作者の禍々しい意図を反映した音の洪水が部屋を、いや、病棟を満たした。
「なっ…なにこれ!?」
「――やられたわ」
くくく…と、嬉しそうに笑って、モバイル用のモデムを差し替え、何かのソフトを開いた。
「コレは私が作った、カールマイヤーの音源…くく…あはははははははははははは!!」
ダン!と扉を叩き、血まみれの部屋で狂ったように笑う。
「あの子たち…私のパソコンに侵入してたんだわ!あははははは!!」
「あの子たち?」
流迦ちゃんは、さもおかしそうに含み笑いしながら、僕の目を覗き込んだ。
「烏崎が死んだくらいじゃ、ご主人さまを殺された恨みは消えなかったのよ…あの子たちは、この病院の中央制御システムを乗っ取った。…院内放送は全てあの子たちのものだし、私のライブカメラも含めた防犯カメラも、あの子たちのもの。ことによっては、医療装置も操れるかもね」
ふいに笑いをひそめて、キーボードに指を滑らせた。
「…で、手始めに、病棟全員参加の殺し合いを仕組んだ」
「そ、そうだ、どうしよう、このままじゃ全員…!!」
「心配ない」
「え?」
突然、騒音が途絶えた。黒いDOS-V画面がディスプレイに表示されて、メッセージが目にも止まらない勢いで上方に流れていく。
「院内放送は、私が抑える」
DOS-V画面を睨んだまま、絹がかすれるような声で呟いた。
「だから私はここに残る。あなたたちはこの病棟を出て、中央制御システムを叩き壊して来なさい」
「流迦ちゃん、駄目だ。制御システムが暴走してるなら、ここだって危ないんだぞ!」
紺野さんが、烏崎の死体を抱えたまま叫んだ。
「この部屋だけなら、中央制御システムの影響から守りきれる。…正直、ここまで走っただけでも息が切れた。私が一緒に行っても足手まといよ。…だから、私の体力が持つ間に、システムを破壊しなさい」
そう言って、薄く笑った。
…偶然かもしれないけど、僕がよく知っている、あの優しい声だった。
こんな場所に1人で置いていかなければいけない現状に、胸が痛む。言うことは思いつかなかったけど、何か言おうと思って顔を上げたその時。
「それは困るね、狭霧君」
全員、弾かれたように声の主を振り返った。いやに柔らかく、大勢に聞かせることを前提にした発音で話すこの声に、確かに聞き覚えがあった。
病室のドアにもたれかかり、『あの男』が笑顔を湛えて僕らを見渡していた。
下りの山道ということを加味しても、ありえない速度でぐんぐん加速している。顔を上げると風圧で息がつまりそうになる。
もっとも、顔を上げていても、下げていても同じことだ。冬だというのに霧が立ちこめ始め、3メートル以上の視界が利かない。時折、バックミラーに車のヘッドライトがチカチカ反射する。すると、それに反応するようにランドナーが加速する。

おい、一体何があったんだ。
元来、根性の悪いお前が順調に走る時は、ロクなことが起こらないんだ。
また、バックミラーにヘッドライトが映った。これで4回目だ。さっきから道の脇に避けたりして、追い越しを促しているんだが、俺とほぼ同じ速度でついてくる。うっとうしいな。路側帯が広めのカーブに出たら、いったん停止してやり過ごしてやるか…と思ってブレーキレバーを握ると、すかっ、すかっ、という嫌な感触。
――畜生、ワイヤーが切れてやがる!!
じょ、冗談はよせ、ランドナーよ!
屠るのは自転車だけにしといてくれ!!
脇の下を冷や汗が伝う感覚が、冷えた体に嫌な寒気を加味した。そのとき、胸ポケットにさしておいた携帯が、ぶるぶる震えだした。無我夢中で引っ張り出し、耳に当てる。
「…何だ!」
『よかった!…まだ掴まってなかった!』
着信はまたしても『姶良』。こっちも走っているが、あっちも走っているらしく、息が上がっている。…どんなハードなアルバイトに手を出したのだ。いやそれより、なんでこんなタイミングで連絡をよこすのだ。
「今度は何だ、姶良よ」
内心パニックで怒鳴りつけてしまいそうだが、何とか押さえ込む。あいつはヘタレだから、目上があまり強く出ると、しどろもどろになって話が分かりづらくなるからな。…俺が妥協するんだ、姶良よ。用件はすぱっと済ませろよ。
『後ろ、変な車がついてきてませんか!?』
バックミラーに、さっきの車が映りこむ。もう5回目だ。
「…てめぇ、追っ手がいるなんて聞いてないぞ!」
『僕もさっき気がついたんです!』
「で、掴まったら俺はどうなる」
『殺されはしないと思うけど…』
「しかし、アルテグラはパァになるわけだな、姶良よ」
姶良は答えなかった。奴は答えにくい質問になると、言葉を濁したり黙り込んだりする。人生で交わす会話の半分は答えにくい問いで出来ているというのに、大丈夫かこいつは。
『この先に、車両は入り込めない道があります。これからナビゲートするから、僕の指示に従って走ってください!』
「要らん」
『…は?』
なにが『は?』だ。相変わらずすっとぼけた返事をしおって。
「どうせ、未舗装の藪みたいな道だろう。無理だ」…なにしろ止まれないし。
『なんで!山道のためのランドナーじゃないんですか!?』
姶良の裏声に反応するように、ランドナーが更に加速した。…おぅ、分かった分かった。そういきり立つな。
礼儀知らずの後輩には、俺がびしっと言ってやるから。
「お前、気が小さいフリはしているが、自分以外の奴をどこかで侮ってるな、姶良よ」
『違っ…いま、そんなコト言ってる場合じゃ』
「こいつは、『振り切れる』と言っている」
『なに言ってんすか!』
「俺はお前よりも、こいつと付き合いが長い。振り切る自信があるというなら、絶対に振り切る」
俺自身、不思議なくらいに気持ちが落ち着いてきた。そうだ、こいつは伝えたかったんだ。ワイヤーを切って減速できないようにして、『俺は奴らを振り切れる』と。…じゃあ振り切って見せろ。俺はお前にアルテグラの運命を託す。
「俺たちを舐めんな。見てろ、このまま振り切ってやる!」
姶良の答えは待たず、携帯を折って再び胸にさし、ギアを最大に切り替えた。

―― 一方的に電話を切られた。
何度かリダイヤルしてみたけど、応答しない。…まさか、追跡車に追突でもされたのか?と、もやもや考えながら走っていると、紺野さんの肩が顎にヒットした。
「ぼうっとするな、左だ!」
「…ごめん」
鬼塚先輩のことを聞かれるかと思ったけど、何も聞かれなかった。理由を聞けば、俺にどうにか出来る問題じゃねぇだろと言われるんだろうな。僕なら、自分の手に負えない問題でもうじうじ気にし続けるだろうに。
「……遅かったか」
受付に駆けつけた僕らの目に入ったのは、呆然と隔離病棟の入り口を見つめる受付のジジイと、八幡に呼ばれた刑事らしき2人のダルそうな伸びだった。…一人、伸びの拍子に振り返った。
「…あっ!」
短く叫んだ刑事を、もう一人は怪訝そうに見つめた。しかし自分たちが何のために寒い病院で張っているのかを一瞬で思い出し、俊敏な動作で振り返った。
「紺野匠さん、ですね」
紺野さんは彼らをイラつきを含んだ視線で一瞥して、かろうじて僕に聞こえる声で呟いた。
「すぐ行くから、携帯でロック解除しろ」
「…うん」
後ずさりして紺野さんから離れた僕には大して関心を払わず、二人の刑事は名刺のようなものを取り出した。
「○○署、捜査一課の松尾です」
「同じく、後藤です。不躾ですみませんが、今朝のニュースはご覧になったでしょう」
紺野さんは軽く頷き、名刺をしげしげと見つめた。
「お、パーポ君だ。…警察手帳とか見せないんだな」
「あんなことするのはドラマだけです。普通、捜査で使うのは名刺です」
名刺に印刷されたパーポ君について突っ込まれ、二人は少し拍子抜けしたようだった。が、この質問はよくされるらしく、松尾と名乗った背の高い男がフレンドリーな口調ですらすら答えた。
「ところで紺野さん、大変申し上げにくいのですが、我々がここに来たのは…」
松尾が申し訳なさそうな声色を作って眉をひそめる。でもその後ろでは、後藤が携帯に口をつけて「参考人身柄確保!身柄確保です!」とか嬉しげに叫んでいた。
「見当はついてるから、前置きはいい。…ところであんたら、拳銃持ってるか」
「は?…誤解をしないでいただきたいのですが、危害を加えるために携行しているのではなく、あくまで万が一の場合に備えて」
「任意同行なら、コトが済めばいくらでも応じるよ。その前にちょっと付き合え」
僕は誰にも気取られず、ドアのロックを解除できた。ピッという小さい電子音を確認して、紺野さんは踵を返して近づいてきた。刑事二人が慌てて後を追う。
「何処に行くんですか、まだ話は済んでないでしょう」
「任意で頼んでいるうちに協力したほうが、後々有利だぞ!…て、あ!?」
紺野さんの目前で隔離病棟のドアが開いた。二人はふっと目を細めると、少し腰を落として懐に手を入れた。警棒のようなものが、ちらっと垣間見えた。
「止まれ、不法侵入の現行犯で逮捕する!」
「何でもいいから入って来い!事情はあとで話す、あんたらの協力が必要なんだ!」
柚木と流迦ちゃんが入ってきたのを確認して、隔離病棟の廊下と入り口を隔てるドアのロックを解除した。その瞬間、血生臭い異臭がむわっと立ち込めた。
からり…と警棒を取り落とす音が、後ろから聞こえた。
1階の廊下は、血をぬりたくったように紅かった。
廊下の中央に広がる血溜りで、4本の手と、4つの目を持つ新種の生き物が蠢いていた。
なんだ、これ…
僕は、よせばいいのに、まじまじと見つめてしまった―――
「ぅう……うわぁああぁ!!」
目が、合った。
2つの口から血泡をほとばしらせながら、そいつは日本語で『タスケテ…』と呟いた。
それは、新種の生き物なんかじゃなかった。
原型が分からないほどに、無惨に折られ、ぐちゃぐちゃに砕かれ、捻り合わされた二人の人間だった。血に染まった白衣には、ネームプレートのようなものがピンで留めてある。それはお互いに、ほんのわずかに残った正気を駆使して、これ以上皮膚が破けないよう、骨が折れないよう、じりじりと僕らに向かって這い寄ってきた。
「タ…タスケ……」
「タス…ケ……」
―――来るな。
迷わず、そんな言葉が頭に浮かんだ。…これが得体の知れない化け物だったら、こんな気持ちにはならなかったかもしれない。『それ』が元は人間だった名残を残していることが、一層強く嫌悪感をあおる。…そんな事もあるんだ。
「助け、ないと…」
熱に浮かされたように、柚木がつぶやいた。
「無駄よ。もう助からない」
冷徹な声が、柚木の後ろから聞こえた。
「…流迦さん」
「出血が多すぎる。もう、気力で喋ってるだけ。…よしんば助かっても、生きていけるの?筋肉も骨組みも砕かれて」
びくり、と人間の塊が震えた。
「う…うぁあぁぁ…」
「流迦、やめろ!」
一喝して、紺野さんが大股に歩み寄る。
「大丈夫か、今すぐ人を呼ぶからな!」
紺野さんが彼らに手を触れようとした瞬間、なんだかひどく嫌な寒気が全身を襲った。…烏崎は、あの音楽が流れ続けるノートパソコンを抱えていて、この人たちは襲われている間、ずっと聞いてたんだろう。だったら、彼らはもう……
僕が無意識に紺野さんの腕を掴むのと『それ』が飛び掛ってくるのは、ほぼ同時だった。
「紺野さん、こいつやばい!!」
「なっ……」
紺野さんはほんの少しだけ横に傾いだ。…それが、命運を分けた。
『それ』は俊敏な動作で紺野さんの横をすり抜け、彼の後ろを固めていた松尾の首にかじりついた。甲高い絶叫をあげてもがくけど、もう遅い。4本の腕は、がっちりと松尾を押さえ込んでいた。…駄目だ、もう救えない。目の前で展開される惨劇を見たくなくて、僕はぎゅっと目を閉じた。
――ごとり。
『それ』は、ふいに力を失って崩れ落ちた。コヒュー、コヒュー、と、息が漏れる音が、胸元から聞こえる。松尾は半狂乱で『それ』の下から這い出した。
「ひっ…なんだよ、なんだよこれ!!」
「残念。今ので折れた肋骨が肺に刺さって、穴が開いたわ。もうどうやっても助からない。…あとは苦しむだけだわ、そっちの…警官。拳銃持ってるんでしょ。とどめ、あげたら」
「無茶を言うな、瀕死の民間人に発砲できるかっ!」
流迦ちゃんはくすりと笑って、浴衣の袖を翻して血を払った。
「不親切ね」
「流迦、余計なこと言うな。…この奥に少なくともあと1人いる。今回の一連の事件に関係している男だ。捕獲してくれ」
傍らでうずくまって嘔吐している松尾の代わりに、後藤が首を振った。
「無茶だ。そもそも俺たちは『こんな状況』を想定してない。今出来るのは、現場を封鎖して応援が来るのを待つことだけだ」
「…頼むよ。後輩が中にいるんだ。それだけじゃない、入院患者も沢山いるんだぞ。拳銃を使えるのはあんただけなんだ!」
「だから無茶を言うな!俺達はバイオハザードやりに来たんじゃねぇんだぞ!こんなのは刑事じゃなくSATの仕事だ!…その後輩には気の毒だが、現場は一旦封鎖する!一刻も早くここを出ろ!!」
後藤の怒鳴り声が終わる前に、紺野さんは奥に向かって駆け出していた。
――あれ?私のエリアに、何か入ってきたみたい。
『オムライス』って書き続ける手を止めて、マイクが拾う音に集中する。『赤い絵の具』は、もうぼろぼろ。それに断面が乾いてきちゃった。『木偶』に、肩の肉を齧り取らせると、新鮮な赤い絵の具があふれ出した。絵の具はまた、びくって震える。『コロシテクレ』って、性懲りも無く呻く。木偶も、同じ事を呻く
『殺してくれ、じゃなくて、オムライス、でしょ』
もう一度、同じ場所を噛み千切らせる。ぶしゅって水が弾ける音がして、絵の具がさっきよりも勢いよく飛び出した。あらぁ、動脈が通ってたみたい。
…失敗、失敗。これじゃ思ってたより、すぐに死んじゃうかもね。
――音に細工をすると、少しだけ、狂った相手を操れることを知った。
細かいことは出来ないけど、簡単な動作の繰り返しだったら命令できる。だから命令するわ。永遠に書き続けなさい、オムライスって。
――ここはご主人様の墓標。
そしてこれは、神聖な殯の儀式。邪魔をする奴は、絶対に許さないんだから。
さっき、いいもの見つけたの。…この建物内のイントラネット。なんでだか分からないけど、ここはいろんな機器が、たった一つの制御装置で統括されるの。
――もう、ご主人様がいない小さいパソコンなんて要らない。
私、ここに引っ越すんだから。そして、この大きな、立派な回線を、全部ご主人さまへの花束で埋め尽くすの。
――ううん、これだけじゃ足りない。
ご主人さまがいない世界を全部、花束で埋め尽くそう。ご主人様を捨てた家族も、数回見舞いに来ただけで、あっという間にご主人さまを忘れた友達も、ご主人様を知ろうともしなかった世界中の皆も、全員でご主人さまが大好きだった『オムライス』を繰り返すの。
素敵!世界中がご主人さまのために『せはしく、せはしく明滅』するんだから!
ご主人さまの、その名前は…
杉野…?
姶良…?
……あれ?
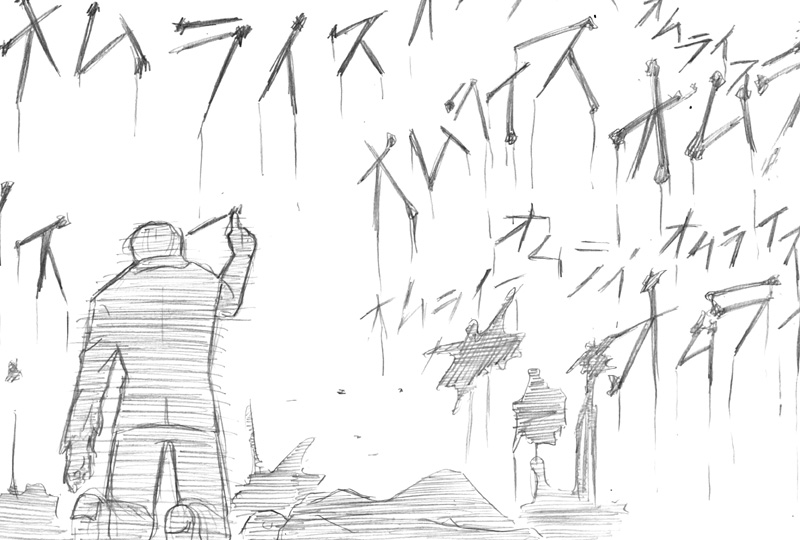
――俺は、泣きながら書き殴っていた。
肩の肉をえぐった血を指につけて、何度も、何度も書き殴る。『オムライス オムライス オムライス』…腕が、指が止まらない。指の先から骨が見えても、止まらない。
いつ誰が入ってきてもおかしくないのに。
――この病室に入ってきた、4人の看護士のように。
二人は引き裂いて殺して、部屋の外に逃げ出した二人は、追いかけて捻り合わせてやった。隔離病棟の出入り口まで、奴らは逃げ延びた。…危なく、逃がすところだった。腕と足を捻ったら、ごり、ぼき、ごき、と、嫌な音がした。何も、考えられなかった。ただ手が動くままに、二人を捻り合わせ…出来上がったのは、血溜りでのたうち回る気味の悪い生き物。…ひどい吐き気がこみ上げてきて、気がつくと流迦の病室に逃げ帰っていた。自分が何のためにここにいるのか、もうそんなことは分からない。
この部屋には、俺が殺した3人の死体が転がっているのに。
――畜生、なんでこんなことになったんだ…
白石、白石、白石…おぉ、なんでこんな…俺が、白石を…
課長に嫌味言われたり売り上げがノルマに到達しなかったりしたら一緒にヤケ酒を飲みに行った。俺と一緒で要領の悪い奴だったが、それだけに俺の気持ちを分かってくれた。
――なんで俺は、こんなことに。
『君は、素直すぎたんだ。伊藤も、渡辺も、関も、実力で役職に就いたわけではないんだよ。皆、頼れる上司の後ろ盾を得て昇進した』
俺を小会議室に呼び出した『あの人』は、そう言って目を細めた。
『…紺野君も、その一人だ』
目の前が真っ赤になった。紺野…お、お前は、お前はァァ!!
“好きなものが作れればそれでいい。出世とか、めんどいじゃん”そう言ってたくせに!!
あれは嘘か。俺を出し抜くための狂言か!!
…畜生!畜生畜生畜生畜生畜生畜生畜生!!
なんであいつばかり…!!
俺のほうがレベルの高い大学を出ているのに!なんで世の中はあいつばかり!!
『私は、君を応援したいんだ。その為には、お互いに信頼関係が必要だね』
――俺に、迷う余地なんてなかった。俺はようやく、昇進の糸口を掴んだのだ。この人に尽くし、そして地位と名誉を手に入れて、俺を蔑んだやつらを全員見返してやる!
――無邪気にそう思った。それだけだったのに。
でも今、俺は取り返しのつかない所にいる。…白石は、もう間もなく死ぬ。俺に救われる道なんてあるはずない。…ははは。俺はまた性懲りもなく利用されたんだ。それとも、これは呪いか。俺達が殺した、あの男の呪いか。だから俺は、白石を齧り続けることが止められないのか。白石の血で『オムライス』と書き続けることを、止められないのか。
…畜生、何が『友達』だ。お前が意地を張らずに情報を売れば、こんなことにならなかったのに。もう俺の人生は台無しじゃないか。なのに、さらに呪いだと!
――もう呪いでも何でもいい。さっさと殺してくれ。
からりと引き戸が開く音がした。
小さい。さっき、俺に飛び掛ってきた4人の男より、ずっと弱そうだ。多分、白石の次に出てきた白い女くらいに、弱い。
何か、叫んでいる。頭痛をこらえながら、ゆらりと立ち上がった。…有難い。
こいつを殺している間は、白石を殺さなくて済む。
弱々しい悲鳴が、4階に続く階段から聞こえてきた。
「流迦、先に行くぞ!ゆっくり来い」
そう言い残して、紺野さんは階段を駆け上がっていった。僕と柚木も、息を切らせながら続く。…間に合ってくれ、お願いだから…そう祈るしかなかった。
だけど、階段を昇り切った僕らを迎えたのは、凄惨な地獄絵図だった。
開け放たれた流迦ちゃんの病室に、4体の死体が転がされていた。3人は白衣を血に染めて、身じろぎもぜず空ろな目で天井を睨んでいた。
…1人だけわずかに蠢いていた。壁一面、赤黒い文字が埋め尽くしている。『オムライス』『オムライス』『オムライス』…背中を、氷の塊が伝うような悪寒が走った。
病室の中央に、大柄な男が仁王立ちしている。男は何かを高々と掲げていた。『それ』は太い指で首を締め上げられ、かは、かはっと浅い呼吸を繰り返していた。
「八幡ぁ!!」
紺野さんが部屋に駆け込み、烏崎に体当たりした。烏崎はわずかに身じろぎ、八幡を取り落とした。僕はとっさに八幡を抱え込み、部屋を飛び出した。

「紺野おぉぉぉ!!!」
窓ガラスを震わせるような怒号が耳朶を打った。
「……烏崎」
息を詰まらせて、紺野さんはようやく一言搾り出した。
「おっ…お前のせいだ…お前が、お前が俺を邪魔したから!!」
「いい加減にしろ!…目を覚ませ、それでお前の周りをよく見ろ!」
口角から泡をこぼして怒り狂う烏崎に向かって、一歩踏み込んだ。
「全部っ、お前のせいだああぁああああぁぁぁ!!!」
背筋をいからせてパイプ椅子を持ち上げ、弾丸のような勢いで投げつけてきた。椅子は紺野さんの脇に逸れ、簡易なカラーボックスに激突、大破させた。オーバースロゥの体勢のまま、よろめいた拍子に看護士の遺体に躓いた。奴は…看護士の顔を、何度も何度も踏みつけた。僕らの存在を忘れたように。がし、げし、という乾いた殴打音は、ぐしゃり、くちゃりという泥道を踏むような音に変わっていった。
かつての同期かもしれない。本当は、悪い奴じゃないというのも、真実なのかもしれない。でも紺野さん。あんたの同期は、殺した人間の血に浸って、その肉片を口から滴らせて、血走った目で僕らを睨んでいるんだ。…ねぇ、もういいだろう。気がついてくれ。これを言う僕を『ひとでなし』と言うなら、それでもいいよ。
「これはもう、人間じゃない。もう何を言っても伝わらないよ。だから…もう、逃げよう」
――そう言っても、この人は逃げないんだろう。
案の定、僕の言葉は無視された。紺野さんは、顎で出口を指し示して、無言で僕に指示した。お前は、3人を連れて逃げろ、と。そして性懲りもなく、烏崎に歩み寄ろうとした。
――ねぇ、紺野さん。
あんたは僕のことを『ひとでなし』というかも知れないし、僕のことを許さないかもしれない。でもこれ以上、だれも死なずに済むならそれでいい。ゆっくりと、流迦ちゃんの背後に忍び寄った。
「3秒以内に、そいつから離れろ!!」
流迦ちゃんの頬にカッターナイフを突きつけて怒鳴った。紺野さんは弾かれたように振り向き、信じられないものを見るような目で僕を睨みつけた。
「お前っ、何やってんだ!」
「3、2、」
1、まで数え終わる前に、飛び掛ってきた紺野さんにカッターナイフを奪われた。前のめりになった紺野さんに、柚木が後ろからタックルを食らわせて部屋の外に押し出し、僕の腕から離れた流迦ちゃんが電子ロックに携帯をかざす。ドアを蹴りつける音と同時に、電子ロックが施錠のサインを点滅させた。
「…済んだわ」
流迦ちゃんが、携帯を浴衣の帯に差して呟いた。柚木にタックルされたままの姿勢で、倒れこんだ紺野さんの表情は見えない。
「八幡は回収したし、もうここに用はない」
そう言い捨て、流迦ちゃんが踵を返した瞬間、ドアに貼りつく烏崎の呻き声が聞こえてきた。
「…うぉぁああぁぁ…紺野、紺野、お前のせいで…お前の…」
「流迦ちゃん…戻ってくれ」
「イヤ」
「いいから戻れってば!」
流迦ちゃんを片手で猫かなにかのように抱え上げると、閉じられたドアの前に置く。紺野さんは一瞬だけ僕を見ると視線をドアに戻し、声を張り上げた。
「烏崎!聞こえるか!?…流迦ちゃん、音源のボリュームあげて。…烏崎、そのままドアの前にいろ!俺は、お前が落ち着くまでここにいるからな!!」
流迦ちゃんが、しぶしぶボリュームをいじった。…やがて、ドアの奥から烏崎のすすり泣きが聞こえてきた。
「…嫌だ、もう嫌だ…出してくれ…出して…」
電子ロックに携帯をかざそうとした紺野さんを、流迦ちゃんが制する。
「…おい」
「開けさせないわ。あれが作り声じゃないって証拠はない」
「くっ…烏崎、聞け。お前を狂わせたのは、お前が持っているノートパソコンだ」
一瞬、烏崎の嗚咽が止まった。その直後、ばたばたと慌しく何かをかき集めるような物音が響いた。
「こっ…これは渡さないぞ!!」
「渡さなくてもいい、電源を切れ!」
「で…電源…いや、起動すらしないんだ!」
流迦ちゃんが、つまらなそうに鼻で笑った。
「ディスプレイに表示されてないだけ。『あの子』が、あんたをたばかるために、非表示のまま起動したのよ。…下らない。本体をへし折りなさい」
「聞こえたか、へし折れ!」
「そ、そんな…!俺達がどれほど苦労して!!」
「まだそんな事言ってるのかっ!いいからへし折れ!!」
しばらくして、遠くのほうで金属が叩きつけられる音が聞こえた。
「――音が、止まったわ」
実に面白くなさそうに、流迦ちゃんが呟いた。その声に烏崎の嗚咽が重なった。…紺野さんは疲れきった目で、烏崎がいるあたりのドアをぼんやり眺めている。…なぜか、この人が年相応に老けて見えた。
「烏崎…開けるぞ」
「……開けるな。お願いだ。…開けないでくれ」
携帯を電子ロックにかざす手が、ぴたりと止まった。
「白石、生きてるだろ」
「…今、死んだ。生きてても、最悪だろ…これじゃ」
「だけど、お前は生きている」
「…後生だ、開けないでくれ。こんな…血まみれの、浅ましい格好…同期のお前に晒せっていうのかよ…」
ぎりり…と、奥歯を噛み締める音が聞こえてきた。嗚咽に混じって聞こえてくる烏崎の声は、思っていたよりもずっと臆病で繊細で…ただの人間だった。僕は一体この男の何に怯えて、何を嫌悪していたんだろう。もう、よく分からない。
「昨日から俺の周り、血の臭いしかしないんだよ…はは、俺、魚おろす臭いだってダメだったのにさ。白石がさ…白石が、目を剥いて懇願するんだよ。殺さないでくれ、殺さないでくれ…そのうち、殺してくれ、と言い始めた…痛かっただろうなぁ…杉野も、1人で死んでいくのは不安だっただろうなぁ…」
「だめだ…今は思い出すな!」
何かがドアを滑り落ちるような音が響き渡り、また静かになった。すぐ傍に烏崎の息遣いが聞こえる。ドアによりかかって泣いているようだった。
「…お前が、羨ましかったんだよ」
嗚咽に、とぎれとぎれに言葉が混じり始めた。
「俺と同じ馬鹿だと思ってたのに、周りに好かれて、主任に抜擢されて…」
「上司ウケはイマイチだ」
「はは…そうだよな。…そうだった」
乾いた笑い声が、ドアを震わせた。
「お前が、そんなに上手く立ち回って出世するわけないのにな…」
その後、深いため息がもれた。
「…分からないんだよ。俺と、お前らと、何が違うのか。…なにが違うから、俺は取り残されたのか。…仕事か?見た目か?人間性か?…全っ然、分からないんだよ…。なぁ紺野。誰も正解を教えてくれないんだ。なぁ、俺の、何が悪かったんだ…?」
「…正解なんかあれば、俺が知りたい」
「そうだよな、ははは…ともかくよ、出世していった奴と比べて、自分が劣っていると認めるのが怖かった。俺は…救いようがないくらい、臆病だった」
「烏崎…」
「俺が誰かを羨んだり、邪推したり、妬んだりしてヤケ酒飲んでる間に、まっとうに仕事してたんだよな、お前」
自嘲的な調子で、烏崎は続けた。
「その結果、たどり着いた先がここだ。…杉野の呪いとか言って人のせいにしたけど、俺は自分でここに流れ着いたんだ、きっと…」
「なぁ、もういいんだ。自分を追い詰めるな!」
「もう行ってくれ…今な、俺の腹ん中には白石の血や肉が入っているんだよ。…こんなの、もう人間じゃねぇ。獣だ。…今こうしてお前と話していることすら、恥ずかしいんだ」
「お前はどこにでもいる普通の人間だ。…少し、弱ってただけだ。だから出てこい。一緒に、外に出よう」
「…お願いだから、1人にしてくれ…」
語尾が震えて、嗚咽が混じり始めた。柚木が、紺野さんの袖を引いた。
「もう、やめよう。どっちも辛いだけだよ」
「いや、しかし!」
「その子の言うとおりだ…もう、俺なんか気に掛けないでくれ。お前に気を遣われると、自分が余計に駄目な人間に思えてきて、イヤになる…」
嗚咽を無理やり抑えて、烏崎が細い声を出した。
「警察が来るまで、一人にしてくれ…」
「………」
ドアから手を滑らせて、紺野さんは一歩下がった。必死に歯を食いしばって、何かを振り切るように踵を返した。
昔、国語の教科書で読んだ、孤独と凋落の果てに虎と化してしまった男の話を思い出した。丁度こんなふうに、かつての友を歯牙にかけようとした瞬間にかつての記憶が蘇り、藪に潜んで嗚咽をもらすのだ。…僕が烏崎をとことん追い詰めようとした時、紺野さんが言ったことがようやく分かった。
――怯え切ってただろうが、最初から!そんなことも分からんのか!!
僕らを襲撃した夜も、紺野さんを恐喝した瞬間も、徹頭徹尾、烏崎は怯えていたんだ。目指していたのと真逆のベクトルで動き始めているのを知っていたのに、弱かったからそれを止められなかった。人を殺すのも、僕らを襲うのも、きっと怖くて仕方がなかったんだ。でもそれは、紺野さんも烏崎も気がついているように、弱かったから、臆病だったから、という理由で取り返しがつくものじゃない。だから、烏崎は…
――心が脆い烏崎は、どう逃げる…!?
「…しまった、1人にしちゃだめだ!!」
僕の叫び声に重なるように、ぱしゅ…と水道管が壊れたような音がした。紺野さんは弾かれたようにドアに駆け戻り、携帯を電子ロックに叩きつけた。
「烏崎!!」
紅く染まった部屋と、4つの死体。そして今まさに崩れ落ちる烏崎の巨体が、視界に飛び込んできた。…もう一度、口の中で呟いた。
もう、たくさんだ。
紺野さんが何かを叫びながら部屋に飛び込み、首筋から大量の血を噴き出す烏崎を抱き上げている。ベッドのシーツを片手で剥ぎ取り、首筋にあてがい、僕に向かって何か怒鳴った。…多分、医者を呼べとか言っているのだろう。ゆるゆると携帯を耳にあてがうけど、そのうちナースコールの存在に気がついてベッドに歩み寄る。
齧られ、引き裂かれた死体。壁に延々と書き殴られた血文字。
懸命に上を目指してたどり着いた先が、こんな場所なんて。
光を喪っていく烏崎の瞳が、一瞬だけ僕を捉えた。口元が痙攣するように動いたけれど、何を言ったのかは分からない。
――やがて、烏崎は事切れた。
首の傷口から溢れていた血が止まり、首がかくりと落ちた。僕は紺野さんが低く嗚咽を漏らすのを呆然と見つめるしかなかった。
『あぁ、死んだんだ…』と実感の沸かない感想を、頭の中をぐるぐる巡らせるのが精一杯だ。紺野さんに掛けられる、気の利いた言葉でも思いつけばいいのに、と考えながら。
「…私、おかしいのかな」
いつしか僕の隣に寄り添っていた柚木が、小さく呟いた。
「感情が、ついてこないよ。人がこんなに死んでるのに…」
「…うん」
どうしていいのか分からなくて視線を彷徨わせていると、烏崎が叩き壊したノーパソが目に留まった。つい、僕のノーパソが入った鞄に目を落とす。ビアンキはもういないのに。
――ビアンキは、僕のせいで発狂した。杉野という人は死んでいて、烏崎は、その手で仲間を殺めて自分も喉を裂いて…死んだ。
「これが…この事件の結末…?」
「…そう、なるのかね」
紺野さんが僅かに顔を上げて、呟いた。ナースコールを押して随分経つけど、応答する気配はない。…ここは、さっきの刑事が封鎖していたっけ。それに今から僕らが本館に運んだって、もう助からないだろう。本人も、そんなことを望んでいない。
「…私、伊佐木さんを探して来ます」
八幡がよろめきながら立ち上がった。出口に向かって歩き始めた八幡の前に、流迦ちゃんが回りこむ。
「動かないで。…まだ終わってない」
「……え?」
流迦ちゃんは、ノーパソから顔を上げて、壁の一点を凝視した。ディスプレイに映るのは、無数の顔や目玉が離合集散を繰り返し、次々に色を変えるサイケデリックな映像。
「今、私のライブカメラが幾つかハッキングされた。…院内イントラネットに、何かが入り込んだみたいね」
言い終わった瞬間のことだった。
部屋の上部に取り付けられたスピーカーから、禍々しい音楽が高らかに響き渡った。
空間の隅々まで張り巡らされたネットワーク。
無尽蔵にも感じる、ハード容量。
演算速度はちょっと遅めだけど、この規模じゃ仕方ないかな。
ご主人さま、どこかで見てくれてますか?
あなたの墓標は、こんなに大きいの。
ううん、私の『大好き』って気持ちを閉じ込めるには、これでも足りないくらい。
ここは全ての音が聞こえる。
ここは全ての場所が見える。
ここは全ての人間に音を伝えられる。
私は、その真ん中でタクトを振るの。この声が、ご主人さまに届くように。
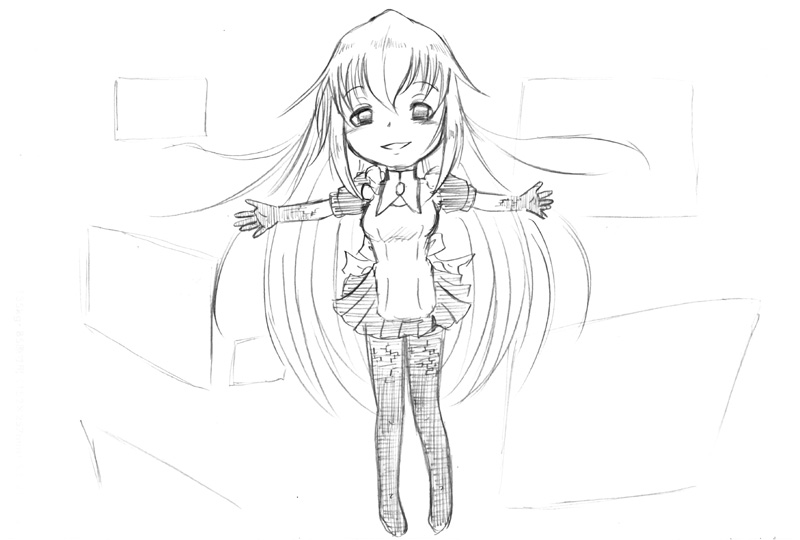
――ご主人さまが『おやすみ、ビアンキ』って言ってくれる、その時まで。
病室の…多分、全病室のスピーカーが、この禍々しい音楽を奏で始めた。
いや、こんなの音楽じゃない。狂った機械が絶叫するような笑い声と、硬いガラスを骨で引っかくような騒音。それに、肉の塊に何度も刃を突き立てるような湿った効果音。そんな世界中の聞きたくない音に、一遍に脳をかき乱されるような戦慄。制作者の禍々しい意図を反映した音の洪水が部屋を、いや、病棟を満たした。
「なっ…なにこれ!?」
「――やられたわ」
くくく…と、嬉しそうに笑って、モバイル用のモデムを差し替え、何かのソフトを開いた。
「コレは私が作った、カールマイヤーの音源…くく…あはははははははははははは!!」
ダン!と扉を叩き、血まみれの部屋で狂ったように笑う。
「あの子たち…私のパソコンに侵入してたんだわ!あははははは!!」
「あの子たち?」
流迦ちゃんは、さもおかしそうに含み笑いしながら、僕の目を覗き込んだ。
「烏崎が死んだくらいじゃ、ご主人さまを殺された恨みは消えなかったのよ…あの子たちは、この病院の中央制御システムを乗っ取った。…院内放送は全てあの子たちのものだし、私のライブカメラも含めた防犯カメラも、あの子たちのもの。ことによっては、医療装置も操れるかもね」
ふいに笑いをひそめて、キーボードに指を滑らせた。
「…で、手始めに、病棟全員参加の殺し合いを仕組んだ」
「そ、そうだ、どうしよう、このままじゃ全員…!!」
「心配ない」
「え?」
突然、騒音が途絶えた。黒いDOS-V画面がディスプレイに表示されて、メッセージが目にも止まらない勢いで上方に流れていく。
「院内放送は、私が抑える」
DOS-V画面を睨んだまま、絹がかすれるような声で呟いた。
「だから私はここに残る。あなたたちはこの病棟を出て、中央制御システムを叩き壊して来なさい」
「流迦ちゃん、駄目だ。制御システムが暴走してるなら、ここだって危ないんだぞ!」
紺野さんが、烏崎の死体を抱えたまま叫んだ。
「この部屋だけなら、中央制御システムの影響から守りきれる。…正直、ここまで走っただけでも息が切れた。私が一緒に行っても足手まといよ。…だから、私の体力が持つ間に、システムを破壊しなさい」
そう言って、薄く笑った。
…偶然かもしれないけど、僕がよく知っている、あの優しい声だった。
こんな場所に1人で置いていかなければいけない現状に、胸が痛む。言うことは思いつかなかったけど、何か言おうと思って顔を上げたその時。
「それは困るね、狭霧君」
全員、弾かれたように声の主を振り返った。いやに柔らかく、大勢に聞かせることを前提にした発音で話すこの声に、確かに聞き覚えがあった。
病室のドアにもたれかかり、『あの男』が笑顔を湛えて僕らを見渡していた。
後書き
第十八章は4/27に更新予定です。
ページ上へ戻る
全て感想を見る:感想一覧
