| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
くらいくらい電子の森に・・・
作者:たにゃお
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動第三章 (1)
ここに入学してまだ日が浅い桜の頃。
サークルのチラシ片手に新入生を追い回す上級生の群れを縫って、ふらふらと歩いていた。新入生歓迎コンパへの参加を約束させられたり、時には強引なサークルの追撃をかわしたりしながら、僕なりにサークルを吟味していた。
これまでの人生、なんとなくインドア系の団体に吸収されがちだった僕は、一念発起して東京に出てきて、大きな野望を抱いていたのだ。僕自身を変えるためにも、
―――アウトドア系の、ちょっとおしゃれなサークルに入りたい。
…テニスや乗馬なんか露骨におしゃれだけど、そんな高級な集いに僕が紛れ込んだりしたら、僕のそこはかとないダサさが悪目立ちして、周りのセレブな人々に「あら、なに、この負のオーラ」「まぁ、本当ですわね、何処からともなく負のオーラが…」とか囁かれて、一月もした頃には何となく遠巻きにされて、さらに一層強い負のオーラを身にまとう羽目になりかねない。
旅行サークルなんかは比較的、懐が深そうだけど、きっと金が続かない…。
ひとまず勧誘地帯を抜け出し、桜の下に設えられたベンチに腰をおろす。そして散々押し付けられたチラシを読むでもなく、ただ漫然と眺めていた。無造作に広げられたチラシの束に、そろそろ散り始めた桜の花びらがぽつり、ぽつりと舞い落ちてきた。
―――ピンとこない
この一言に尽きた。
だいたい僕の選定条件が悪い。おしゃれだのアウトドアだの、金が掛からなくてちょっと知的だの。そんなあやふやな条件でどんどん選択の幅を狭めていけば、しまいにゃ「野外百人一首同好会」とか、アウトドアだかアバンギャルドだか分からない珍妙なサークルに入ってしまい、冬の寒波にうち震えながら、木枯らしに舞い散るカルタを必死の形相で追いかけるような羽目になりかねない。
…急に、全部面倒になってチラシから顔をあげ、散り初めの桜を見上げた。花散らしの風がさあっ…と頬を撫で、周囲を桜色に染めていく。こういうの、なんていうんだっけ。…そうそう、桜霞。
散り初めの桜が好きだ。薄い桜色の花弁を含んだ風は、世間を曖昧な霞に閉じ込めて、僕からやんわり遠ざけてくれる。
…変わりたいなんて気張る必要、ないじゃないか。
今までどおり、やんわりと世間と距離をおきながら、ただ潮目に沿って流れていこう……ふいにそんな考えが浮かんできて、ふっと目を細めたその刹那

桜霞を切り裂いて、空色の自転車が駆け抜けた。
はっとした。
目の前を横切った瞬間の、彼女の横顔を今でも鮮烈に覚えている。
凛とした、迷いのない横顔。そして高校の頃、雑誌で見たことがある憧れの自転車『ビアンキ』。女学生らしい軽快なペダルさばきを見せる、細くて白い足首。…正直、綺麗だけど気が強そうだし、街中で見かけたとしたら全然好みのタイプじゃない。ただ、あの瞬間、あの横顔は、いやに鮮明に眼窩に焼きついた。
僕はベンチから立ち上がると、先刻なんとなく受け取ったチラシをすべて屑篭に放り込んだ。風が凪ぎ、桜霞が嘘のように晴れ渡る。その向こうに広がるのは、まだ少しくすんだ空の色。
僕は、自転車に乗れるサークルを探して、勧誘地帯に踏み出した…
……そんな感じでポタリング部に入部して、早や9ヶ月近く経とうとしている。
部活動のために予約された会議室の片隅で、ちょうど僕と対角線上の席で女の子と談笑している柚木の横顔を眺めながら、あの桜の頃を思い出していた。
あの横顔を初めて見た瞬間、自転車に乗りたい!という思いが沸きあがって入部した。そこに、あの横顔の子がいて、自己紹介で『柚木』という名前を知った。サークルに綺麗な女の子がいる、その事実だけで、僕も『あっち側』の人になれるかも!と内心小躍りしたことを覚えている。
……僕は、浅はかだった。
このサークルは、大まかに3つの派閥に分けられる。
まず1つは、このサークルの主流とも言える、ちょっとイイ自転車とスポーティーなスタイルで街を走る『おしゃれ街乗り派』。女の子が多く、柚木なんかもこの派閥に入る。ビアンキとかルイガノとかの、おしゃれでメジャーな街乗りサイクルを好むのが特徴だ。他サークルとの掛け持ちの子が多く、会合の顔ぶれが毎回異なる。
そしてもう一つは、ある意味ここの主力とも言える、体育会系派閥『ロードレーサー派』。いかにも速そうなロードバイクを好み、なんか過酷そうなレースに参加する。空気抵抗少なそうな、ピッタリ体に張りつくウェアに身を包み、街乗り派の男子を一段低く見ている感じ。その割には街乗り派女子の目は異様に気にしている。
そして最後の一つ。…ポタリング部の暗部に君臨し、ヴィンテージパーツをヤフオクで落とした話とか、古いクロスバイクをドロップハンドルに改造したいんだけど誰か部品余らせてないか、とかそんな話に花を咲かせる『改造マニア派』。「CNC!」とか「カンパニョーロ!」とかそういう単語にいちいち反応して、どうせ使わない部品を有難がったり磨いたりするのが主な活動内容。メンテナンスも簡単なやつなら出来る。ロードレーサー派とは利害が一致するので仲がいいけど、街乗り派には若干遠巻きにされている。
―――僕が、所属する派閥だ。
無事アウトドアサークルに入って油断しきっていた僕は、あっさりとマニア派の強引な勧誘の餌食になった。そして元々手先が器用でインドア系の素養があったこともあり、夏休みが終わる頃には主要メンバーの1人に落ち着いていたのだ。
「姶良よ」
「なんすか」
神妙な顔で自転車パーツ情報誌を読んでいた鬼塚先輩が、ふと顔を上げて話しかけてきた。
「俺はまだ、『おしゃれ化』への道を諦めてないといったら、笑うか」
「……もうやめましょ、そういうの。……あの件、忘れたんですか」
今年の夏頃、誰かの提唱で始まった『マニア派おしゃれ化計画』を思い出した。
「インテリな俺達が、おしゃれすれば鬼に金棒じゃね?」をスローガンに誰ともなく始まり、計画段階では異様な盛り上がりを見せた。そして次のサークル会議で、全員一斉おしゃれデビューという流れになり、めいめいの本気モードで集合することになったのだ。
――今にしてみると、正常な判断力を喪ってたとしか思えない。
その日、僕は少し遅れて会議室に着いた。新品を買う余裕なんてないので、街乗り用に一本だけ持っているクォーターパンツに、まだヨレてないTシャツを合わせただけの簡素な『本気モード』に落ち着いていた。どきどきしながら室内を見回すと、定位置となっている部屋の片隅に、マニア派の面々が暗い目つきで腰をおろしていた。
…全員、おろしたてと思われるラコステのポロシャツに、アメ横で買ってきたと思しきシルバーのネックレスをぶら下げていた。
「…おう、姶良よ」
恐る恐る近づくと、鬼塚先輩が僕に気がついて顔を上げた。軽く会釈をすると、そのまま視線を下半身に落としてみた。これもまた、全員似たようなバミューダで統一されている。…いや、これ全員同じバミューダだ!しかも普段すねを出し慣れてないひとたちが全員一斉に出したものだから、予想以上にすね毛密度が濃くて不快指数が高めな感じだ。変な臭いがしそう。沈んでいるところを本当に申し訳ないけど、僕もできれば近寄りたくない。
「…なんすかこれ」
「…元凶はこれだ、姶良よ」
鬼塚先輩に手渡された、おしゃれ街乗り派御用達の自転車情報誌を開く。巻頭に掲載されているチョイ悪な男性モデルが、ルイガノの街乗りバイクを背に、ラコステのポロシャツをざっくりと着こなし、クロムハーツのシルバーを胸元にチラ見せしつつ、定番のバミューダですっきりとまとめていた。金髪の外人さんだから、すね毛はあまり目立たない。
「あの…全員、まっさきに巻頭の外人に飛びついたんすか」
「俺達おしゃれ初心者に、吟味をする余裕があると思うか、姶良よ……」
「そう、ですね」
「……なぁ、姶良よ。俺、こうなってみて、つくづく思ったんだけどな」
普段無口な鬼塚先輩が、あえて皆を代弁するように口を開いた。
「すね毛は、思いつきで出すもんじゃねぇな……」
鬼塚先輩の口の端に、自嘲的な笑みが洩れた。それは次第にくっくっく…という低い笑いへと変わっていき、その笑い声は、徐々に回りに伝播していった。
「ひっひっひ……」
「いっひっひっひっひ……」
「くっくっくっ……」
「あっはっはっはっは!!」
全員の引き笑いが合流し、やがて互いの肩を叩きながらの不気味な大哄笑へと発展していった。そんな僕たちを、不審者を見る目で遠巻きに眺めている柚木を視界の隅にとらえた瞬間、僕はおしゃれなアウトドア系キャンパスライフを諦めたのだ……。

「…あれ見た時は、みんな僕に内緒で『ラコステをかっこ悪くする会』でも結成したのかと思いましたよ」
「本気でやったとバレなくて幸いだったじゃねぇか…あれからうちのサークルじゃ、誰一人ラコステを着てこなくなったしな。嫌がらせとしては大成功だ」
鬼塚先輩は、またぼんやりと女子の溜まり場を眺めている。今日は春近く…というか冬真っ盛りの時期になるとコンビニで大量にリリースされる『イチゴ味の菓子』をみんなで買い込んで試食しているようだ。鬱全開の深く長いため息を吐き出すと、鬼塚先輩は半分潰れた煙草の箱を傾けてライターを出した。…やがて、ため息混じりの煙が辺りを満たす。鬱って、こうして伝染するものなのかな、と、ふと思った。
「…もう諦めろ。人には持って生まれた天分ってもんがあるんだよ」
ヤフオクで落としたというCNCのディレイラーを磨いていた武藤先輩が、なげやりに呟いた。
「あるんですよね…どうやっても変えられない『自分の核』みたいなもの…」
「最初にダサい核を入れられた俺達は、もう一生ダサいまんまかい、姶良よ……」
「イヤそれは、その……」
「あのオシャレな街乗りの連中に俺の核を移植すれば、奴らもたちどころにダサくなるのかい、姶良よ」
「いや、アメーバじゃないんですから……」
「姶良に絡むな、仕方がないだろうが!」
武藤先輩が、部品を布ごとガツンと机に置いて鬼塚先輩の方に身を乗り出した。
「『核』に優劣なんかないんだよ。盗んだバイクで走り出す奴がいれば、その盗まれるバイクを作る奴も必要だろうが」
「作ったバイクを盗まれて、俺らいいトコなしって感じだな、武藤よ……」
「あはは、うまい事言いましたね」
つい納得してしまい、武藤先輩に頭をはたかれる。
「そんなことより、次のツーリングコースの普請は終わったのか!」
「…はあ、叩き台程度ですけど」
ノーパソを取り出し、電源を入れる。武藤さんが僕の後ろに回りこんで、肩越しに覗き込んだ。
「ビアンキちゃんは元気か」
「…元気だけど起動時に画面覗くのやめてください。他の人の網膜が映ると、認証システムが混乱するんです」
武藤先輩をなだめて画面から遠ざけると、程なくしてノーパソが起動し始めた。最近少し人見知りが取れてきた(セキュリティ的には取れていいのか分からないが)ビアンキと武藤先輩が微笑み合っているのを尻目に、グーグルにログインしてマップを開く。程なくして、ラインと書き込みでいっぱいの地図が表示された。
「お、もうほぼ出来てるじゃないか!仕事速いな」
全画面表示にして、地図を縮小して全体を表示する。多摩川に沿って、弧を描くように赤のラインで囲った地図が表示された。
「…ほう、ちゃんと走ってみたんだろうな。ロードバイクで未舗装の道とか、きつい坂道とかシャレにならんぞ」
「…通しで走ってはいないけど、大体」
「大体ってお前ね」
「まぁ、まてまて武藤よ」
先刻から、それとなく覗いていた鬼塚先輩が、割って入ってきた。
「よく出来てるじゃないか。俺が知る限りの厄介な道は、ほぼ迂回できている。寄り道が出来るスポットも盛り込んであって、なかなかセンスのよいコースだ。…よく、走ってないのにこれだけのものが作れたもんだ。驚いた」
「この辺の地理は、大体把握してますから」
僕は小さく笑って地図を全体表示にした。鬼塚先輩が、再度感心したように呟いた。
「…さすが『鋼の方向感覚』だな」
僕は生まれてこのかた、方向を見誤ったことがない。
小さい頃、車で30分かかるばあちゃん家に泊まりに行った日、お気に入りの絵本を家に置き忘れた。明日には帰ると分かっていたけど、なんとなくイライラしてしまい、祖母の自転車を拝借して絵本を取りに戻った。道は、完全に覚えている自信があったから。
事実、僕は一度も迷うことなく、4時間余りで往復してばあちゃん家に戻ってきた。今思い出しても、結構いいスコアだ。
…まぁ、そのあと半狂乱の母さんに半殺しにされたのだけど。
それに加えて一度通った道は、建物や造りも含めて絶対に忘れたことがない。一見凄い能力のような気がするけれど、この異常な記憶力は『道』にしか作用しない。僕の一般的な記憶力は、極めて人並みなのだ。
「なにそれ?次のコース?」
ゴテゴテしたデコレーションのイチゴポッキー(?)をくわえて、柚木が寄って来た。
「あー……まぁ…」「ふぅーん…」
柚木が、分かったような分からないような顔をして、マップを覗き込む。
間違いなく、分からないのだ。
多摩川のサイクリングロードくらいはギリギリ分かっているかもしれないが、むしろ半端に分かってしまったせいで、自分の分かってなさが分からない状態になっていることだろう。
街乗り派の合言葉に「柚木を1人で走らせるな」というのがある。
順調についてきているな、と思って一瞬目を離した隙に、何かに気をとられては、ふっといなくなるのだ。…まぁ、道を知ったうえでコースを外れているのなら、何も言うことはないんだけど、彼女は百発百中で迷子になる。
それでも発見が早ければ、割とラクに元のコースに戻せる。しかし彼女の場合、無駄に脚力がある上に、闇雲な行動力であっちこっち走り回るので、迷子が発覚した時には取り返しがつかないほど遠くに行ってしまっていることが多い。そして「なんか、変な所に出ちゃった!…んとね、十字路の先に薬屋があってね、『山梨↑10km』って書いた青い看板が…」みたいな絶望的な電話が掛かってくるのだ。
それでも僕の守備範囲にいるうちは、なんとか携帯で遠隔操作して正規ルートに戻せるけれど(この「柚木サルベージ」のお陰で、僕は鋼の方向感覚と呼ばれ始めた)、たまに僕もお手上げな程、遠征している場合がある。そんなときはどうするか…
放っておくのだ。
すると、嗅覚なんだか帰巣本能だか知らないが、彼女は不思議と源流にたどり着く。
「鮭と同じ原理で帰ってきているのだ」と、鬼塚先輩は言う。だとすると嗅覚のほうか。
「食べる?」
ふいにポッキーの袋を差し出されて我に返る。
「あ…ありがと」おずおずと手を伸ばす。先輩達も、のそりのそりと群がってきた。
「最近のポッキーはすげぇなぁ、柚木よ」
「なんだこのデコレーションは。ポッキー異様に太くなってんじゃねぇか」
武藤先輩が、毛の生えたごつい指を袋にねじ込んで可愛いポッキーをつまみ出し、面白くもなさそうな顔で噛みしめる。ポッキーがケダモノに汚されたような絵ヅラだ。
「文句言うなら食べないでくださいよぅ」
柚木がぷぅ、とむくれる。続いて鬼塚先輩がポッキーに手を伸ばした。
「ははは…それより柚木、鬼塚はさっき便所でチンコ触って手を洗ってないぞ」
「え!?」
柚木が、そして鬼塚先輩がびくっと肩を震わせる
「そして、俺もだ」
「キャアアァァァア!!」
柚木が飛びのいた拍子にポッキーの箱を取り落とす。
「あーあ、もったいね」
「最っ低!!もうそれいらないから!!」
「いらねぇか、ラッキー」
武藤先輩はポッキーをひょいとくわえると、床に落ちた箱をつまみあげた。
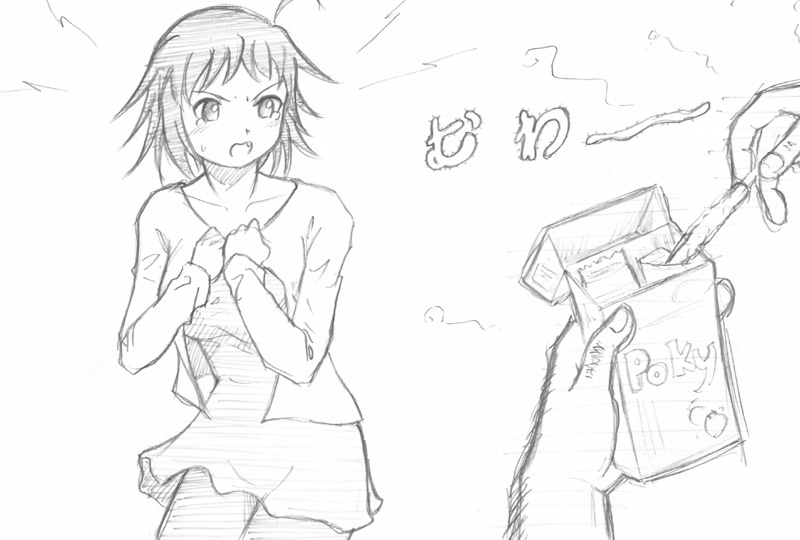
「うめぇ!…ほれ、お前も食わんか」
「…いや、いいっす」僕は即座に断った。
「ちょっと!それ高かったんだから!ポッキー代返して下さいよ!!」
「じゃ、ポッキー返す」
「そうじゃないでしょ!!…ああぁぁもう!!最近こんなことばっかし!!」
頭をかきむしって柚木が叫ぶ。…『こんなこと』とは、紺野さんがMOGMOGを勝手にインストールした件のことを言っているのだろう。
「まぁまぁ…じゃあこれ開けようか」
僕はカバンの奥から『期間限定キノコの山 野イチゴ味』を取り出して机に置く。真っ先に手を出してきた武藤先輩を払いのけ、柚木がキノコの山を奪い取った。
「やった、いいの持ってんじゃん!これ、どっちにしようか迷ったんだよねー!」
「ははは…偶然ね…」
実は前回のサークルで、女子が「新作イチゴ菓子をみんなで持ち寄って試食しよう!」と相談していたのを立ち聞きして、あわよくば「うわっ偶然~!僕も今持ってるんだよね!」などと、どさくさに紛れて試食に混ざりたい!と考え、用意しておいた。しかし、部屋に入って早々先輩達に捕まり、野望はあえなく潰えたのだ。
「で、これが次のコース?」
キノコの山をぽりぽりかじりながら、柚木は僕のノーパソを覗きこんだ。もう機嫌は直っているようだ。
柚木は例えば、理不尽な手段で先輩にポッキーを取られても、代わりのものが手に入れば、ポッキーを取られた経緯をすっかり忘れて無防備になる。
彼女のそういう部分を、僕はいつも「生き物的にはどうなのか」と思ってしまうが、潔い感じがしてわりと嫌いじゃない。とりあえず、人間が捕食される側の生き物じゃなくて本当に良かった。柚木みたいな子でも、厳しい大自然とかに淘汰されることなく元気に生きていける。
しかし、逆に柚木は『代わるものが手に入らないと絶対に許さない』という一面も持っている。だからこそ、僕はしつこく気になっているのだ。
柚木はどうして、紺野さんを許したのだろう?
紺野さんを気に入っているのは態度から分かるけど、それは「代わるもの」じゃない。いや、むしろ紺野さんが「代わるもの」を差し出したことが、柚木の態度の豹変に関わっている気がする……
そして僕は、一つだけ確信している。
紺野さんが柚木に提供したものは、『物』じゃなくて『情報』だ。
柚木と紺野さんが物陰で何かを話し合っていたのは、ほんの1~2分。柚木は小さな封筒以外、なにも持っていなかった……MOGMOGを手に入れると同等の、紙切れ1枚分程度の情報、とは一体なんだろう……。
「やだ!ちょっとやめて下さいよ!!」
柚木の悲鳴で、はっとわれに返る。武藤先輩が、再びキノコの山にちょっかいを出し始めたのだ。
「なにをキサマ!先輩命令だ、キノコの山もよこせ!」
「絶対イヤ!近寄らないでよ、このモテない菌!!」
「菌ならキノコは俺の眷属だろうが!その手を離せ、この方向音痴の鉄砲玉が!!」
「方向音痴が関係あるかっ!これ以上食べ物に触れたら殺す!!」
小学生のようにキノコの山を奪い合う二人を尻目に、鬼塚先輩が再び画面に向き直る。
「…柚木も放っておけばいいのに。武藤のアレは、気になる子に意地悪したくなる小学生と何も変わらんというのにな、姶良よ」
そういいつつ、柚木から巻き上げたポッキーをちゃっかり自分の物にしている。彼らが小学生なら、この人は中学生だ。僕は適当にあいづちをうつ。
「…ですよね。そんなに気になるなら優しくして距離を縮めるとか…。」
「『いい人』というのも、なかなか救いがたい立ち位置だがな…」
僕のことを言われている気がした。
「分かってますよ。…でも面倒じゃないですか、駆け引きとか」
「あぁ…ギャルゲーのように、ひたすら優しさの積み重ねで女が落ちてくれるなら、俺達ゃどんだけモテモテだろうな、姶良よ…」
「空しいこと言わないでください…」
しばらくぼんやりと宙を見据えていた鬼塚先輩の視線が、ふいに画面に戻った。
「本当に、良く出来たコースだな」
「なんですか、改まって」
「…メンテナンスの腕も、そこそこ上がってきたな、姶良よ」
「そんな…まだまだ勉強中ですよ」
「いや、お前の仕事には、高いポテンシャルを感じずにはいられない」
「いえ!断じてそんなことは…」
「謙遜をするな。お前には力がある…次世代のマニア派を束ねていく力が!」
「そんなイヤな力、断じてありません!!」
ふいに外堀を埋めていくように言葉を重ねはじめた鬼塚先輩に、危険な予感を覚えてイスごとあとじさる。
「なぁ姶良よ、お前に折りいって話があるのだが…」
「時期早尚もいいトコです、それだけは勘弁してください!!」
僕の悲鳴にも近い懇願の声に、武藤先輩がいち早く反応して、キノコの山争奪戦から離脱してきた。
「お?鬼塚、とうとう『アレ』を譲るのか?」
「イヤほんとやめてください!僕、ああいうのはちょっと…」
「やれやれ、やっちまえ!『アレ』は早いに越したことはない!」
武藤先輩が野次馬根性で煽りまくると、柚木も首を突っ込んできた。
「姶良なら『アレ』、ぜったい似合うよ!」
「似合いたくないよ!」
「……うぅむ……予感がしてきた……予感がしてきたぞ」
身をすくませる僕の肩を乱暴に掴むと、鬼塚先輩は地を這うような声で宣言した。
「…お前は『呪われたランドナー』を継承する…」
「イヤですよ!!」
…我がポタリング部(の一部)には、代々継承されている自転車がある。
『ランドナー』とは、長距離走行用にフランスで開発され、日本の自転車職人によって独自の進化を遂げていった、アンティーク自転車のことである。
もう一度言おう、アンティーク自転車だ。
今でこそ『自転車界の絶滅危惧種』だの『デコチャリの一種』だのひどいこと言われ放題だけど、昔は、未舗装道路も山岳地帯もものともしない頑丈なボディで人気を博していたのだ。懐中電灯のようなライトや太いタイヤ、いやに立派なスタンドやキャリアなどの、今では冗談みたいな装備も、当時は魅力の一つだった(と現オーナー・鬼塚先輩から聞いた)。でもやがてMTBやロードバイクなどに人気を奪われ、取り扱い店は激減。パーツも続々生産中止となり、いくら頑丈でも、壊すと代わりのパーツが手に入らない、デンジャラスな車種と成り果てた。
だから今では一部の熱心なマニアが、数少ない取扱い店でオーダーメイドで手に入れて、乗りもしないで飾っておく骨董品的なポジションに落ち着いている。
しかし、我が部に伝わる『それ』は、そういう類のものじゃない。
古いのは古いのだろう。50年以上は乗り継がれていると聞いた。正確な年代は分からない。何しろメーカーが不明だから、製造年の見当をつけようがないのだ。自作なのかもしれない。
そして幾星霜にわたり、素人に毛がはえたような部員にテキトーなメンテナンスを施され続け、部品が壊れればMTBやロードバイクの部品を無理やりはめ込まれ、ますます正体不明さを増していく、鵺のような自転車。もはやこれは本当にランドナーなのかも疑わしくなってきている。
それでもランドナーとしてアイデンティティを主張し続ける、ボコボコに膨らんだサイドバッグや、荷台にくくりつけられた寝袋の絶妙な貧乏臭さが、乗る者をしてホームレスかと思わしめる。しかも随分前の継承者が、ライトが壊れた際に冗談でくくりつけた懐中電灯が、そのまま引き継がれてしまっている。アンティークの尊厳なんか微塵もない。
そしてこれを引き継いだ部員は、次の継承者が現れるまで、このランドナーでサークルに参加しなければならない。
ならない、というか、せざるを得ない状況になる。
ランドナーが次の継承者を求めるとき、継承者の愛車が「屠られる」。
事故か、盗難か、寿命か…理由は様々だけど、とにかく継承者は偶然の不幸で愛車を喪う。そして、備品貸与の形でランドナーを受け継ぐ羽目になるのだ。それが『呪われたランドナー』たる由縁らしい。
歴代継承者の中には、愛車が潰れた直後、新車を買った人もいたそうだ。しかし新車はものの3日で、愛車と同じ末路を辿った(と鬼塚さんから聞いた)。
それ以来、半ば諦めをもって受け入れられ続けているこのランドナー継承。こいつ自体を屠ってしまおうという提案は、不思議と挙がったことがない。
「…今まで何十台も自転車を屠ってきたランドナーを潰して、無事で済むと思うのか、姶良よ…」
現オーナーは、鬱っ気たっぷりのため息を吐き出して、そう答えた。
そしてここからが、最も恐ろしい話なんだけど……
『呪われたランドナー』を継承した者は、列島縦断の旅に出るしきたりがあるのだ。
あの貧乏ランドナーで3000キロ以上の距離を走破!……死人が出てもおかしくない、無謀旅行だ。そして案の定、ランドナーは毎日のようにぶっ壊れまくるそうだ。近くに部品屋がなくて、半分泣きながらランドナー引き引き十数キロ歩くなんてことも1回や2回じゃなかった、と鬼塚さんから聞いた。事実、列島縦断から生還した部員は、別人のようにメンテナンスの腕が上がっているという……。
「……ランドナー継承も列島縦断もお断りします」
「それを決めるのは俺じゃない」
鬼塚先輩が、窓の外に視線を走らせた。無個性な自転車たちが居並ぶ駐輪場で、ホームレス仕様の『それ』は異彩を放っている。
「…『屠られる』とか言うけど、年に1人くらい、うっかり者が自転車を壊したりなくしたりするなんて、何処のサークルでもあることでしょう?連続して自転車を壊したとかいう人は、よっぽど迂闊だったんですよ」
「…俺も、最初はそう思っていたよ…」
鬼塚先輩は、一瞬にやりと笑うと、再びノーパソに向き直った。
「…あいつには何か、魔性があるんだ。…姶良よ、お前にもいずれ分かる」
「魔性じゃなくて愛着でしょう。それこそ、よくあることですよ」
「あ、あのぅ…むつかしいお話、終わり…ですか?」
地図の端をめくって、ビアンキがそっと顔を覗かせた。せっかく全画面表示にしたのに…。
「ん、そろそろ終わりだよ。悪かったね、放っておいて」
「あ――――!!!」
柚木が突然声を張り上げ、ノーパソの方に身を乗り出した。
「な、何だよ」
「この服!なにこの服!!」
「服って…べつにいつも通りの」「あんたの服じゃない!!」
ぴしゃりと言い放つと、柚木はノーパソの液晶を叩いた。
「ビアンキのワンピース!MOGMOGには着せ替え機能はなかったはずだよ!!」
「……げ」
そっと、メッセンジャーバッグに手を伸ばす。これ以上騒がれる前に、ノーパソをひったくって逃走しよう……。
サークルのチラシ片手に新入生を追い回す上級生の群れを縫って、ふらふらと歩いていた。新入生歓迎コンパへの参加を約束させられたり、時には強引なサークルの追撃をかわしたりしながら、僕なりにサークルを吟味していた。
これまでの人生、なんとなくインドア系の団体に吸収されがちだった僕は、一念発起して東京に出てきて、大きな野望を抱いていたのだ。僕自身を変えるためにも、
―――アウトドア系の、ちょっとおしゃれなサークルに入りたい。
…テニスや乗馬なんか露骨におしゃれだけど、そんな高級な集いに僕が紛れ込んだりしたら、僕のそこはかとないダサさが悪目立ちして、周りのセレブな人々に「あら、なに、この負のオーラ」「まぁ、本当ですわね、何処からともなく負のオーラが…」とか囁かれて、一月もした頃には何となく遠巻きにされて、さらに一層強い負のオーラを身にまとう羽目になりかねない。
旅行サークルなんかは比較的、懐が深そうだけど、きっと金が続かない…。
ひとまず勧誘地帯を抜け出し、桜の下に設えられたベンチに腰をおろす。そして散々押し付けられたチラシを読むでもなく、ただ漫然と眺めていた。無造作に広げられたチラシの束に、そろそろ散り始めた桜の花びらがぽつり、ぽつりと舞い落ちてきた。
―――ピンとこない
この一言に尽きた。
だいたい僕の選定条件が悪い。おしゃれだのアウトドアだの、金が掛からなくてちょっと知的だの。そんなあやふやな条件でどんどん選択の幅を狭めていけば、しまいにゃ「野外百人一首同好会」とか、アウトドアだかアバンギャルドだか分からない珍妙なサークルに入ってしまい、冬の寒波にうち震えながら、木枯らしに舞い散るカルタを必死の形相で追いかけるような羽目になりかねない。
…急に、全部面倒になってチラシから顔をあげ、散り初めの桜を見上げた。花散らしの風がさあっ…と頬を撫で、周囲を桜色に染めていく。こういうの、なんていうんだっけ。…そうそう、桜霞。
散り初めの桜が好きだ。薄い桜色の花弁を含んだ風は、世間を曖昧な霞に閉じ込めて、僕からやんわり遠ざけてくれる。
…変わりたいなんて気張る必要、ないじゃないか。
今までどおり、やんわりと世間と距離をおきながら、ただ潮目に沿って流れていこう……ふいにそんな考えが浮かんできて、ふっと目を細めたその刹那

桜霞を切り裂いて、空色の自転車が駆け抜けた。
はっとした。
目の前を横切った瞬間の、彼女の横顔を今でも鮮烈に覚えている。
凛とした、迷いのない横顔。そして高校の頃、雑誌で見たことがある憧れの自転車『ビアンキ』。女学生らしい軽快なペダルさばきを見せる、細くて白い足首。…正直、綺麗だけど気が強そうだし、街中で見かけたとしたら全然好みのタイプじゃない。ただ、あの瞬間、あの横顔は、いやに鮮明に眼窩に焼きついた。
僕はベンチから立ち上がると、先刻なんとなく受け取ったチラシをすべて屑篭に放り込んだ。風が凪ぎ、桜霞が嘘のように晴れ渡る。その向こうに広がるのは、まだ少しくすんだ空の色。
僕は、自転車に乗れるサークルを探して、勧誘地帯に踏み出した…
……そんな感じでポタリング部に入部して、早や9ヶ月近く経とうとしている。
部活動のために予約された会議室の片隅で、ちょうど僕と対角線上の席で女の子と談笑している柚木の横顔を眺めながら、あの桜の頃を思い出していた。
あの横顔を初めて見た瞬間、自転車に乗りたい!という思いが沸きあがって入部した。そこに、あの横顔の子がいて、自己紹介で『柚木』という名前を知った。サークルに綺麗な女の子がいる、その事実だけで、僕も『あっち側』の人になれるかも!と内心小躍りしたことを覚えている。
……僕は、浅はかだった。
このサークルは、大まかに3つの派閥に分けられる。
まず1つは、このサークルの主流とも言える、ちょっとイイ自転車とスポーティーなスタイルで街を走る『おしゃれ街乗り派』。女の子が多く、柚木なんかもこの派閥に入る。ビアンキとかルイガノとかの、おしゃれでメジャーな街乗りサイクルを好むのが特徴だ。他サークルとの掛け持ちの子が多く、会合の顔ぶれが毎回異なる。
そしてもう一つは、ある意味ここの主力とも言える、体育会系派閥『ロードレーサー派』。いかにも速そうなロードバイクを好み、なんか過酷そうなレースに参加する。空気抵抗少なそうな、ピッタリ体に張りつくウェアに身を包み、街乗り派の男子を一段低く見ている感じ。その割には街乗り派女子の目は異様に気にしている。
そして最後の一つ。…ポタリング部の暗部に君臨し、ヴィンテージパーツをヤフオクで落とした話とか、古いクロスバイクをドロップハンドルに改造したいんだけど誰か部品余らせてないか、とかそんな話に花を咲かせる『改造マニア派』。「CNC!」とか「カンパニョーロ!」とかそういう単語にいちいち反応して、どうせ使わない部品を有難がったり磨いたりするのが主な活動内容。メンテナンスも簡単なやつなら出来る。ロードレーサー派とは利害が一致するので仲がいいけど、街乗り派には若干遠巻きにされている。
―――僕が、所属する派閥だ。
無事アウトドアサークルに入って油断しきっていた僕は、あっさりとマニア派の強引な勧誘の餌食になった。そして元々手先が器用でインドア系の素養があったこともあり、夏休みが終わる頃には主要メンバーの1人に落ち着いていたのだ。
「姶良よ」
「なんすか」
神妙な顔で自転車パーツ情報誌を読んでいた鬼塚先輩が、ふと顔を上げて話しかけてきた。
「俺はまだ、『おしゃれ化』への道を諦めてないといったら、笑うか」
「……もうやめましょ、そういうの。……あの件、忘れたんですか」
今年の夏頃、誰かの提唱で始まった『マニア派おしゃれ化計画』を思い出した。
「インテリな俺達が、おしゃれすれば鬼に金棒じゃね?」をスローガンに誰ともなく始まり、計画段階では異様な盛り上がりを見せた。そして次のサークル会議で、全員一斉おしゃれデビューという流れになり、めいめいの本気モードで集合することになったのだ。
――今にしてみると、正常な判断力を喪ってたとしか思えない。
その日、僕は少し遅れて会議室に着いた。新品を買う余裕なんてないので、街乗り用に一本だけ持っているクォーターパンツに、まだヨレてないTシャツを合わせただけの簡素な『本気モード』に落ち着いていた。どきどきしながら室内を見回すと、定位置となっている部屋の片隅に、マニア派の面々が暗い目つきで腰をおろしていた。
…全員、おろしたてと思われるラコステのポロシャツに、アメ横で買ってきたと思しきシルバーのネックレスをぶら下げていた。
「…おう、姶良よ」
恐る恐る近づくと、鬼塚先輩が僕に気がついて顔を上げた。軽く会釈をすると、そのまま視線を下半身に落としてみた。これもまた、全員似たようなバミューダで統一されている。…いや、これ全員同じバミューダだ!しかも普段すねを出し慣れてないひとたちが全員一斉に出したものだから、予想以上にすね毛密度が濃くて不快指数が高めな感じだ。変な臭いがしそう。沈んでいるところを本当に申し訳ないけど、僕もできれば近寄りたくない。
「…なんすかこれ」
「…元凶はこれだ、姶良よ」
鬼塚先輩に手渡された、おしゃれ街乗り派御用達の自転車情報誌を開く。巻頭に掲載されているチョイ悪な男性モデルが、ルイガノの街乗りバイクを背に、ラコステのポロシャツをざっくりと着こなし、クロムハーツのシルバーを胸元にチラ見せしつつ、定番のバミューダですっきりとまとめていた。金髪の外人さんだから、すね毛はあまり目立たない。
「あの…全員、まっさきに巻頭の外人に飛びついたんすか」
「俺達おしゃれ初心者に、吟味をする余裕があると思うか、姶良よ……」
「そう、ですね」
「……なぁ、姶良よ。俺、こうなってみて、つくづく思ったんだけどな」
普段無口な鬼塚先輩が、あえて皆を代弁するように口を開いた。
「すね毛は、思いつきで出すもんじゃねぇな……」
鬼塚先輩の口の端に、自嘲的な笑みが洩れた。それは次第にくっくっく…という低い笑いへと変わっていき、その笑い声は、徐々に回りに伝播していった。
「ひっひっひ……」
「いっひっひっひっひ……」
「くっくっくっ……」
「あっはっはっはっは!!」
全員の引き笑いが合流し、やがて互いの肩を叩きながらの不気味な大哄笑へと発展していった。そんな僕たちを、不審者を見る目で遠巻きに眺めている柚木を視界の隅にとらえた瞬間、僕はおしゃれなアウトドア系キャンパスライフを諦めたのだ……。

「…あれ見た時は、みんな僕に内緒で『ラコステをかっこ悪くする会』でも結成したのかと思いましたよ」
「本気でやったとバレなくて幸いだったじゃねぇか…あれからうちのサークルじゃ、誰一人ラコステを着てこなくなったしな。嫌がらせとしては大成功だ」
鬼塚先輩は、またぼんやりと女子の溜まり場を眺めている。今日は春近く…というか冬真っ盛りの時期になるとコンビニで大量にリリースされる『イチゴ味の菓子』をみんなで買い込んで試食しているようだ。鬱全開の深く長いため息を吐き出すと、鬼塚先輩は半分潰れた煙草の箱を傾けてライターを出した。…やがて、ため息混じりの煙が辺りを満たす。鬱って、こうして伝染するものなのかな、と、ふと思った。
「…もう諦めろ。人には持って生まれた天分ってもんがあるんだよ」
ヤフオクで落としたというCNCのディレイラーを磨いていた武藤先輩が、なげやりに呟いた。
「あるんですよね…どうやっても変えられない『自分の核』みたいなもの…」
「最初にダサい核を入れられた俺達は、もう一生ダサいまんまかい、姶良よ……」
「イヤそれは、その……」
「あのオシャレな街乗りの連中に俺の核を移植すれば、奴らもたちどころにダサくなるのかい、姶良よ」
「いや、アメーバじゃないんですから……」
「姶良に絡むな、仕方がないだろうが!」
武藤先輩が、部品を布ごとガツンと机に置いて鬼塚先輩の方に身を乗り出した。
「『核』に優劣なんかないんだよ。盗んだバイクで走り出す奴がいれば、その盗まれるバイクを作る奴も必要だろうが」
「作ったバイクを盗まれて、俺らいいトコなしって感じだな、武藤よ……」
「あはは、うまい事言いましたね」
つい納得してしまい、武藤先輩に頭をはたかれる。
「そんなことより、次のツーリングコースの普請は終わったのか!」
「…はあ、叩き台程度ですけど」
ノーパソを取り出し、電源を入れる。武藤さんが僕の後ろに回りこんで、肩越しに覗き込んだ。
「ビアンキちゃんは元気か」
「…元気だけど起動時に画面覗くのやめてください。他の人の網膜が映ると、認証システムが混乱するんです」
武藤先輩をなだめて画面から遠ざけると、程なくしてノーパソが起動し始めた。最近少し人見知りが取れてきた(セキュリティ的には取れていいのか分からないが)ビアンキと武藤先輩が微笑み合っているのを尻目に、グーグルにログインしてマップを開く。程なくして、ラインと書き込みでいっぱいの地図が表示された。
「お、もうほぼ出来てるじゃないか!仕事速いな」
全画面表示にして、地図を縮小して全体を表示する。多摩川に沿って、弧を描くように赤のラインで囲った地図が表示された。
「…ほう、ちゃんと走ってみたんだろうな。ロードバイクで未舗装の道とか、きつい坂道とかシャレにならんぞ」
「…通しで走ってはいないけど、大体」
「大体ってお前ね」
「まぁ、まてまて武藤よ」
先刻から、それとなく覗いていた鬼塚先輩が、割って入ってきた。
「よく出来てるじゃないか。俺が知る限りの厄介な道は、ほぼ迂回できている。寄り道が出来るスポットも盛り込んであって、なかなかセンスのよいコースだ。…よく、走ってないのにこれだけのものが作れたもんだ。驚いた」
「この辺の地理は、大体把握してますから」
僕は小さく笑って地図を全体表示にした。鬼塚先輩が、再度感心したように呟いた。
「…さすが『鋼の方向感覚』だな」
僕は生まれてこのかた、方向を見誤ったことがない。
小さい頃、車で30分かかるばあちゃん家に泊まりに行った日、お気に入りの絵本を家に置き忘れた。明日には帰ると分かっていたけど、なんとなくイライラしてしまい、祖母の自転車を拝借して絵本を取りに戻った。道は、完全に覚えている自信があったから。
事実、僕は一度も迷うことなく、4時間余りで往復してばあちゃん家に戻ってきた。今思い出しても、結構いいスコアだ。
…まぁ、そのあと半狂乱の母さんに半殺しにされたのだけど。
それに加えて一度通った道は、建物や造りも含めて絶対に忘れたことがない。一見凄い能力のような気がするけれど、この異常な記憶力は『道』にしか作用しない。僕の一般的な記憶力は、極めて人並みなのだ。
「なにそれ?次のコース?」
ゴテゴテしたデコレーションのイチゴポッキー(?)をくわえて、柚木が寄って来た。
「あー……まぁ…」「ふぅーん…」
柚木が、分かったような分からないような顔をして、マップを覗き込む。
間違いなく、分からないのだ。
多摩川のサイクリングロードくらいはギリギリ分かっているかもしれないが、むしろ半端に分かってしまったせいで、自分の分かってなさが分からない状態になっていることだろう。
街乗り派の合言葉に「柚木を1人で走らせるな」というのがある。
順調についてきているな、と思って一瞬目を離した隙に、何かに気をとられては、ふっといなくなるのだ。…まぁ、道を知ったうえでコースを外れているのなら、何も言うことはないんだけど、彼女は百発百中で迷子になる。
それでも発見が早ければ、割とラクに元のコースに戻せる。しかし彼女の場合、無駄に脚力がある上に、闇雲な行動力であっちこっち走り回るので、迷子が発覚した時には取り返しがつかないほど遠くに行ってしまっていることが多い。そして「なんか、変な所に出ちゃった!…んとね、十字路の先に薬屋があってね、『山梨↑10km』って書いた青い看板が…」みたいな絶望的な電話が掛かってくるのだ。
それでも僕の守備範囲にいるうちは、なんとか携帯で遠隔操作して正規ルートに戻せるけれど(この「柚木サルベージ」のお陰で、僕は鋼の方向感覚と呼ばれ始めた)、たまに僕もお手上げな程、遠征している場合がある。そんなときはどうするか…
放っておくのだ。
すると、嗅覚なんだか帰巣本能だか知らないが、彼女は不思議と源流にたどり着く。
「鮭と同じ原理で帰ってきているのだ」と、鬼塚先輩は言う。だとすると嗅覚のほうか。
「食べる?」
ふいにポッキーの袋を差し出されて我に返る。
「あ…ありがと」おずおずと手を伸ばす。先輩達も、のそりのそりと群がってきた。
「最近のポッキーはすげぇなぁ、柚木よ」
「なんだこのデコレーションは。ポッキー異様に太くなってんじゃねぇか」
武藤先輩が、毛の生えたごつい指を袋にねじ込んで可愛いポッキーをつまみ出し、面白くもなさそうな顔で噛みしめる。ポッキーがケダモノに汚されたような絵ヅラだ。
「文句言うなら食べないでくださいよぅ」
柚木がぷぅ、とむくれる。続いて鬼塚先輩がポッキーに手を伸ばした。
「ははは…それより柚木、鬼塚はさっき便所でチンコ触って手を洗ってないぞ」
「え!?」
柚木が、そして鬼塚先輩がびくっと肩を震わせる
「そして、俺もだ」
「キャアアァァァア!!」
柚木が飛びのいた拍子にポッキーの箱を取り落とす。
「あーあ、もったいね」
「最っ低!!もうそれいらないから!!」
「いらねぇか、ラッキー」
武藤先輩はポッキーをひょいとくわえると、床に落ちた箱をつまみあげた。
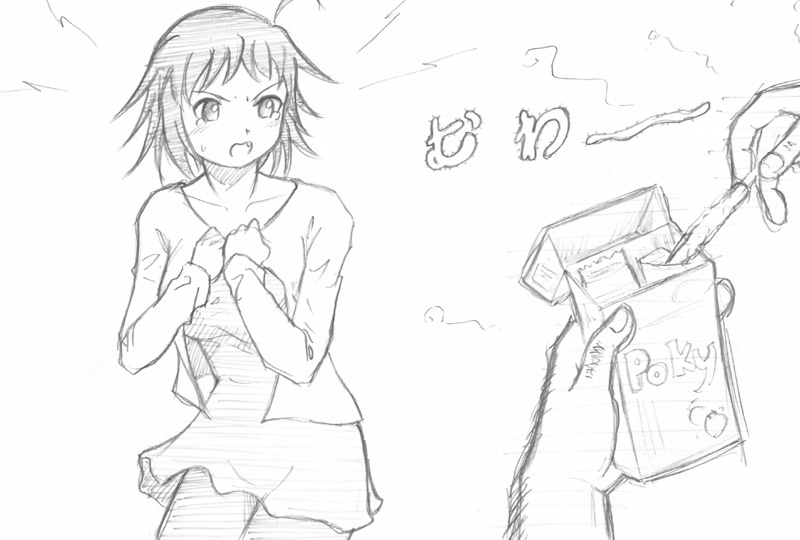
「うめぇ!…ほれ、お前も食わんか」
「…いや、いいっす」僕は即座に断った。
「ちょっと!それ高かったんだから!ポッキー代返して下さいよ!!」
「じゃ、ポッキー返す」
「そうじゃないでしょ!!…ああぁぁもう!!最近こんなことばっかし!!」
頭をかきむしって柚木が叫ぶ。…『こんなこと』とは、紺野さんがMOGMOGを勝手にインストールした件のことを言っているのだろう。
「まぁまぁ…じゃあこれ開けようか」
僕はカバンの奥から『期間限定キノコの山 野イチゴ味』を取り出して机に置く。真っ先に手を出してきた武藤先輩を払いのけ、柚木がキノコの山を奪い取った。
「やった、いいの持ってんじゃん!これ、どっちにしようか迷ったんだよねー!」
「ははは…偶然ね…」
実は前回のサークルで、女子が「新作イチゴ菓子をみんなで持ち寄って試食しよう!」と相談していたのを立ち聞きして、あわよくば「うわっ偶然~!僕も今持ってるんだよね!」などと、どさくさに紛れて試食に混ざりたい!と考え、用意しておいた。しかし、部屋に入って早々先輩達に捕まり、野望はあえなく潰えたのだ。
「で、これが次のコース?」
キノコの山をぽりぽりかじりながら、柚木は僕のノーパソを覗きこんだ。もう機嫌は直っているようだ。
柚木は例えば、理不尽な手段で先輩にポッキーを取られても、代わりのものが手に入れば、ポッキーを取られた経緯をすっかり忘れて無防備になる。
彼女のそういう部分を、僕はいつも「生き物的にはどうなのか」と思ってしまうが、潔い感じがしてわりと嫌いじゃない。とりあえず、人間が捕食される側の生き物じゃなくて本当に良かった。柚木みたいな子でも、厳しい大自然とかに淘汰されることなく元気に生きていける。
しかし、逆に柚木は『代わるものが手に入らないと絶対に許さない』という一面も持っている。だからこそ、僕はしつこく気になっているのだ。
柚木はどうして、紺野さんを許したのだろう?
紺野さんを気に入っているのは態度から分かるけど、それは「代わるもの」じゃない。いや、むしろ紺野さんが「代わるもの」を差し出したことが、柚木の態度の豹変に関わっている気がする……
そして僕は、一つだけ確信している。
紺野さんが柚木に提供したものは、『物』じゃなくて『情報』だ。
柚木と紺野さんが物陰で何かを話し合っていたのは、ほんの1~2分。柚木は小さな封筒以外、なにも持っていなかった……MOGMOGを手に入れると同等の、紙切れ1枚分程度の情報、とは一体なんだろう……。
「やだ!ちょっとやめて下さいよ!!」
柚木の悲鳴で、はっとわれに返る。武藤先輩が、再びキノコの山にちょっかいを出し始めたのだ。
「なにをキサマ!先輩命令だ、キノコの山もよこせ!」
「絶対イヤ!近寄らないでよ、このモテない菌!!」
「菌ならキノコは俺の眷属だろうが!その手を離せ、この方向音痴の鉄砲玉が!!」
「方向音痴が関係あるかっ!これ以上食べ物に触れたら殺す!!」
小学生のようにキノコの山を奪い合う二人を尻目に、鬼塚先輩が再び画面に向き直る。
「…柚木も放っておけばいいのに。武藤のアレは、気になる子に意地悪したくなる小学生と何も変わらんというのにな、姶良よ」
そういいつつ、柚木から巻き上げたポッキーをちゃっかり自分の物にしている。彼らが小学生なら、この人は中学生だ。僕は適当にあいづちをうつ。
「…ですよね。そんなに気になるなら優しくして距離を縮めるとか…。」
「『いい人』というのも、なかなか救いがたい立ち位置だがな…」
僕のことを言われている気がした。
「分かってますよ。…でも面倒じゃないですか、駆け引きとか」
「あぁ…ギャルゲーのように、ひたすら優しさの積み重ねで女が落ちてくれるなら、俺達ゃどんだけモテモテだろうな、姶良よ…」
「空しいこと言わないでください…」
しばらくぼんやりと宙を見据えていた鬼塚先輩の視線が、ふいに画面に戻った。
「本当に、良く出来たコースだな」
「なんですか、改まって」
「…メンテナンスの腕も、そこそこ上がってきたな、姶良よ」
「そんな…まだまだ勉強中ですよ」
「いや、お前の仕事には、高いポテンシャルを感じずにはいられない」
「いえ!断じてそんなことは…」
「謙遜をするな。お前には力がある…次世代のマニア派を束ねていく力が!」
「そんなイヤな力、断じてありません!!」
ふいに外堀を埋めていくように言葉を重ねはじめた鬼塚先輩に、危険な予感を覚えてイスごとあとじさる。
「なぁ姶良よ、お前に折りいって話があるのだが…」
「時期早尚もいいトコです、それだけは勘弁してください!!」
僕の悲鳴にも近い懇願の声に、武藤先輩がいち早く反応して、キノコの山争奪戦から離脱してきた。
「お?鬼塚、とうとう『アレ』を譲るのか?」
「イヤほんとやめてください!僕、ああいうのはちょっと…」
「やれやれ、やっちまえ!『アレ』は早いに越したことはない!」
武藤先輩が野次馬根性で煽りまくると、柚木も首を突っ込んできた。
「姶良なら『アレ』、ぜったい似合うよ!」
「似合いたくないよ!」
「……うぅむ……予感がしてきた……予感がしてきたぞ」
身をすくませる僕の肩を乱暴に掴むと、鬼塚先輩は地を這うような声で宣言した。
「…お前は『呪われたランドナー』を継承する…」
「イヤですよ!!」
…我がポタリング部(の一部)には、代々継承されている自転車がある。
『ランドナー』とは、長距離走行用にフランスで開発され、日本の自転車職人によって独自の進化を遂げていった、アンティーク自転車のことである。
もう一度言おう、アンティーク自転車だ。
今でこそ『自転車界の絶滅危惧種』だの『デコチャリの一種』だのひどいこと言われ放題だけど、昔は、未舗装道路も山岳地帯もものともしない頑丈なボディで人気を博していたのだ。懐中電灯のようなライトや太いタイヤ、いやに立派なスタンドやキャリアなどの、今では冗談みたいな装備も、当時は魅力の一つだった(と現オーナー・鬼塚先輩から聞いた)。でもやがてMTBやロードバイクなどに人気を奪われ、取り扱い店は激減。パーツも続々生産中止となり、いくら頑丈でも、壊すと代わりのパーツが手に入らない、デンジャラスな車種と成り果てた。
だから今では一部の熱心なマニアが、数少ない取扱い店でオーダーメイドで手に入れて、乗りもしないで飾っておく骨董品的なポジションに落ち着いている。
しかし、我が部に伝わる『それ』は、そういう類のものじゃない。
古いのは古いのだろう。50年以上は乗り継がれていると聞いた。正確な年代は分からない。何しろメーカーが不明だから、製造年の見当をつけようがないのだ。自作なのかもしれない。
そして幾星霜にわたり、素人に毛がはえたような部員にテキトーなメンテナンスを施され続け、部品が壊れればMTBやロードバイクの部品を無理やりはめ込まれ、ますます正体不明さを増していく、鵺のような自転車。もはやこれは本当にランドナーなのかも疑わしくなってきている。
それでもランドナーとしてアイデンティティを主張し続ける、ボコボコに膨らんだサイドバッグや、荷台にくくりつけられた寝袋の絶妙な貧乏臭さが、乗る者をしてホームレスかと思わしめる。しかも随分前の継承者が、ライトが壊れた際に冗談でくくりつけた懐中電灯が、そのまま引き継がれてしまっている。アンティークの尊厳なんか微塵もない。
そしてこれを引き継いだ部員は、次の継承者が現れるまで、このランドナーでサークルに参加しなければならない。
ならない、というか、せざるを得ない状況になる。
ランドナーが次の継承者を求めるとき、継承者の愛車が「屠られる」。
事故か、盗難か、寿命か…理由は様々だけど、とにかく継承者は偶然の不幸で愛車を喪う。そして、備品貸与の形でランドナーを受け継ぐ羽目になるのだ。それが『呪われたランドナー』たる由縁らしい。
歴代継承者の中には、愛車が潰れた直後、新車を買った人もいたそうだ。しかし新車はものの3日で、愛車と同じ末路を辿った(と鬼塚さんから聞いた)。
それ以来、半ば諦めをもって受け入れられ続けているこのランドナー継承。こいつ自体を屠ってしまおうという提案は、不思議と挙がったことがない。
「…今まで何十台も自転車を屠ってきたランドナーを潰して、無事で済むと思うのか、姶良よ…」
現オーナーは、鬱っ気たっぷりのため息を吐き出して、そう答えた。
そしてここからが、最も恐ろしい話なんだけど……
『呪われたランドナー』を継承した者は、列島縦断の旅に出るしきたりがあるのだ。
あの貧乏ランドナーで3000キロ以上の距離を走破!……死人が出てもおかしくない、無謀旅行だ。そして案の定、ランドナーは毎日のようにぶっ壊れまくるそうだ。近くに部品屋がなくて、半分泣きながらランドナー引き引き十数キロ歩くなんてことも1回や2回じゃなかった、と鬼塚さんから聞いた。事実、列島縦断から生還した部員は、別人のようにメンテナンスの腕が上がっているという……。
「……ランドナー継承も列島縦断もお断りします」
「それを決めるのは俺じゃない」
鬼塚先輩が、窓の外に視線を走らせた。無個性な自転車たちが居並ぶ駐輪場で、ホームレス仕様の『それ』は異彩を放っている。
「…『屠られる』とか言うけど、年に1人くらい、うっかり者が自転車を壊したりなくしたりするなんて、何処のサークルでもあることでしょう?連続して自転車を壊したとかいう人は、よっぽど迂闊だったんですよ」
「…俺も、最初はそう思っていたよ…」
鬼塚先輩は、一瞬にやりと笑うと、再びノーパソに向き直った。
「…あいつには何か、魔性があるんだ。…姶良よ、お前にもいずれ分かる」
「魔性じゃなくて愛着でしょう。それこそ、よくあることですよ」
「あ、あのぅ…むつかしいお話、終わり…ですか?」
地図の端をめくって、ビアンキがそっと顔を覗かせた。せっかく全画面表示にしたのに…。
「ん、そろそろ終わりだよ。悪かったね、放っておいて」
「あ――――!!!」
柚木が突然声を張り上げ、ノーパソの方に身を乗り出した。
「な、何だよ」
「この服!なにこの服!!」
「服って…べつにいつも通りの」「あんたの服じゃない!!」
ぴしゃりと言い放つと、柚木はノーパソの液晶を叩いた。
「ビアンキのワンピース!MOGMOGには着せ替え機能はなかったはずだよ!!」
「……げ」
そっと、メッセンジャーバッグに手を伸ばす。これ以上騒がれる前に、ノーパソをひったくって逃走しよう……。
後書き
(2)に続きます。
ページ上へ戻る
全て感想を見る:感想一覧
