| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
Dragon Quest外伝 ~虹の彼方へ~
作者:読名斉
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動Lv28 アルカイム街道(i)
[Ⅰ]
やや曇った空の元、風の帽子の力によってマルディラントを発った俺達は、昨日と同様、リジャールさんの家の裏手へと降り立った。
そして、正面に回って玄関扉を開き、中に向かって呼びかけたのである。
「おはようございます、リジャールさん。コータローです。言われた通りやってきました」
家の奥からリジャールさんの元気な声が聞こえてくる。
「おお、来たか。ではコータローよ、お主だけ中に入ってきてくれ。昨日、報酬を渡した部屋じゃ」
「え? 俺だけですか。……わかりました。では、お邪魔します」
なぜ俺だけなのかがわからなかったが、とりあえず、指示に従う事にした。
昨日の部屋へと進むと、丸テーブルの椅子に腰掛けるリジャールさんの姿があった。
リジャールさんは俺の姿を見るとニコリと微笑んだ。
「ではコータローよ。そこの空いている椅子に腰掛けてくれ」
「はい」
俺が椅子に腰掛けたところで、リジャールさんは話し始めた。
「まずは、おはようじゃな。昨夜はよく眠れたかの?」
「ええ、よく眠れましたので、今日は調子がいいですよ」
「それは良かった。さて、それでは本題に入ろうかの……」
と言うとリジャールさんは、茶色い革製の巾着袋をテーブルの上に置いたのである。
巾着袋の大きさは、日本で売っている一般的な弁当箱が入る程度の物で、中に重い物が入っているのか、ずっしりとした感じであった。テーブルに置いた時にシャリンという金属音が聞こえたので、もしかすると、中身は金物系のアイテムかもしれない。
リジャールさんは巾着袋を俺に差し出した。
「昨日、お主に渡すと言った物じゃが、それはコレの事じゃ」
「これは?」
「とりあえず、中を見てみい」
「では……」
リジャールさんの意図がよく分からないが、俺は巾着袋を手に取ると、言われるがままに中を確認した。
だが次の瞬間、俺は目を見開いて驚いたのである。
なぜなら、巾着袋の中には、カーンの鍵に似た物が幾つも入っていたからだ。
「え!? これは一昨日のアレですよね……しかも、こんなに沢山……どうしてこんなに」
「ああ、お主の言うとおり、それはアレじゃ。しかしの、それは代替え素材で作った紛い物なのじゃよ。1度使うと形状を維持できずに砕けてしまうので、不便といえば不便じゃが、もし何かあった時の為に予備で持っておくとよいと思っての。まぁそういわけで、アレの事は、あまり大きな声で話すわけにはいかぬから、お主だけを呼んだのじゃよ」
俺はリジャールさんの話を聞いて、ドラクエⅠに出てきた魔法の鍵を思い出してしまった。
確か、Ⅰの魔法の鍵も、一度使うと壊れる設定だったからだ。
まぁそれはさておき、持っていても損はない物なので、俺は快く鍵を貰う事にした。
「そうなのですか。では、ありがたく頂戴いたします」
「うむ。持ってゆけ。それから、また欲しくなったら、儂の所に来るがいい。幾らでも作れるからの」
「はい、その時はまたよろしくお願いします」
代替え素材とはいえ、こういった物を作り上げてしまう、その手腕は流石だなと思った。
老いたりとはいえ、今でも超一流の錬成技術を持っているのだろう。ヴァロムさんが頼るわけだ。
「ところでコータローよ。ティレス様は、守護隊の派遣について何か言っておったかの?」
「ええ、それなのですが……ティレス様は今日中に第1陣を発たせると言っておりました。なので、恐らく、2日後には第1陣の部隊がこちらに到着すると思われますよ」
リジャールさんは安堵の表情を浮かべた。
「そうか、それは良かった。儂もその旨を村長に伝えておこう」
俺も昨晩の事を訊いてみた。
「昨晩はどうでしたかね? ヴァイロン達は現れましたか?」
リジャールさんは頭を振る。
「いや、現れなんだ。お主の言うとおり、今は攻め手を欠いておるのかもしれぬの。まぁこちらも今の内に警備体制を整えておけるので、その方が好都合じゃがな」
「確かに……あ」
と、そこで俺は、昨日、訊けなかった事を思い出したのである。
ちなみにそれは、サナちゃん達がいたので訊けなかった事であった。
「あの……この魔導の手なんですけど、ヴァロムさんが使っているところを見た事がないんですが、ヴァロムさんも以前は使っていたのですかね?」
「いや、ヴァルは魔導の手を使っておらぬ。というか、ヴァルなら、使わぬでも同じ事が出来るからの」
「え、それってどういう……」
「お主のその口振りじゃと、まだヴァルから、大賢者が編み出した秘法を学んではおらぬようじゃな」
大賢者の編み出した秘法……多分、アレの事だろう。
「それって……もしかして、魔生の法の事ですかね? それなら、今、学んでいる最中ですが」
「ほう、そうか。ならば話は早い。これはヴァルが言っておったのじゃが、魔生の法を使っておる時は、周囲に漂う大地の魔力に干渉出来るらしく、魔導の手を使わぬでも同じことが出来るそうなのじゃよ。まぁそういうわけで、ヴァルは魔導の手を使ってはおらんのじゃ」
「そ、そうだったんですか、初めて知りました」
まさか、魔生の法にそんな秘密があったとは……。
「実は儂も、お主と同じような事をヴァルに訊いた事があるんじゃ。するとヴァルの奴はの、こんな事を言っておったわ。――やろうと思えば道具無しでもできるのだから、無理して魔導の手を装備する必要はない。腕は2つしかないのだから、自分の能力をもっと高めてくれる物を装備する――との。あ奴らしい答えじゃわい」
「確かにそうですね。ヴァロムさんらしい合理的な考え方です」
「ああ、全くじゃ。……さて、儂から渡す物は以上じゃ。これ以上引き留めると、お主等の旅に支障が出るじゃろうから、もうこの辺にしておこうかの。……っと、そうじゃ、これを言い忘れたわい。投獄されているヴァルに会う事があったならば、儂がこう言っていたと伝えておいてくれ。『何をするつもりなのか知らんが、お主も年なんじゃから、あまり無理をするなよ』との」
「ええ、必ず伝えておきます」
リジャールさんからしたら、こう言いたくなるのも仕方ないだろう。
まぁそれはともかく、俺もそろそろお暇させてもらうとしよう。
「ではリジャールさん。皆も待っていると思いますので、俺もこれで失礼させて頂こうと思います」
「うむ、見送ろう」――
玄関の前で待っている皆の所へ戻った俺は、そこでリジャールさんに向き直り、別れの挨拶をした。
「リジャールさん、短い間でしたが、色々とありがとうございました」
「いやいや、世話になったのはこちらの方だ。またいつでも気兼ねなく訪ねてきてくれ。お主等にはそれが出来るのじゃからな。カッカッカッ」
リジャールさんはそう言って豪快に笑った。
俺は思わず苦笑いを浮かべる。
「はは、その時はよろしくお願いしますよ」
「うむ」
出会って2日しか経っていないが、この人ともこれでお別れかと思うと、少し寂しさが込み上げてくるから不思議なものである。
多分、話しやすい人だからなのだろう。
なぜか知らないが、何日も一緒にいたような錯覚を覚えるくらいである。
「それから、カディスさん達にもよろしくお伝えください。警備の邪魔しては悪いので、俺達はこのままガルテナを発つつもりですから」
「ああ、伝えておこう。それと道中は気を付けるがよいぞ。人づてに聞いた話じゃが、王都に向かうにつれて、魔物も強くなってきておるそうじゃからの」
「ええ、十分に気を付けて進むつもりです」
続いて、他の皆もリジャールさんに挨拶をしていった。
「ありがとうございました、リジャールさん。色々と勉強になりましたわ。またお会いしましょう」
「リジャールさんもお元気で」
「お世話になりました、リジャールさん」
「ではリジャール殿、お身体に気を付けて下され」
リジャールさんは皆にニコリと微笑んだ。
「うむ。お主達も元気でな。たまには顔を見せに来るがよい」
「はい、その時はまたよろしくお願いします」と、サナちゃん。
そして、俺達は最後にもう一度、リジャールさんにお別れの言葉を告げ、この場を後にしたのであった。
「ではリジャールさん、お元気で」と。
俺達はその後、宿屋の厩舎に立ち寄り、馬と馬車を引き取りに行った。
そして、来る途中にあった分かれ道にまで戻り、その先にあるモルドの谷へと向かって馬車を走らせたのである。
[Ⅱ]
ひっそりと静かな木陰が続く山道に、カラカラとした俺達の馬車音が響き渡る。
耳を澄ますと、そよ風に揺れる枝葉のさわさわとした音や、キィキィと鳴く野鳥の声が聞こえてきた。
俺は今まで魔物の襲撃を過剰に警戒するあまり、自然界の音にそれほど気を配ってこなかったが、こうやって耳を傾けてみると、妙に気分が落ち着くものだなと思った。
もしかすると、自然が奏でる何気ない音には、思った以上にリラクゼーション効果があるのかもしれない。
まぁそれはさておき、俺達がガルテナを出発してから20分程経過したところで、前方にV字型になった深い谷が見えてくるようになった。恐らく、あれがモルドの谷と呼ばれる所なのだろう。
谷には頭上を遮る枝葉もない為、空一面がモクモクとした灰色の雲に覆われているのが、ここからでもよく見える。が、見た感じだと雨雲ではなさそうなので、今しばらくは雨の心配をしなくてもよさそうだ。
また、果てしなく伸びる道の両脇には、青々とした草木が生い茂る緩やかな山の裾野が広がっており、その遥か頂きへ視線を移すと、天を突き刺すかのような鋭利な刃物を思わせる山の先端部が、俺の視界に入ってくるのである。
見た感じだと、標高は2000mくらいだろうか……。まぁその辺の事はわからないが、ここはガルテナ連峰と呼ばれる山岳地帯なので、それくらいはあっても不思議ではないだろう。
とりあえず、モルドの谷とはそんな感じの所であった。
話は変わるが、谷の名前であるモルドとは、その昔、この地で活躍した旅の戦士の名前だそうだ。
これはガルテナを出発する前に宿屋の主人から聞いた話なのだが、なんでも、300年ほど前に谷で悪さしていた魔物がいたらしく、それをモルドという戦士が退治してくれた事から、村の者達が感謝の意を込めてそう名付けたそうである。
まぁこの手の英雄譚は日本昔話でもよく見かけるので珍しくもなんともないが、何気ない地名にもちゃんと由来はあるようだ。
つーわけで、話を戻そう。
モルドの谷を暫く進んだところで、ティレスさんから預かっている物があるのを俺は思い出した。
ちなみにそれは、旅が始まったらアーシャさんに渡してくれと言われていた手紙であった。
とまぁそんなわけで、俺は道具入れの中から白い封筒を取り出し、隣に座るアーシャさんにそれを差し出したのである。
「あの、アーシャさん。ティレスさんから預かった手紙があるんですよ。これなんですけど」
「え、お兄様から? 何かしら、一体……」
アーシャさんは首を傾げながら手紙を受け取ると、早速、封を解いて中のモノに目を通していった。
すると次第に、アーシャさんは口元をヒクつかせ始めたのである。
「ん、もうッ! お兄様は、私がコータローさん達と旅をしているのを知っていたのですね。知っていたのなら、ハッキリと仰って下されば良かったのにッ」
実を言うと、既にバレている事をアーシャさんは知らない。
ティレスさんから内緒にしておいてくれと言われたので、それについては話してないのだ。
なぜこんな事をしたのかわからないが、多分、ティレスさんのちょっとした悪戯なのだろう。
「まぁまぁ、アーシャさん。多分、ティレスさんなりの考えがあったんだと思いますよ。でもよかったじゃないですか、ティレスさんも俺達と同行するのを認めてくれたのですから」
「ええ、まぁそれはそうなのですが……って、なんで貴方が、それを知っているんですの?」
しまった……。
余計な事を言ってしまったようだ。
「じ、実はですね。昨晩、ティレスさんから、そう聞いたんです」
「なんですってぇ! あんまりですわ、お兄様! コータローさんもコータローさんですわよ。知っていたのなら、一言仰って下されば良かったのにッ。これじゃ、気を使ってきた私が馬鹿みたいですわ」
アーシャさんは捲し立てるようにそう言うと、釣り上げられたトラフグの如くプンスカと頬を膨らましたのである。
このままだと俺に火の粉が降りかかりそうなので、とりあえず、事情を話しておくことにした。
「だ、黙っていてすいませんでした。ですが、黙っているようにという指示を出したのはティレスさんなんですよ。お、俺はそれに従っただけなんです」
「へぇ……そうなのですか。帰りましたら、お兄様にはどういう事なのか、問いたださなければなりませんわね……」
アーシャさんは執念深いので、ティレスさんも後が大変そうだ。
まぁそれはさておき、俺は他の内容について訊いてみる事にした。
「それはそうとアーシャさん。手紙には他に、なんて書いてあったのですか?」
「ここに書かれているのは、今言った内容と、引き続き、朝と晩はちゃんと顔を見せに来るように、という事だけですわ」
「じゃあ、今まで通りって事ですね」
「確かにそうですが、納得いきませんわッ」
アーシャさんはまだご立腹のようだ。
暫くはこんな感じが続きそうである。はぁ……。
と、ここで、サナちゃんが話に入ってきた。
「でもよかったですね、アーシャさん。お忍びで旅を続けるのは、アーシャさんも気が楽でなかったと思いますから。それに、コータローさんとアーシャさんは、レイスとシェーラ以外で、私が気を許せた初めての方達ですから、アーシャさんが気兼ねなく旅を続けられると聞いて、今、凄くホッとしてるんです。ですから、これからもよろしくお願いしますね、アーシャさん」
サナちゃんはそう言って、屈託のない笑みを浮かべた。
するとアーシャさんは、サナちゃんの微笑みに毒気を抜かれたのか、少し戸惑いながら、いつもの表情に戻ったのである。
「え、ええ……こちらこそよろしくお願いしますわ、サナさん」
どうやらサナちゃんは微笑みだけで、アーシャさんを鎮めるのに成功したようだ。
回復系魔法が得意なだけあって、この子自身も、癒しの効果を持っているのかもしれない。ある意味、貴重な人材かも。
続いてサナちゃんは俺へと視線を向けた。
「あの、コータローさん。……昨日の事でお訊きしたい事があるのですが、今いいでしょうか?」
「いいよ、何?」
「昨日、リジャールさんの家を出発する前なのですけど、コータローさんは、坑道内に水が流れている所や湧いている所があるのかどうかを訊ねていた気がするのですが、あれは何の為に訊いたのですか?」
何かと思ったら、それの事か。
「ああ、あれはね、もし死体以外の魔物がいた場合、飲み水はどうしてるのかと思って訊いたんだよ。俺達のように食料や水を摂取しながら生きる魔物なら、長い間、飲まず食わずというのは流石に厳しいからね。その上、水は食料以上に持ち運びや保存が難しいし。だからさ」
サナちゃんは納得したのか、感心したように首をゆっくりと縦に振る。
「そ、そういう意図があったのですか。それは気が付きませんでした」
「まぁ、それが理由さ。で、あの時リジャールさんは、出入り口が1つしかない事と、警備を付けてから20日以上経過している事に加え、魔物の出入りもないような事を言っていたので、俺はこう考えていたんだよ。『坑道内にいるのは、水や食料を必要としない魔物ばかりの可能性がある』とね。でも、まさか、死骸だらけとは思わなかったけどさ」
実を言うと、事前にオッサンから魔物を操る奴がいるかも知れないと聞いていたので、腐った死体だけでなく、泥人形みたいな魔物もいるかも知れないと思っていたのである。
なので、少し拍子抜けした部分もあるのだった。まぁ色々と理由もあるのだとは思うが……。
と、ここで、アーシャさんも話に入ってきた。
「貴方って時々、意味の分からない質問をしますが、こうやって聞いてみると、的を得た事を訊いてるのですね。勉強になりますわ」
「いやぁ~そうですかね。そんな風に言われると、なんか照れるなぁ。なははは」
俺は思わず後頭部をポリポリとかいた。
「コータローさんのお話って為になるのが多いので、もっと色々と聞かせてください」
「う~ん……お話といわれてもねぇ。じゃあ、サナちゃんは何について聞きたいの?」
「では、コータローさんが見たという、魔物や魔法について書かれた書物のお話をお願いします」
「あ、それは私も聞きたかった事ですわ」
「それかぁ……」
あまり触れたくない話題ではあったが、仕方ない。
当たり障りない話でもしておこう。
とまぁそんなわけで、俺はこの道中、サナちゃんとアーシャさんに幾つかのドラクエ話をする事になったのである。
[Ⅲ]
ガルテナを発ってから3時間ばかり経過すると、前方に、広大な緑の平原が見えてくるようになった。地図で確認すると、どうやら、あれがバルドア大平原のようだ。
そんなわけで、程なくして、モルドの谷を抜けた俺達は、そのままバルドア大平原を真っ直ぐと北に進み続けるのである。
今まで少し閉鎖的な山の中にいた所為か、このバルドア大平原は凄く解放された気分になるところであった。
馬車の中からバルドア大平原をグルリと見回すと、果てしなく広がる平坦な緑の草原と、そこにポツンポツンと点在する木々に加え、遠くに舞う鳥達の姿が視界に入ってくる。
そして、時折吹く心地よい風が、穏やかな大海原の波のように、草原を優しく靡かせているのである。
それは美しい光景であったが、どことなく夏の北海道に広がる牧草地帯のようにも見える所為か、それほどの感動は湧いてこなかった。というか、懐かしさのようなものを感じさせる光景であった。
俺は北海道に行った事はないが、日本でも見かける風景なので、そう感じるのだろう。
まぁとりあえず、バルドア大平原はそんな感じの所である。
話は変わるが、このバルドア大平原からはマール地方でなくバルドア地方と呼ばれる地域になる。
この地を治める太守はイシュマリア八支族の1つであるラインヴェルス家が担っているそうで、このバルドア地方最大の都市であるバルドラントという街にて、執政を行っているようである。
そんなわけで、必然的にアレサンドラ家の管轄外になる地域なのだが、境となる部分に関所のようなものはないそうだ。多分、そういった物が必要ない統治方法をしているのだろう。
ちなみにだが、イシュマリア国には地方が九つあり、それらは八支族とイシュマリア王家によって分割統治されているそうである。
各地域の統治形態は中世の欧州や日本でも見られる封建制度のようだが、統治する者が神の御子イシュマリアの血族ということもあり、この国では統治者による戦乱の歴史とかはあまりないそうだ。とはいっても領地間における多少のいざこざはあるみたいだが……。
まぁそれはともかく、王家と八支族による地方分権型の統治システムは、建国以来うまく機能しているみたいである。
つーわけで、話を戻そう。
バルドア大平原に入ってからというもの、俺は少し気が楽になっていた。
なぜなら、辺りには背の低い草木しかない為、非常に見通しが良く、魔物の監視がしやすいからだ。
以上の事から、俺は少しだけ緊張を解き、肩の力を抜いて周囲の警戒に当たっているのである。
とはいえ、ここまでの道中、魔物との戦闘は4回ほどあった。遭遇した魔物は、キャットフライや兜百足、それから毒芋虫といった感じなので、ゲームならば、まだまだ序盤の敵である。撃退するのはそれほど難しくはない。が、しかし……王都に向かうにつれて、徐々に魔物が強くなってきているという、この事実が、精神的に重く圧し掛かってくるのである。
そして、俺は1人、考えるのであった。
この先、一体、どんな魔物が待ち受けているのだろうかと……。
バルドア大平原を暫く進み続けると、街道のすぐ脇に、幅100mほどの大きな河が流れている所があった。
馬の休憩がそろそろ必要だったので、俺達はそこで少し休むことにしたのである。
俺はレイスさんとシェーラさんに馬の世話をお願いすると、馬車を降りて外に出る。
それから、両手を目一杯に広げて背伸びをした後、軽い屈伸運動をして、俺は旅の疲れを癒したのであった。
暫くそうやって体を動かしていると、サナちゃんとアーシャさんが俺の隣にやって来た。
「コータローさんは、この辺りに来たことがあるのですか?」
「いや、初めてだよ。サナちゃん達と同じさ。アーシャさんは?」
「私も初めてですわ。ところでコータローさん、ルーヴェラまでは、あとどの位かわかりますか?」
「ちょっと待ってくださいね」
俺は馬車の中から地図を持ってくると、2人の前に広げた。
「地図を見る限りだと、あと暫くは進まないといけないようですね。今進んでいるアルカイム街道とこの河の位置関係を考えるに、多分、俺達はこの辺にいるんだと思います。ですから、もう半分以上は進んだようですよ。この調子だと、日が落ちる前には、今日の目的地であるルーヴェラに着けるんじゃないですかね」
今言ったアルカイム街道がルーヴェラへと続く道の名前であり、王都へと続く道の名前でもある。
ちなみにだが、アルカイムという名前は王都オヴェリウスのあるアルカイム地方へと続くことからつけられた名前のようだ。
わかりやすいネーミングである。
「では、順調に進んでいるんですね。よかったです」
「そのようですわね。次の街はどんな所か楽しみですわ」
アーシャさんはそう言ってニコリと微笑んだ。
と、その時である。
【お~い、あんちゃん達ィ~、大変や~、向こうで大変な事が起きとるんや~】
流暢な関西弁が、俺達の頭上から小さく聞こえてきたのであった。
(ン……誰だ一体)
俺は声の聞こえた上空に視線を向ける。
そして、俺は驚きのあまり、思わず目を見開いたのである。
「なッ、なんだありゃ!?」
そこにいたモノ……それはなんと、愛らしい顔に蝙蝠の翼をもつ赤色の魔物であった。そう、ドラキーである。
しかも、黒い鞄をランドセルのように背負った、奇妙な出で立ちの赤いドラキーが、パタパタと羽ばたいていたのだ。
(なんなんだ……この流暢な関西弁を喋るドラキーは……)
と、ここでアーシャさんの声が聞こえてきた。
「あら? あれはドラキー便のドラキーじゃありませんの」
「へ? あれがドラキー便なんですか……」
「ええ、間違いありませんわ。鞄を背負った赤いドラキーですし」
「あっ、そうか……赤いドラキーは書簡配達してるんでしたっけ……」
そういえば以前、ヴァロムさんがこんな事を言っていた。
遠隔地の書簡配達業務は、ドラキー便が良く使われているというような事を。
しかもヴァロムさん曰く、この赤いドラキーは結構な距離を休みなしで飛べるだけでなく、幾つかの攻撃魔法も使えるので、危険地帯の書簡配達員みたいな事を生業としているのだそうだ。
おまけに、人と会話も出来るほど知能も高く、話の分かる魔物なので、人とも仲良く共存共栄できるそうである。
余談だが、貴族お抱えのドラキー便もあるそうだ。以前、ヴァロムさんに書簡を持ってきたドラキーも、オルドラン家のお抱えドラキーらしいので、その辺は色々と込み入った事情があるのだろう。
俺のプレイしたドラクエでは敵であった赤いドラキーだが、ここでは意外にも人間社会に溶け込む種族のようである。
つーわけで、話を戻そう。
流暢な関西弁を喋るドラキーは、馬車の屋根に降り立つと慌てたように話し始めた。
【あ、あんちゃん達、イキナリですまんけど、この先の十字路付近で、旅の商人が魔物の集団に襲われとるんや。護衛についた冒険者だけでは多勢に無勢で手に負えんようやから、助けてやってや。お願いや! あんちゃん達、強そうやし】
さて、どうしたもんか……。
人間と共生してる魔物なので嘘ではない気がするが、このドラキーが一芝居うっている可能性も勿論否定できない。
だが、もし本当ならば放っておくのも後味が悪いところである。
とりあえず、俺は皆の意見を聞くことにした。
「魔物かぁ……。皆、どうします?」
「かなり差し迫った状況のようですので、助けに行った方がいいのでは」と、アーシャさん。
と、ここで間髪入れず、ドラキーがお世辞を言う。
【ありがとう、綺麗なネェちゃん。ネェちゃんならそう言うてくれると思った。綺麗なだけじゃなくて、すごく素敵な人やわぁ。棘の無い綺麗な女の人に、こんな所で会えるなんて思わんかったわぁ。長生きはするもんやで、ほんま】
するとアーシャさんは今の言葉に気をよくしたのか、声高にこう告げたのだ。
「コータローさん、早く行きましょう! こうしてる間も、魔物に苦しんでいる方々がいるのですよ!」
中々煽てるのが上手いドラキーのようだ。が、とはいえ、本当ならば確かに不味い。
仕方ない……ここはこのドラキーの言う事を信じてみるとしよう。
「レイスさん、馬の調子はどうですか?」
「もう少し休みたいところだが、事情が事情だ。仕方あるまい。行こう、コータローさん」
「じゃあ、行きますか。と、その前に……。襲っている魔物はどんな奴等なんだ? それと魔物の数は?」
【襲ってるのは、ごっつい百足とごっつい大猿が10数体に、ドルイドとかいう酒樽みたいな格好のけったいな奴等が8体や。キツイ敵かも知れんけど、助けてあげてぇな】
多分、ごっつい百足は兜百足か鎧百足あたりで、ごっつい猿が暴れ猿かキラーエイプってとこだろう。
とりあえず、その程度の魔物なら、何とかなりそうだ。
「数が多いから面倒だが、仕方ない。急ごう」
【よっしゃ、そうと決まれば善は急げや。ワイについてきてぇな】
そして俺達はこの場を後にしたのである。
[Ⅳ]
ドラキーに案内される事、約5分。前方に、ドラキーの言っていた十字路が見えてくるようになった。
またそれと共に、十字路付近で9名の者達が、20数体の魔物に取り囲まれるという、非常に危険な状況に陥っているのも、目に飛び込んできたのである。
彼等の内の何名かは深い傷を負っているようで、地面には幾つかの赤い血痕が出来ていた。まさしく、絶体絶命といった感じの光景である。早く手当をしないと不味いかもしれない。
俺は次に、魔物達へ視線を向ける。
魔物は思った通り、兜百足と暴れ猿にドルイドのようだ。
数がかなり多かったが、敵はある程度グループ化しているのが好都合であった。
と、ここでドラキーの声が聞こえてきた。
【あそこや! あんちゃん達、ワイは空から援護するさかい、後は頼んだで!】
ドラキーはそう言うと更に上空へと舞い上がった。
そして俺達は、魔物達に近づいたところで馬車を止め、臨戦態勢に入ったのである。
俺はまずアーシャさんとサナちゃんに指示を出した。
「敵はある程度固まっていますんで、手っ取り早くやっちゃいましょう。先手必勝です。アーシャさんは向こうにいる百足の一団にヒャダルコをお願いします。それからサナちゃんは、杖を持った黄土色のドルイドという魔物達にマホトーンをお願いします」
2人は頷くと、言われた通り、魔法を唱えた。
「ヒャダルコ!」
「マホトーン!」
百足の一団に無数の氷の矢が容赦なく突き刺さってゆく。
また同じくして、ドルイド達の周りには、呪文をジャミングする黄色い霧が纏わりつきはじめていた。
霧が全てのドルイドに纏わりついたのを見ると、どうやら魔法を封じるのに成功したみたいである。
俺は次の指示を前衛に出した。
「ではレイスさんとシェーラさん、今から俺がイオラを使います。ですが、ドルイドは攻撃魔法全般に耐性があると思いますんで、生き残った奴等を仕留めていってください」
「わかったわ」
「よし、いつでもいいぞ」
俺は掌を魔物達に向かって突きだした。
「ではいきますよ。イオラ!」
俺の掌から魔力の塊である白い光が飛んでゆく。
光は魔物達の付近でフラッシュをたいたかのような閃光を放ち、爆発を巻き起こした。
魔物達は爆発をモロに浴びて吹っ飛んでゆく。
この一撃で半数の魔物は死ぬか虫の息状態となったが、思った通り、ドルイドにイオ系は効かないのか、ピンピンとしていた。が、想定の範囲内である。
ここでレイスさんとシェーラさんが、付近のドルイドに一気に間合いを詰め、破邪の剣を振り降ろす。
その刹那、2体のドルイドは脳天から真っ二つに両断されて息絶えたのだ。
と、その時であった。
向こうの冒険者達も俺達の加勢に気付いたようで、生き残った魔物達に向かい攻撃を開始した。
すると瞬く間に戦況は逆転し、魔物達は打つ手なく、俺達の刃に掛かって倒れていったのである。
魔物達を全て倒したところで、ドラキーが俺達の所に舞い降りてきた。
【あんちゃん達、めっちゃ強いやんけ! ワイの援護なんか、全然必要なかったやん。凄いわぁ】
「褒めても何も出んぞ」
【そんなん期待してへんて、ワイの素直な気持ちや】
俺とドラキーがそんなやり取りしてると、向こうの冒険者の1人が俺達の方へとやってきた。
近づいてきたのは眼鏡を掛けた色白の若い男で、イシュラナの紋章が描かれた神官服を身に纏っていた。
ちなみに、イシュラナの紋章とは、一本線が多いアスタリスクみたいなシンボルである。
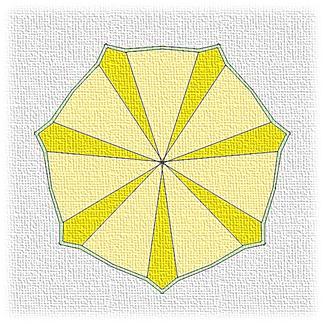
年はかなり若く、俺よりも年下に見える。多分、10代半ばから後半といったところだろう。体型は痩せ型で、背はそれほど高くない。170cmあるかないかといったくらいだ。
この見た目から察するに、どうやらイシュラナ神殿の神官のようである。
男は俺達の前に来ると、深々と頭を下げてきた。
「ど、どなたか存じませんが、危ないところを本当にありがとうございました」
「いや、気にしなくていいよ。それよりも、仲間がかなり深い傷を負っているみたいだから、早く治療をしないと不味いよ」
「あ、そ、そうでした。で、ですが……薬草も魔力も尽きてしまって……」
男は消え入りそうな声で、そう呟いた。
まぁこうなった以上仕方ない。俺達が治療するしかないだろう。
「わかった、手を貸そう。サナちゃんもいいかい?」
「はい」
「あ、ありがとうございます」
男は涙を流して頭を下げた。
というわけで、俺とサナちゃんは、怪我人の元へと急ぎ駆け寄ったのである。
負傷者は男3人で、見たところ全員戦士タイプのようだ。先程の神官同様、年も若い。
だが、銅の剣や鎖帷子を装備しているところを見ると、経験の浅い、駆け出しの冒険者のようであった。
それから、この負傷者の周囲には商人と思われる者が2名と、駆け出しの魔法使いと思われる若い男女が2名、それと戦士タイプの若者が1名の計5名がおり、彼等は今、地に伏せる負傷者に声掛けしながら介抱している最中であった。
「おい、しっかりしろ!」
「ゲイル! アンザ! ヒュイ! 返事をして!」
必死に名前を呼んでいるが、虫の息といった感じだ。
この3名の負傷者は至る所にかなり深い裂傷を負っている上に、毒に侵されている者もいるみたいであった。
そんなわけで、俺とサナちゃんは、キアリーやベホイミを使って急ぎ治療を開始したのである。
ここまでの怪我人にベホイミを使った事はなかったので、上手くいくのかどうかが少し不安ではあったが、ベホイミは流石に回復力が強く、彼等の深い傷も見る見る塞がっていくのがよくわかった。
治療しておいてなんだが、その効果を目の当たりにして、心強い回復魔法だと俺は改めて思ったのである。
まぁそれはさておき、ある程度傷が回復したところで、俺は彼等に言った。
「これでもう大丈夫だろう。でも出血が多かったから、少し安静にしていた方がいいね。魔法で傷は治せても血は戻らないからさ」
そう……実は、魔法で傷は治せても、出血した血液までは戻らないのである。
これをヴァロムさんから教わった時は、俺も少し驚いた。が、よくよく考えてみると、それが当然なのである。なぜなら、ホイミ系は傷を癒す魔法だからだ。造血まではしてくれないのである。
俺の言葉を聞き、イシュラナの神官服を着た先程の男が、深々と頭を下げた。
「あ、ありがとうございました。助けていただいた上に、仲間の治療までしていただいて。本当に、本当に、ありがとうございました」
「礼なら、あのドラキーにも言ってやってよ。彼が俺達に知らせてくれたんだから」
「そ、そうだったのですか。どうもありがとうございました。貴方のお蔭で私達は救われました」
そう言って、男はドラキーに頭を下げた。
【別にええって。持ちつ持たれつや】
気さくなドラキーである。
「しかし、それにしても災難だったね。あんなに沢山の魔物と遭遇するなんてさ」
「はい……まったくです。私達は、この遥か向こうにあるネルバという小さな村から来たのですが、道中現れる魔物は、ネルバ周辺程度だろうと思って旅してきたのです。ですが……まさか、この地の魔物がここまで強力だとは思いもしませんでした……」
と、ここで、商人と思わしき中年の男が話に入ってきた。
「すまないな、テト君。俺が久しぶりに仕入れに行きたいなんて言ったばかりに、こんな目に遭わせてしまって……」
「いや、僕達の考えが甘かったんです。謝るのはこちらの方ですよ」
「しかし……村で一番の冒険者である君達でも手に負えない魔物が出るとはなぁ……。嫌な世の中になっちまったもんだ。はぁ……」
【はぁ……】
この男の言葉を聞き、冒険者6人も大きく溜め息を吐いた。
と、そこで、レイスさんがやや強い口調で、彼等に忠告をしたのであった。
「ここ最近、王都に向かうにつれ、次第に魔物が強くなってきているそうだ。君達がどこに向かっているのか分からないが、甘い考えで行動すると、次は命を落とすことになるぞ。この先は、よく考えて行動をするんだな」
今の話を聞き、6人の冒険者達は更にショボ~ンとなった。
神官服の男が気まずそうに口を開く。
「はい、仰る通りです。面目ありません……。あの、ところで、貴方がたはこれからどちらに向かわれるのですか?」
「俺達は、ルーヴェラに向かっている途中だけど」
と、俺が言った直後、彼等はパァと笑顔になったのである。
「我々もルーヴェラに向かっているのです。どうか是非、ご一緒させてください。この通りです」
神官服の男はそう言って、また深々と頭を下げてきた。
他の者達も、彼に続く。
俺はそこで仲間に視線を向け、アイコンタクトを取った。
「私は別に構いませんわよ」
「私も良いわよ」
「私も良いです」
「こうなった以上、仕方あるまい」
仲間の了解がとれたので、俺は彼等に返事をした。
「じゃあ、一緒に行くとするか。でも日が落ちる前に街に着きたいから、急いで出発の準備に取り掛かってくれるかい」
「は、はい、すぐに準備します」
【ワイもルーヴェラに行かなアカンから、あんちゃん達と一緒に行くわ】
とまぁそんなわけで、俺達は彼等と共に、ルーヴェラへと進むことになったのである。
ページ上へ戻るやや曇った空の元、風の帽子の力によってマルディラントを発った俺達は、昨日と同様、リジャールさんの家の裏手へと降り立った。
そして、正面に回って玄関扉を開き、中に向かって呼びかけたのである。
「おはようございます、リジャールさん。コータローです。言われた通りやってきました」
家の奥からリジャールさんの元気な声が聞こえてくる。
「おお、来たか。ではコータローよ、お主だけ中に入ってきてくれ。昨日、報酬を渡した部屋じゃ」
「え? 俺だけですか。……わかりました。では、お邪魔します」
なぜ俺だけなのかがわからなかったが、とりあえず、指示に従う事にした。
昨日の部屋へと進むと、丸テーブルの椅子に腰掛けるリジャールさんの姿があった。
リジャールさんは俺の姿を見るとニコリと微笑んだ。
「ではコータローよ。そこの空いている椅子に腰掛けてくれ」
「はい」
俺が椅子に腰掛けたところで、リジャールさんは話し始めた。
「まずは、おはようじゃな。昨夜はよく眠れたかの?」
「ええ、よく眠れましたので、今日は調子がいいですよ」
「それは良かった。さて、それでは本題に入ろうかの……」
と言うとリジャールさんは、茶色い革製の巾着袋をテーブルの上に置いたのである。
巾着袋の大きさは、日本で売っている一般的な弁当箱が入る程度の物で、中に重い物が入っているのか、ずっしりとした感じであった。テーブルに置いた時にシャリンという金属音が聞こえたので、もしかすると、中身は金物系のアイテムかもしれない。
リジャールさんは巾着袋を俺に差し出した。
「昨日、お主に渡すと言った物じゃが、それはコレの事じゃ」
「これは?」
「とりあえず、中を見てみい」
「では……」
リジャールさんの意図がよく分からないが、俺は巾着袋を手に取ると、言われるがままに中を確認した。
だが次の瞬間、俺は目を見開いて驚いたのである。
なぜなら、巾着袋の中には、カーンの鍵に似た物が幾つも入っていたからだ。
「え!? これは一昨日のアレですよね……しかも、こんなに沢山……どうしてこんなに」
「ああ、お主の言うとおり、それはアレじゃ。しかしの、それは代替え素材で作った紛い物なのじゃよ。1度使うと形状を維持できずに砕けてしまうので、不便といえば不便じゃが、もし何かあった時の為に予備で持っておくとよいと思っての。まぁそういわけで、アレの事は、あまり大きな声で話すわけにはいかぬから、お主だけを呼んだのじゃよ」
俺はリジャールさんの話を聞いて、ドラクエⅠに出てきた魔法の鍵を思い出してしまった。
確か、Ⅰの魔法の鍵も、一度使うと壊れる設定だったからだ。
まぁそれはさておき、持っていても損はない物なので、俺は快く鍵を貰う事にした。
「そうなのですか。では、ありがたく頂戴いたします」
「うむ。持ってゆけ。それから、また欲しくなったら、儂の所に来るがいい。幾らでも作れるからの」
「はい、その時はまたよろしくお願いします」
代替え素材とはいえ、こういった物を作り上げてしまう、その手腕は流石だなと思った。
老いたりとはいえ、今でも超一流の錬成技術を持っているのだろう。ヴァロムさんが頼るわけだ。
「ところでコータローよ。ティレス様は、守護隊の派遣について何か言っておったかの?」
「ええ、それなのですが……ティレス様は今日中に第1陣を発たせると言っておりました。なので、恐らく、2日後には第1陣の部隊がこちらに到着すると思われますよ」
リジャールさんは安堵の表情を浮かべた。
「そうか、それは良かった。儂もその旨を村長に伝えておこう」
俺も昨晩の事を訊いてみた。
「昨晩はどうでしたかね? ヴァイロン達は現れましたか?」
リジャールさんは頭を振る。
「いや、現れなんだ。お主の言うとおり、今は攻め手を欠いておるのかもしれぬの。まぁこちらも今の内に警備体制を整えておけるので、その方が好都合じゃがな」
「確かに……あ」
と、そこで俺は、昨日、訊けなかった事を思い出したのである。
ちなみにそれは、サナちゃん達がいたので訊けなかった事であった。
「あの……この魔導の手なんですけど、ヴァロムさんが使っているところを見た事がないんですが、ヴァロムさんも以前は使っていたのですかね?」
「いや、ヴァルは魔導の手を使っておらぬ。というか、ヴァルなら、使わぬでも同じ事が出来るからの」
「え、それってどういう……」
「お主のその口振りじゃと、まだヴァルから、大賢者が編み出した秘法を学んではおらぬようじゃな」
大賢者の編み出した秘法……多分、アレの事だろう。
「それって……もしかして、魔生の法の事ですかね? それなら、今、学んでいる最中ですが」
「ほう、そうか。ならば話は早い。これはヴァルが言っておったのじゃが、魔生の法を使っておる時は、周囲に漂う大地の魔力に干渉出来るらしく、魔導の手を使わぬでも同じことが出来るそうなのじゃよ。まぁそういうわけで、ヴァルは魔導の手を使ってはおらんのじゃ」
「そ、そうだったんですか、初めて知りました」
まさか、魔生の法にそんな秘密があったとは……。
「実は儂も、お主と同じような事をヴァルに訊いた事があるんじゃ。するとヴァルの奴はの、こんな事を言っておったわ。――やろうと思えば道具無しでもできるのだから、無理して魔導の手を装備する必要はない。腕は2つしかないのだから、自分の能力をもっと高めてくれる物を装備する――との。あ奴らしい答えじゃわい」
「確かにそうですね。ヴァロムさんらしい合理的な考え方です」
「ああ、全くじゃ。……さて、儂から渡す物は以上じゃ。これ以上引き留めると、お主等の旅に支障が出るじゃろうから、もうこの辺にしておこうかの。……っと、そうじゃ、これを言い忘れたわい。投獄されているヴァルに会う事があったならば、儂がこう言っていたと伝えておいてくれ。『何をするつもりなのか知らんが、お主も年なんじゃから、あまり無理をするなよ』との」
「ええ、必ず伝えておきます」
リジャールさんからしたら、こう言いたくなるのも仕方ないだろう。
まぁそれはともかく、俺もそろそろお暇させてもらうとしよう。
「ではリジャールさん。皆も待っていると思いますので、俺もこれで失礼させて頂こうと思います」
「うむ、見送ろう」――
玄関の前で待っている皆の所へ戻った俺は、そこでリジャールさんに向き直り、別れの挨拶をした。
「リジャールさん、短い間でしたが、色々とありがとうございました」
「いやいや、世話になったのはこちらの方だ。またいつでも気兼ねなく訪ねてきてくれ。お主等にはそれが出来るのじゃからな。カッカッカッ」
リジャールさんはそう言って豪快に笑った。
俺は思わず苦笑いを浮かべる。
「はは、その時はよろしくお願いしますよ」
「うむ」
出会って2日しか経っていないが、この人ともこれでお別れかと思うと、少し寂しさが込み上げてくるから不思議なものである。
多分、話しやすい人だからなのだろう。
なぜか知らないが、何日も一緒にいたような錯覚を覚えるくらいである。
「それから、カディスさん達にもよろしくお伝えください。警備の邪魔しては悪いので、俺達はこのままガルテナを発つつもりですから」
「ああ、伝えておこう。それと道中は気を付けるがよいぞ。人づてに聞いた話じゃが、王都に向かうにつれて、魔物も強くなってきておるそうじゃからの」
「ええ、十分に気を付けて進むつもりです」
続いて、他の皆もリジャールさんに挨拶をしていった。
「ありがとうございました、リジャールさん。色々と勉強になりましたわ。またお会いしましょう」
「リジャールさんもお元気で」
「お世話になりました、リジャールさん」
「ではリジャール殿、お身体に気を付けて下され」
リジャールさんは皆にニコリと微笑んだ。
「うむ。お主達も元気でな。たまには顔を見せに来るがよい」
「はい、その時はまたよろしくお願いします」と、サナちゃん。
そして、俺達は最後にもう一度、リジャールさんにお別れの言葉を告げ、この場を後にしたのであった。
「ではリジャールさん、お元気で」と。
俺達はその後、宿屋の厩舎に立ち寄り、馬と馬車を引き取りに行った。
そして、来る途中にあった分かれ道にまで戻り、その先にあるモルドの谷へと向かって馬車を走らせたのである。
[Ⅱ]
ひっそりと静かな木陰が続く山道に、カラカラとした俺達の馬車音が響き渡る。
耳を澄ますと、そよ風に揺れる枝葉のさわさわとした音や、キィキィと鳴く野鳥の声が聞こえてきた。
俺は今まで魔物の襲撃を過剰に警戒するあまり、自然界の音にそれほど気を配ってこなかったが、こうやって耳を傾けてみると、妙に気分が落ち着くものだなと思った。
もしかすると、自然が奏でる何気ない音には、思った以上にリラクゼーション効果があるのかもしれない。
まぁそれはさておき、俺達がガルテナを出発してから20分程経過したところで、前方にV字型になった深い谷が見えてくるようになった。恐らく、あれがモルドの谷と呼ばれる所なのだろう。
谷には頭上を遮る枝葉もない為、空一面がモクモクとした灰色の雲に覆われているのが、ここからでもよく見える。が、見た感じだと雨雲ではなさそうなので、今しばらくは雨の心配をしなくてもよさそうだ。
また、果てしなく伸びる道の両脇には、青々とした草木が生い茂る緩やかな山の裾野が広がっており、その遥か頂きへ視線を移すと、天を突き刺すかのような鋭利な刃物を思わせる山の先端部が、俺の視界に入ってくるのである。
見た感じだと、標高は2000mくらいだろうか……。まぁその辺の事はわからないが、ここはガルテナ連峰と呼ばれる山岳地帯なので、それくらいはあっても不思議ではないだろう。
とりあえず、モルドの谷とはそんな感じの所であった。
話は変わるが、谷の名前であるモルドとは、その昔、この地で活躍した旅の戦士の名前だそうだ。
これはガルテナを出発する前に宿屋の主人から聞いた話なのだが、なんでも、300年ほど前に谷で悪さしていた魔物がいたらしく、それをモルドという戦士が退治してくれた事から、村の者達が感謝の意を込めてそう名付けたそうである。
まぁこの手の英雄譚は日本昔話でもよく見かけるので珍しくもなんともないが、何気ない地名にもちゃんと由来はあるようだ。
つーわけで、話を戻そう。
モルドの谷を暫く進んだところで、ティレスさんから預かっている物があるのを俺は思い出した。
ちなみにそれは、旅が始まったらアーシャさんに渡してくれと言われていた手紙であった。
とまぁそんなわけで、俺は道具入れの中から白い封筒を取り出し、隣に座るアーシャさんにそれを差し出したのである。
「あの、アーシャさん。ティレスさんから預かった手紙があるんですよ。これなんですけど」
「え、お兄様から? 何かしら、一体……」
アーシャさんは首を傾げながら手紙を受け取ると、早速、封を解いて中のモノに目を通していった。
すると次第に、アーシャさんは口元をヒクつかせ始めたのである。
「ん、もうッ! お兄様は、私がコータローさん達と旅をしているのを知っていたのですね。知っていたのなら、ハッキリと仰って下されば良かったのにッ」
実を言うと、既にバレている事をアーシャさんは知らない。
ティレスさんから内緒にしておいてくれと言われたので、それについては話してないのだ。
なぜこんな事をしたのかわからないが、多分、ティレスさんのちょっとした悪戯なのだろう。
「まぁまぁ、アーシャさん。多分、ティレスさんなりの考えがあったんだと思いますよ。でもよかったじゃないですか、ティレスさんも俺達と同行するのを認めてくれたのですから」
「ええ、まぁそれはそうなのですが……って、なんで貴方が、それを知っているんですの?」
しまった……。
余計な事を言ってしまったようだ。
「じ、実はですね。昨晩、ティレスさんから、そう聞いたんです」
「なんですってぇ! あんまりですわ、お兄様! コータローさんもコータローさんですわよ。知っていたのなら、一言仰って下されば良かったのにッ。これじゃ、気を使ってきた私が馬鹿みたいですわ」
アーシャさんは捲し立てるようにそう言うと、釣り上げられたトラフグの如くプンスカと頬を膨らましたのである。
このままだと俺に火の粉が降りかかりそうなので、とりあえず、事情を話しておくことにした。
「だ、黙っていてすいませんでした。ですが、黙っているようにという指示を出したのはティレスさんなんですよ。お、俺はそれに従っただけなんです」
「へぇ……そうなのですか。帰りましたら、お兄様にはどういう事なのか、問いたださなければなりませんわね……」
アーシャさんは執念深いので、ティレスさんも後が大変そうだ。
まぁそれはさておき、俺は他の内容について訊いてみる事にした。
「それはそうとアーシャさん。手紙には他に、なんて書いてあったのですか?」
「ここに書かれているのは、今言った内容と、引き続き、朝と晩はちゃんと顔を見せに来るように、という事だけですわ」
「じゃあ、今まで通りって事ですね」
「確かにそうですが、納得いきませんわッ」
アーシャさんはまだご立腹のようだ。
暫くはこんな感じが続きそうである。はぁ……。
と、ここで、サナちゃんが話に入ってきた。
「でもよかったですね、アーシャさん。お忍びで旅を続けるのは、アーシャさんも気が楽でなかったと思いますから。それに、コータローさんとアーシャさんは、レイスとシェーラ以外で、私が気を許せた初めての方達ですから、アーシャさんが気兼ねなく旅を続けられると聞いて、今、凄くホッとしてるんです。ですから、これからもよろしくお願いしますね、アーシャさん」
サナちゃんはそう言って、屈託のない笑みを浮かべた。
するとアーシャさんは、サナちゃんの微笑みに毒気を抜かれたのか、少し戸惑いながら、いつもの表情に戻ったのである。
「え、ええ……こちらこそよろしくお願いしますわ、サナさん」
どうやらサナちゃんは微笑みだけで、アーシャさんを鎮めるのに成功したようだ。
回復系魔法が得意なだけあって、この子自身も、癒しの効果を持っているのかもしれない。ある意味、貴重な人材かも。
続いてサナちゃんは俺へと視線を向けた。
「あの、コータローさん。……昨日の事でお訊きしたい事があるのですが、今いいでしょうか?」
「いいよ、何?」
「昨日、リジャールさんの家を出発する前なのですけど、コータローさんは、坑道内に水が流れている所や湧いている所があるのかどうかを訊ねていた気がするのですが、あれは何の為に訊いたのですか?」
何かと思ったら、それの事か。
「ああ、あれはね、もし死体以外の魔物がいた場合、飲み水はどうしてるのかと思って訊いたんだよ。俺達のように食料や水を摂取しながら生きる魔物なら、長い間、飲まず食わずというのは流石に厳しいからね。その上、水は食料以上に持ち運びや保存が難しいし。だからさ」
サナちゃんは納得したのか、感心したように首をゆっくりと縦に振る。
「そ、そういう意図があったのですか。それは気が付きませんでした」
「まぁ、それが理由さ。で、あの時リジャールさんは、出入り口が1つしかない事と、警備を付けてから20日以上経過している事に加え、魔物の出入りもないような事を言っていたので、俺はこう考えていたんだよ。『坑道内にいるのは、水や食料を必要としない魔物ばかりの可能性がある』とね。でも、まさか、死骸だらけとは思わなかったけどさ」
実を言うと、事前にオッサンから魔物を操る奴がいるかも知れないと聞いていたので、腐った死体だけでなく、泥人形みたいな魔物もいるかも知れないと思っていたのである。
なので、少し拍子抜けした部分もあるのだった。まぁ色々と理由もあるのだとは思うが……。
と、ここで、アーシャさんも話に入ってきた。
「貴方って時々、意味の分からない質問をしますが、こうやって聞いてみると、的を得た事を訊いてるのですね。勉強になりますわ」
「いやぁ~そうですかね。そんな風に言われると、なんか照れるなぁ。なははは」
俺は思わず後頭部をポリポリとかいた。
「コータローさんのお話って為になるのが多いので、もっと色々と聞かせてください」
「う~ん……お話といわれてもねぇ。じゃあ、サナちゃんは何について聞きたいの?」
「では、コータローさんが見たという、魔物や魔法について書かれた書物のお話をお願いします」
「あ、それは私も聞きたかった事ですわ」
「それかぁ……」
あまり触れたくない話題ではあったが、仕方ない。
当たり障りない話でもしておこう。
とまぁそんなわけで、俺はこの道中、サナちゃんとアーシャさんに幾つかのドラクエ話をする事になったのである。
[Ⅲ]
ガルテナを発ってから3時間ばかり経過すると、前方に、広大な緑の平原が見えてくるようになった。地図で確認すると、どうやら、あれがバルドア大平原のようだ。
そんなわけで、程なくして、モルドの谷を抜けた俺達は、そのままバルドア大平原を真っ直ぐと北に進み続けるのである。
今まで少し閉鎖的な山の中にいた所為か、このバルドア大平原は凄く解放された気分になるところであった。
馬車の中からバルドア大平原をグルリと見回すと、果てしなく広がる平坦な緑の草原と、そこにポツンポツンと点在する木々に加え、遠くに舞う鳥達の姿が視界に入ってくる。
そして、時折吹く心地よい風が、穏やかな大海原の波のように、草原を優しく靡かせているのである。
それは美しい光景であったが、どことなく夏の北海道に広がる牧草地帯のようにも見える所為か、それほどの感動は湧いてこなかった。というか、懐かしさのようなものを感じさせる光景であった。
俺は北海道に行った事はないが、日本でも見かける風景なので、そう感じるのだろう。
まぁとりあえず、バルドア大平原はそんな感じの所である。
話は変わるが、このバルドア大平原からはマール地方でなくバルドア地方と呼ばれる地域になる。
この地を治める太守はイシュマリア八支族の1つであるラインヴェルス家が担っているそうで、このバルドア地方最大の都市であるバルドラントという街にて、執政を行っているようである。
そんなわけで、必然的にアレサンドラ家の管轄外になる地域なのだが、境となる部分に関所のようなものはないそうだ。多分、そういった物が必要ない統治方法をしているのだろう。
ちなみにだが、イシュマリア国には地方が九つあり、それらは八支族とイシュマリア王家によって分割統治されているそうである。
各地域の統治形態は中世の欧州や日本でも見られる封建制度のようだが、統治する者が神の御子イシュマリアの血族ということもあり、この国では統治者による戦乱の歴史とかはあまりないそうだ。とはいっても領地間における多少のいざこざはあるみたいだが……。
まぁそれはともかく、王家と八支族による地方分権型の統治システムは、建国以来うまく機能しているみたいである。
つーわけで、話を戻そう。
バルドア大平原に入ってからというもの、俺は少し気が楽になっていた。
なぜなら、辺りには背の低い草木しかない為、非常に見通しが良く、魔物の監視がしやすいからだ。
以上の事から、俺は少しだけ緊張を解き、肩の力を抜いて周囲の警戒に当たっているのである。
とはいえ、ここまでの道中、魔物との戦闘は4回ほどあった。遭遇した魔物は、キャットフライや兜百足、それから毒芋虫といった感じなので、ゲームならば、まだまだ序盤の敵である。撃退するのはそれほど難しくはない。が、しかし……王都に向かうにつれて、徐々に魔物が強くなってきているという、この事実が、精神的に重く圧し掛かってくるのである。
そして、俺は1人、考えるのであった。
この先、一体、どんな魔物が待ち受けているのだろうかと……。
バルドア大平原を暫く進み続けると、街道のすぐ脇に、幅100mほどの大きな河が流れている所があった。
馬の休憩がそろそろ必要だったので、俺達はそこで少し休むことにしたのである。
俺はレイスさんとシェーラさんに馬の世話をお願いすると、馬車を降りて外に出る。
それから、両手を目一杯に広げて背伸びをした後、軽い屈伸運動をして、俺は旅の疲れを癒したのであった。
暫くそうやって体を動かしていると、サナちゃんとアーシャさんが俺の隣にやって来た。
「コータローさんは、この辺りに来たことがあるのですか?」
「いや、初めてだよ。サナちゃん達と同じさ。アーシャさんは?」
「私も初めてですわ。ところでコータローさん、ルーヴェラまでは、あとどの位かわかりますか?」
「ちょっと待ってくださいね」
俺は馬車の中から地図を持ってくると、2人の前に広げた。
「地図を見る限りだと、あと暫くは進まないといけないようですね。今進んでいるアルカイム街道とこの河の位置関係を考えるに、多分、俺達はこの辺にいるんだと思います。ですから、もう半分以上は進んだようですよ。この調子だと、日が落ちる前には、今日の目的地であるルーヴェラに着けるんじゃないですかね」
今言ったアルカイム街道がルーヴェラへと続く道の名前であり、王都へと続く道の名前でもある。
ちなみにだが、アルカイムという名前は王都オヴェリウスのあるアルカイム地方へと続くことからつけられた名前のようだ。
わかりやすいネーミングである。
「では、順調に進んでいるんですね。よかったです」
「そのようですわね。次の街はどんな所か楽しみですわ」
アーシャさんはそう言ってニコリと微笑んだ。
と、その時である。
【お~い、あんちゃん達ィ~、大変や~、向こうで大変な事が起きとるんや~】
流暢な関西弁が、俺達の頭上から小さく聞こえてきたのであった。
(ン……誰だ一体)
俺は声の聞こえた上空に視線を向ける。
そして、俺は驚きのあまり、思わず目を見開いたのである。
「なッ、なんだありゃ!?」
そこにいたモノ……それはなんと、愛らしい顔に蝙蝠の翼をもつ赤色の魔物であった。そう、ドラキーである。
しかも、黒い鞄をランドセルのように背負った、奇妙な出で立ちの赤いドラキーが、パタパタと羽ばたいていたのだ。
(なんなんだ……この流暢な関西弁を喋るドラキーは……)
と、ここでアーシャさんの声が聞こえてきた。
「あら? あれはドラキー便のドラキーじゃありませんの」
「へ? あれがドラキー便なんですか……」
「ええ、間違いありませんわ。鞄を背負った赤いドラキーですし」
「あっ、そうか……赤いドラキーは書簡配達してるんでしたっけ……」
そういえば以前、ヴァロムさんがこんな事を言っていた。
遠隔地の書簡配達業務は、ドラキー便が良く使われているというような事を。
しかもヴァロムさん曰く、この赤いドラキーは結構な距離を休みなしで飛べるだけでなく、幾つかの攻撃魔法も使えるので、危険地帯の書簡配達員みたいな事を生業としているのだそうだ。
おまけに、人と会話も出来るほど知能も高く、話の分かる魔物なので、人とも仲良く共存共栄できるそうである。
余談だが、貴族お抱えのドラキー便もあるそうだ。以前、ヴァロムさんに書簡を持ってきたドラキーも、オルドラン家のお抱えドラキーらしいので、その辺は色々と込み入った事情があるのだろう。
俺のプレイしたドラクエでは敵であった赤いドラキーだが、ここでは意外にも人間社会に溶け込む種族のようである。
つーわけで、話を戻そう。
流暢な関西弁を喋るドラキーは、馬車の屋根に降り立つと慌てたように話し始めた。
【あ、あんちゃん達、イキナリですまんけど、この先の十字路付近で、旅の商人が魔物の集団に襲われとるんや。護衛についた冒険者だけでは多勢に無勢で手に負えんようやから、助けてやってや。お願いや! あんちゃん達、強そうやし】
さて、どうしたもんか……。
人間と共生してる魔物なので嘘ではない気がするが、このドラキーが一芝居うっている可能性も勿論否定できない。
だが、もし本当ならば放っておくのも後味が悪いところである。
とりあえず、俺は皆の意見を聞くことにした。
「魔物かぁ……。皆、どうします?」
「かなり差し迫った状況のようですので、助けに行った方がいいのでは」と、アーシャさん。
と、ここで間髪入れず、ドラキーがお世辞を言う。
【ありがとう、綺麗なネェちゃん。ネェちゃんならそう言うてくれると思った。綺麗なだけじゃなくて、すごく素敵な人やわぁ。棘の無い綺麗な女の人に、こんな所で会えるなんて思わんかったわぁ。長生きはするもんやで、ほんま】
するとアーシャさんは今の言葉に気をよくしたのか、声高にこう告げたのだ。
「コータローさん、早く行きましょう! こうしてる間も、魔物に苦しんでいる方々がいるのですよ!」
中々煽てるのが上手いドラキーのようだ。が、とはいえ、本当ならば確かに不味い。
仕方ない……ここはこのドラキーの言う事を信じてみるとしよう。
「レイスさん、馬の調子はどうですか?」
「もう少し休みたいところだが、事情が事情だ。仕方あるまい。行こう、コータローさん」
「じゃあ、行きますか。と、その前に……。襲っている魔物はどんな奴等なんだ? それと魔物の数は?」
【襲ってるのは、ごっつい百足とごっつい大猿が10数体に、ドルイドとかいう酒樽みたいな格好のけったいな奴等が8体や。キツイ敵かも知れんけど、助けてあげてぇな】
多分、ごっつい百足は兜百足か鎧百足あたりで、ごっつい猿が暴れ猿かキラーエイプってとこだろう。
とりあえず、その程度の魔物なら、何とかなりそうだ。
「数が多いから面倒だが、仕方ない。急ごう」
【よっしゃ、そうと決まれば善は急げや。ワイについてきてぇな】
そして俺達はこの場を後にしたのである。
[Ⅳ]
ドラキーに案内される事、約5分。前方に、ドラキーの言っていた十字路が見えてくるようになった。
またそれと共に、十字路付近で9名の者達が、20数体の魔物に取り囲まれるという、非常に危険な状況に陥っているのも、目に飛び込んできたのである。
彼等の内の何名かは深い傷を負っているようで、地面には幾つかの赤い血痕が出来ていた。まさしく、絶体絶命といった感じの光景である。早く手当をしないと不味いかもしれない。
俺は次に、魔物達へ視線を向ける。
魔物は思った通り、兜百足と暴れ猿にドルイドのようだ。
数がかなり多かったが、敵はある程度グループ化しているのが好都合であった。
と、ここでドラキーの声が聞こえてきた。
【あそこや! あんちゃん達、ワイは空から援護するさかい、後は頼んだで!】
ドラキーはそう言うと更に上空へと舞い上がった。
そして俺達は、魔物達に近づいたところで馬車を止め、臨戦態勢に入ったのである。
俺はまずアーシャさんとサナちゃんに指示を出した。
「敵はある程度固まっていますんで、手っ取り早くやっちゃいましょう。先手必勝です。アーシャさんは向こうにいる百足の一団にヒャダルコをお願いします。それからサナちゃんは、杖を持った黄土色のドルイドという魔物達にマホトーンをお願いします」
2人は頷くと、言われた通り、魔法を唱えた。
「ヒャダルコ!」
「マホトーン!」
百足の一団に無数の氷の矢が容赦なく突き刺さってゆく。
また同じくして、ドルイド達の周りには、呪文をジャミングする黄色い霧が纏わりつきはじめていた。
霧が全てのドルイドに纏わりついたのを見ると、どうやら魔法を封じるのに成功したみたいである。
俺は次の指示を前衛に出した。
「ではレイスさんとシェーラさん、今から俺がイオラを使います。ですが、ドルイドは攻撃魔法全般に耐性があると思いますんで、生き残った奴等を仕留めていってください」
「わかったわ」
「よし、いつでもいいぞ」
俺は掌を魔物達に向かって突きだした。
「ではいきますよ。イオラ!」
俺の掌から魔力の塊である白い光が飛んでゆく。
光は魔物達の付近でフラッシュをたいたかのような閃光を放ち、爆発を巻き起こした。
魔物達は爆発をモロに浴びて吹っ飛んでゆく。
この一撃で半数の魔物は死ぬか虫の息状態となったが、思った通り、ドルイドにイオ系は効かないのか、ピンピンとしていた。が、想定の範囲内である。
ここでレイスさんとシェーラさんが、付近のドルイドに一気に間合いを詰め、破邪の剣を振り降ろす。
その刹那、2体のドルイドは脳天から真っ二つに両断されて息絶えたのだ。
と、その時であった。
向こうの冒険者達も俺達の加勢に気付いたようで、生き残った魔物達に向かい攻撃を開始した。
すると瞬く間に戦況は逆転し、魔物達は打つ手なく、俺達の刃に掛かって倒れていったのである。
魔物達を全て倒したところで、ドラキーが俺達の所に舞い降りてきた。
【あんちゃん達、めっちゃ強いやんけ! ワイの援護なんか、全然必要なかったやん。凄いわぁ】
「褒めても何も出んぞ」
【そんなん期待してへんて、ワイの素直な気持ちや】
俺とドラキーがそんなやり取りしてると、向こうの冒険者の1人が俺達の方へとやってきた。
近づいてきたのは眼鏡を掛けた色白の若い男で、イシュラナの紋章が描かれた神官服を身に纏っていた。
ちなみに、イシュラナの紋章とは、一本線が多いアスタリスクみたいなシンボルである。
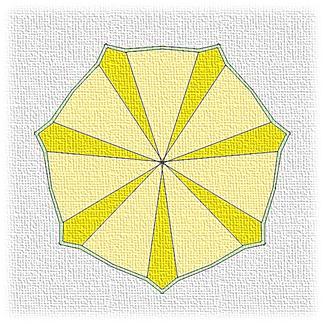
年はかなり若く、俺よりも年下に見える。多分、10代半ばから後半といったところだろう。体型は痩せ型で、背はそれほど高くない。170cmあるかないかといったくらいだ。
この見た目から察するに、どうやらイシュラナ神殿の神官のようである。
男は俺達の前に来ると、深々と頭を下げてきた。
「ど、どなたか存じませんが、危ないところを本当にありがとうございました」
「いや、気にしなくていいよ。それよりも、仲間がかなり深い傷を負っているみたいだから、早く治療をしないと不味いよ」
「あ、そ、そうでした。で、ですが……薬草も魔力も尽きてしまって……」
男は消え入りそうな声で、そう呟いた。
まぁこうなった以上仕方ない。俺達が治療するしかないだろう。
「わかった、手を貸そう。サナちゃんもいいかい?」
「はい」
「あ、ありがとうございます」
男は涙を流して頭を下げた。
というわけで、俺とサナちゃんは、怪我人の元へと急ぎ駆け寄ったのである。
負傷者は男3人で、見たところ全員戦士タイプのようだ。先程の神官同様、年も若い。
だが、銅の剣や鎖帷子を装備しているところを見ると、経験の浅い、駆け出しの冒険者のようであった。
それから、この負傷者の周囲には商人と思われる者が2名と、駆け出しの魔法使いと思われる若い男女が2名、それと戦士タイプの若者が1名の計5名がおり、彼等は今、地に伏せる負傷者に声掛けしながら介抱している最中であった。
「おい、しっかりしろ!」
「ゲイル! アンザ! ヒュイ! 返事をして!」
必死に名前を呼んでいるが、虫の息といった感じだ。
この3名の負傷者は至る所にかなり深い裂傷を負っている上に、毒に侵されている者もいるみたいであった。
そんなわけで、俺とサナちゃんは、キアリーやベホイミを使って急ぎ治療を開始したのである。
ここまでの怪我人にベホイミを使った事はなかったので、上手くいくのかどうかが少し不安ではあったが、ベホイミは流石に回復力が強く、彼等の深い傷も見る見る塞がっていくのがよくわかった。
治療しておいてなんだが、その効果を目の当たりにして、心強い回復魔法だと俺は改めて思ったのである。
まぁそれはさておき、ある程度傷が回復したところで、俺は彼等に言った。
「これでもう大丈夫だろう。でも出血が多かったから、少し安静にしていた方がいいね。魔法で傷は治せても血は戻らないからさ」
そう……実は、魔法で傷は治せても、出血した血液までは戻らないのである。
これをヴァロムさんから教わった時は、俺も少し驚いた。が、よくよく考えてみると、それが当然なのである。なぜなら、ホイミ系は傷を癒す魔法だからだ。造血まではしてくれないのである。
俺の言葉を聞き、イシュラナの神官服を着た先程の男が、深々と頭を下げた。
「あ、ありがとうございました。助けていただいた上に、仲間の治療までしていただいて。本当に、本当に、ありがとうございました」
「礼なら、あのドラキーにも言ってやってよ。彼が俺達に知らせてくれたんだから」
「そ、そうだったのですか。どうもありがとうございました。貴方のお蔭で私達は救われました」
そう言って、男はドラキーに頭を下げた。
【別にええって。持ちつ持たれつや】
気さくなドラキーである。
「しかし、それにしても災難だったね。あんなに沢山の魔物と遭遇するなんてさ」
「はい……まったくです。私達は、この遥か向こうにあるネルバという小さな村から来たのですが、道中現れる魔物は、ネルバ周辺程度だろうと思って旅してきたのです。ですが……まさか、この地の魔物がここまで強力だとは思いもしませんでした……」
と、ここで、商人と思わしき中年の男が話に入ってきた。
「すまないな、テト君。俺が久しぶりに仕入れに行きたいなんて言ったばかりに、こんな目に遭わせてしまって……」
「いや、僕達の考えが甘かったんです。謝るのはこちらの方ですよ」
「しかし……村で一番の冒険者である君達でも手に負えない魔物が出るとはなぁ……。嫌な世の中になっちまったもんだ。はぁ……」
【はぁ……】
この男の言葉を聞き、冒険者6人も大きく溜め息を吐いた。
と、そこで、レイスさんがやや強い口調で、彼等に忠告をしたのであった。
「ここ最近、王都に向かうにつれ、次第に魔物が強くなってきているそうだ。君達がどこに向かっているのか分からないが、甘い考えで行動すると、次は命を落とすことになるぞ。この先は、よく考えて行動をするんだな」
今の話を聞き、6人の冒険者達は更にショボ~ンとなった。
神官服の男が気まずそうに口を開く。
「はい、仰る通りです。面目ありません……。あの、ところで、貴方がたはこれからどちらに向かわれるのですか?」
「俺達は、ルーヴェラに向かっている途中だけど」
と、俺が言った直後、彼等はパァと笑顔になったのである。
「我々もルーヴェラに向かっているのです。どうか是非、ご一緒させてください。この通りです」
神官服の男はそう言って、また深々と頭を下げてきた。
他の者達も、彼に続く。
俺はそこで仲間に視線を向け、アイコンタクトを取った。
「私は別に構いませんわよ」
「私も良いわよ」
「私も良いです」
「こうなった以上、仕方あるまい」
仲間の了解がとれたので、俺は彼等に返事をした。
「じゃあ、一緒に行くとするか。でも日が落ちる前に街に着きたいから、急いで出発の準備に取り掛かってくれるかい」
「は、はい、すぐに準備します」
【ワイもルーヴェラに行かなアカンから、あんちゃん達と一緒に行くわ】
とまぁそんなわけで、俺達は彼等と共に、ルーヴェラへと進むことになったのである。
感想を書く
この話の感想を書きましょう!
全て感想を見る:感想一覧
