| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
俺たちで文豪ストレイドッグスやってみた。
作者:絶炎with八咫烏
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動第1話「舞えない黒蝶のバレリーナ」
「……ねぇ達也、大切なお話があります」
「ん、唐突になんです?」
デスクの前の椅子に深く腰掛けた青年が神妙そうな顔で呟き、ソファで寛いでいたもう一人の青年……江西 達也が、寝転びつつ読んでいた雑誌から目を離して問いを投げる。
その問いに目を伏せた青年はゆっくりと立ち上がると、デスクの上に広がるいくつかの資料に目を通した。それらの資料はここ最近、この事務所に舞い込んできた以来の数々であり、ほぼほぼ解決済みまで終わらせてある。何も改まって話し合うほどの問題も起きていない。であればなんなのかと、達也が訝しげな視線を向けた。
が、その視線を意にも返さず、彼は一纏めに依頼書を束ねると――
「そぉいっ!!」
――一気に放り捨てた。
「今明かされる衝撃の真実ぅっ!!実は僕現在進行形でものすごーーく暇です!来てる依頼も全ッ部つまらない!なんだ猫探しって!なんだ浮気調査って!!テンプレか?テンプレなのかっ!?」
「……そんな事だろうなとは思ってましたよ」
オーバーな演劇のように振る舞う健の姿を見て一気に脱力した達也が溜息を吐き、一枚飛んで来た依頼書を手に取り、目を通す。
迷子になったペットの猫探し。実に探偵らしいというか、『いかにも』といった依頼だ。今の地位に落ち着くまではまさか本当にこんな依頼が来るとは思ってもいなかった。
達也は雑誌をテーブルの上に捨て、寝転んでいたソファから立ち上がる。散らばった書類を適当に纏めると、クリップで留めてデスクに戻した。
その様子に不満げな顔を浮かべた青年――三國 健は、不貞腐れた表情で上体をデスクにもたれさせる。
「だってさぁ、ここ最近何にも起きてないでしょ?達也は暇じゃないの?なんかこう……ときめく様な事件とか転がってない訳?」
「健さんの言う『ときめく事件』は大概ロクなことがないから是非とも遠慮したい。この川越中が大惨事になる……」
半眼で突っ込んだ達也はポリポリと頭を掻き、何度目とも分からない溜息を吐く。だが実際問題、健の言う通り、この探偵事務所にはここ数ヶ月、マトモな依頼が来ていない。暇であることはまあ達也も同意出来る。彼の言う『ときめく依頼』程ではないにしろ、もう少しやり甲斐のある依頼はないものか。
などと考えていると、噂をすれば何とやらとでも言うのか。
「はいはいそこのダラけたお二人さん、待ちに待ったマトモなお仕事の時間だ。キリキリ働け」
突如事務所のドアが開けられ、煽る様に手を叩く青年が乱入する。その青年の背後には何やら女性が佇んでおり、彼女を引き連れてきた青年は、手に持った報告書をデスクに放り投げた。
健が気怠げにその報告書に目を通すが、中身を読んだ途端に顔色を変え、唐突に勢い良く立ち上がる。
「ナイスだ双樹君っ!君は神か!?」
嬉しそうに依頼書を読み込む健の姿を見て全てを察した達也は、来たる『ときめく依頼』に対する覚悟を、固めているしかなかった。
◇ ◇ ◇
「『不思議な絵描きさん』……ね」
「絵に描いたものを実体化させる……面白い異能だねぇ」
双樹 兵児が持ってきた依頼――女性の依頼内容は、『子がお世話になった不思議な絵描きを探して欲しい』、と言うものだった。一先ずはそう飛び抜けた依頼でないと達也が安心したのも束の間、その『不思議な絵描き』がどうにも異能力者である事が判明する。
現代に於ける異能者――その存在は基本的に、なるべく隠されるようになっている。そもそもの数が少ない上、他の人々との明確な差が生まれる為、人間社会に馴染めない者が殆どであるからだ。人間というものは面倒なもので、自分達と違う存在は無意識下に排除しようとする。故に異能者達の道はおおよそ三つに絞られるのだ。
その力を隠して細々と暮らすか、公に国の機関に就き、異能者としての力を生活に役立てるか、或いは――
――異能集団マフィアの一員となり、裏社会を暗躍する超常者となるか。
この依頼はその絵描きへと礼を言いたい、というのが本筋ではあるが、また別種の目的も存在する。これは全く以来とは関係のない話だが、今は迅速にその『絵描き』を見つけ出す事が先決だろう。
「んで、時に達也君よ。どういった方針で?」
「ふむ、俺の異能で……見つけられたら良いんだけど、面倒な事に30秒しか持たないからなぁ……」
ボヤくように達也が言い、袖をめくって腕時計の時刻を確認する。短針は既に六の数字を超えており、空は既に赤らみ始めている。早い所捜査は終わらせた方が、スムーズに進行するだろう。
一先ずは探偵らしく聞き込みかと、一先ずは人溢れる大通りの周辺を見回してみる。
……と。
「……ねぇ達也、あれ」
「……うん、まあ、モロ……だよな」
二人の視線の先、大通りからは逸れた小さな裏路地の暗闇の中で、座り込み、スケッチブックに何やら描き込んでいる女性が見えた。
暫く待てばそのスケッチブックからは鯨の尾のようなモノが伸び、まるでスケッチブックが水面であるかのように、尾ひれで水飛沫を弾き出す。それは彼女が凭れ掛かるマンションの壁を黒く染めて、重力に従い流れ落ちていった。
当然ながらこの2020年現在、水飛沫を発生させるスケッチブックなどある筈もない。ましてやスケッチブックから鯨の尾が出て来るわけもない。そもそもあんなミニサイズの鯨は居ない。
つまりは、早速の大当たりな訳で。
「目標確認……だなぁ、意外と早かったね」
一応は警戒させないように、自然と歩み寄っていく。ある程度まで近付いた所で向こうも気づいたのか、少しばかり警戒するような視線を二人へと向けた。パタンとスケッチブックを閉じ、胸に抱き抱え立ち上がった。
まあ、この状況であればナンパとでも疑られても仕方はない。まずはその誤解を解かねばならないだろう。
「突然すいません。今の、異能力ですよね?少し聞きたい事が……」
「またですか……!」
唐突にそう呟いた女性はすぐさま走り出し、二人が呆然としている内にみるみる遠ざかっていく。なんとか我に返って健が呼び止めようとするも、女性は全く聞こうとしない。
「あっ、ちょっとー!追った方が良さげー!?」
「そりゃそうでしょ……『また』って事は、大体予想つきますしね……!」
慌てて飛び出して、人混みの中に消えて行く女性を追う。その複雑な人の海を掻き分けつつ、後ろ姿を視界から外さぬよう走り続けていく。どうやら大きめのスケッチブックを持っているせいか、上手く進む事が出来ないらしい。焦った様子で彼女が飛び込んでいったのは、行き止まりになっている裏路地だ。
言い方は悪いが、これで追い詰めた事になる。
最奥へと走り、そのビルの壁を見上げる女性に、今度こそ話をする。きちんと説得せねば、彼女はいずれ必ず不幸な目に遭う。というか、あの様子からするに、既にもう不幸な目に『遭った後』なのだろう。
であればこそ、そこからの脱却の仕方を知らない今の彼女には、国の保護が必要だ。
息を切らせつつも、眼鏡越しにこちらをキッと睨み付けた女性は、忌々しげに呟く。
「……はっ……はっ……っ、しつこい、です……」
「ふぅ……残念ながら、それは達也に言ってね。全く……彼は本当に女の子に」
「ちょっと黙ってて」
「あっはい」
巫山戯てみせる健を少し睨んで止め、気を取り直して相対する。今の誤解が続いても厄介だし、このままでは彼女の身の危険にも関わるのだ。彼女には悪いが、あまり話している余裕はない。
少しだけ息を整えて、改めて彼女に話し掛ける。
「危害を加えるつもりはありません、驚かせてしまったなら謝ります。ですが、今はどうか同行してくれませんか?貴女の身の危険にも関わる事です」
「……嘘。どうせ、私の能力狙いなんでしょう?」
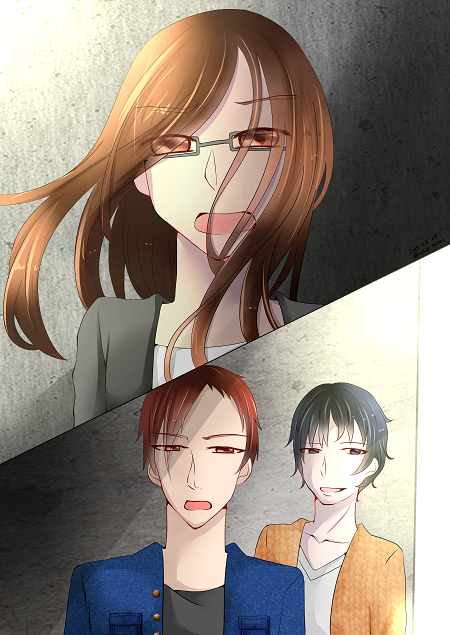
「能力狙い?」
「分ってるでしょ、健さん」
首を傾げる健に達也が呆れつつツッコミを入れるが、健はまたも首を傾げる。今はそんな問答をしている暇もない。先に話を通さなければならないのだ。
と、内心で抱く焦りすら知らぬとばかりに、女性がスケッチブックを開く。それはまるでおとぎ話に出てくる魔法書の様にパラパラと捲れ、大きな鳥が描かれたページへと変わった。
次の瞬間にはその絵が輝き、光を撒き散らし始める。
「私は、貴方達には加担しない……絶対に!」
光の中から生まれたのは、スケッチブックに描かれていた大きな鳥。流石にスケッチブックと同じ程度のサイズではあるが、羽ばたくその鳥の足に捕まった女性の体が、ふわりと宙に浮き上がる。その鳥が大きく羽ばたくと同時、周囲には暴風が吹き荒れ、ぐんぐんとその高度を高めていった。
やがてその姿は粒ほどにまで縮んでいき、空の青の中へと吸い込まれて行く。
「……あーあ、逃しちゃった。達也がボサッとしてるからー」
「酷い責任転嫁を見た」
酷い言いがかりを付けてくる健にツッコミつつ、みすみす逃してしまった失態に内心で舌打ちする。本来なら、無理矢理に止めてでも保護するべきだった。健にも稀に言われるが、やはり自分は詰めが甘いのだと改めて思い知る。
運良く掴んだ手掛かりを、こうも簡単に逃してしまうとは。
「さてさて、冗談はこの位にして……少し拙いね。達也、少し頼みがあるんだけれど」
そう切り出した健の手にはいつの間にか、先程の鳥の羽が載っていた。
◇ ◇ ◇
「――という訳で、どうにもあちらさん何やら事情が立て込んでいるらしいね。足取りも見失った。依頼は失敗だね……ごめんよ」
「そうですか……」
三日後。
約束の期日となり探偵事務所に訪れた依頼人の女性に、健が依頼を失敗した旨を報告する。あの後健も独自の伝で色々な所から探ってみたが、やはり居場所は掴めなかった。
あの絵描きの女性は健には見つけられず、依頼人の女性が残念そうに声を漏らす。
「はぁ……ったく、何みすみす逃してんだか」
「まあまあ、そう怒らないで。福が逃げるよ?」
「ほう、それは面白いことを聞いた。取り敢えず今まで逃げた福を今すぐ利息込みで耳揃えて払ってもらおうか。代金一生文の運命力となりますお客様」
「やめてください事故死してしまいます」
戯けた様子で言う健に何の関心も示した様子もなく、双樹は依頼人の女性に事務的な事項をつらつらと話していく。女性もそれに無難に答えてからソファを立ち、荷物を纏めだす。
「ごめんね、見つけられなくって」
「いいんですよ、元々私のささやかな希望でしたし。見つからなければ見つからなかったで、それは仕方ない事です。有難うございました」
女性はささやかな笑みを浮かべて礼を言うと、事務所から出ていこうとする。双樹が途中まで見送り、女性は川越の街に出た。
――そのままスタスタと、自然な様子で裏路地へと歩いていく。
自然に、無表情のまま、ただただ暗く細い道を歩いていく。少しばかり進んでいった所で彼女は急に動きを止めて、背後に振り向いた。酷く冷たい視線が伸び、その先にいる『彼女』を射抜く。
『絵描き』の彼女は、その視線に少し怯えた様に後ろ足を踏むも、スケッチブックを抱く手に力を込めつつ、気丈にも声を発した。
そのスケッチブックから、一丁の拳銃を引き抜いて。
「……貴女ですよね。私の事、ずっと付け狙ってたの」
「あぁ……自分から来て下さるとは。気付いてたんですね」
女は恐ろしくなる程に冷たい、悍ましい笑みを口元に浮かべる。
その顔立ちは整っており、長く伸びた髪から覗く真っ白な瞳が今はとても恐ろしい。美しさが逆に恐怖となって、その女を構成する要素となっている。その顔に張り付いた作り物めいた笑みが、ただただ恐ろしい。
残虐。浮かぶ印象は、その一言のみ。
「それで、私に何か御用ですか?」
「……私を狙うのはやめてください。私は絶対に、貴女達に加担するつもりはありません」
「それは出来ませんよ。貴女が、私達に協力してくれる気になるまでは」
その返答を聞き、絵描きの女性は拳銃の引き金に指を当てる。その銃口を彼女に向け、その腕を震わせつつも、再度言い放つ。
「やめてって、言ってるの。じゃないと、本当に撃つわ」
「……そうですか」
女は興味もなさそうに呟くと、銃口を向けられていると言うのに、平然と絵描きの女性に歩み寄っていく。ビクリと震えた彼女は拳銃を両手で支えて、より一層の力を込めて拳銃を突きつけた。近付けば撃つ、そう言外に伝えようと。
しかし、女は歩みを止めない。
ただ冷たい表情のまま彼女の下に近付き、その銃を持つ。手に指先を伸ばす。その異常性から来る恐怖に耐えきれなくなったのか、絵描きの女性が引き金を引こうと力を込め――
――しかし、銃声は響かない。
「……な、なんで……っ!引けない……?撃って!撃ってよっ!」
「銃を持ったこともないんですね……いや、そもそも銃についても、あんまり知らないでしょう?」
女は彼女の手から拳銃を奪い取ると、セーフティーを外し、スライドを引いて、壁に向けて引き金を引く。同時に一発の銃声が響き、コンクリートの壁が少し欠けた。火薬の匂いが周囲に満ち、銃を奪われた女性は呆然とその光景を見ているしかなかった。
女はそのまま銃口を移動させ、彼女の額へと向ける。同時に女が手を挙げると、共にアサルトライフルを携えた何人もの黒服の男達が、二人しかいなかった路地裏へと入り込んで来る。
無数の銃口が、彼女に向けられた。
「……っ!」
「形勢逆転、とでも言うんでしょうか。どうです?協力して下さる気にはなりましたか?」
この状況に於いても、女はただただ冷たい表情を浮かべるばかりで、その顔からは一筋の善性すら感じられない。この女は、本当に、根っこからの悪人だ。自分ではどう足掻いても、この女をどうこうする事は出来ない。
今引き金が引かれれば、自分の命は簡単に消えて無くなってしまう。死にたくない。こんな事に巻き込まれて死んでしまうなんて、絶対に嫌だ。けれど。
けれど――
「……やだ」
この力で、こんな奴らの悪事に協力して、誰かを不幸にしてしまうなんて、もっと嫌だ――!
「嫌です……この能力は、悪事なんかに使うものじゃない……っ、貴女達の一員になんかならない……!」
「そうですか……仕方ないですね。時間を無駄にしましたか」
女がトリガーに指を掛け、引き金を引く。同時に黒服の男達が一斉に銃撃を引き起こし、無数の弾丸が撃ち放たれた。
黄金色の弾丸が亜音速を超え、空気を引き裂き、彼女の身を幾重にも貫こうと、暴力的なまでの力を以って飛来する。自身の終わりを察して、恐怖に蝕まれて、ぎゅっと目を瞑った。
――。
――――。
――――――?
「……っ、やはり、気付いていましたか……!」
そんな、女の声が聞こえた。
まだ自分は死んでいないのか、確かに銃弾は撃たれたはずなのに。そう不思議に思ってゆっくりと目を開けると、黒服の男達とその女から道を遮るように、二人の男女が立っていた。
「あー、大丈夫ですかー?お怪我はないでしょーか?」
長く伸びた髪をツインテールにした少女が彼女に手を差し伸べ、何処か間の抜けた声音で言う。もう一人の男は何処かで見た覚えがあり、それが以前話し掛けてきた二人の男の片割れだと気付いた。
「い、今……撃たれた、のに……」
「あー、それに関しては大丈夫ですよー。ウチのなんでもあり枠がどうにかしましたからー」
にっこりと笑顔を浮かべて背後の男を指す少女に従い視線を移すと、その男の両手からポロポロと銃弾が零れ落ちた所だった。
その光景を見て、今までただ冷たい表情を浮かべるだけだった女の顔に、初めて表情が浮かぶ。忌々しげに、憎々しげに、女は彼を睨み付けた。
「……三國、健」
「お久しぶり、『カミサキ』」
――あぁ。
ここは、もう既に、日常の通じる世界ではなくなってしまったらしい――。
ページ上へ戻る「ん、唐突になんです?」
デスクの前の椅子に深く腰掛けた青年が神妙そうな顔で呟き、ソファで寛いでいたもう一人の青年……江西 達也が、寝転びつつ読んでいた雑誌から目を離して問いを投げる。
その問いに目を伏せた青年はゆっくりと立ち上がると、デスクの上に広がるいくつかの資料に目を通した。それらの資料はここ最近、この事務所に舞い込んできた以来の数々であり、ほぼほぼ解決済みまで終わらせてある。何も改まって話し合うほどの問題も起きていない。であればなんなのかと、達也が訝しげな視線を向けた。
が、その視線を意にも返さず、彼は一纏めに依頼書を束ねると――
「そぉいっ!!」
――一気に放り捨てた。
「今明かされる衝撃の真実ぅっ!!実は僕現在進行形でものすごーーく暇です!来てる依頼も全ッ部つまらない!なんだ猫探しって!なんだ浮気調査って!!テンプレか?テンプレなのかっ!?」
「……そんな事だろうなとは思ってましたよ」
オーバーな演劇のように振る舞う健の姿を見て一気に脱力した達也が溜息を吐き、一枚飛んで来た依頼書を手に取り、目を通す。
迷子になったペットの猫探し。実に探偵らしいというか、『いかにも』といった依頼だ。今の地位に落ち着くまではまさか本当にこんな依頼が来るとは思ってもいなかった。
達也は雑誌をテーブルの上に捨て、寝転んでいたソファから立ち上がる。散らばった書類を適当に纏めると、クリップで留めてデスクに戻した。
その様子に不満げな顔を浮かべた青年――三國 健は、不貞腐れた表情で上体をデスクにもたれさせる。
「だってさぁ、ここ最近何にも起きてないでしょ?達也は暇じゃないの?なんかこう……ときめく様な事件とか転がってない訳?」
「健さんの言う『ときめく事件』は大概ロクなことがないから是非とも遠慮したい。この川越中が大惨事になる……」
半眼で突っ込んだ達也はポリポリと頭を掻き、何度目とも分からない溜息を吐く。だが実際問題、健の言う通り、この探偵事務所にはここ数ヶ月、マトモな依頼が来ていない。暇であることはまあ達也も同意出来る。彼の言う『ときめく依頼』程ではないにしろ、もう少しやり甲斐のある依頼はないものか。
などと考えていると、噂をすれば何とやらとでも言うのか。
「はいはいそこのダラけたお二人さん、待ちに待ったマトモなお仕事の時間だ。キリキリ働け」
突如事務所のドアが開けられ、煽る様に手を叩く青年が乱入する。その青年の背後には何やら女性が佇んでおり、彼女を引き連れてきた青年は、手に持った報告書をデスクに放り投げた。
健が気怠げにその報告書に目を通すが、中身を読んだ途端に顔色を変え、唐突に勢い良く立ち上がる。
「ナイスだ双樹君っ!君は神か!?」
嬉しそうに依頼書を読み込む健の姿を見て全てを察した達也は、来たる『ときめく依頼』に対する覚悟を、固めているしかなかった。
◇ ◇ ◇
「『不思議な絵描きさん』……ね」
「絵に描いたものを実体化させる……面白い異能だねぇ」
双樹 兵児が持ってきた依頼――女性の依頼内容は、『子がお世話になった不思議な絵描きを探して欲しい』、と言うものだった。一先ずはそう飛び抜けた依頼でないと達也が安心したのも束の間、その『不思議な絵描き』がどうにも異能力者である事が判明する。
現代に於ける異能者――その存在は基本的に、なるべく隠されるようになっている。そもそもの数が少ない上、他の人々との明確な差が生まれる為、人間社会に馴染めない者が殆どであるからだ。人間というものは面倒なもので、自分達と違う存在は無意識下に排除しようとする。故に異能者達の道はおおよそ三つに絞られるのだ。
その力を隠して細々と暮らすか、公に国の機関に就き、異能者としての力を生活に役立てるか、或いは――
――異能集団マフィアの一員となり、裏社会を暗躍する超常者となるか。
この依頼はその絵描きへと礼を言いたい、というのが本筋ではあるが、また別種の目的も存在する。これは全く以来とは関係のない話だが、今は迅速にその『絵描き』を見つけ出す事が先決だろう。
「んで、時に達也君よ。どういった方針で?」
「ふむ、俺の異能で……見つけられたら良いんだけど、面倒な事に30秒しか持たないからなぁ……」
ボヤくように達也が言い、袖をめくって腕時計の時刻を確認する。短針は既に六の数字を超えており、空は既に赤らみ始めている。早い所捜査は終わらせた方が、スムーズに進行するだろう。
一先ずは探偵らしく聞き込みかと、一先ずは人溢れる大通りの周辺を見回してみる。
……と。
「……ねぇ達也、あれ」
「……うん、まあ、モロ……だよな」
二人の視線の先、大通りからは逸れた小さな裏路地の暗闇の中で、座り込み、スケッチブックに何やら描き込んでいる女性が見えた。
暫く待てばそのスケッチブックからは鯨の尾のようなモノが伸び、まるでスケッチブックが水面であるかのように、尾ひれで水飛沫を弾き出す。それは彼女が凭れ掛かるマンションの壁を黒く染めて、重力に従い流れ落ちていった。
当然ながらこの2020年現在、水飛沫を発生させるスケッチブックなどある筈もない。ましてやスケッチブックから鯨の尾が出て来るわけもない。そもそもあんなミニサイズの鯨は居ない。
つまりは、早速の大当たりな訳で。
「目標確認……だなぁ、意外と早かったね」
一応は警戒させないように、自然と歩み寄っていく。ある程度まで近付いた所で向こうも気づいたのか、少しばかり警戒するような視線を二人へと向けた。パタンとスケッチブックを閉じ、胸に抱き抱え立ち上がった。
まあ、この状況であればナンパとでも疑られても仕方はない。まずはその誤解を解かねばならないだろう。
「突然すいません。今の、異能力ですよね?少し聞きたい事が……」
「またですか……!」
唐突にそう呟いた女性はすぐさま走り出し、二人が呆然としている内にみるみる遠ざかっていく。なんとか我に返って健が呼び止めようとするも、女性は全く聞こうとしない。
「あっ、ちょっとー!追った方が良さげー!?」
「そりゃそうでしょ……『また』って事は、大体予想つきますしね……!」
慌てて飛び出して、人混みの中に消えて行く女性を追う。その複雑な人の海を掻き分けつつ、後ろ姿を視界から外さぬよう走り続けていく。どうやら大きめのスケッチブックを持っているせいか、上手く進む事が出来ないらしい。焦った様子で彼女が飛び込んでいったのは、行き止まりになっている裏路地だ。
言い方は悪いが、これで追い詰めた事になる。
最奥へと走り、そのビルの壁を見上げる女性に、今度こそ話をする。きちんと説得せねば、彼女はいずれ必ず不幸な目に遭う。というか、あの様子からするに、既にもう不幸な目に『遭った後』なのだろう。
であればこそ、そこからの脱却の仕方を知らない今の彼女には、国の保護が必要だ。
息を切らせつつも、眼鏡越しにこちらをキッと睨み付けた女性は、忌々しげに呟く。
「……はっ……はっ……っ、しつこい、です……」
「ふぅ……残念ながら、それは達也に言ってね。全く……彼は本当に女の子に」
「ちょっと黙ってて」
「あっはい」
巫山戯てみせる健を少し睨んで止め、気を取り直して相対する。今の誤解が続いても厄介だし、このままでは彼女の身の危険にも関わるのだ。彼女には悪いが、あまり話している余裕はない。
少しだけ息を整えて、改めて彼女に話し掛ける。
「危害を加えるつもりはありません、驚かせてしまったなら謝ります。ですが、今はどうか同行してくれませんか?貴女の身の危険にも関わる事です」
「……嘘。どうせ、私の能力狙いなんでしょう?」
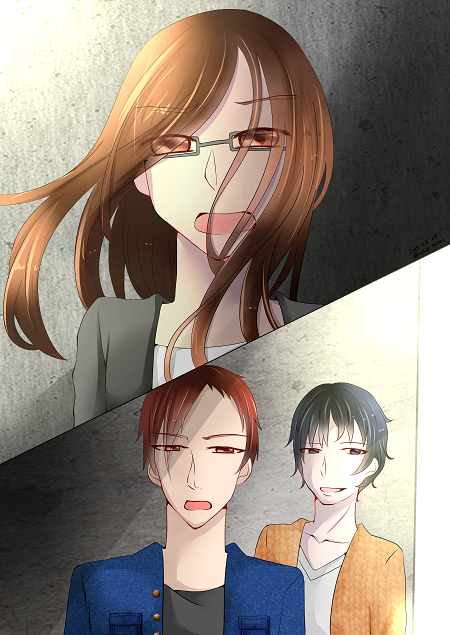
「能力狙い?」
「分ってるでしょ、健さん」
首を傾げる健に達也が呆れつつツッコミを入れるが、健はまたも首を傾げる。今はそんな問答をしている暇もない。先に話を通さなければならないのだ。
と、内心で抱く焦りすら知らぬとばかりに、女性がスケッチブックを開く。それはまるでおとぎ話に出てくる魔法書の様にパラパラと捲れ、大きな鳥が描かれたページへと変わった。
次の瞬間にはその絵が輝き、光を撒き散らし始める。
「私は、貴方達には加担しない……絶対に!」
光の中から生まれたのは、スケッチブックに描かれていた大きな鳥。流石にスケッチブックと同じ程度のサイズではあるが、羽ばたくその鳥の足に捕まった女性の体が、ふわりと宙に浮き上がる。その鳥が大きく羽ばたくと同時、周囲には暴風が吹き荒れ、ぐんぐんとその高度を高めていった。
やがてその姿は粒ほどにまで縮んでいき、空の青の中へと吸い込まれて行く。
「……あーあ、逃しちゃった。達也がボサッとしてるからー」
「酷い責任転嫁を見た」
酷い言いがかりを付けてくる健にツッコミつつ、みすみす逃してしまった失態に内心で舌打ちする。本来なら、無理矢理に止めてでも保護するべきだった。健にも稀に言われるが、やはり自分は詰めが甘いのだと改めて思い知る。
運良く掴んだ手掛かりを、こうも簡単に逃してしまうとは。
「さてさて、冗談はこの位にして……少し拙いね。達也、少し頼みがあるんだけれど」
そう切り出した健の手にはいつの間にか、先程の鳥の羽が載っていた。
◇ ◇ ◇
「――という訳で、どうにもあちらさん何やら事情が立て込んでいるらしいね。足取りも見失った。依頼は失敗だね……ごめんよ」
「そうですか……」
三日後。
約束の期日となり探偵事務所に訪れた依頼人の女性に、健が依頼を失敗した旨を報告する。あの後健も独自の伝で色々な所から探ってみたが、やはり居場所は掴めなかった。
あの絵描きの女性は健には見つけられず、依頼人の女性が残念そうに声を漏らす。
「はぁ……ったく、何みすみす逃してんだか」
「まあまあ、そう怒らないで。福が逃げるよ?」
「ほう、それは面白いことを聞いた。取り敢えず今まで逃げた福を今すぐ利息込みで耳揃えて払ってもらおうか。代金一生文の運命力となりますお客様」
「やめてください事故死してしまいます」
戯けた様子で言う健に何の関心も示した様子もなく、双樹は依頼人の女性に事務的な事項をつらつらと話していく。女性もそれに無難に答えてからソファを立ち、荷物を纏めだす。
「ごめんね、見つけられなくって」
「いいんですよ、元々私のささやかな希望でしたし。見つからなければ見つからなかったで、それは仕方ない事です。有難うございました」
女性はささやかな笑みを浮かべて礼を言うと、事務所から出ていこうとする。双樹が途中まで見送り、女性は川越の街に出た。
――そのままスタスタと、自然な様子で裏路地へと歩いていく。
自然に、無表情のまま、ただただ暗く細い道を歩いていく。少しばかり進んでいった所で彼女は急に動きを止めて、背後に振り向いた。酷く冷たい視線が伸び、その先にいる『彼女』を射抜く。
『絵描き』の彼女は、その視線に少し怯えた様に後ろ足を踏むも、スケッチブックを抱く手に力を込めつつ、気丈にも声を発した。
そのスケッチブックから、一丁の拳銃を引き抜いて。
「……貴女ですよね。私の事、ずっと付け狙ってたの」
「あぁ……自分から来て下さるとは。気付いてたんですね」
女は恐ろしくなる程に冷たい、悍ましい笑みを口元に浮かべる。
その顔立ちは整っており、長く伸びた髪から覗く真っ白な瞳が今はとても恐ろしい。美しさが逆に恐怖となって、その女を構成する要素となっている。その顔に張り付いた作り物めいた笑みが、ただただ恐ろしい。
残虐。浮かぶ印象は、その一言のみ。
「それで、私に何か御用ですか?」
「……私を狙うのはやめてください。私は絶対に、貴女達に加担するつもりはありません」
「それは出来ませんよ。貴女が、私達に協力してくれる気になるまでは」
その返答を聞き、絵描きの女性は拳銃の引き金に指を当てる。その銃口を彼女に向け、その腕を震わせつつも、再度言い放つ。
「やめてって、言ってるの。じゃないと、本当に撃つわ」
「……そうですか」
女は興味もなさそうに呟くと、銃口を向けられていると言うのに、平然と絵描きの女性に歩み寄っていく。ビクリと震えた彼女は拳銃を両手で支えて、より一層の力を込めて拳銃を突きつけた。近付けば撃つ、そう言外に伝えようと。
しかし、女は歩みを止めない。
ただ冷たい表情のまま彼女の下に近付き、その銃を持つ。手に指先を伸ばす。その異常性から来る恐怖に耐えきれなくなったのか、絵描きの女性が引き金を引こうと力を込め――
――しかし、銃声は響かない。
「……な、なんで……っ!引けない……?撃って!撃ってよっ!」
「銃を持ったこともないんですね……いや、そもそも銃についても、あんまり知らないでしょう?」
女は彼女の手から拳銃を奪い取ると、セーフティーを外し、スライドを引いて、壁に向けて引き金を引く。同時に一発の銃声が響き、コンクリートの壁が少し欠けた。火薬の匂いが周囲に満ち、銃を奪われた女性は呆然とその光景を見ているしかなかった。
女はそのまま銃口を移動させ、彼女の額へと向ける。同時に女が手を挙げると、共にアサルトライフルを携えた何人もの黒服の男達が、二人しかいなかった路地裏へと入り込んで来る。
無数の銃口が、彼女に向けられた。
「……っ!」
「形勢逆転、とでも言うんでしょうか。どうです?協力して下さる気にはなりましたか?」
この状況に於いても、女はただただ冷たい表情を浮かべるばかりで、その顔からは一筋の善性すら感じられない。この女は、本当に、根っこからの悪人だ。自分ではどう足掻いても、この女をどうこうする事は出来ない。
今引き金が引かれれば、自分の命は簡単に消えて無くなってしまう。死にたくない。こんな事に巻き込まれて死んでしまうなんて、絶対に嫌だ。けれど。
けれど――
「……やだ」
この力で、こんな奴らの悪事に協力して、誰かを不幸にしてしまうなんて、もっと嫌だ――!
「嫌です……この能力は、悪事なんかに使うものじゃない……っ、貴女達の一員になんかならない……!」
「そうですか……仕方ないですね。時間を無駄にしましたか」
女がトリガーに指を掛け、引き金を引く。同時に黒服の男達が一斉に銃撃を引き起こし、無数の弾丸が撃ち放たれた。
黄金色の弾丸が亜音速を超え、空気を引き裂き、彼女の身を幾重にも貫こうと、暴力的なまでの力を以って飛来する。自身の終わりを察して、恐怖に蝕まれて、ぎゅっと目を瞑った。
――。
――――。
――――――?
「……っ、やはり、気付いていましたか……!」
そんな、女の声が聞こえた。
まだ自分は死んでいないのか、確かに銃弾は撃たれたはずなのに。そう不思議に思ってゆっくりと目を開けると、黒服の男達とその女から道を遮るように、二人の男女が立っていた。
「あー、大丈夫ですかー?お怪我はないでしょーか?」
長く伸びた髪をツインテールにした少女が彼女に手を差し伸べ、何処か間の抜けた声音で言う。もう一人の男は何処かで見た覚えがあり、それが以前話し掛けてきた二人の男の片割れだと気付いた。
「い、今……撃たれた、のに……」
「あー、それに関しては大丈夫ですよー。ウチのなんでもあり枠がどうにかしましたからー」
にっこりと笑顔を浮かべて背後の男を指す少女に従い視線を移すと、その男の両手からポロポロと銃弾が零れ落ちた所だった。
その光景を見て、今までただ冷たい表情を浮かべるだけだった女の顔に、初めて表情が浮かぶ。忌々しげに、憎々しげに、女は彼を睨み付けた。
「……三國、健」
「お久しぶり、『カミサキ』」
――あぁ。
ここは、もう既に、日常の通じる世界ではなくなってしまったらしい――。
全て感想を見る:感想一覧
